『吾妻鏡』で読む大河ドラマ『鎌倉殿の13人』(4)以仁王の令旨
- 2022/02/20
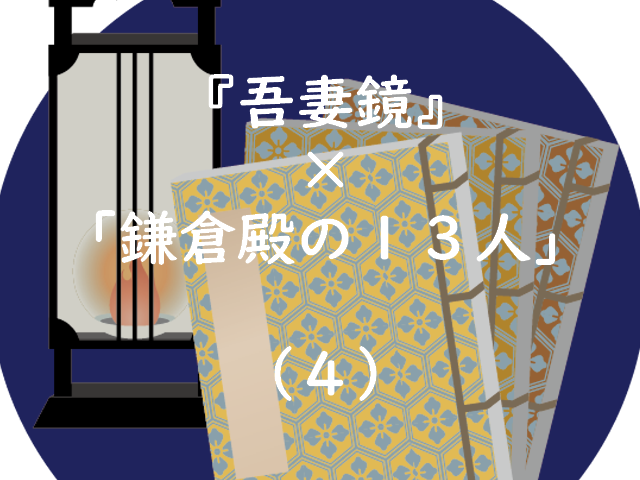
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
- ※本記事はユーザー投稿です
以仁王(演:木村昴)は源頼政(演:品川徹)の協力を得て、平家打倒の挙兵に踏み切りました。以仁王は、日本各地に散らばった清和源氏の一族にも決起を呼びかける命令書を下します。一般に、以仁王の令旨(りょうじ)とよばれるものです。その伝達役に選ばれたのが、頼朝の叔父・源行家(演:杉本哲太)でした。
行家は、頼朝の祖父・源為義の十男で、もともと「義盛」と名乗っていました。平治の乱で兄・源義朝が討たれ、義朝の子の頼朝は伊豆国へ流されましたが、義盛は姉の嫁ぎ先である熊野速玉大社を頼り、同社のある紀伊国新宮(現在の和歌山県新宮市)に潜伏して生き延びました。そのため、『平家物語』では「新宮十郎義盛」とよばれています。
一方、第2回で引用した通り、『吾妻鏡』では「陸奥十郎義盛」とよばれます。行家の曽祖父で、清和源氏の武名を高めた英雄とされる源義家の官職が陸奥守(むつのかみ)だったことから、義家の子・源義忠は「陸奥二郎」、義忠の後を継いだ為義は「陸奥四郎」を名乗りました。行家は陸奥四郎為義の十男なので「陸奥十郎」となるわけです。ドラマでは、頼朝が「十郎叔父」とよんでいました。
それまで無位無官だった義盛は、令旨の伝達役を任された時に、ふさわしい官職として「八条院蔵人」(はちじょういんのくろうど)に任ぜられました。
八条院とは、後白河法皇の妹・暲子(しょうし)内親王のことで、甥である以仁王の養母となって庇護していました。八条院蔵人は、彼女の臣下として秘書や家政を担当する職名です。これを機に、義盛は「行家」に改名したので、これ以降はもっぱら「十郎蔵人行家」とよばれるようになります。
ドラマでも、蔵人任官と同時に改名したことが、行家自身の台詞で説明されていました。頼朝からは「うさんくさいといえば十郎叔父」と、さんざんな陰口を言われた行家ですが、どのようにうさんくさいかは、今後描かれる行動でよくわかることでしょう。
行家が令旨を携えて伊豆の北条館を訪れたのは、治承4年4月27日(1180年5月24日)のことです。ドラマで行家が山伏に変装しているのは、『吾妻鏡』にはなく、『源平盛衰記』による描写です。
山伏は僧侶の一種ですが、髪を剃らず、太刀を帯びて、諸国の山岳を回って修行するという特異な習慣があります。そのため、武士が身分を隠して旅をするには格好の隠れ蓑でした(平家滅亡後、源頼朝と対立した弟・義経が、同様に山伏に変装して逃亡したことは有名です)。しかも行家は熊野育ちなので、山伏の行をよく見習っていたのだと『源平盛衰記』では説明されています。
ドラマでは、頼朝は平服のまま行家に対面し、令旨は側近の安達盛長(演:野添義弘)が取り次ごうとしましたが、行家から無礼を一喝されます。そこで頼朝は衣服を改めて、令旨を行家からじかに受け取るという段取りになりました。
この描写は、『吾妻鏡』の
武衛、水干を装ひ、先づ男山の方を遥拝し奉り、謹みて之を披閲せしめ給ふ
という記述に基づいています。
「武衛」(ぶえい)とは兵衛佐(ひょうえのすけ)という官職名を中国風に表記したもので、右兵衛権佐であった源頼朝のことをさします(もちろん、この官職は流罪になった時点で剥奪されているので、ドラマの時点では「前右兵衛権佐」(さきのうひょうえのごんのすけ)とよばれます)。
「水干」(すいかん)は、ここでは武士の普段着である「狩衣」(かりぎぬ)よりも儀式的な服装として使われています。
ドラマ内で、頼朝だけでなく武士たちがいつも揃って着ている、前を紐で結んで留めるゆったりした上着が狩衣です。
一方、行家に叱られたあとの頼朝が着ている、襟首の丸く立てられた、詰襟のような上着が水干です。狩衣よりは確かにみやびやかですが、窮屈そうで、頼朝もうんざりしたような顔をしていました。
「男山」(おとこやま)は、京の郊外(現在の京都府八幡市)にある石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)のことです。先にも書いた、清和源氏の英雄・源義家が元服した地であり、源氏の氏神、ひいては武士の守護神として信仰されていました。
このように頼朝が衣服を改め、わざわざ源氏の氏神である石清水八幡宮を遥拝してから令旨を受け取ったことは、清和源氏の棟梁としての自意識が強くうかがわれる行動だと思われます。しかし、ドラマでは遥拝の件は省略され、行家に叱られた頼朝がしぶしぶと着替えるという描写に変わっています。
こうして、以仁王の権威を笠に着る行家の空威張りと、「うさんくさい十郎叔父」の言動に振り回される頼朝との対照が、コミカルに描かれました。この辺りは、やはり喜劇を得意とする三谷幸喜氏ならではの創作でしょう。
行家はすぐさま、全国各地の源氏に令旨を伝えるために旅立っていきました。
挙兵の機会をうかがう頼朝の前に、以仁王の令旨という大義名分が舞い込んできた――さて頼朝はどうするのか。
これがドラマ第3回の主題となります。そう、「挙兵は慎重に」!





コメント欄