※ この記事はユーザー投稿です
幕末の秀才・橋本左内が15歳で書いた自己啓発の心得とは?
- 2024/05/20

江戸時代末期の幕末は、若き才能のある志士が次々と登場する時代でしたが、そのなかでも越前藩(福井県)の橋本左内は、誰もが認める秀才だったと言われています。驚くことに左内は、15歳にして「自己啓発の心得」を作文にまとめていたのです。
橋本左内とはどんな人物?
橋本左内は天保5年(1834)、越前藩の藩医の子として生まれました。幼い時から秀才と言われ、10歳にして「三国志」を読破していたそうです。16歳の時に緒方洪庵の適塾に学び、いったん帰藩したのち、21歳で江戸に遊学。蘭学を学ぶとともに、藤田東湖や佐久間象山といった超一流の学者たちとも交流を深めます。
そんな左内を藩主・松平春嶽が見逃すわけはありません。御書院番への抜擢を皮切りに、若き英才を側近くに置き、将軍継嗣問題では一橋慶喜を推す同志たちとの連携や交渉といった重要な任務を与えたのです。
左内と親交の深かった西郷隆盛は「同世代では橋本左内が最も立派な人で、学問や人物の大きさでは私はかなわない」と高く評価しています。
15歳で書いた「啓発録」
そんな橋本左内が、15歳の時に書いたのが「啓発録」です。もともと、立派な人間になるためにはどうすればよいかを自分自身に言い聞かせるために書いた作文だったそうで、以下の5つの項目を掲げています。
・稚心(ちしん)を去る
・気を振う
・志を立てる
・学を勉める
・交友を択(えら)ぶ
この5項目は順不同ではなく、「稚心を去る」から順序立てて記載しています。15歳の左内の文章構成力にも驚かされます。
書いてから約10年後、左内は本箱の隅にあった作文を見つけ、清書して弟たちに渡した書物が、今日「啓発録」として残されました。
「啓発録」に書かれていること
項目を一つずつ読み解いていきましょう。「稚心を去る」とは、子供っぽい心を捨て去れということです。遊びにふけったり、父母に甘えていたりしては、いつになっても本気で勉強はできないと戒めています。
「気を振う」とは、何事も他人には負けていられないという気持ちを言い表しています。また、今の武士は士気に欠けていると痛烈に批判しているのです。
「志を立てる」では、ひとたび志を立てたのであれば、まず目標を定め、無駄な時を過ごさずに確実に歩を進めよと記しています。
「学を勉める」は文字通り「勉学」の意味で、一事を長時間続けることは困難であっても、それに打ち勝つだけの忍耐力を養成せよと鼓舞しています。
「交友を択ぶ」では、人との交際は必要だとしつつも、友人には「損友と益友」があり、益友ほど大切なものはないとしています。
おわりに
橋本左内は「あとがき」として、15歳の時の自分は今よりも気概があったとし、10年後に読み直した時に赤面せずに済めばいいと記しています。それからわずか2年後、左内は安政の大獄によって刑場の露と消え、左内が「啓発録」を再び読む機会は永遠に失われてしまったのです。
この記事を書いた人
フリーランスでライターをやっています。歴女ではなく、レキダン(歴男)オヤジです!
戦国と幕末・維新が好きですが、古代、源平、南北朝、江戸、近代と、どの時代でも興味津々。
愛好者目線で、時には大胆な思い入れも交えながら、歴史コラムを書いていきたいと思います。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



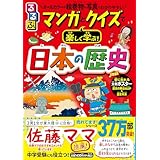
コメント欄