現代価値への換算は実質不可能!?「一両」の意味を解説
- 2021/06/28
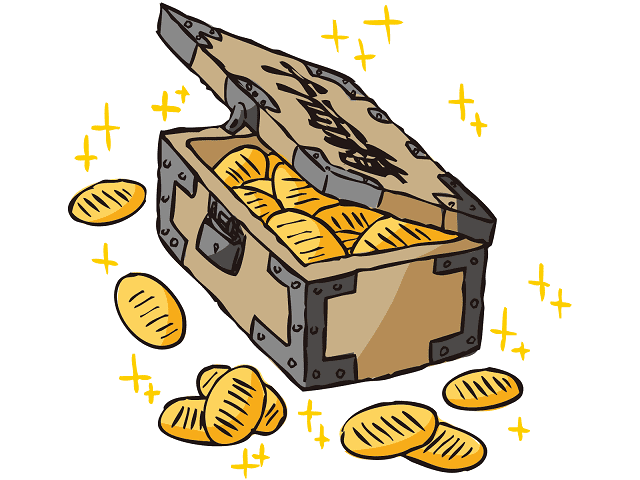
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
時代劇などを見ていると、よく「両(りょう)」というお金の単位が出てきますよね。「千両役者」などの言葉が残るように、かなり大きな金額を表しているように感じられます。
重そうな紙包みを開くと小判が積まれており、「〇〇両!」などとびっくりするシーンがあれば、どれほどの大金なのかついつい気になってしまいますね。
そこで今回は、いまいちわかりにくい江戸時代の通貨単位について概観し、「一両」がいったいいくら位になるのかを考えてみましょう!
重そうな紙包みを開くと小判が積まれており、「〇〇両!」などとびっくりするシーンがあれば、どれほどの大金なのかついつい気になってしまいますね。
そこで今回は、いまいちわかりにくい江戸時代の通貨単位について概観し、「一両」がいったいいくら位になるのかを考えてみましょう!
「両」とは
日本における「両」とは、江戸時代の「小判」や「分判(ぶばん)」といった金貨に使われる単位でした。これは慶長6年(1601)、係数貨幣として「慶長大判」「慶長小判」「慶長一分判」が発行され、小判1枚を1両としたことに始まります。


この小判という金貨は4.75匁(もんめ)で、約17.8グラムに相当します。小判10枚で大判1枚という価値でしたが、一分判は4枚で小判1枚となります。
しかし、この価値は江戸時代を通じて一定していたわけではなく、激しく変動していました。また、小判は幾度か改鋳されていますが意図的に金純度を下げることが行われ、貨幣価値の失墜を招いています。
「1両=〇〇円」と言いにくいワケとは
本題の1両が現代の価値ではいくらになるのかというお話ですが、これは結論からいうと「換算が非常に難しい」という答えになります。まったくすっきりしない、納得しづらい回答ですが、その理由について以下に述べていきたいと思います。江戸時代を通じて経済の基準となったのは「米」でしたが、その価値は時代とともに変わり、現代の感覚とも異なるものでした。たとえばごく大まかにいうと、江戸時代初期では1両で米が約350kg買えたものが、中期~後期では約150kgに激減しています。
さらに幕末になると、15~30kgと、米を指標とした1両の価値は江戸初期の10~20分の1以下にまで下落してしまいます。したがって、江戸時代のどの段階かによって1両の価値が細かく変動することが、単純に何円と言い切ることを難しくする原因となっているのです。
また、江戸時代に1両の価値とされたものは、それぞれに現代の日本円との感覚差が生じてきます。つまりは何を基準にして換算するかによって、いくらになるかが変わってきてしまうのです。
あわせて読みたい
貨幣博物館による試算モデル
以下に、貨幣博物館による試算モデルを参考にした数値をみてみましょう。18世紀の1両で買える米を約150kgとし、現代の米が1kgあたり約420円と仮定した場合、1両は約6万3千円となります。
試算モデル1)1両あたり、米150kg × 420円=6万3千円
一方、18世紀後半の人件費の例として、1両で大工23人分の日当を支払えたという記録があります。このことから、現代の大工の一日当たり賃金を約1万4千円と仮定すると、1両は32万2千円となります。
試算モデル2)1両あたり、大工23人 × 1万4千円=32万2千円
最後にもう一つ、江戸期を通じてもっとも物価変動がすくなかったとされる、かけそば1杯の値段を基準にしてみましょう。
江戸時代の中期~後期でのかけそばは1杯が約16文。江戸時代後期の公定相場では1両は6500文にあたるため、かけそば約406杯分に相当します。現代のかけそば1杯を約300円と仮定すると、1両は約12万1千800円となります。
試算モデル3)1両あたり、かけそば406杯 × 300円=12万1千800円
このように、物価や人件費ごとに現代価値との差が生じるため、何を基準として換算するかによって1両で買えるものが変わってきてしまうのです。単純に「1両=〇〇円」と断言するのが難しいというのは、このような事情が原因となっています。
江戸期の物価上昇と両の価値下落
先に述べたように、米を基準にして考えた場合には江戸時代の初めから約270年の間に、1両の価値は大きく下がっていることがわかります。つまりは物価が上がっていったことを示しており、これは現代の円についても同じことがいえるでしょう。たとえば厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、令和2年(2020)の大卒初任給は22万6千円ですが、昭和43年(1968)では3万600円となっています。
後者は現代価値に換算しても約13万8千円程度となり、わずか50年ばかりの間での物価高騰をみてとることができます。
幕末当時にはさらに、ハイパーインフレとすら呼ばれる巨大な物価上昇を招きました。この一因としては、開国によって金が大量に海外へと流出したためという説があります。
当時の日本では織豊時代以来のレートで金と銀は1:4の交換比率でしたが、海外では1:16ほどになっていたため安い銀が持ち込まれ、代わりに国内の金が激減したとされています。
もちろん未曽有の情勢不安などその他多くの状況が物価上昇を招いたはずですが、これらのこともまた、1両の価値を把握しづらくしている要因となっています。
おわりに
いかがだったでしょうか。1両を現代の円に換算することが難しい理由を述べてみました。よく1両=10万円というざっくりした基準を耳にしますが、これは江戸時代初期頃の米を基準にしての概算と考えられます。したがって、貨幣博物館では1両の目安を江戸時代初期で約10万円、中期~後期で4~6万円、幕末で4千円~1万円と解説しています。
【主な参考文献】
- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館
- 『日本大百科全書』(ジャパンナレッジ版) 小学館
- 江戸東京博物館HP 江戸時代の一両の価値は現在のいくら位か。
- 日本銀行金融研究所貨幣博物館HP 江戸時代の1両は今のいくら?
- 厚生労働省HP 賃金構造基本統計調査


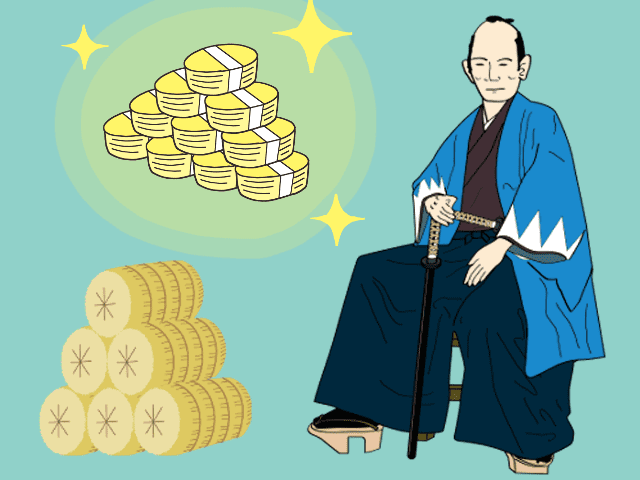

コメント欄