【やさしい歴史用語解説】「イエズス会」
- 2025/08/03
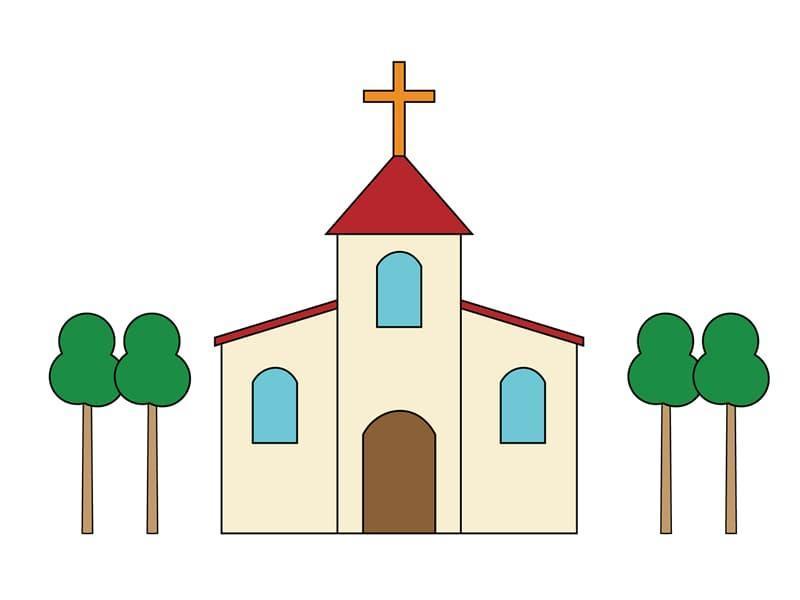
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
- ※本記事はユーザー投稿です
戦国時代には多くの宣教師たちが海を渡り日本へやって来ました。その主体となったのが「イエズス会」です。
そもそもイエズス会は、カトリック修道士ロヨラが中心となって1534年に創設された修道会ですが、その背景には経済的事情がありました。
16世紀初めに起こった宗教改革はローマ教皇の権威を衰退させ、カトリック教会に対するヨーロッパ諸侯からの献金も激減していました。さらにプロテスタント信者の激増によってカトリック信者が目減りするという事態を迎えていたのです。
そこでイエズス会が目を付けたのが、ヨーロッパ以外の地域へキリスト教を広めることでした。主にインドやアジア地域へ布教活動を拡大することで、各地の有力者から経済的援助を得ることを目的としたのです。
やがて布教活動が功を奏し、インドのゴアやフィリピンのマニラなどが大きな拠点となりました。さらに日本を足掛かりにすることで、中国大陸での布教まで視野に入れていたようです。
天文18年(1549)にザビエルが来日して以来、西日本を中心にキリシタンの数は増え続け、仏教に次ぐ信教となりました。また布教とともにもたらされたのが、南蛮貿易による巨大な富です。貿易利権を得たい大名が続々と洗礼を受けてキリシタン大名となり、日本とヨーロッパは宗教的・経済的・文化的に深い繋がり持つことになりました。

ところが宣教師たちの活動に危機感を持ったのが豊臣秀吉です。その発端となったのが、秀吉の側近として仕えていた施薬院全宗の讒言でした。全宗はキリスト教の影響が拡大することを懸念し、いずれ仏教が排斥されるのでは?と恐れていたようです。
秀吉も大名の多くがキリシタンになっている現状を恐れていました。しかしながら南蛮貿易の利権は手放したくありませんし、新しく日本準管区長となったコエリョに布教活動を正式に許していました。そこで秀吉はイエズス会に対して申し開きの機会を与え、その考えを聞こうとしたのです。
ところがコエリョは生来傲慢な男でした。日本側の対応に苛立ったコエリョは口論を始めてしまい、怒った秀吉はついにバテレン追放令を出してしまうのです。
こうしてイエズス会の活動が制限されたいっぽう、勢力を伸ばしたのがフランシスコ会です。のちに伊達政宗と結びついた修道会ですが、かねてからイエズス会とは反目し合っており、利益ばかり追求する姿勢に反発していたとも。
しかし文禄5年(1596)にスペインのガレオン船、サン=フェリペ号が土佐国に漂着した事件、いわゆるサン・フェリペ号事件が起こります。乗組員の発言により、「スペインが日本を征服しようとしている」と激怒した秀吉がキリスト教への弾圧を強め、26名を処刑した「日本二十六聖人の殉教」につながったことは有名です。

本格的な禁教令が発せられて以降、布教は停滞していきました。やがて江戸幕府が弾圧政策に大きく舵を切ると、もはや日本国内においてイエズス会・フランシスコ会は活動を停止せざるを得なくなったのです。




コメント欄