日本刀はどうして生まれた?その誕生秘話に迫る
- 2021/11/24
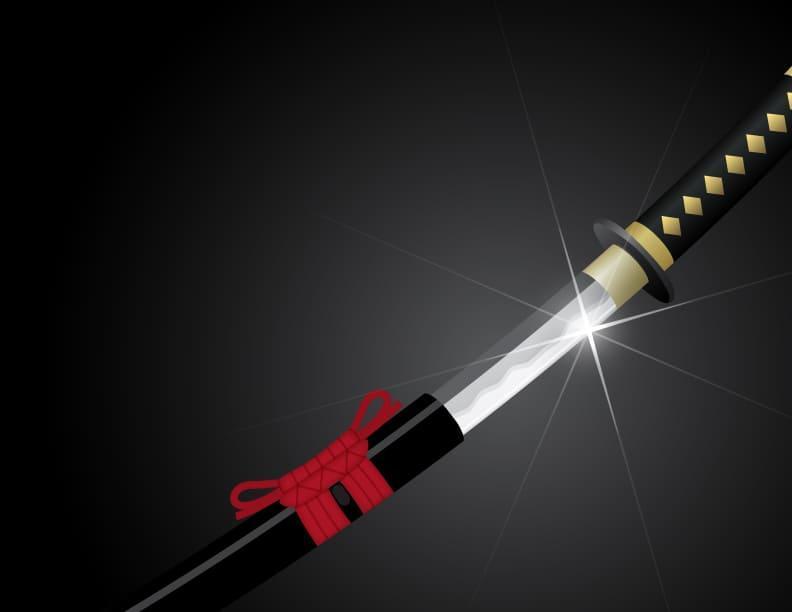
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
鋼の芸術とも呼ばれる「日本刀」。武器として生み出されながら、その製作には神事そのものの厳しさが求められ、その姿は至高の清冽さをもって見る者の心に迫ります。「武」と「美」とを兼ね備えた、まさしく世界に類のないスタイルの刀剣と言われています。
近年、刀剣をテーマにしたメディア作品のヒットにより、日本刀はより広い層のファンを獲得するようになりました。雅やかな曲線とほっそりした刀身は、一見女性的ですらあるような印象を与えますが、「折れず・曲がらず・よく切れる」という性質を実現した、優れた武器としても知られています。
そんな日本刀の人気が高まるにつれ、その歴史についても注目されています。そもそも日本刀は、いつごろ・どうして生まれたのか?そんな疑問に、分かりやすくお答えしたいと思います。
近年、刀剣をテーマにしたメディア作品のヒットにより、日本刀はより広い層のファンを獲得するようになりました。雅やかな曲線とほっそりした刀身は、一見女性的ですらあるような印象を与えますが、「折れず・曲がらず・よく切れる」という性質を実現した、優れた武器としても知られています。
そんな日本刀の人気が高まるにつれ、その歴史についても注目されています。そもそも日本刀は、いつごろ・どうして生まれたのか?そんな疑問に、分かりやすくお答えしたいと思います。
「日本刀」はいつごろ生まれた?
反りのある片刃の刀、という日本刀のスタイルは、確認できる最古級のもので平安時代後期に遡ります。東北地方の陸奥国・出羽国で起こった大規模な戦争である、「前九年の役(1051年)」「後三年の役(1083年)」によって大量の武器が必要とされたことが大きな要因と考えられています。「日本刀」といえば、通常はこの時代以降の刀剣類を指しており、武家の台頭と不可分の要素をもっています。
「湾刀化」の謎と日本刀のミッシングリンク
鉄製の刀剣類そのものは古墳時代の副葬品としてもよく知られています。それらは真っすぐな諸刃の剣(つるぎ)か、または片刃の直刀(ちょくとう。まっすぐで反そりのない刀のこと)であり、奈良時代以前の刀剣を「上古刀(じょうことう)」と呼んで分類しています。実は刀剣学においては、これらの直刀から曲線をもった「湾刀」(わんとう。弓なりにそった刀のこと)への変遷がどのようになされたのかが、長らくの謎とされてきたのです。
平安時代初期ごろからやや反りを生じたものや、刀身と柄が一体となって柄にスリットが設けられた「毛抜形太刀(けぬきがたたち)」など、過渡的なものは確認されていましたが、明確な祖型が不明だったのです。これは「日本刀の湾刀化」と呼ばれる問題で、上古刀と日本刀をつなぐ、いわばミッシングリンクと呼べる存在が探求されてきました。
東北に見る蝦夷の刀剣からの影響
そんな日本刀のミッシングリンクに、有力な説が登場します。それは東北地方を中心に出土する鉄製刀剣、「蕨手刀(わらびてとう)」の存在です。蕨手刀は6世紀から8世紀にかけて東北地方で製作されたと考えられている片刃の鉄刀で、柄頭に蕨の芽のような渦巻き状のあしらいがあることからの命名です。特に岩手県から多く出土することが知られています。
岩手県一関市には最も古い刀工集団である「舞草(もくさ)鍛冶」が存在し、この集団が蕨手刀の系譜をひくものと考える説があります。
大和朝廷は古代から東北経営を画策し、在地の「蝦夷(えみし)」と呼ばれる集団と長期にわたる戦争状態にありました。蕨手刀はそんな蝦夷たちが大和の軍勢と戦うために使った刀であるともいわれ、戦闘を通じて大和の刀剣もその影響を受けたことが想定されています。
それというのも、蕨手刀は当初の形状は柄と刀身がほぼ真っすぐな直刀状だったものが、徐々に柄が斜めに付くようになり、疑似的な外湾を呈するようになります。
やがて刀身そのものが湾曲していき、刀身と共造り(一体で成形されていること)の柄の中心に衝撃吸収用と思われるスリットが設けられたものが登場します。この蕨手刀の変遷を受けて作られたのが先述の「毛抜形太刀」の形式であるとされ、ここに日本刀の湾刀化の重要なヒントが秘められていると考えられるようになりました。
馬上戦闘の最適解としての湾刀
そもそも、刀剣が外側に向かって湾曲していくというのはどのような意味があるのでしょうか。その点について考察し、まとめとしたいと思います。日本刀の威力は「斬る」という点に特徴がありますが、刃物は物体に対して押すか引くかすることで、その切断力を最大限発揮します。刀を振るということは、切っ先は円弧の軌道を描くため自然に引き斬りの形となります。そのため、切断面により多く接触するためには外湾の形状が望ましいものとなります。
また、騎馬の状態から斬り下ろすように使われたことが想定されており、斬り付けたときの衝撃吸収のため深い反りが必要とされたとも考えられています。これは騎兵用のサーベルや、各地騎馬民族の刀剣類でも同様の変遷であり、疾駆する馬上から激しく斬撃を加えるという戦法によって湾刀が発達したとされています。
戦国期までの「太刀」から江戸期の「打刀」へと武士の兵装が変化し、幕末の頃にはほとんど反りの無い刀が流行したことからも、戦法の違いによる刀剣形状へのニーズを推測することができるでしょう。
おわりに
いまや「神器」とまで称される美しい日本刀ですが、その歴史は現実的な戦いの渦中で、必要から生みだされた姿だったのです。ただ綺麗なだけではなく、恐ろしい威力を秘めた日本刀は、それ故に見る者の心を揺さぶり、敬虔な気持ちにさせるのでしょう。「武」という漢字は「戈(ほこ)」を「止」める、すなわち争いを未然に防ぐ力を意味しているそうです。日本刀が魅せる武威から、そんな強さを感じ取りたいものですね。
【主な参考文献】
- 『歴史群像シリーズ【決定版】図説 日本刀大全Ⅱ 名刀・拵・刀装具総覧』(学習研究社、2007年)
- 『歴史群像シリーズ特別編集【決定版】図説・日本武器集成』(学習研究社、2005年)
- 『特別展 草創期の日本刀―反りのルーツをさぐる』(財団法人佐野美術館・大阪歴史博物館・一関市博物館、2003年)


コメント欄