光秀生涯のターニングポイントになった坂本城主時代を探る!
- 2019/12/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
光秀ゆかりの城はいくつもありますが、いちばん印象的なのは近江坂本城ではないでしょうか。光秀が比叡山焼き討ちの武功によって信長から近江国志賀郡を与えられて得た城であり、光秀のターニングポイントにもなっています。今回は ”坂本城主の光秀” にフォーカスをあててみます。
信長に近江国志賀郡を賜る
明智光秀が信長から近江国志賀郡を賜ったのは、元亀2年(1571)のこと。光秀は比叡山焼き討ちを中心で指揮して武功をあげたことによるものでした。この頃の信長はすでに上洛して将軍足利義昭を誕生させており、近江国の支配体制を進めていた頃です。それまで光秀は前年に討死した森可成に代わり、宇佐山城に入っていました。
光秀は幕臣か、信長家臣か
ここで気になるのは、この時点で光秀は幕臣・信長家臣のどちらに属していたのかということ。義昭の上洛自体、光秀が両者をつなく役割を担っていたと考えられています。両者の橋渡し役として両属していたとみられていますが、光秀はこの後、義昭から完全に離れることになります。光秀はどのタイミングで義昭と袂を分かつ決断をしたのか…。それは坂本城主になった事にあると思われます。同年12月ごろ、義昭に暇乞い(いとまごい。別れを告げること)の書状を出しています。将軍の近臣である曽我助乗(そがすけのり)に宛てた書状で、どうか取りなしてほしいと送ったものでした(『神田孝平氏所蔵文書』)。
当時義昭と信長の関係は悪化しつつあったので、その流れで光秀と義昭の関係にも亀裂が入ったのでしょう。この時点で光秀はかなり信長側に傾いており、もはやこれ以上幕臣としてはやっていけないと決断して暇乞いをしたのだと考えられます。
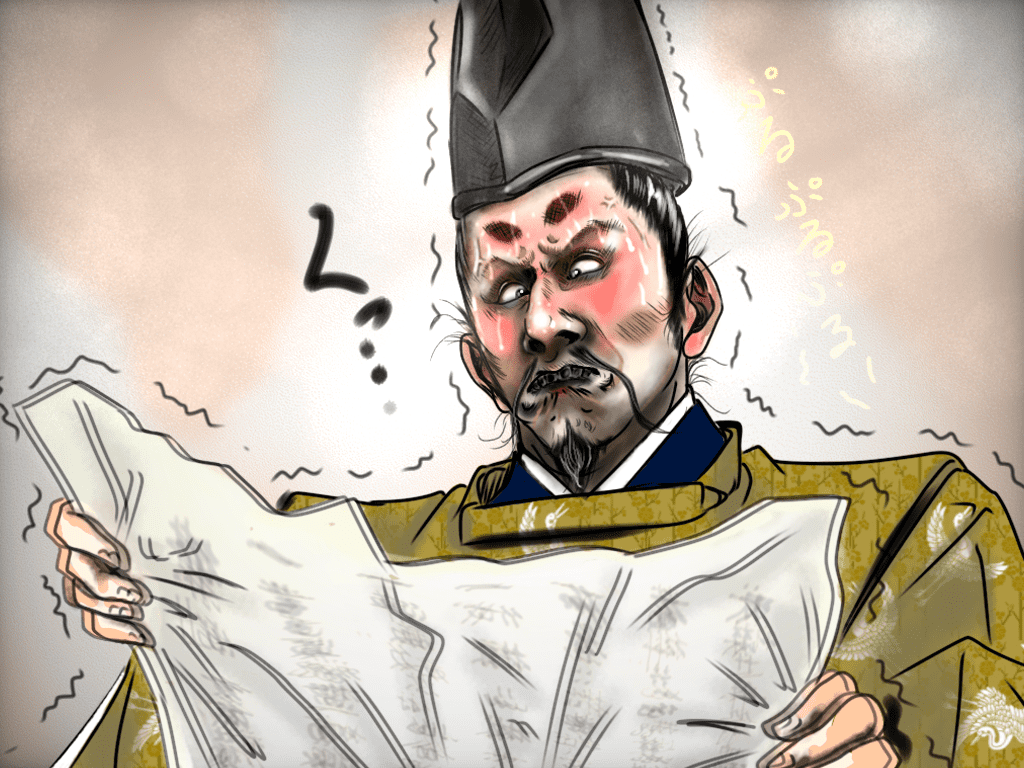
義昭と光秀の関係に亀裂が入ったきっかけはおそらく志賀郡を信長から任されたことでしょう。実は暇乞いの書状が出された時期と坂本城の築城開始時期はほぼ同じ頃なのです。光秀が義昭をあっさりと見限ったのも、信長から重要な地の支配権を与えられた、このことが大きいように思われます。
坂本城の築城
先にも述べましたが、『年代記抄節』によると、坂本城の築城開始時期は元亀2年(1571)12月です。光秀と親しかった吉田兼見の日記『兼見卿記』の中で、元亀3年(1572)の正月に訪れた際には坂本城築城に関することが記録されていません。まだ築城に着手したことを知らされていなかったのでしょう。
この頃の光秀はずっと築城だけに集中していたわけではなく、合間には浅井長政、朝倉義景らとにらみ合い、出陣することもありました。その割には城の完成ははやく、同年の12月24日には落成しています。
安土城に次ぐ豪華な城?
信長の時代、もっとも華麗で立派な城といえば安土城を置いてほかにはなかったでしょうが、坂本城はそれに次ぐすばらしさだったようです。また、城に瓦を使用することが許されたのは国持大名だけだったとか。光秀は武将としても有能な人物でしたが、築城を指揮する能力にも優れていたようです。宣教師のルイス・フロイスは、その著書『日本史』のなかで光秀を
「築城のことに造詣が深く、優れた建築手腕の持ち主である」
と評しているほどです。
こうしたこともあってか、光秀は信長から築城のための潤沢な資金も得ていたようです。それなら坂本城がとても豪華であったのは当然ですね。安土城は坂本城築城の後に建てられていますが、信長に天守を築くように進言したのも光秀であったとか。
もっとくわしく
坂本城を軍事拠点として…
光秀が志賀郡の支配権を与えられて坂本城を居城としたのは、比叡山に睨みをきかせるためだったと言われています。信長が拠点とする岐阜から京都への中間地点にあり、重要な地でした。比叡山に眼を光らせつつ、関係が悪化した幕府も抑える必要がある。幕臣であった光秀はその役に最適な人物だったわけです。
坂本城の築城以後、丹波攻めの命が下るまでの動き
- 【元亀3(1572)年】3月、木戸城、田中城を攻める。
- 【天正元(1573)年】2月~3月、石山・今堅田を攻め、近江国志賀郡をおおむね統一。
- 7月、槇島城の戦いに従軍。将軍義昭は敗れて追放される。
- 8月、越前朝倉を滅ぼした一乗谷の戦いに従軍
- 9月、京都代官を村井貞勝とともに果たす(以後天正3年まで)。
- 【天正2(1574)年】1月、大和多聞山城に城代として入城。
- 10月、佐久間信盛らと河内国を転戦。
- 【天正3(1575)年】4月、河内高屋城の三好康長を攻撃。
- 7月、惟とう、日向守の官途を与えられる。
- 8月、越前加賀攻めに従軍。
- 9月、丹波出陣の命が下る。
上述のように天正元年(1573)には将軍義昭との戦いで石山・今堅田を手に入れ、近江国は信長の手中におさまります。
坂本は vs義昭 の軍事拠点であり、光秀がその地を任されたということは、信長から家臣として大変評価されていたことがわかりますね。義昭追放後は河内国、越前国など近隣での戦にも従軍しています。
さらにはのちの丹波攻略のための重要な拠点となるのです。信長はのちのち丹波平定を任せることを視野に入れ、近江の指揮を光秀に託したのかもしれません。
多くの文化人を招く
坂本城城主となった光秀は、交流のあった文化人たちを招いてさまざまな会を開いています。信長に仕える以前から教養人・細川藤孝と付き合いがあったとされており、友人として長く交流していた光秀もまた、武士にしては高い教養を身につけた人物でした。
連歌会を主催
光秀の連歌の才能がどの程度だったのかはよくわかりませんが、史料として残っている最初の永禄11年(1568)に詠んだものから年月を経るごとに着実に上達していたらしいことはわかっています。光秀が坂本城の主として連歌会を催したのは、天正元年(1573)6月28日のこと。『兼見卿記』にそのことが記録されています。同史料に次いで坂本城での連歌会が記されるのは天正9年(1581)1月6日のこと。それ以外にも、合計9回もの連歌会を主催したとされています。
吉田兼見ほか、細川藤孝親子や連歌師の里村紹巴(さとむらじょうは)らも招かれたものと思われます。
茶会を主催
また、茶の湯をたしなんでいた光秀は坂本城で茶会も開いています。『津田宗及他会記』の記録に残っている最初のものは、天正6年(1578)の正月、7・8日の茶会。同年9月にも茶会を開いており、以降は正月と秋の年2回の茶会を定期的に主催しています。この茶会には、宗及ほか、筒井順慶、細川藤孝親子、茶人の山上宗二など、教養ある人物たちが多く招かれていたようです。その場では、光秀所有の数々の高価な茶道具や、藤原定家の色紙といった名品が披露されたといいます。
坂本城は軍事拠点でしたが、光秀が文化人らと交流する場でもあったのです。
訪問者から見る光秀の交友関係
坂本城に関する史料を見ていると、『兼見卿記』の記録が多いことに気づきます。吉田兼見(当時の名は兼和)はたびたび坂本城を訪問しており、光秀と親密な仲だったことがわかります。ところで、吉田兼見とはどんな人物かというと、京都にある吉田神社の神主であり公卿に名を連ねる人物。卜部氏の嫡流の家系でした。光秀が兼見と交流するようになったきっかけは、おそらく細川藤孝とのつながりでしょう。兼見は藤孝の従兄弟でもありました。
兼見は光秀や藤孝だけでなく、信長や秀吉との交流もあったのですが、特に光秀と仲が良かったと思われます。それは『兼見卿記』の光秀の登場回数からも明らか。坂本城普請に際してはたびたび訪問し、それ以外でもことあるごとに会っています。
これは光秀が信長の動静を詳細に伝え、それが兼見にとって利益になっていたというのも大きいでしょうが、趣味も合う親友だったのだろうと感じます。
天正10年(1582)6月7日、本能寺の変の5日後の話になりますが、兼見は勅使として安土城にいた光秀と面会しています。
朝廷は光秀に禁裏守護を任せると勅命を出し、光秀を信長に代わる天下人と認めると言っていたようですから、光秀は本能寺の変から短い期間であっても朝廷と交渉するパイプを持てていました。
光秀は9日には上洛して昇殿し、禁中に銀子を贈っています。朝廷を尊重する姿勢を見せており、それを朝廷も認めた。ここまでスムーズにいったのは朝廷との橋渡し役である兼見との関係が親密であったことが大きいように思えます。
光秀は幕府だけでなく、朝廷とのつながりも持っていた。朝廷とのパイプである兼見と親密であったこと、それがよく見えるのが坂本城時代の交流なのです。
もっとくわしく
西教寺にまつわるエピソード
滋賀県大津市坂本にある西教寺は、坂本城とも近い場所にあったとされています。この寺は光秀やその妻・煕子、それ以外の明智一族らも眠る菩提寺です。西教寺との付き合いから、何が見えてくるでしょうか。比叡山焼き討ちのときに消失
西教寺は、信長の比叡山焼き討ちに際して消失しています。その再建に尽力したのが、坂本城を居城としていた光秀でした。光秀は西教寺の檀徒になり、坂本城の城門を寄進して移築し総門としています。また、鐘楼堂の鐘は陣鐘だったとか。比叡山焼き討ちのとばっちりを受けた形ですが、それをフォローしたのが光秀だった。寺を消失させた信長の家臣とはいえ、光秀の復興支援にはずいぶん助けられたでしょう。

戦死した家臣を供養
光秀は、比叡山焼き討ちの際に戦死した家臣らの供養のため、西教寺に供養枚を寄進したという記録が寺に残されています。戦死した部下にまで心を配る光秀の行いはとても珍しく、光秀が心優しい人物であった美談として語り継がれている出来事。明智氏の菩提寺として
また、西教寺は明智一族の菩提寺でもありました。山崎の戦いで敗死した光秀と、それに先んじて亡くなった愛妻・煕子の菩提を弔われています。光秀は西教寺の復興に助力していたころから、ここを一族の菩提寺としようと考えていたのではないでしょうか。それは、今後坂本の地を自分の拠点として大事に守っていこうという決意の表れだったかもしれません。

光秀が坂本城をどこまで気に入っていたかはわかりませんが、丹波を平定して以降、亀山城を手に入れてもなお坂本城の城主としてあり続けました。
天正4年に亡くなった煕子のそばにいたい(※本能寺の変に際して亡くなった説もあり)という思いもあったでしょうが、西教寺を菩提寺としようと定めた時点で、坂本城に強い思い入れがあったのではないかと思うのです。
まとめ
坂本城主時代。それは光秀が勢いをつけ始めた時期ではないでしょうか。義昭と信長に両属していた光秀が信長を主君と定め、信長の優秀な家臣として歩み始めたのが坂本城築城のころです。京都に近い坂本。この地を与えられたことで光秀は畿内全域を手にするところまで進んでいきます。志賀郡支配はその第一歩だったのです。
【参考文献】
- 藤田達生『明智光秀伝: 本能寺の変に至る派閥力学』(小学館、2019年)
- 歴史読本編集部『ここまでわかった! 明智光秀の謎』(新人物文庫、2014年)
- 明智憲三郎『本能寺の変 431年目の真実』(文芸社文庫、2013年)
- 新人物往来社『明智光秀 野望!本能寺の変』(新人物文庫、2009年)
- 谷口克広『検証 本能寺の変』(文芸社文庫、2007年)
- 二木謙一編『明智光秀のすべて』(新人物往来社、1994年)
- 高柳光寿『人物叢書 明智光秀』(吉川弘文館、1986年)




コメント欄