温泉は武将のメディカルセンターだった?豊臣秀吉の健康法、「湯治」について
- 2020/09/23
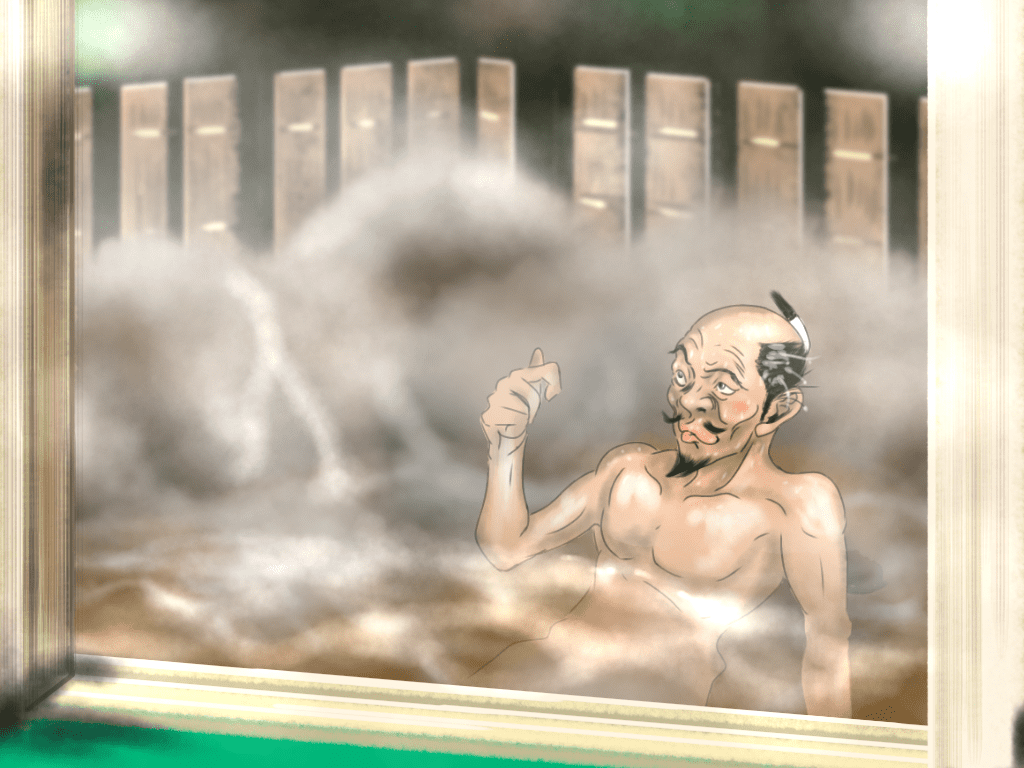
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
戦塵にまみれ、弓槍を手に駆け続けた戦国武将たちにとって、創傷や身体の不調は日常茶飯事のことでした。それだけに体力を回復させ、健康を維持することは重要な課題であったのです。
現代と比べると、当然ながら当時の医療技術には限度があり、健康維持のアプローチは自然治癒力を引き出すための方法が中心となりました。漢方や灸などの東洋医学、鷹狩りや武技といった運動などが例としてあげられます。そして天然の治療施設ともいえる温泉の存在も忘れてはいけません。現代でも様々な症状や外傷に効能があり、「湯治」という治療目的での入浴がよく知られています。
温泉が持つこの力に武将たちも着目し、戦傷を癒すメディカルセンターとして活用しました。その代表例がいまも「太閤」の愛称で呼ばれる「豊臣秀吉」でしょう。今回はそんな秀吉が愛した健康法である湯治についてフォーカスしてみたいと思います!
現代と比べると、当然ながら当時の医療技術には限度があり、健康維持のアプローチは自然治癒力を引き出すための方法が中心となりました。漢方や灸などの東洋医学、鷹狩りや武技といった運動などが例としてあげられます。そして天然の治療施設ともいえる温泉の存在も忘れてはいけません。現代でも様々な症状や外傷に効能があり、「湯治」という治療目的での入浴がよく知られています。
温泉が持つこの力に武将たちも着目し、戦傷を癒すメディカルセンターとして活用しました。その代表例がいまも「太閤」の愛称で呼ばれる「豊臣秀吉」でしょう。今回はそんな秀吉が愛した健康法である湯治についてフォーカスしてみたいと思います!
有馬温泉の歴史と秀吉
秀吉と温泉との関わりは、現代の有名な温泉地にもよく伝承されています。その代表格が兵庫県神戸市の「有馬温泉」ではないでしょうか。
温泉地としての有馬の歴史は古く、『日本書紀』『釈日本紀』には7世紀の舒明・孝徳両天皇の行幸が記録されています。以降も奈良時代の名僧・行基が有馬に堂を建立したり、清少納言の『枕草子』に有馬の湯が記されたりと、天下の名湯として人々に認識されていたことがわかります。
11世紀初めに起こった大洪水や、16世紀に連続した大火・戦火などによって幾度も存亡の危機を迎えましたが、天正11年(1583)に秀吉が同地を直轄領としたことで後の繁栄の礎となりました。
これは本能寺の変後、事実上の信長後継者として実権を握っていったことと関連し、それまで摂津国を池田恒興・元助父子を治めていたものを美濃国へと移封しての直接統治でした。
秀吉が認めた湯治の効能
入浴はもとより、天然温泉の成分が健康増進や疲労回復などさまざまな効能をもっているのは周知の通りです。打撲や切り傷などの外傷から特定の内臓疾患等の回復、または自律神経を整えリラックス効果を得られるなど、温泉成分と血行促進が肉体の好循環を促進します。
湯治による特定の効能は早くから認識されたようで、秀吉が文禄3年(1594)に側室の「京極殿」を湯治に送り出した際の書状にもその旨が記されています。
そこには「打肩」と「眼病」に関する治療効果を期待したことが述べられており、自身が同行できないことや京極殿の体調への細やかな気遣いがうかがえます。
秀吉が有馬温泉で湯治を行った確実な記録は、その生涯で9回確認することができます。以下に時系列順にピックアップしてみましょう。
- 1回目…天正11(1583)年8月17日~27日
- 2回目…天正12(1584)年8月2日~8日
- 3回目…天正13(1585)年1月22日~2月3日
- 4回目…天正13(1585)年9月14日~(期間不明)
- 5回目…天正18(1590)年9月25日~10月14日
- 6回目…天正19(1591)年8月9日~18日
- 7回目…文禄2(1593)年9月27日~閏9月7日(約10日間)
- 8回目…文禄3(1594)年4月29日~5月17日
- 9回目…文禄3(1594)年12月(期間不明)
いずれも最低でも一週間、長ければ20日間あまりというまとまった期間での本格的な湯治であり、大きな作戦が完了したり、あるいは次に行動を起こしたりする直前などに実施している点に注目されます。
たとえば1回目の湯治は天正11年(1583)6月に信長の一周忌法要を執行し、7月に近江・坂本で家臣団の論功行賞を済ませた後のことで、名実ともに信長の後継の座に収まった節目の時期でした。
2回目は徳川家康らと対峙した小牧・長久手の戦い(1584)の最中のことであり、戦線が膠着し一度大坂に帰還した際のことであるため、心身のリセットを企図したものかもしれません。
3~5回目は戦勝や和平・昇進などに付随するタイミングで、それぞれ家康との和睦・四国平定と関白就任・事実上の天下統一等々、直近に重大な成果をあげた年回りでした。
6回目は淀殿との最初の子である鶴松を亡くしたことの傷心、7回目は後の「豊臣秀頼」誕生の報を受けて肥前・名護屋から大坂に帰還した時です。
8回目は晩年になって体調不良に悩まされていた頃で、失禁や手足のしびれといった症状が出ていたといいます。
9回目は京都・伏見城が完成した頃で、10回目の湯治計画があったともいいますが病状の悪化により、ついに実現することはありませんでした。
実在した、まぼろしの「湯山御殿」
有馬の温泉を愛した秀吉は、その地に専用の湯治施設を建設したとされ、「極楽寺」にはかつて「湯山御殿」が存在したという伝承がありました。その存在が確認されたのは平成7年(1995)のことで、阪神淡路大震災の影響で破損した庫裏の下から御殿の一部とみられる湯舟や茶器、瓦や庭園遺構などが検出されました。
建設にあたっては周囲65軒もの建物を撤去したと伝えられ、慶長元年(1596)の伏見大地震で倒壊し、慶長3年(1598)に再建されました。現在では「神戸市立太閤の湯殿館」において、遺構や出土遺物が展示保存されています。

おわりに:湯治だけではなく、医療制度充実にも努めた秀吉
温泉好き、というイメージが定着している感のある秀吉ですが、医療制度の充実にも十分な注意を払っていました。高名な医師を結集した医師団の設立や、彼らによる24時間体制での治療即応、そして各医師の所見を立ち会いのもとで発表させあう等々、先進的な制度確立に尽力しています。
湯治に関しても単純な娯楽に留まらず、心身に関わる医療行為という認識があったのかもしれませんね。
【参考文献】
- 『戦国武将の健康法』 宮本義己 1982 新人物往来社
- 有馬温泉観光協会 HP
- 神戸市埋蔵文化財センター
- 大坂城豊臣石垣公開プロジェクト


コメント欄