※ この記事はユーザー投稿です
江戸幕府にも人材がいた!幕末三俊とは誰だ?
- 2025/04/08
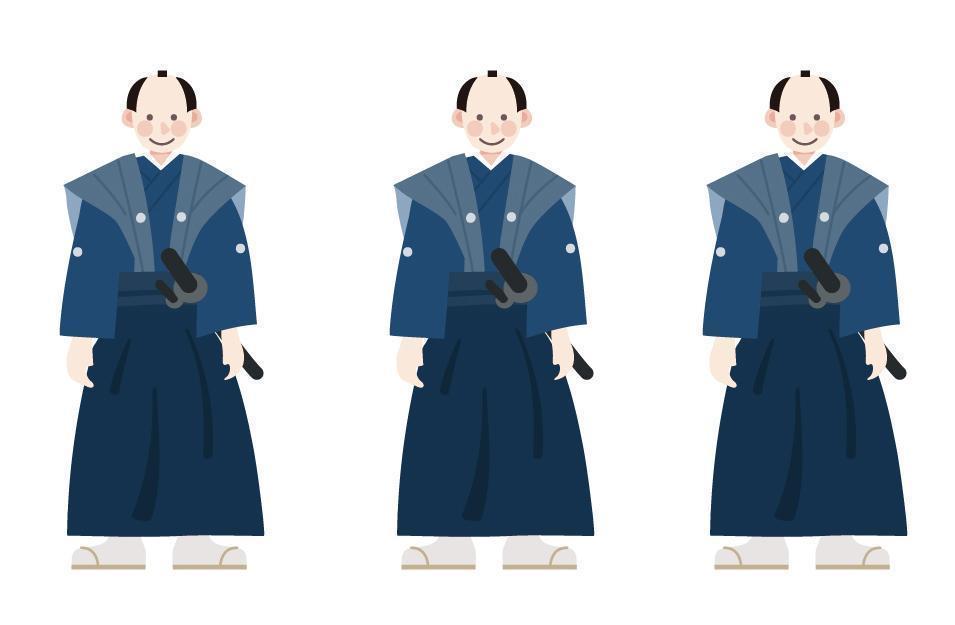
幕末の徳川幕府は「幕臣に人なし」と陰口を叩かれがちですが、明治維新を成し遂げた諸藩の英才たちに引けを取らない「幕末三俊」と呼ばれた幕府官僚がいたことをご存じでしょうか。幕末三俊の水野忠徳、岩瀬忠震、小栗忠順とは、どんな人物だったのでしょう。
日本の危機に登用された人材
嘉永6年(1853)、アメリカ合衆国のペリーが艦隊を率いて浦賀沖に現れました。欧米諸国の船が日本近海に現れることが増え、欧米諸国の影が日に日に大きくなり、幕府が危機感を持っていた時代の事件・・・いわゆる「黒船襲来」です。未曽有の国難と察した幕府の老中・阿部正弘が、朝廷から外様大名まで幅広く意見を求めたことで、日本国内が開国、攘夷とヒートアップしていくのですが、一方で阿部は国難を乗り切るため、家柄に関係なく優秀な人材の登用にも力を入れていました。
水野忠徳、岩瀬忠震、小栗忠順は、そうした人材たちだったのです。
三俊の一人目「水野忠徳」
3人のなかで最も年長なのが水野忠徳です。忠徳は文化12年(1815)の生まれで、ペリー来航時には長崎奉行を務めていました。長崎には出島があり、海外と唯一交易が行われていたところ。海外の事情に通じた有能な人物でなければ務まらない職務と言えます。
忠徳は、日米に続いてイギリスとの日英和親条約の締結に調印したほか、オランダの海軍軍人からの提言を受け、幕府に軍艦の購入や海軍教育機関設置のお伺いを立てました。これが幕府海軍の前身である長崎海軍伝習のスタートとなります。
文久元年(1861)に忠徳は外国奉行として小笠原諸島へ派遣され、日本の領有を宣言するという役目を果たしました。
三俊の二人目「岩瀬忠震」
続いては岩瀬忠震(ただなり)です。忠震は文政元年(1818)生まれの幕府官僚で、阿部正弘の抜擢によって目付となり、日米和親条約締結後は外交官として諸外国との対外交渉にあたります。

安政3年(1856)にアメリカ領事のハリスが来航し、通商条約の締結を求めてきました。外交官である忠震は交渉の窓口に立っただけでなく、朝廷への勅許を得るために老中の堀田正睦に随行するなど、重要な任務を担っていました。
当時イギリスやフランスが日本へ連合艦隊を仕向けて交易を迫るとの情報があり、交渉役の忠震と井上清直は一刻を争うと判断し、勅許なしで日米修好通商条約の調印に踏み切ったとされています。
三俊の三人目「小栗忠順」
最後は小栗忠順(ただまさ)です。忠順は文政10年(1827)の生まれ。目付に就任後、日米修好通商条約の批准交換使節の一員としてアメリカに渡り、見聞を深めてきました。

帰国後に外国奉行になりますが長続きせず、以後も勘定奉行や軍艦奉行などの要職に抜擢されては辞職を繰り返しています。裏を返せば、何度も要職に就けるだけの才覚を持っていたということにもなるわけです。
忠順は、幕府の軍事力強化が必要だとして、フランスの支援を受けて横須賀製鉄所の建設や軍制改革に着手します。しかし、慶応3年(1867)に徳川慶喜が大政奉還し、王政復古のクーデターによって、忠順の施策は道半ばで終わってしまいました。
おわりに
幕末という困難な時代に、幕府の官僚として幕政を担ってきた幕末三俊でしたが、岩瀬忠震は文久元年(1861)に病没し、慶応4年・明治元年(1868)には小栗忠順が新政府軍によって処刑され、引退していた水野忠徳も亡くなりました。3人が明治という新時代にその才覚を発揮することは、かなわなかったのです。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。


コメント欄