幕末の女傑と呼ばれた女性・村岡局の真の姿とは
- 2025/03/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
幕末といえば、若き尊攘志士や新選組達の命がけの活躍、坂本龍馬や西郷隆盛らの東奔西走する姿が思い浮かぶ人が多いだろう。しかし命の危険を顧みずに彼らを支えた多くの支援者も忘れてはならない。彼らを助けた人々の中には、女性の姿も少なくない。中でも齢70歳を超えながら、精力的に尊攘派をサポートし、勤王女傑とも呼ばれたのが村岡局(むらおかの つぼね)だ。
西郷や梅田雲浜らと連携しながら尊王攘夷運動を支えた村岡局であったが、安政の大獄で処罰されたのちはそれまでのエネルギッシュな行動とは全くかけ離れた静かな隠遁生活を送っている。いったいどちらが彼女の本当なのか、村岡局とはどのような女性だったのだろうか。今回は女傑と呼ばれた村岡局の本当を探ってみたい。
西郷や梅田雲浜らと連携しながら尊王攘夷運動を支えた村岡局であったが、安政の大獄で処罰されたのちはそれまでのエネルギッシュな行動とは全くかけ離れた静かな隠遁生活を送っている。いったいどちらが彼女の本当なのか、村岡局とはどのような女性だったのだろうか。今回は女傑と呼ばれた村岡局の本当を探ってみたい。
陽明家の清少納言
京の西北・北嵯峨で、村岡局は代々大覚寺門跡の家士を勤めていた津崎家の娘として生まれた。生年は天明6年(1786)、幼名は梅、のちに矩子(のりこ)といった。幼い頃の矩子に関するエピソードが残っている。利発な少女・矩子
近衛家の老女が嵯峨野(京都府京都市右京区)へいったときのこと。大覚寺の土塀脇で子守娘に百人一首を教えている少女に出会った。その様子を見ていた老女は少女の利発さに感心し、主家である近衛家に推薦し、少女は侍女として近衛家に入ることになった。この少女が矩子、のちの村岡局であったと伝わっているのである。「幼年より事理にさとい」といわれた彼女らしい話である。
矩子が実際に近衛家に仕え始めたのは、12~13歳の頃だといわれている。近衛家は五摂家の筆頭で、三条家や鷹司家と共に反幕府派の公家であった。
篤姫の養母として大奥へ
やがて、22歳年下の近衛忠熈(このえ ただひろ)に仕えた矩子は、順調に出世し、老女となって村岡を名乗る。天保11年(1840)には、55歳になった村岡が近衛家名代として江戸へ下向している。この時には100人を超える人物と面会し、近衛家の外交役として活躍した。村岡にとって大きな転機となったのは、安政3年(1856)である。第14代将軍・徳川家定への輿入れに際し、島津家の篤姫は近衛忠熈の養女となった。しかし忠熈の正室であり薩摩島津藩の出身の郁姫はすでに亡き人であったため、村岡が篤姫の養母格となったのである。71歳となっていた村岡は、篤姫と共に江戸へ下向した。
将軍継嗣問題で活躍
篤姫が家定に輿入れした大きな理由として、将軍継嗣問題があった。家定の後継ぎをだれにするかで、幕府内は2つに分かれていた。前水戸藩藩主・徳川斉昭の子であり一橋徳川家当主の一橋慶喜(のちの15代将軍徳川慶喜)を推す一橋派と、紀州徳川家藩主の徳川慶福(よしとみ:のちの14代将軍徳川家茂)を推す大老・井伊直弼を筆頭とした南紀派である。(以下参考)
◆ 南紀派(徳川慶福を支持)
- 井伊直弼(大老)
- 平岡道弘(御側御用取次)
- 薬師寺元真(御側御用取次)
- 松平容保(会津藩主)
- 松平頼胤(高松藩主)
- 水野忠央(紀伊新宮藩主)
など…
VS
◆ 一橋派(一橋慶喜を支持)
- 徳川斉昭(前水戸藩主)
- 徳川慶勝(尾張藩主)
- 松平慶永(越前藩主)
- 島津斉彬(薩摩藩主)
- 伊達宗城(宇和島藩主)
- 堀田正睦(老中、佐倉藩主)
など…
一橋派を指示していた島津斉彬は、大奥からの一橋派へのサポートを期待して篤姫を輿入れさせたのだ。その養母格である村岡も、篤姫・幾島(篤姫付のお年寄り)・西郷隆盛・月照(尊攘派の清水寺成就院僧侶)・梅田雲浜らとともに動いていた。しかし結果はご存じの通り、後継となったのは南紀派が推していた慶福だった。
尊攘派への援助
将軍継嗣問題だけでなく、村岡は日米修好通商条約調印をめぐっても活躍している。朝廷の勅許を得ないまま条約に調印した井伊直弼に対し、朝廷や薩摩藩をはじめとする勤王派が反撃を企てていた。その中で村岡は近衛家と勤王派を繋げる重要な役割を担う。梅田雲浜は、村岡を称して「陽明家(近衛家)の清少納言」とし、水戸藩の鵜飼吉左衛門らからの信頼も篤かった。西郷の手紙を主人の忠熈に取り次いだり、月照らの近衛家出入りを支援したり、村岡は密かに尊攘派の活動を援助した。
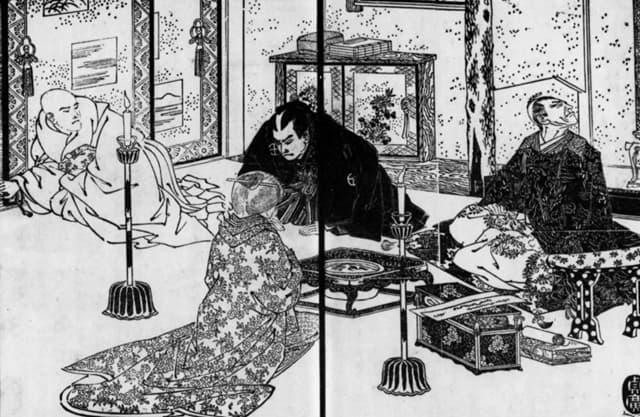
安政の大獄で入牢
事態が大きく動いたのは安政5年(1858)に始まった安政の大獄である。井伊直弼は、将軍継嗣問題で一橋派についていた大名や藩士を中心に、幕府の方針に反対する者たちを次々に捕縛していった。その数百人あまり。鵜飼吉左衛門・水戸藩家老の安島帯刀・長州藩士の吉田松陰・福井藩士の橋本左内・頼三樹三郎らが死罪や獄門に処せられ、梅田雲浜は獄死した。安政の大獄の苦難は、村岡の身にも降りかかる。

安政6年(1859)正月、村岡は京の町奉行所への出頭を命じられる。厳しい取調のあと江戸へ送られた村岡は、松平丹波守光則邸へのお預けとなった。
破格の待遇
丹波守邸でも継続して取り調べが行われたのだが、なにしろ今は亡き家定の正室、大奥を統べている天璋院の養母である。普通の囚人のようには扱えるわけがない。3度の食事は二汁五菜、昼八つ(午後2時ごろ)にはお茶と菓子が出され、衣服は7日ごとに羽二重を新調するといった具合で、まさに至れり尽くせりだ。その上、天璋院から賜った三つ葉葵の打掛をまとって出頭されては、取り調べる方も困ってしまう。
結局、村岡は30日の押込という非常に軽い刑が言い渡された。信濃松本藩の松平家お預けとなったが、押込期間も来客や入浴も自由、『古今集』などの講義を受けるなど、破格の待遇であったという。
そして、同年9月、村岡は再び江戸へ呼び出されて訊問を受けたあとに放免された。
京嵯峨の庵へ
京へ戻った村岡は、生まれ故郷の嵯峨へ向かう。彼女がその身を落ち着けたのは、直指庵(じきしあん)であった。※参考:直指庵HP
晩年を過ごした直指庵
直指庵は大覚寺の北、竹林に囲まれた静かな地に建っている。現在は紅葉の名所として知られ、女性の駆け込み寺としても有名である。そのため、一部の人には尼寺と勘違いされていたこともあるが、それは誤解。正保3年(1646)に黄檗宗の独照禅師が創建したが、寺名は付けられていなかった。時が流れ、村岡が隠遁地として選んだ際に再興され「直指庵」と命名された。以後は浄土宗の寺院となる。
境内には村岡自筆の「津崎氏村岡矩子之墓」と刻まれた墓がある。
余生は静かに
村岡が直指庵へ移り住んだあとも、彼女のもとにやって来る志士は少なくなかった。文久2年(1862)の春には、九州の勤王女性として知られている野村望東尼(ぼうとうに)が庵を訪ねたが、村岡は障子越しにわずかな言葉を交えただけだったという。文久3年には再び幕府に捕らえられたこともあったが、その後も静かに過ごしていたようだ。村岡が詠んだ歌に次のようなものがある。
「雨あられ 激しく降れど 軒深き わが家はそれと 聞こえざりけり」
激動の嵐が吹き荒れている世情ではあるが、隠遁者として仏道を歩む者として生きていく私には(嵐のような彼らの声は)何も聞こえてこない、というほどの意味だろうか。
晩年は、焚き物として木を燃やすことも殺生になると避けていたそうだ。その代わりに村の子供たちが拾ってきたマツカサをくべていたという。
烈女・村岡の最期
明治6年(1873)8月23日。村岡は、嵯峨直指庵で88歳の生涯を静かに閉じた。たまたま反幕府派・尊攘派の近衛家に仕え、たまたま篤姫の養母となり、たまたま時代の激動に飛び込んでしまい、主人や篤姫のために懸命に働いた結果が勤王烈女としての村岡という女性を生み出した。
尊攘派を支えた女傑村岡は、本当は穏やかな人生を望んでいた心根の優しい女性だったのではないだろうか。その晩年こそが村岡こと津崎矩子の真の姿だったのだと、私は思う。
あとがき
幕末はもちろん、歴史上に残る有名な人々の後ろには多くの支援者が存在している。その中には彼らの妻や恋人、愛人、母などもいただろう。今回紹介した村岡はそのどれにも当たらないが、彼女もやはり志士たちを支えた女性の1人であった。ひたすらに主人に仕え、思いがけず縁が出来た篤姫こと天璋院に協力することで、村岡は自身の知らないところで、勝手に勤王烈女や女傑などといった呼び名が付けられていた。それは、村岡にとってはあまりうれしいことではなかったのかもしれない。だが、彼女が親しく接してきた若者たちに対する愛情は、変わらなかっただろう。
政争から遠く離れた直指庵で、村岡はただの矩子に戻った。そして幕末の動乱に命を散らしていった彼らを偲び、弔う1人の尼僧として生きた。
【主な参考文献】
- 京都新聞社編集『おんなの史跡を歩く』(京都新聞企画事業、2000年)
- 堀野廣『京に燃えたおんな』(京都新聞企画事業、2004年)
- 大石学監修『幕末の1000人』(世界文化社、2009年)




コメント欄