武田騎馬隊も信長も家康もポニー?…戦国武将の馬は意外に小さかった
- 2025/09/17
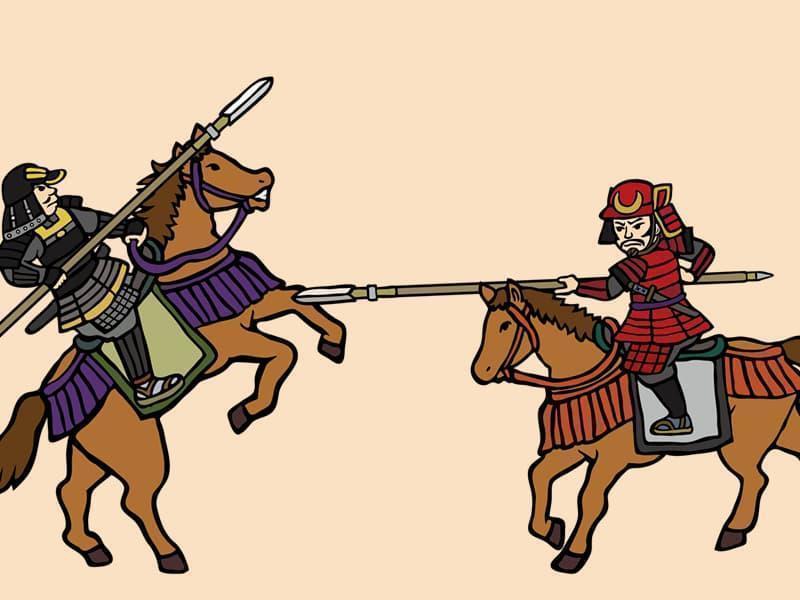
今回は、馬を愛した戦国武将たちのユニークなエピソードを紐解きながら、合戦で活躍した名馬の知られざるルーツを辿っていきます。
戦国時代の騎馬のルーツは長野産の木曽馬
大河ドラマの合戦シーンに登場するのは、アニマルアクターのサラブレッド。しかし、その馬たちは明治以降に欧米から輸入された種であり、戦国時代の日本には存在しませんでした。私たちが時代劇で見慣れた馬は、実はフィクションの産物だったのです。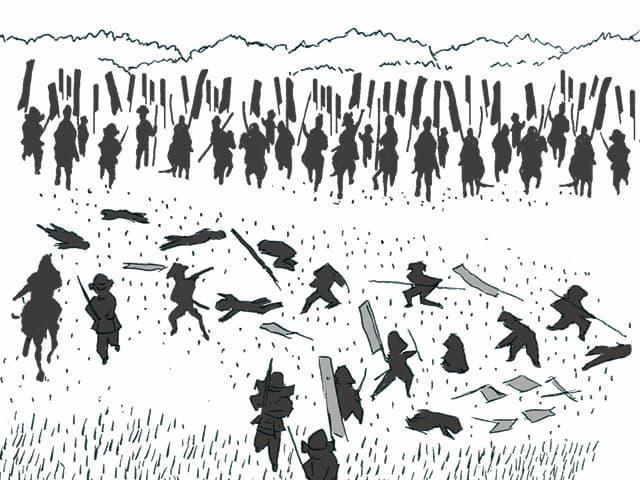
では、当時の人々はどんな馬を使っていたのでしょうか?答えはポニー。ですが現在の牧場で飼われる愛玩用ポニーとは明確に異なる、日本の在来種でした。
当時の馬は、合戦に出す騎馬や、田畑を耕す家畜として育てられました。代表的なのは長野県に生息する木曽馬です。人懐こく従順な性質を持ち、繁殖と調教に向いています。

木曽馬は古墳時代に朝鮮半島を経由して持ち込まれた在来種です。小柄で寸胴な見た目に似合わぬ馬力の持ち主で、甲冑姿の武将を乗せ、峠越えも余裕だったと言われています。その代わり、時速20~30キロと脚力はサラブレッドに劣る点はご愛嬌でしょうか。
その他に愛媛県の野間馬、宮崎県の御崎馬なども有名です。在来馬の体高は平均147センチ以下なので、当時の騎馬は全てポニーであったと断定できます。
戦国時代一の馬好き・織田信長が愛した名馬たち
人馬一体となり戦場に臨む時代、馬を愛する戦国武将は枚挙にいとまがありません。その代表格が、天下布武を掲げた織田信長。彼が手に入れた馬は生涯で三桁を超えました。若い頃から馬に親しんだ信長は、安土城や岐阜城の敷地内に広い馬場を備え、常に騎馬の訓練を怠りませんでした。厩を視察した宣教師は、その清潔さと手厚い飼育に驚いたそうです。

信長の馬好きは全国的に知られていたため、諸国の大名が良馬を贈りました。伊達家から献上された奥州の名馬、白石鹿毛やがんぜき黒もその中に含まれます。
天正9年(1581)、信長は「京都御馬揃え」と呼ばれる大規模な軍事パレードを主催しました。これは一番部隊から十一番部隊に分け、内裏東を行進しながら名馬を披露するもので、信長の腹心だけでなく、室町幕府の幕臣や有力な公家衆も参加しました。番号が若いほど家格が上がるらしく、一番部隊には丹羽長秀が配属されています。
パレードの主旨は騎馬武者の雄々しさや馬の優劣を競うことで、この翌年に本能寺で主君を討つ明智光秀も、威風堂々と加わっていました。正親町天皇まで貴賓席に座したというのですから、主催者の大胆さには驚きます。
信長がこのパレードに出した馬は鬼葦毛、小鹿毛、遠江鹿毛、小雲雀、大鹿毛、河原毛など。信長自身は大黒と名付けた馬に跨り、豪華絢爛な唐織物と小袖をまとっていました。まるで仮装大会のようですね。
馬好きのエピソードは家臣たちも負けていません。特に徳川家康は乗馬の達人として名高く、古流馬術「大坪流」を学び、「海道一の馬乗り」と称賛されました。彼の愛馬は白石。名前とは裏腹に、体色は漆黒だったというから意味深です。厩の建て替えの際に最低限の修繕しか施さなかった理由を問われると、「過保護にされた馬は長旅で病に倒れる」と答えました。信長とは対照的です。
豊臣秀吉はもともと信長の馬廻りを務めていました。しかし彼自身は馬を持たない足軽だったため、美濃国へ赴く際に、母方の伯父である焼き物商人に馬を貸してくれないかと頼みに行きます。最大の誤算は、伯父が武家奉公に反対していたこと。「他を当たれ」とすげなく断られ、義兄に泣きついてどうにか馬を借りた苦労話が残っています。
そんな秀吉が出世後に手に入れたのが、早駆けに優れた奥州驪です。林長兵衛尉に宛てた朱印状も残されており、陣中見舞いで馬の沓を10足もらったことを感謝していました。天正15年(1587)には、戦場へ向かう途中で愛馬村雨が力尽き、泣く泣く別の馬に乗り換えて再出発。村雨が葬られた場所には「馬之神(うまのかみ)」を祀る祠が建ち、現在は氷川町の指定文化財となっています。
戦国最強・武田騎馬隊の活躍
戦国最強の騎馬といえば、武田騎馬隊に触れないわけにはいきません。甲斐の武将、武田信玄の愛馬黒雲は大変な暴れん坊で、主以外は決して背に乗せませんでした。父の信虎も馬好きとして知られ、彼の愛馬鬼鹿毛を若き信玄が欲しがって断られた一件が、のちに信虎を追放する確執に繋がったのでは、と憶測を呼んでいます。もとより甲斐は良馬の産地であり、信玄は幼い頃から馬を見る目を養っていました。武田二十四将と呼ばれる家臣たちも馬をよく乗りこなし、永禄12年(1569)の三増峠の戦いでは、側面からの奇襲攻撃で北条氏康軍を突き崩しています。これは重臣・山県昌景が率いる精鋭騎馬部隊「赤備え」の手柄でした。
元亀3年(1573)の三方ヶ原の戦いでは、徳川軍を圧倒しています。信玄は騎馬の機動性を理解し、別動隊に挟撃を指示することで、巧みに敵軍の死角を突きました。その戦略の見事さには舌を巻きます。
しかし、信玄亡き後の天正3年(1575)長篠合戦では、武田勝頼軍と織田・徳川連合軍が激突。数々の戦を制して無敵と恐れられた武田騎馬隊は、信長の馬防柵と鉄砲隊、攻防一体の布陣の前に敗れ去ってしまいました。

おわりに
以上、戦国武将が愛した名馬たちのエピソードと馬のルーツを解説しました。余談ですが、信長が京都御馬揃えに出した小雲雀は、家臣の蒲生氏郷に下賜されたそうです。一歩間違えば本能寺の変に巻き込まれていたかもしれないと考えると、何が幸運に働くかわかりませんね。その後の詳細な記録は残っていませんが、平和な余生を送れたことを願ってやみません。
【参考文献】
- 蒲池明弘『「馬」が動かした日本史』(文藝春秋、2020年)
- 岩﨑正吾『武田信玄はどこから来たか』(山梨ふるさと文庫、2017年)
- 武田鏡村『織田信長はなぜ「天才」と言われるのか』(三笠書房、2011年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。




コメント欄