織田信長と足利義昭の微妙な政治関係 「殿中掟九ヵ条」が示す信長の幕府観
- 2025/08/15
渡邊大門
:歴史学者
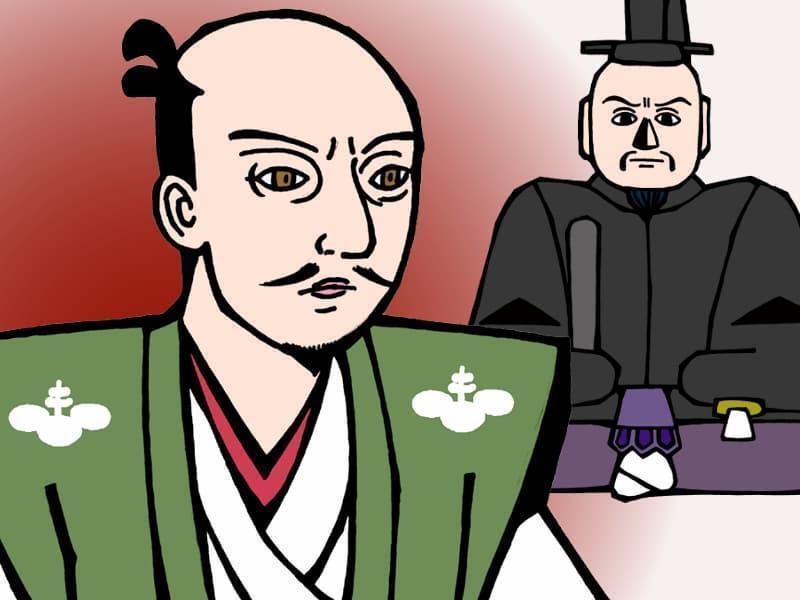
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
信長に擦り寄る義昭
永禄11年(1567)10月、足利義昭は織田信長の助力により上洛を果たし、室町幕府を再興できたので、お礼の意味を込めて管領に任命しようとした。おそらく義昭は、信長を手なずけようと考えたのだろうが、それは見事に失敗した。以後も義昭は、何かと信長の気を引こうとした。ほぼ同じ頃、義昭は信長が敵対する三好三人衆らに勝利したので、尽力した礼を述べるために感状を送り、その武功を「武勇天下第一」と称えた(『信長公記』)。感状の宛先には「御父織田弾正忠殿」と書かれていたので、義昭は信長の武功を最大限に評価するだけでなく父のように慕った様子がうかがえる。
加えて義昭は、信長の「大忠」に報いるため、本来は将軍家が用いる桐紋と二引両の紋を下賜した。この点について太田牛一(『信長公記』の著者)は、「前代未聞の名誉なことであり、この上もなく喜ばしく、言葉にすらできない」と記しているので、信長にとっても喜ばしいことだったことがうかがえる。
あわせて読みたい
義昭の信長に対する厚遇は、それだけに留まらなかった。義昭は、信長に管領家の斯波氏の名跡を継がせようとし、信長を足利氏の一門に加えようとしたのである(「古今消息集」)。義昭は滅亡した斯波氏の名跡を信長に継がせることによって、配下に収めたかったのではないだろうか。
参考にすぎないが、二次史料の『足利季世記』や『重編応仁記』によると、義昭は信長に兵衛佐の官途や近江など五ヵ国を与えようとしたというが、おそらく実現しなかったと考えられる
すべてを辞退した信長
義昭は信長に3通の御内書(将軍の手紙)を送ったが、うち1通に書かれた申し出(斯波氏の名跡を引き継ぐこと。下記の3)は辞退されたと伝わる。3通の御内書の内容は、以下のとおりである。- (1)信長の武功を称えたもの
- (2)足利家の家紋の使用を許可したもの
- (3)斯波氏の名跡の継承を許可したもの
信長は「斯波氏の名跡の継承は家の名誉ですが、私はもともと陪臣の家の出なので、拝受するのは恐れ多いことでございます」という理由で辞退したという(『重編応仁記』)。二次史料に書かれたことであるが、実際に信長は斯波氏の名跡を継承していないので、史実と考えて差し支えないだろう。
信長が斯波氏の名跡の継承を辞退した理由は、足利氏一族の管領・斯波氏の名跡を継ぐのは名誉であるが、将軍配下の副将軍や管領という立場になってしまうことだった。つまり、信長は義昭の配下に収まることを嫌い、辞退した可能性があろう。それは、義昭が信長に斯波氏の名跡を継がせようとした際、辞退したのと同じ理屈である。
信長は義昭を支えること自体は何の問題もないが、室町幕府の秩序に組み込まれ、義昭の配下になることは避けていた。信長は自身の軍事力などが強力であることに自信を持っていたので、将軍の義昭という権威はさほど重要視していなかったようだ。逆に、義昭が信長を配下に収めようとしたのは、将軍には直属の軍隊がなかったので、信長を頼らざるを得なかったという事情があった。
信長の「殿中掟九ヵ条」
上洛以後、信長と義昭は良好な関係を保っていた。永禄12年(1568)1月に信長が「殿中掟九ヵ条」と追加の「七ヵ条」を定めると、義昭との間に確執が生じたといわれている。「殿中掟九ヵ条」などには、いったい何が書かれていたのだろうか。「殿中掟九ヵ条」の前半の4ヵ条には、室町幕府の再興に際しての措置が書かれている。御部屋衆などの仕官、公家衆などの参勤、惣番衆などの伺候が再開されたので、そうした人々の勤務体制について先例を守るよう指示した。信長は積極的に室町幕府を支援したので、その存在を否定したわけではない。
後半の4ヵ条は、室町幕府の訴訟・裁判にかかわる条文であり、幕府が公正・公平な裁判を執り行うための規定(以下)だった。
- (1)裁判を内々に将軍に訴えること(直訴)の禁止
- (2)奉行衆の意見を尊重すること
- (3)裁判の日をあらかじめ定めておくこと
- (4)申次の当番を差し置いて、別人に披露することがないこと
最後の9条目は、門跡などが妄りに伺候することを制約したものである。
追加の「七ヵ条」もまた室町幕府の訴訟・裁判に関するもので、「殿中掟九ヵ条」の後半の4ヵ条の補足的な意味合いがあり、裁判を起こす者は奉行人を通すこと、あるいは直訴の禁止などが規定されている。
もっとも注目されるのは、第1条と第7条である。第1条は、寺社本所領の当知行(現実に当該地を知行している状態)安堵の原則を規定したものである。第7条は義昭が当知行を安堵する場合は、安堵の対象者に当知行が虚偽でない旨の請文を提出させることを定めたものである。
「殿中掟九ヵ条」の評価
最近の研究によると、「殿中掟九ヵ条」と追加の「七ヵ条」は特に目新しいものではないと指摘されている。すでに、それらは室町幕府で規定された基本的な事項にすぎず、信長はそれを再確認し、室町幕府に京都や畿内の秩序維持を期待したとされる。信長が室町幕府―守護体制の再構築、あるいは公武統一政権の可能性を模索したとは考えられない。信長は旧来の室町幕府のシステムをそのまま復活させようとしたのであって、もちろん幕府を滅ぼそうとしたわけではない。
信長は将軍配下の副将軍や管領になるつもりもなく、また自らが将軍になるつもりもなかった。室町幕府を温存した体制を志向し、京都や畿内の秩序維持の枠組みを再興しようとしたのである。
まとめ
かつて、信長が足利義昭を推戴して上洛したのは、義昭を傀儡として裏で糸を引き、頃合いを見て室町幕府を滅亡させる計画だったと指摘された。しかし、信長の軍事力をもってすれば、室町幕府を滅ぼすことなどたやすいことなので疑わしい。最近の研究によると、信長が義昭を傀儡にする意図もなく、ましてや室町幕府を滅亡させる気はなかったという。むしろ信長は、義昭や幕府の最大の庇護者だったのである。

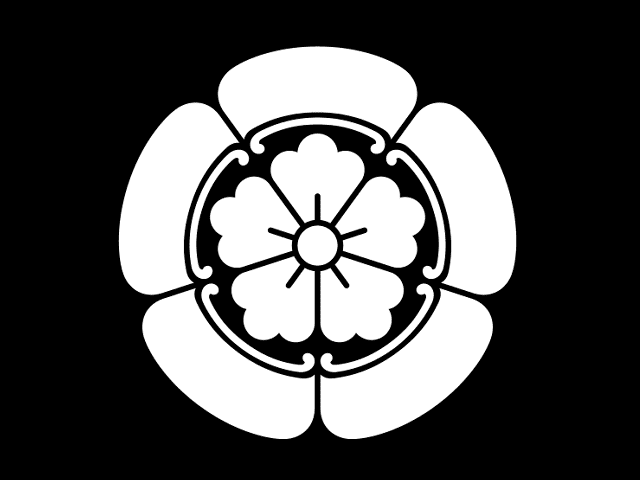



コメント欄