「お初(常高院)」豊臣と徳川の和議に尽力した浅井三姉妹の次女!
- 2021/02/10

あまた存在した武将たちの、男同士の戦いや生きざまを思い描く戦国時代。しかし戦国の世は、男性だけでなく女性たちにとっても命がけの日々であり、過酷な運命に敢然と立ち向かっていった人々がいました。
戦国当時の女性の記録は、一般庶民はおろか、高貴な出自であっても残りにくいものでしたが、特殊な事績を残した女性は例外的に多くの史料が残される場合もあります。そんな戦国の姫の一人が、浅井三姉妹の次女で知られる「お初」です。
激動の時代を生き抜き、その歴史を見届けた初姫はどのような人生を送ったのでしょうか。今回は、お初の生涯について概観してみることにしましょう!
戦国当時の女性の記録は、一般庶民はおろか、高貴な出自であっても残りにくいものでしたが、特殊な事績を残した女性は例外的に多くの史料が残される場合もあります。そんな戦国の姫の一人が、浅井三姉妹の次女で知られる「お初」です。
激動の時代を生き抜き、その歴史を見届けた初姫はどのような人生を送ったのでしょうか。今回は、お初の生涯について概観してみることにしましょう!
浅井三姉妹の次女
お初は北近江の戦国大名・浅井長政と、織田信長の妹で知られるお市の方との間に永禄13年(1570)に生まれたと推定されています。本来の名前は「浅井 初」。一般的には「お初」や「初姫」などと呼ばれ、幼名は「御鐺(おなべ)」や「於那」といいました。姉には茶々、妹には江(ごう)がいます。お初はいわゆる浅井三姉妹の次女ですが、この他に万福丸や万菊丸と、兄弟もいました。

戦国の世で父母を失う
父長政と信長は同盟関係にありましたが、信長が浅井氏の盟友である越前朝倉氏を攻撃したことをきっかけに浅井と織田の両家は対立関係となります。そして天正元年(1573)、浅井氏の居城である小谷城は信長の攻撃を受けて落城。お初は、父長政と祖父久政が自害するという、憂き目にあいます。ただ、このとき母のお市と三姉妹たちは織田氏家臣の「藤掛永勝」に救出されて落ち延びています。その後、母娘は織田家の縁者のもとに身を寄せたとされていますが、天正2年(1574)以降に信長のいる岐阜へと移ったと考えられています。
天正10年(1582)に本能寺の変で信長が倒れると、同年同月にその後継をめぐる「清洲会議」が開かれます。その席で、お市の方は織田家重臣の「柴田勝家」に再嫁することが決定したため、越前国(現在の福井県あたり)北ノ庄城へと母娘は移転します。
わずかな結婚生活ではありましたが、勝家とお市の仲はむつまじかったとされ、翌年に「羽柴秀吉」と対立して北ノ庄城が落城した際には、お市は勝家と運命を共にする道を選びました。
浅井三姉妹を保護したのは仇である羽柴秀吉で、その後は信長次男の「織田信雄」が後見になったという説もあります。
京極家に嫁ぐ
天正15年(1587)、成長したお初は秀吉の計らいにより、浅井家の旧主筋である京極家の当主で従兄にもあたる「京極高次」に嫁ぐこととなりました。余談ではありますが、この高次の時代には京極氏の力はすでに衰退しており、下剋上で台頭した浅井氏の方がはるかに強大な勢力をもっていました。高次も浅井氏の居城で生まれたとされ、のちに妹の「竜子」は秀吉の側室となっています。
お初との結婚にしても長姉の「茶々」が同じく秀吉の側室であり、政権に近しい位置であったことから妻や肉親の縁故で出世した「蛍大名」と陰口をたたかれたといいます。
しかし慶長5年(1600)に勃発した関ケ原の戦いの前哨戦「大津城の戦い」においては、居城の大津城に籠城して1万人以上もの西軍を足止め。関ケ原主戦場への進軍を阻止するという優れた武将でもありました。高次はこの功により若狭小浜藩初代藩主となり、お初は国持ち大名の妻となったのでした。
大坂の陣で「徳川vs豊臣」の和議に尽力
しかし慶長14年(1609)、高次は46歳で死去。お初は出家し、「常高院」の号を名乗りました。この頃には豊臣方と徳川方の対立が激化しており、お初は両者の対決を回避するため豊臣方の使者として仲介に尽力することになります。豊臣の長・「豊臣秀頼」の母はお初の姉、「茶々」でした。そして、家康の後継者である「徳川秀忠」の正室・「お江の方」は妹にあたります。
このように浅井三姉妹は東西の陣営に分かれてしまい、両者が一触即発の危険な状態に置かれていたのです。
慶長19年(1614)の大坂冬の陣では家康の側室・「阿茶局」とともに和議を推進し、戦後処理に力を尽くしました。翌年の夏の陣で豊臣家は滅亡しますが、お初は生き延び、度々妹のお江と会うことがあったといいます。
お初は夫の高次との間に子はできなかったものの、側室との間に生まれた「京極忠高」が若狭一国とそのほかの領地を継承し、近世大名として京極氏の命脈が保たれることになります。
寛永10年(1633)、お初は忠高の江戸屋敷においてその生涯を閉じました。生年が定かではないため行年は64歳とも66歳ともいわれますが、遺命によって夫・高次の菩提を弔うために建立した若狭国・常高寺に葬られました。
おわりに
戦国時代の女性たちにフォーカスした論文や作品が増えてきた感がありますが、なかでも浅井三姉妹の生涯は戦国の終焉を象徴するかのような劇的なものでした。一度ならず父と居城を失い、姉妹が天下分け目の両陣営に分かれて戦わなくてはならないという悲運など、戦国の姫が直面した過酷な生を示しています。
お初たちだけではなく、当時を生きた記録には残らない多くの女性たちもまた、同様の運命と戦ったのでしょう。戦国史をひもとくとき、そんな人々に思いをいたすのもまた必要なことではないでしょうか。
【主な参考文献】
- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館
- 『日本大百科事典』(ジャパンナレッジ版) 小学館
- 若狭小浜のデジタル文化財 常高寺
この記事を書いた人
古代史・戦国史・幕末史を得意とし、武道・武術の経験から刀剣解説や幕末の剣術についての考察記事を中心に執筆。 全国の史跡を訪ねることも多いため、歴史を題材にした旅行記事も書く。
「帯刀古禄」名義で歴史小説、「三條すずしろ」名義でWEB小説をそれぞれ執筆。 活動記録や記事を公開した「すずしろブログ」を ...
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



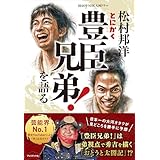
コメント欄