【麒麟がくる】第36回「訣別」レビューと解説
- 2020/12/15

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
虫のたとえが多い作品ですが、今回は鳥でした。帝にとっては「珍しい鳥」、将軍にとっては「籠から出た鳥」である光秀。信長と義昭(幕府)のパイプ役として働いてきた光秀は、ついに幕府から離反することになりました。
「尋胡隠君(胡隠君を尋ぬ)」
三条西実澄のお供として御所を訪れた光秀。光秀の立場で帝と対面することはできませんから、ただ中から聞こえてくる声に耳を傾けるばかりです。「渡水復渡水(水を渡り復た水を渡り)
看花還看花(花を看還た花を看る)
春風江上路(春風江上の路)
不覺到君家(覺えず君が家に到る)」
聞こえてくるのは、明代初期の詩人・高啓の詩「尋胡隠君」です。幼いころから神童と呼ばれ、詩文の才があった人で、明代第一と名高い詩人です。
独裁者として知られる明の初代皇帝・太祖(朱元璋/洪武帝)の文人弾圧の犠牲者のひとりで、太祖を風刺する詩(皇帝の好色ぶりを詠んだ)を詠んだこと、そして友人の罪に連座して腰斬の刑に処されて亡くなっています。
高啓のこの詩は、隠者となった友人の胡氏を訪ねた時のもので、のどかでゆったりとした穏やかな詩です。人は水の流れや花を見る時無心に時を過ごす。帝はこの詩のごとく日々を生きたいと光秀に文をやります。
が、そういう穏やかな世をめざす光秀は迷いばかりの路に苦しんでいて、帝もまた迷う。それでも「迷わずに歩もうではないか」と答えます。
迷うのに、迷わずに歩もうという……。ん?と思ってしまいますが、帝は相手がほしい言葉をくれるんですよね。信長を褒めてやったことにしても。
帝も迷うというのは本心なのでしょうが、それはそれとして、何が一番大事なのかわかっている人です。だから迷いながらも、正しいと思う道を歩んでいける。あの言葉にはそういう意味があるのではないでしょうか。光秀もまた、理想と現実に悩みながらも、選ぶべき路を選べる人です。
佐久間信盛
帝と言葉を交わしたことに感激しながら帰宅した光秀。屋敷には、木下藤吉郎、柴田勝家、佐久間信盛の信長家臣3人が訪ねてきていました。藤吉郎は、ほかのふたりに向かって「信長におもねりすぎる」と苦言を呈します。不満や意見があっても誰も何も言えない。帰る直前、佐久間信盛は光秀に「此度の戦も明智殿の思うところを殿に直言していただきたい」と言います。
比叡山焼き討ちの時、皆殺しにしろという信長の命令に対し、後から女子どもを助けたことを報告した光秀に期待してるよ、というわけです。直属の家臣すら直言できない状況……。この時点で光秀はどちらかといえば幕府の人間なのですが、外の者に頼るしかないというのはよくない状況ですね。
この信盛は、のちに本願寺との戦いで何の功績も挙げなかったことで折檻状を突き付けられ、追放されてしまいます。
『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』
帝と言葉を交わして、信長が帝を敬う気持ちが少しわかったと言う光秀。武士ならば武家の棟梁たる将軍のもとで世を平らかにするため働くべきと考えていたが、信長はもはやそうは考えていないのかもしれないと気づきます。またひとつ信長を理解し、妻子を人質にとるという義昭に不満をもらす光秀。光秀は京に妻子を留め置くつもりはさらさらなく、湖上で子どもらに古歌を教えたいと語ります。
「月は船星は白波雲は海 いかに漕ぐらん桂男はただ一人して」(梁塵秘抄・二句神歌・450)
光秀と煕子が口ずさんだ歌は、平安末期に編纂された『梁塵秘抄』の歌のひとつ。今様(いまよう)を好んだ後白河法皇によって編まれた歌集です。
「月は船、星は白波、雲は海。さて、その中でどのように漕ぐのやら。船頭の桂男はたった一人で」
桂男というのは、古代中国の伝承で、月に住むという男のこと。また、美男子のことでもあります。この歌は、『万葉集』にある柿本人麻呂の歌「天の海に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ」(万葉集・雑・1068)の比喩表現を用いた歌では、と言われます。ここでもまた人麻呂。
近江は美濃と京のちょうど中間あたりでしょうかと言う煕子に「どちらに心引かれておられますか」と問われ、「どちらも大事なのだ、どちらも」「今のままでは済まぬやもしれぬ」と、迷いを見せつつ、光秀が決断する前に事が動き始めていることに苦しんでいます。
十七カ条の異見書にちょっと後悔
信長は義昭の求めにより、松永久秀を敵に回すことに。本人は松永討伐に積極的ではないものの、これで有力な味方をひとり失いました。一方、甲斐では、義昭の再三の要請により武田信玄が上洛の動きを見せていて……。信長は武田に負けて義昭に耳と鼻を削がれ五条河原に晒されそうになる夢まで見るように。
義昭の行い17例を挙げて諫めた「十七カ条の異見書(意見書)」と呼ばれる文を義昭に送りつけた信長は、いささか遠慮が足りなかったと後悔しているようで、ご機嫌とりに鵠(くぐい/白鳥)を送ると言います。
鵠(白鳥)で機嫌をとろうというと、『史記』「陳渉世家」の「燕雀(えんじゃく)安くんぞ鴻鵠の志を知らんや」でしょうか。燕や雀のような小鳥には、鴻(おおとり)や鵠(白鳥、またはコウノトリ)のような大きな鳥の志はわからない。つまり、小物に大人物の志はわかりません、という意味です。ここでは小物=信長、大人物=義昭とするのでしょうか。
そんな信長のもとに、三方ヶ原の戦いでの徳川軍大敗の報せが入ります。朝倉、浅井、本願寺、三好、そして武田。信長は周囲を敵に囲まれ、いよいよ危うい。
あわせて読みたい
籠から出た鳥
義昭は、「この鵠は来るのが遅かった」と言い、もはや何の説得にも応じません。光秀が義昭を「大事」だというように、義昭にとっても光秀は大事な存在。藤英とともに信長討伐の戦にはせ参じよと迫ります。「信長から離れよ」と。しかし光秀は応じませんでした。泣きながら「それはできませぬ」とはっきり拒絶した光秀はそのまま二条城を立ち去り、義昭はただ黙って見送ることしかできません。
籠に入った鵠をかたわらに、「十兵衛は鳥じゃ 籠から出た鳥」「また飛んで戻ってくるやもしれぬ」とたとえました。
義昭は、駒に借りた金を鉄砲購入のため使わせてほしいと、空の虫籠に入れた文で伝えています。義昭は自分自身を自由のない籠の中の虫と捉えているようです。将軍の要請に否や突き付けて去る光秀はまだ自分の思いのとおりに行動できるだけ、籠から出た自由な鳥のように見えたのでしょうか。
それにしても、「借りた金は別のことに使う。勝ったら返す」という言葉、駒も信用できないのでは……。本来の目的(福祉)から離れて信長を討つことだけに全精力を注ぐ義昭。駒も離れていってしまいそうですね。
蘭奢待(らんじゃたい)とは
次回の予告に登場した蘭奢待。これは正倉院中倉に所蔵されているという香木(沈香)のことで、天下第一の名香とされます。「蘭奢待」と命名したのは聖武天皇であるという伝承があります。実際には10世紀ごろに渡来したとか。この蘭奢待は足利義満、義教、義政が截香(せっこう/切り取った)ことで知られ、信長が蘭奢待を切り取ったのも過去の権力者に倣って天下人として権威を示すためであったと思われます。
信長ののちには、明治天皇が截香したとされます。
【主な参考文献】
- 校注・訳:新間進一・外村南都子『新編日本古典文学全集 42 神楽歌 催馬楽 梁塵秘抄 閑吟集』(小学館、2000年)※本文中の引用はこれに拠る。
- 奥野高広・岩沢愿彦・校注『信長公記』(角川書店、1969年)
- 『世界大百科事典』(平凡社)
- 『日本大百科全書』(小学館)


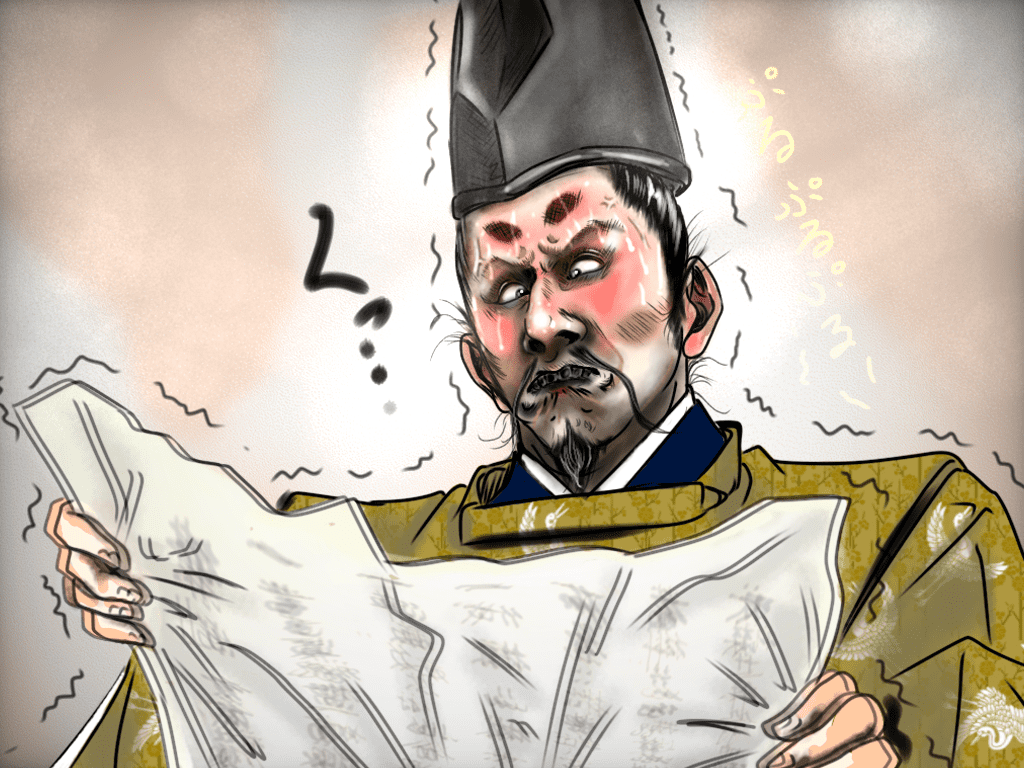

コメント欄