もはや奇跡!? 今なお、お宝が残る東大寺「正倉院」について
- 2025/04/22

約1260年前よりコレクションされた品々ながら、現存する数はなんと約9000点。国産のものや、シルクロードを通ってきた外国製のものなど、当時の文化を知ることができる貴重な宝物が現存しています。
今回は正倉院や正倉院宝物について紹介していきます。
正倉院とは
まず、正倉院とは何かについて説明します。「正倉院」とは、奈良県奈良市にある東大寺の宝物庫のことです。「正倉」とは、大切な品物を保管する倉のことで、東大寺以外の寺社や大蔵省・民部省などの国家機関にも複数設置されていました。東大寺の正倉も元は複数存在していましたが、次第に数が減り、現在では奈良の東大寺に1つのみ現存しています。
8世紀に建造されたこの倉は、総ヒノキでできた校倉造り(あぜくらづくり)の高床式倉庫で、建物自体も国宝、世界遺産になっています。


正倉院は東大寺の境内奥にあり、その建物の規模は全長33メートル、高さ14メートル、奥行き9.4メートル。床下はなんと2.7メートルもあり、倉の中は2階建てで、北倉・中倉・南倉の3室に分かれています。
多くの宝物が収蔵されていた宝物庫…ものすごく巨大な建物であることがわかりますね。
正倉院宝物の保存・管理について
それでは、正倉院ではどのように宝物の保存・管理をしていたのでしょうか?まず、高床式で校倉造りになっている正倉院の建物自体も、保存状態の良さを保っている理由の1つになっています。素材である檜は防虫効果があり、虫食いなどで宝物が痛むことを防いでいます。
この校倉造りの高床式倉庫が、宝物の保存状態に一役買っていたと言われることが多いですが、実は宝物を収納していた辛櫃(からびつ)こそ、宝物の保存を良好に保つことができた要因だとされています。
この辛櫃は杉製のものが多く、湿度を一定に保ち、さらに密閉状態にすることが可能でした。これによって良い環境で宝物を保管することができたのです。
また、エビ香というものも当時製造されていました。これは防虫剤としての役割を担っていて、書物などの宝物の近くに置いていたそうです。
さらに曝涼(ばくりょう)という定期的に風通しや虫干しを行う際には、宝物の保存状態を調査したり、在庫の確認を行っていました。このように1260年以上もの長い歳月の中、保管や管理を徹底していたのです。
また、正倉院は「勅封(ちょくふう)」という形式を導入しています。これは天皇の勅命によって宝物の管理が行われるというものです。正倉院の鍵は朝廷で所持しており、天皇の許可なしに、宝物庫を開けることはできないようにされていました。
まさに宝の山 ~正倉院所蔵の貴重なお宝について~
では、正倉院の宝物には一体どんなものがあるのでしょうか。まず、北倉。こちらには聖武天皇と光明皇后ゆかりの宮廷日常用や貴重な薬物がメインに収められています。ここに収められている宝物は、螺鈿紫檀五弦琵琶(らでんしたんのごげんびわ)、鳥毛立女屏風(とりげりつじょのびょうぶ)など。皆さんも一度は歴史の教科書などでみたことがあるような有名なお宝が収蔵されていました。


次に中倉。こちらは、東大寺や造東大寺司(東大寺の造営、それに付随する品物の製作や写経事業を受け持つ部署)が管理していた宝物を収めている倉です。剣などの武器や筆などの文房具、記録などの史料関係では、『正倉院文書』などが収蔵されています。有名な宝物には、瑠璃杯(るりのはい)、白瑠璃椀(はくるりのわん)、大大論戯画(だいだいろんぎが:写経生の書いた落書き)などがあります。

最後に南倉。こちらには、東大寺での儀式関係の品や塔頭にあった品が宝物として保管されています。有名な宝物としては、伎楽面(ぎがくめん)、三彩磁鉢(さんさいじはち)などがあります。

また、保管された宝物には国内で製作されたもの、外国で製作されたものなど様々です。外国からの伝来の品としては、朝鮮・中国・ペルシャ製などシルクロードを渡ってきた品物が多く、アフリカ・インド・アフガニスタン・フィリピン産などの素材を使用したり、様々な地域のものが保管されています。
ちなみに、先ほど少し触れた中倉に所属されている『正倉院文書』は、所蔵されている宝物の目録や天皇や皇后の直筆文書、戸籍などの公文書もあれば、下級役人の昇進嘆願書や盗まれた物を探すための休暇届、写経生の待遇改善書状や落書きなど、当時の人たちの実態を知ることができる大変興味深い史料が残っています。
わりと盗難にあっていた!?正倉院のお宝たち
まさに宝の山とも言えるこの正倉院。実は何度か盗難事件にあっています。いったい何が盗まれてしまったのでしょうか?ここでは、鎌倉時代初期に起きた寛喜2年(1230)の盗難事件について紹介します。この時の盗難では、倉の鍵を焼き切って中に入ったとされ、盗まれたのは鏡8面の他、銅製の小さな壺1つと銅製の小さな仏像3体。犯人は約1ヶ月後、無事に逮捕されますが、主犯となった人物は、なんと東大寺の元僧侶だったのです。彼らは鏡の白銅部分を銀だと勘違いしたらしく、砕いて細かくし、その破片を売り払おうと考えました。
しかし、実際は銀ではなかったため、思うように値が付かなかったとのこと。そこで盗んだ鏡の破片を東大寺の境内に埋めてしまったのです。発見された鏡はしばらく破損した状態のまま保管されていました。その後、一部の鏡は明治時代に修復され、当時の面影が再現されています。

この事件以外にも記録が残っているだけで3件あり、正倉院の宝物が世間に流入していた事例があったようです。それでも、現代まで約9000点ほど宝物が残っているわけですから、約1260年もの長い間宝物を守ってきた先人たちには改めて驚かされますね。
有名人がこぞって切り取った香木「蘭奢待」
現代では「正倉院展」があるため、一般人でも宝物の一部を拝観することができますが、昔は容易に宝物を拝観することはできませんでした。とは言ったものの、天皇や一部の武将など、時の権力者たちは特別に拝観することができたそうです。なかでも、「蘭奢待(らんじゃたい)」という宝物がよく拝観されていました。この蘭奢待と言うのは、正倉院に所蔵されている香木の1つ。「天下第一の名香」と称賛され、大変価値がある香木です。
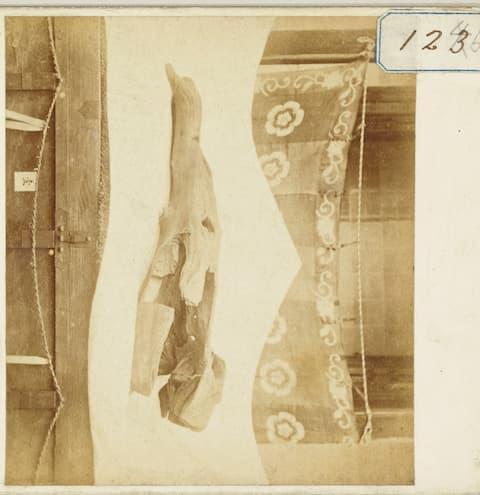
蘭奢待の大きさは、長さ156センチ、最大直径部分42.5センチ、重さ11.6キロほどで、その香りは沈香に似ているそうです。正式名称は黄熟香(おうじゅくこう)と言い、この蘭奢待という名前はあくまで通称です。
では、ここで豆知識。実は“蘭奢待”という名前には、文字の中に"東・大・寺"の名が隠れているのです。

まさに東大寺の宝物中の宝物、と言ったところでしょうか。
この蘭奢待を拝観し、截香(せっこう:香木の一部を切り取ること)するということは、権力者たちの一種のステータスとされていました。蘭奢待を切り取った有名な人物としては、足利義満、足利義教、足利義政、織田信長、明治天皇などの人たちがあげられています。
ちなみに、蘭奢待の3箇所の切り口には、足利義政、織田信長、明治天皇の3名が截香したとされる箇所に付箋がつけられているそうです。
おわりに
このように正倉院では、1000年以上も前から宝物の保存や管理を徹底しており、何度か盗難や災害に遭うものの、現代でも状態の良い宝物がたくさん残っています。まさに奇跡と言っても過言ではありません。これは、長い歳月の間に引き継がれてきた、人々の努力の賜物と言えるでしょう。また、昭和21年(1946)より、令和6年(2024)までに計76回を数える「正倉院展」は、一部例外はあるものの、毎回奈良国立博物館で開催されています。ここでは、正倉院所蔵の貴重なお宝が展示され、一般の方でも拝見することができます。
天平文化特有の異国情緒漂う宝物たち。これらに出会える「正倉院展」にも、ぜひ足を運んでみてくださいね。
【主な参考文献】
- 山本忠尚『正倉院宝物を10倍楽しむ』(吉川弘文館、2022年)
- 丸山裕美子『正倉院文書の世界 よみがえる天平の時代』(中央公論新社、2010年)
- 米田雄介『すぐわかる正倉院の美術 改訂版』(東京美術、2019年)
- 杉本一樹『正倉院 歴史と宝物』(中央公論新社、2008年)
- 奈良国立博物館監修『知ってる?正倉院 今なおかがやく宝物たち』(ミネルヴァ書房、2011年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。


コメント欄