和歌の原型「記紀歌謡」──『古事記』『日本書紀』に隠された“最古の歌”が語る世界
- 2025/10/22

8世紀の終わりごろに『万葉集』ができ、五・七・五・七・七という和歌の形式が確立したといわれていますが、万葉集よりも前にできた『日本書紀』や『古事記』にも、歌が収められています。
記紀(日本書紀と古事記の総称)に掲載されている歌は、文学史的に和歌が成立する以前の古い歌のかたちとされています。ここでは「記紀歌謡」といわれる記紀に収録されている歌について、ご紹介します。
記紀(日本書紀と古事記の総称)に掲載されている歌は、文学史的に和歌が成立する以前の古い歌のかたちとされています。ここでは「記紀歌謡」といわれる記紀に収録されている歌について、ご紹介します。
記紀に収められた歌
『日本書紀』『古事記』は、奈良時代に完成した日本の歴史書です。『日本書紀』の完成時期は明らかではありませんが、『続日本紀』(日本書紀の後に編纂された歴史書)の記述などから、7世紀の終わりに天武天皇によって編纂命令が出され、奈良時代の初めである720年に完成したといわれています。神代(神話の時代)から7世紀後半の持統天皇(天武天皇の皇后)までの時代を扱っています。
一方、『古事記』は序文に次のようにあります。
「編纂者の太安万侶が天武天皇の命により、稗田阿礼が話る歴史をまとめ、712年に元明天皇に献上した」
扱っている時代は神代から7世紀初めの推古天皇までで、日本書紀よりも少し古い時代で終わっています。
記紀には、文章の途中に「歌」が挿入されています。たとえば、いずれにも、スサノヲがクシナダヒメと結婚して出雲に居処を構えたときに歌った歌として、下記の歌が載っています。
「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を」
「盛んに雲が立つ出雲で妻をめとってともに暮らすため、垣根を幾重にもめぐらせた家を作る」といった意味の歌です。
この歌は形式的には五・七・五・七・七になっており、「最古の和歌」といわれています。しかし、『万葉集』や平安時代の『古今和歌集』などにおける和歌が「詠み手(あるいは登場人物)の心情を歌うもの」であるのに対し、この歌はもともと、出雲で家の新築を祝う歌として歌われたものが物語に取り込まれたのではないかと考えられています。
このような物語に合わせた歌が『古事記』に112首、『日本書紀』に128首収められています。「八雲立つ」の歌のように重複しているものもあり、重複分を除くと記紀合わせて約200首となります。
心情を五・七・五・七・七で詠む和歌のかたちが定まったのは、『万葉集』からといわれていますが、それ以前の古い歌は「上代歌謡」と称されています。中でも、記紀に収められている歌は「記紀歌謡」とよばれています。
記紀歌謡は記紀の記述とは関係ない?
「和歌」といえば五・七・五・七・七の形式のものを指しますが、奈良時代成立の『万葉集』には、短歌・長歌・旋頭歌という3パターンの和歌が収められています。・短歌…五・七・五・七・七の形式
・長歌…五・七のセットを3回以上繰り返し、最後を七で締める
・旋頭歌…五・七・七・五・七・七の形式で、上三句と下三句で詠み手が異なる。下の句は上の句に応える形で歌われ、2人で歌う形になっている。
やがて、平安時代になると短歌以外の形式が廃れ、和歌=短歌を指すようになりました。『万葉集』より成立が古い記紀にも、短歌のほかに長歌や旋頭歌の形式を持つ歌があります。
『万葉集』以降、短歌は親子や恋人への思い、生活の実感など、読み手の心情を歌う短歌に発展していきますが、「記紀歌謡」は先ほどの「八雲立つ」の歌のように、何かをほめるために歌ったり、仕事や祭りなどで歌ったりしたものが多くを占めています。つまり、もとは人々の間で歌い継がれてきたものが記紀の編纂者に採取され、物語と結び付けられたようです。
記紀に登場する「記紀歌謡」で、もう一つ有名な歌があります。『古事記』の中で、ヤマトタケルの辞世の歌として知られている「倭(やまと)は国のまほろば……」の歌です。
倭は国のまほろば たたなづく青垣 山隠(こも)れる 倭し美(うるわ)し
「大和はもっともすぐれた国だ。青い山々が連なって、垣のように囲んでいる大和は美しい」といった意味ですが、ヤマトタケルが本当に死に際して故郷の大和を思って歌ったわけではありません。もとは大和に伝わる国ほめ歌であったものが、物語を盛り上げるために文中に配置されたものです。
「国ほめ」という行為は、土地の支配者が支配する地を見てまわる「国見」の際に行われるもので、言葉にすれば現実になる言霊信仰の反映といわれています。古代ヤマト政権においても、大王による国見が行われました。
ちなみに『日本書紀』では、この歌はヤマトタケルの父・景行天皇が日向国にいるときに歌ったものとされています。
編者がエピソードに合わせて創作した歌も
次は『日本書紀』だけにある歌で「民間に伝わっていた歌を取り入れたのかどうかグレー」なものをご紹介します。淡海(おうみ)の海(み) 瀬田の済(わたり)に 潜(かづ)く鳥 目にし見えねば 憤りしも
神功皇后(仲哀天皇の皇后)が亡き夫に代わって政治を執っていた時代、血のつながらない子どもである忍熊王(おしくまおう)が反乱を起こします。忍熊王は敗れ、琵琶湖にある瀬田の渡しに身を投げて亡くなります。忍熊王の死体を探す将軍・武内宿禰の歌として、上記の歌が載せられています。
歌の意味は「琵琶湖の瀬田の渡しに潜っている鳥が見つからないので、困ったものだ」というもの。もとは、琵琶湖から流れ出す瀬田川で鵜飼をする人々の歌であり、忍熊王のエピソードとは関係ないとされています。
ただ、この歌は鵜飼の歌でもなく、忍熊王のエピソードに合わせて日本書紀の編者が創作したものとする説もあります。時代は下りますが『源氏物語』でも、紫式部が物語に合わせて歌を創作していますが、同じようなことが『日本書紀』でも行われたとする考え方です。
宮廷儀礼にかかわる歌
律令制度が整った8世紀以降、天皇を中心とする朝廷ではさまざまな儀礼が執り行われました。宮廷儀礼にかかわる歌も記紀には収録されています。応神天皇が奈良の吉野に出かけた際、吉野川の上流に住む国栖人(くずひと)がやって来て、酒を献上したときに歌った歌として、次のような歌が出てきます。
白檮(かし)の生(ふ)に 横臼(よくす)を作り 横臼に 醸(か)みし大御酒(みき) うまらに 聞(きこ)しもち食(を)せ まろが父(ち)
歌の意味は「樫の林で横臼を作り、その横臼に醸したお酒を おいしく召し上がってください、わが父よ」というもの。この歌は、大嘗祭などの宮中行事に演じられる「国栖奏(くずそう)」という歌舞で歌われていました。
平安時代の半ばまで、国栖の人々は国栖奏を披露するために、宮中に上がっていました。国栖奏の前には土地の産物を献上しており、この歌舞は天皇への服属儀礼の名残と考えられています。しかし平安末期になると、宮中の楽人が勤めるようになり、室町時代には途絶えてしまいます。
記紀は、国栖奏の歌の起源は応神天皇がいたとされる5世紀の出来事としています。しかし、国文学的考察によると、上記の歌は国栖奏が宮廷儀礼として制度化された天武天皇・持統天皇の時代(7世紀後半)の体裁のものと推察されます。
国栖の人々がヤマト王権に従った話が5世紀まで遡るかどうかは定かではありませんが、天武・持統朝よりも前に国栖奏の歌の原型があったのかもしれません。
おわりに
記紀に掲載されている歌の出どころについて、いくつかご紹介しました。「記紀歌謡」をめぐってはさまざまな説があり、研究者によって見解が分かれるところも少なくありません。しかし、記紀に引かれている歌がさまざまなところから採られ、物語を彩っていることを知っていただければと思います。- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
戦国ヒストリーの編集部アカウントです。編集部でも記事の企画・執筆を行なっています。






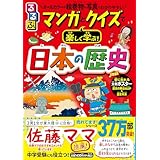

コメント欄