※ この記事はユーザー投稿です
【やさしい歴史用語解説】「金箔瓦」
- 2025/07/18

そもそも「金箔瓦」とは、金箔を押して華麗な意匠を凝らした屋根瓦のことで、豊臣政権の権威の象徴だったと考えられています。なぜ徳川の城である駿府城から豊臣期のものが見つかったのでしょうか?そこには織田信長から豊臣秀吉へ受け継がれた城に対する考え方が現れているのです。
まず信長は「城」を権威として考える第一人者でした。小牧山城や岐阜城、あるいは安土城などを見ても、自分がいる天守を最上部に置き、家臣たちの屋敷はすべて麓にありました。これは主君と家臣の上下関係を表すものだと考えられ、信長はあえて視覚的に上下関係を意識させたといいます。
また、金箔瓦が用いられたのも安土城が最初でした。陽の光を浴びて金色に輝く天主を見て、人々は大変驚いたとも。これも視覚効果を狙った築城法でした。さらに安土城の至る所に提灯を灯し、史上初のライトアップを演じたのも信長です。こうした演出によって誰が統治者であるかをアピールしたのでしょう。

こうして「見せるための城」が登場したわけですが、一門や功績があった者にのみ、こうした城の築城を許したといいます。やがてその考えは豊臣秀吉にも継承されました。秀吉は安土城より巨大な大坂城を築城して次期天下人であることを示し、信長と同様に金箔瓦を用いた築城を許可制にしました。つまり秀吉が認めた者だけが金箔瓦を使用できたというわけです。
従来の説では徳川家康が移った関東で金箔瓦は出土せず、豊臣系大名の城で多く発見されていることから、豊臣の権威を徳川に見せつける必要があったのでは?とされてきました。しかし最新の研究ではそうではなく、あくまで統治者として領民にアピールする意図があったのでは?という説が有力になりつつあります。なぜなら金箔瓦の出土範囲は全国規模に及び、徳川とはまったく関係のない地域で発見されたからです。
さて、家康が関東へ移ったあと、駿府城へ入ったのは中村一氏という大名でした。彼は早くから秀吉に仕えて苦楽を共にした家臣ですから、徳川の旧領に配置するほど全幅の信頼を得ていたのでしょう。領民に豊臣の権威を見せつけるべく金箔瓦を使用するのですが、なぜか信長時代の意匠の瓦を用いていました。その理由は不明ですが、家康に対する牽制の意味はなかったものと考えられます。
ちなみに金箔は瓦全体に押されていたわけではありません。屋根瓦の一番目立つ部分にのみ使用されていました。やはりお金が掛かるものですから、より最大限の費用対効果を意識したのでしょう。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。




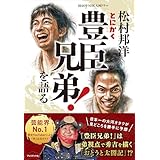



コメント欄