【三重県】鳥羽城の歴史 海賊大名が築いた水の城
- 2025/03/11

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
目の前には近鉄鳥羽線や国道42号線が横切り、すぐ近くには鳥羽水族館、ミキモト真珠島などの施設が存在するなど、すっかり周辺は観光地と化していますね。ただ、古い石垣は随所に残っており、確かに城があったことをうかがわせます。
鳥羽城がどんな城であり、どんな歴史をたどったのか? 詳しく紹介したいと思います。
九鬼嘉隆が志摩の支配者となる
まずは鳥羽城が築かれる以前の歴史についてひも解いてみたいと思います。同時代の一次史料が存在せず、近世史料に頼るしかないのですが、江戸時代中期に編纂された『志陽畧記』によれば、平安時代末期から中世にかけて、橘氏が鳥羽地域を治めていたようです。
累代の橘氏当主は「鳥羽殿」と称され、志摩国に割拠する嶋衆(土豪)たちの盟主的存在でした。また鳥羽城が築かれた城山には、橘氏の居館が建っていたとされています。
永禄年間になると、志摩国では、田城城・波切城を拠点とする九鬼氏の勢力が強くなりました。危機感を覚えた嶋衆たちは結集し、北畠氏の援助を受けつつ九鬼氏に戦いを挑みます。戦況が不利になる中、当主・九鬼浄隆は合戦中に死没し、弟の嘉隆も支えきれずに志摩から逃亡。安濃津を経て尾張へ落ち延びていきました。
『勢州軍記』によれば、しばらく尾張で潜伏した嘉隆は、滝川一益の仲介で織田信長に仕えるようになったといいます。 『九鬼家伝系図』にも「信長公上方ご出張のみぎり、瀧川左近将監奏者として御礼申す」という記述があり、おそらく信長上洛後の、永禄11年(1568)以降のことと推測されるようです。
やがて織田氏の実力を背景に、志摩における九鬼氏の勢いは増していきました。嶋衆はたびたび戦いを挑むものの、最終的には和睦して嘉隆に従うようになります。実力で志摩を我が物とした嘉隆ですが、実質的な惣領になるためには、橘氏の権威を取り込む必要を感じたのでしょう。時の当主・橘宗忠には娘がいましたが、嘉隆は次男・守隆を婿として送り込むことで家督を掌握。宗忠を隠居へ追い込み、また鳥羽の地を手に入れたことで、まんまと橘氏の乗っ取りに成功したのです。
その後、嶋衆を従えた嘉隆は、織田家臣団きっての水軍の将となりました。次いで豊臣秀吉に臣従し、朝鮮出兵でも大きな働きを見せています。
九鬼嘉隆によって鳥羽城が築かれる
室町時代中期の記録『醍醐寺文書』によれば、「泊浦小里の城」「大里の城」「小嶋」といった記述があり、鳥羽のあちこちに城が築かれていたと推測できます。ちなみに「小嶋」は現在のミキモト真珠島を指し、「泊浦小里の城」が北に位置する日和山、そして「大里の城」が城山(鳥羽城)に相当するのだとか。鳥羽城本丸跡の発掘調査では、14~15世紀にかけての土師器などが出土しており、橘氏の城館として機能していたと考えられます。
時代が下って豊臣秀吉の治世になると、数々の功績を挙げた九鬼嘉隆は、伊勢・志摩のうち、3万5千石を賜りました。その後、水軍の運用を重視した嘉隆は、妙慶川南岸に突き出た城山に城を築くことを思い立ちます。築城時期は不明ですが、おおむね文禄3年(1594)頃には完成。とはいえ九鬼氏時代の鳥羽城は、絵図が残っていないため詳細は明らかでありません。
ただし、江戸時代初期の鳥羽城を描いた『極秘諸国城図』が松江歴史館に所蔵されており、これが最も古い絵図とされています。ちなみに鳥羽城二の丸は、内藤氏時代に整備されたと伝わりますが、近年における発掘調査の結果、九鬼氏が築城した段階でほぼ完成ことがわかってきました。おそらく鳥羽城が嘉隆によって築かれた時、その大部分が出来上がっていたのでしょう。
そして鳥羽城の特徴といえば、東と南が海に面していたことです。また陸続きになる北と西には堀を掘削して海水を引き込み、城の周囲を水で防御していました。さらに大手方向には水門を設け、城下には船蔵が置かれるなど、九鬼水軍の居城にふさわしい威容を誇っていたに違いありません。

海を睨む大砲が天守に据え付けられていた!?
次に城の構造について見ていきましょう。当時は海に面する東方向に大手水門、ヒシ櫓、アラミ櫓があり、南方向には同じく水門やアサリ櫓などが存在していました。また城の北には相橋門、西には横町口門、南に藤口門といった城門があり、そのうち横町口門と藤口門は枡形構造になっていたようです。
いっぽう山上へ目を移すと、最高部には本丸があり、近代に旧鳥羽小学校が建ったことで大幅に改変されましたが、現在でも本丸周囲の石垣が良好に残っています。そして本丸の北東方向に三の丸があり、そこから東へ下ると、海に面する二の丸がありました。また本丸の北側には、太鼓櫓があったとされる曲輪も現存しています。

ちなみに絵図によれば、本丸の北西寄りに三層の天守があり、櫓も12基ほど建っていたようです。その中でも特筆すべきは天守の存在でしょうか。延宝8年(1680)、内藤氏から土井氏へ藩主を引き継ぐ際、引渡目録が作成されたのですが、はっきりと天守の構造が浮かび上がってくるようです。
それによると天守の北東に出櫓が付属し、同時に「三方大さま」という記述が確認できます。ふつう天守に付属する櫓といえば、付櫓が一般的ですが、鳥羽城の場合は出櫓が突き出すように伸びていました。
さらに「大さま」というのは、石火矢、つまり大砲のことです。かつて九鬼嘉隆が、第二次木津川海戦で鉄甲船に搭載した大砲を彷彿とさせますね。しかも「三方」というのですから、出櫓には三方向へ向けられた大砲が据えられていたのでしょう。もちろん砲口は海を向いていたはずで、いかにも海賊大名の城という雰囲気を感じさせます。
また、記録によれば、本丸御殿には上段の間があり、床・棚・付書院・帳台構えなどが付属していたようです。この帳台構えは、二条城や名古屋城といった大城郭にしかありません。鳥羽城にそれがあるということは、小大名の居城でありながら、大変格式の高い城だったことがうかがえます。
鳥羽城本丸は近代の改変によって、天守台はじめ遺構のほとんどが失われました。しかし平成23年(2011)から2年にわたる発掘調査の結果、ようやく往時の様子がわかってきています。
まず天守台の場合、土台部分にあたる根石が確認できませんでした。つまり近代の造成でかなり削平されたと考えられます。おそらく現在より、ずっと高い位置に天守台があったのかも知れません。
また本丸跡からは御殿の石列や、土蔵跡などが確認されており、各時代の瓦が出土遺物の大半を占めています。九鬼氏や内藤氏、あとに続く稲垣氏の時代では、必要に応じて補修や瓦の葺き替えを行っていたのでしょう。

九鬼嘉隆・守隆父子の対決
豊臣秀吉の死後、徳川家康は政権内部の対立軸を利用し、会津の上杉景勝を討伐するべく出兵。九鬼氏当主だった守隆は、家康に従って東国へ向かいました。いっぽう隠居していた父・嘉隆の元には、西軍に加わるよう石田三成の要請が届きます。嘉隆は老齢を理由にいったん断るものの、再三にわたる懇願を断ることができませんでした。嘉隆は新宮城主・堀内氏善とともに、鳥羽城へ立て籠もったといいます。
嘉隆が西軍に味方した理由ですが、東軍・西軍どちらが勝利しても家を残せるよう、あえて両軍に分かれたのではないでしょうか。これは九鬼氏に限った話ではなく、真田氏にしても生駒氏にしても、父子が分かれて戦っているため、やはり同様の考えを持っていたはずです。
さて、西軍の挙兵を知った家康は、まず先陣として福島・池田らの諸将を上方方面へ向かわせました。守隆はこれに同行するとともに、伊勢方面へ進出した西軍を牽制する役目が与えられています。やがて池田輝政の所領である三河吉田から、船で伊勢湾を横断した守隆は、ようやく志摩へたどり着きました。
いっぽう嘉隆はといえば、来島村上氏の一族・村上義清らと行動をともにしており、熱田から師崎へ至る伊勢湾沿いの拠点を次々に攻撃しています。この動きを見た守隆は自重し、まず安乗城を修築して家臣の豊田五郎右衛門に守らせ、自身は伊勢湾口の警固にあたりました。すでに東軍方の水軍がこちらへ向かっていたからです。
しかし、ここで思いもよらぬ事態が起こりました。安乗城の守備を任された豊田五郎右衛門が心変わりし、嘉隆に城を引き渡そうとしたのです。ところが嘉隆は喜ぶどころか、「お前を守隆の後見役に引き立ててやったのに、なぜ主君を裏切るのか」と激怒。一切取り合わなかったといいます。
そして関ヶ原の戦いが始まる4日前、ついに嘉隆と守隆は決戦に及びました。
「父子しばしば合戦に及び、氏善が家臣をはじめ敵数人を討取、守隆が手に於いても村田七太夫、工藤祐助某、森田右近某数輩奮戦して討ち死す」
とありますから、相当な激戦だったのでしょう。
やがて関ヶ原合戦の結果が伝わってくると、敗戦を知った村上義清は事情を嘉隆に伝えました。すると嘉隆は鳥羽城から離れ、答志島の和具というところに潜伏したようです。しかし、これを知った豊田五郎右衛門は焦りました。もし嘉隆と守隆が顔を合わせれば、自分の裏切り行為が露見し、間違いなく処罰は免れないでしょう。
そこで五郎右衛門は使者を答志島へ差し向け、守隆の命令と偽って自害を強要しました。嘉隆は最期にこう述べたと伝わります。
その頃、鳥羽城を取り戻した守隆は、家康に父の助命を懇願しています。そして池田らの協力もあって赦免されるのですが、嘉隆はその使者を待つことなく自害に及びました。事の顛末を聞いた守隆は激怒し、豊田五郎右衛門を捕らえると、首を刎ねて獄門に晒したそうです。
その後の九鬼氏と鳥羽城
関ヶ原合戦の論功行賞により、守隆には2万石が加増され、嘉隆の隠居料と合わせて5万5千石を領することになりました。また九鬼氏は国内きっての水軍衆として、幕府の御公儀船手役を務めています。慶長19年(1614)の大坂冬の陣において、守隆は幕府方の水軍主力として出陣。大阪湾の制海権を手中にする活躍ぶりを見せました。
ところが寛永10年(1633)のこと、守隆の後継をめぐって御家騒動が勃発してしまうのです。これは守隆の三男・隆季と、末弟・久隆(寿量)が争ったもので、家臣団を巻き込む騒動へと発展しました。ついには家老・組頭65人が出奔するという騒ぎとなってしまいます。
守隆がいったん隆季に1万石を分知し、久隆に家督を継がせることで決着が付きますが、その直後に守隆が急死したことで、またしても騒動に火が付きました。重臣たちは幕府に対し、次のような訴えを起こしています。
そこには九鬼水軍としてのプライドがあったようです。主君に逆らう謀反だと非難されようが、水軍の自負を持つ彼らにとって、坊主上がりの久隆の指揮下に入ることは、到底我慢できなかったのでしょう。
幕府草創期にあたるこの時期、このような御家騒動は厳しい処罰の対象となりました。実際に多くの大名が改易となっており、九鬼氏もまた例外ではなかったはず。しかし、幕府の裁定は意外なものでした。
守隆の遺領のうち、3万6千石を久隆に与えて摂津へ転封させ、残りの2万石を隆季に分知したうえで、丹波へ所替えするというもの。九鬼氏の特殊な事情を慮った幕府は、決して取り潰すことなく、最善の方法で両者を存続させたのです。
こうして九鬼氏は鳥羽城を手放し、海から切り離されました。また嘉隆いらい培ってきた水軍力も消滅しています。
九鬼氏が国替えになったあと、譜代大名の内藤忠重が新たな藩主となりました。しかし延宝8年(1680)、芝増上寺において、内藤忠勝が刃傷事件を起こしたことで改易となり、その後は幕府直轄地を経て、土井氏・大給松平氏・板倉氏・戸田松平氏が相次いで藩主となっています。
享保10年(1725)に稲垣氏が入封して以降、幕末まで藩主が代わることはありませんでした。明治2年(1869)の版籍奉還によって城は官有地となり、2年後には天守・櫓・門などの建造物が壊されています。
近代になって市街地や造船所が造成されるに伴い、海は埋め立てられ、堀は消滅し、多くの遺構が破壊されることになりました。また昭和に入ると、本丸跡に旧鳥羽小学校が建設されたことで、鳥羽城の姿はすっかり変わってしまったといいます。
おわりに
鳥羽城はじめ、大分県の臼杵城や広島県の三原城など、かつての水城がすっかり様変わりした例は少なくありません。これも時代の流れなのでしょうか。とはいえ鳥羽城の石垣はしっかり残っていて、在りし日の威容を感じることができます。また本丸跡からは鳥羽湾が一望でき、かつて九鬼嘉隆が見たであろう風景が目の前に広がっているのです。
補足:鳥羽城の略年表
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 文禄3年 (1594) | 九鬼嘉隆によって鳥羽城が築かれる。 |
| 慶長2年 (1597) | 嘉隆が家督を譲り、九鬼守隆が城主となる。 |
| 慶長5年 (1600) | 関ヶ原の戦いの際、嘉隆が鳥羽城を占拠する。 |
| 寛永11年 (1634) | 九鬼氏の御家騒動に伴い、内藤忠重が鳥羽藩主となる。 |
| 延宝8年 (1680) | 内藤忠勝が芝増上寺で刃傷事件を起こし、領地没収となる。 |
| 天和元年 (1681) | 土井利益が藩主となる。その後、大給松平氏・板倉氏・戸田松平氏と続く。 |
| 享保10年 (1725) | 稲垣昭賢が藩主となり、以降、幕末まで稲垣氏が続く。 |
| 寛政4年 (1792) | 暴風雨によって櫓などが流失し、石垣や城壁が大破する。 |
| 文政7年 (1824) | 二の丸に藩校・尚志館が開設される。 |
| 明治4年 (1871) | 廃藩置県に伴い、鳥羽城の天守・御殿・櫓・門などの撤去が始まる。 |
| 明治9年 (1876) | 蓮池の堀が埋め立てられ、錦町が成立する。 |
| 昭和4年 (1929) | 本丸跡に旧鳥羽小学校が開設される。 |
| 昭和40年 (1965) | 三重県の史跡に指定される。 |



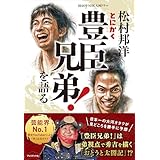
コメント欄