昔のなぞなぞ「母には二たび会ひたれども」…後世の人々にとっては難題すぎた謎
- 2025/03/21
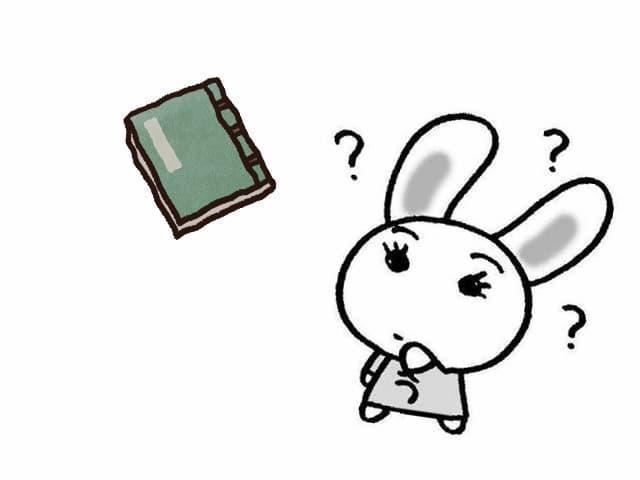
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
次の一文は何のことでしょうか?
これは戦国時代の永正13年(1516)に書かれた『後奈良院御撰何曾』に登場する「なぞなぞ」です。さて、答えは何でしょうか??皆さん、考えてみてください。
実はこのなぞなぞ。答えを聞いても、後世の人々は意味が分からなかったそうです。しかし、日本語に関する「ある真実」の発見によって、ようやくその意味がわかりました。その真実とは「今と昔では日本語の発音が違う」ということです。その根拠になったのが、冒頭のなぞなぞの答えです。
今回は、このなぞなぞの答えを考えてもらいながら、日本語の発音の変遷について説明します。
「母には二たび会ひたれけども 父には一たびも会はず」
(訳:母には二回会うけれど、父には一度も会わない)
これは戦国時代の永正13年(1516)に書かれた『後奈良院御撰何曾』に登場する「なぞなぞ」です。さて、答えは何でしょうか??皆さん、考えてみてください。
実はこのなぞなぞ。答えを聞いても、後世の人々は意味が分からなかったそうです。しかし、日本語に関する「ある真実」の発見によって、ようやくその意味がわかりました。その真実とは「今と昔では日本語の発音が違う」ということです。その根拠になったのが、冒頭のなぞなぞの答えです。
今回は、このなぞなぞの答えを考えてもらいながら、日本語の発音の変遷について説明します。
【目次】
昔は違った日本語の発音
現在、我々が使っている平仮名は46文字あります。それに「が」「ざ」などの濁音、「ぱ」「ぴ」などの半濁音、「きゃ」「しゃ」などの拗音、小さい「つ」や「ん」などを合わせると106文字になります。ですから、単純に考えると日本語の発音は106文字=106音となりますね。しかし、昔はどうやら違ったようです。その根拠として分かりやすいのは、奈良〜平安時代に使われた万葉仮名でしょう。
万葉仮名は日本語(日本人の発する言葉)を文字として表記するため、漢字の音を借用したものです。現代人に万葉仮名を説明するとき、筆者がよく使うのが「夜露死苦(よろしく)」とか「愛羅武勇(アイラブユー)」です。所謂は当て字ですね。(※上記当て字は万葉仮名では登場しません)

万葉仮名では一つの音節に対し、複数種の漢字が使われます。さて、この万葉仮名が何故、昔の発音は今と違う根拠になるのでしょうか。それは上代特殊仮名遣いと呼ばれる万葉仮名の存在です。
例えば、「恋(こい)」と「声(こえ)」の「こ」。
「こ」は発音を表す国際音声字母(IPA)で表すと「ko」です。しかし、万葉仮名においては
- 恋の「こ」→古・故・胡・固など
- 声の「こ」→許・去・居・虚など
が用いられています。 漢字の音では「コ」と「キョ」になり、それぞれ混合されてはいません。
このように、現在では同じ音なのに万葉仮名では発音が違っていたため、漢字を使い分けられてるのが上代特殊仮名遣いです。ここから当時のリアルな発音を知ることができるのです。
なぞなぞを解く鍵
それでは話を本題に戻します。冒頭のなぞなぞを解く鍵は、「母」と「父」(の発音)です。さぁ、はっきりと口を動かして「母(haha)」「父(t∫it∫i)」と発音してみましょう!答えが分かりましたでしょうか?それでも、まだ分からないと思います。当時の発音で「母」「父」を言わなければならないのですから。
「母」の発音
先ず「母」の「は」についてみていきましょう。このなぞなぞが作られた時代の日本語に「ハ(ha)ヒ(çi)フ(Φu)へ(he)ホ(ho)」という現在の発音は存在しなかったようです。
当時のハ行は、唇を上下で合わせ、その隙間から息をすうっと摩擦させて出すような「両唇音」ではないかといわれています。なぜなら室町時代のキリシタン資料に「fito(人)」「fart(春)」というようにハ行が f で書かれた日本語のローマ字表記を見ることができるからです。
f の子音は Φ になりますので、当時のハ行は「ファ(Φa)フィ(Φi)フ(Φu)フェ(Φe)フォ(Φo)」と発音していたのでしょう。
すると「母」は「ファファ(ΦaΦa)」となりますね。
「父」の発音
次に「父」の「ち」を含むタ行をみていましょう。現在の発音をみても「タ(ta)チ(t∫i)ツ(tsu)テ(te)ト(to)」のように、「ち」の発音は他と異なることがわかります。「父」は万葉仮名で「知知」と表記されますので、「ち」は「知」となります。
この「知」という漢字の音は、上古音(周・秦時代の漢字音)も中古音(隋・唐時代の漢字音)も共に「ティ(tie)」なので、「父」は「ティティ(tie tie)」だったのでしょう。
なぞなぞの答えは
それでは当時の発音で「母」「父」とはっきり言ってみましょう。今度こそ分かりましたでしょうか?明らかに「母」と発音するとき、2回会う(合う?)ものとは…。〝くちびる〟ですね。
そしてこの答えが、当時のハ行が「両唇音 ファ(Φa)フィ(Φi)フ(Φu)フェ(Φe)フォ(Φo)」だったことの証明になったのです。
変化するハ行
先述の通り、万葉仮名で使われている漢字の音から、昔の日本人の発音が推測できました。さらにハ行については、キリシタン資料に見られるローマ字表記や、なぞなぞの答えからどんな発音をしていたのか分かりました。そしてもう一つ、このハ行の発音について分かったことがあります。それは、「ハ」は「ファ」だったが、その前は「パ」と発音していたことです。
実際、万葉仮名で「は」は「波」や「播」の漢字が使われていましたが、これらの漢字の音は上古音でも中古音でも p からはじまる音になります。
また、ハ行の半濁音を考えても分かります。ハ行の半濁音「パ(pa)ピ(pi)プ(pu)ペ(pe)ポ(po)」の子音 p もバ行の子音 b も、唇を使い息を破裂させて出す音です。違いは声帯を振動させるか否かです。つまり、バ行に対応するのはハ行ではなく、パ行なのです。
ちなみにカ行子音 k とガ行子音 g 、サ行子音 s とザ行子音 z 、タ行子音 t とダ行子音 d、といった他の清音・濁音は全てこの関係になります。
これが事実ならば、ハ行は
「パ(pa)ピ(pi)プ(pu)ペ(pe)ポ(po)」
↓
「ファ(Φa)フィ(Φi)フ(Φu)フェ(Φe)フォ(Φo)」
↓
「ハ(ha)ヒ(çi)フ(Φu)へ(he)ホ(ho)」
と変化してきたことになります。
いつ変化したのか
では、ハ行の発音はいつ頃どのように変化したのでしょうか。先述のように、万葉仮名を使用し始める奈良時代ごろはまだ「パ」だったと考えられます。平安時代に円仁が記した『在唐記』には、梵語と漢字音・日本語の発音が比較されて書かれています。それを見ると、ハ行の子音が p 、または Φ だったことが分かります。
つまり、平安時代は「パ」と「ファ」の過渡期だったのでしょう。そして室町時代には「パ」から「ファ」へ変化していたことが今回のなぞなぞやキリシタン資料で証明されていますね。
最後の「ファ」から「ハ」への変化は江戸時代くらいと考えられます。こちらは江戸時代に書かれた物語から、当時の話し言葉を調べると分かってきます。
例えば「柄杓(ひしゃく)」を「ししゃく」、「百(ひゃく)」を「しゃく」など。ハ行の「ヒ」とサ行の「シ」の混同が多くみられますが、これは両音が近い音になっている証拠ですね。
筆者は落語を学んでいたことがありましたが、江戸古典落語にもこのような言い回しがありました。また、江戸時代初期のイギリス平戸商館長だったリチャード・コックスが書いた日記には「箱根=Hacony」や「浜松=Hamachi」と書かれています。
これらから、江戸時代にハ行の発音が「ハヒフヘホ」に変わったことが分かります。
最後に
日本語の発音の歴史に大きな発見をもたらした『後奈良院御撰何曾』というなぞなぞ集。他にも面白いなぞなぞがたくさん載っていますので、いくつか出題してみます。みなさん、考えてみてください!- 問1「道風がみちのく紙に山といふ字をかく」 これは何?
- 問2「上を見れば下にあり。下を見れば上にあり。母のはらをとをりて子のかたにあり」 これは何?
- 問3「海の道十里に足らず」 これは何?
さて、今回のコラムでは、昔の日本人は今と同じ言葉でも、発音は異なっていたことが分かりました。このように、古書を読み解くことで過去の出来事だけでなく、実際その場にいないと分からないようなことまで現代の私たちに教えてくれますね。
- 問1の答え「嵐」…道風の字から道を除き、残った風の上(かみ)に山を書くから。
- 問2の答え「一」…上・下・母・子の字をよく見れば分かります。
- 問3の答え「蛤」…海の道、つまり浜が十里に足らない(つまり九里)だから。


コメント欄