江戸っ子も将軍も夢中だった!? 江戸のお菓子文化のおいしい秘密
- 2025/07/31
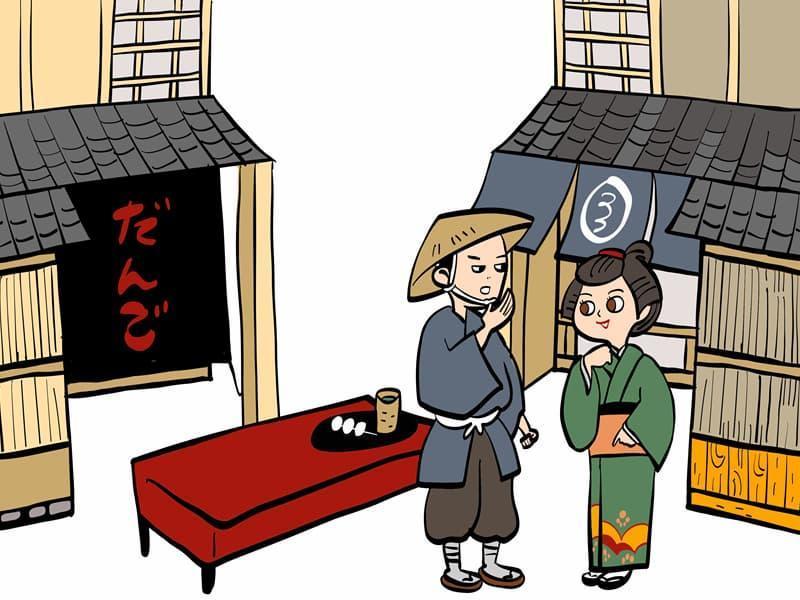
四季折々の行事の時しか食べられない特別なお菓子もあり、人々はさぞかし待ち遠しく思ったことでしょう。今回は江戸中期に流行した和菓子から、江戸っ子たちのお菓子事情を探っていきます。
良薬は口に甘し?砂糖は長寿の妙薬だった
砂糖が伝来したのは奈良時代、偉大な僧侶・鑑真により唐からもたらされたと『種々薬帳』に記されています。当時の砂糖は貴族しか口にできない高級品で、嗜好品よりも長寿の薬として重宝されていました。延喜18年(918年)に編纂された日本最古の薬物辞典『本草和名』にも薬と記述されています。戦国時代に南蛮貿易が始まると、宣教師が色とりどりの金平糖を持ち込み、為政者に献上しました。第六天魔王の異名をとる戦国武将・織田信長も舶来菓子を好み、明智光秀を介し、長宗我部元親に大量の砂糖を貢がせています。
そんな信長の好物は干し柿で、手柄を上げた家臣や所領の戦災孤児に施した記録が残っています。信長は下戸だったので、そのぶん甘味を好んだのでしょうね。

江戸時代には長崎の出島を通じ、中国やオランダから白砂糖が入ってきました。これはまず商人に落札されたのち、船で大坂の薬種問屋へ運ばれ、さらに仲買人を介して全国に広まります。それ以前から薩摩藩管轄の琉球で黒糖が作られていましたが、全体の割合から見ればごく少量でした。
国内で本格的な生産が始まったのは寛政年間、正徳5年(1715年)の長崎新令が発端。8代将軍徳川吉宗も享保の改革の一環として砂糖作りを推し進め、讃岐で和三盆が誕生しました。
享保3年(1718年)には日本初の和菓子製法書『古今名物御前菓子秘伝抄』が編纂され、庶民も徐々にお菓子を楽しめるようになりました。とはいえまだまだ値段は高く、町奉行や大名が取り交わす贈答品や、遊女への貢ぎ物の印象が強かったのは否めません。
国産白砂糖が普及する前の江戸っ子は、一日二食で足りない栄養を補うため、水飴と雑穀を練って作った雑菓子を間食していました。これが駄菓子の語源で、黒砂糖やザラメを混ぜて甘味を付けることもありました。
茶の湯の添え物の和菓子はやがて江戸に下り、桜餅・柏餅・大福・金鍔・甘納豆・干菓子が誕生。団子とお茶を供す茶屋も増え、門前町や城下町は賑わいを増していきます。羊羹や饅頭は特に好まれ、古典落語『まんじゅうこわい』が人気を集めました。

和菓子と茶道の切っても切れない関係
和菓子と茶の湯は縁が深く、共に手を取り合って進化してきた間柄です。安土桃山時代の著名な茶道家・千利休は、南蛮渡来の芥子の実を混ぜた芥子餅を好み、お茶請けとして美しい和菓子を添えました。茶道の世界には懐石のデザートに当たる主菓子と濃茶を飲み終えた後に薄茶と出される干菓子が存在します。四季の移ろいや花鳥風月を表現した練り切りは主菓子の最上級に属し、濃茶で嗜むのが様式美。主菓子は上生菓子と半生菓子を含みます。水分量が少ない干菓子は薄茶に合わせると風味が引き立ちました。
代表的な主菓子は寒天・くずもち・きんとん。干菓子は落雁・煎餅・有平糖・洲浜・寒氷。茶道の主役はあくまでお茶。それ故最初に和菓子を食べ、甘くなった口の中をほろ苦い抹茶で改めます。和菓子は必ず先に食べきること、お茶とお菓子を交互に口に運ぶのはマナー違反でした。
我々がイメージする和菓子はもとは茶の湯の添え物であり、発祥地にちなんで京菓子と呼ばれていました。上質な白砂糖を使った京菓子は江戸っ子の憧れ。当時は関西が流行の中心地だったので、良い物は関東に下って来るのが必然でした。下ってこないものはその価値がないとして、「くだらない」の語源となりました。

和菓子の最盛期は江戸時代 歴代将軍が好んだ甘味とは
和菓子と幕府の関係を語る上で、平安時代から続く行事・嘉祥は外せません。これは楊弓で的を射て、敗者が勝者に中国の銭「嘉定通宝」 16枚と菓子を献上する習わし。徳川家康はこれを重んじ、毎年6月16日には江戸城大広間に2万個以上の饅頭を並べ、直接手渡しで家臣に配りました。
将軍に納められた和菓子は嘉祥菓子と呼ばれ、今でも和菓子屋で売られています。家康個人は静岡銘菓の安倍川餅を好んだそうです。
徳川吉宗の祖父・徳川頼宣(よりのぶ)も大の甘党。幼少期から総本家駿河屋の和菓子が好きだった彼は、駿河に居を移す際に店も移転させ、のちに興す紀州徳川家の献上品に命じています。駿河屋の看板商品・本ノ字饅頭は参勤交代の携行食としても人気でした。
わざわざ京都の職人を招き、自分好みの菓子を作らせる将軍もいました。徳川光圀は友の誕生日に饅頭100個を特注。古希の祝いにちなみ、全体の重さが70匁(260キロ)になるように調整した徹底ぶりには脱帽です。
料理が趣味の13代将軍徳川家定は、江戸城内の畑で採れたサツマイモやカボチャをすり潰し、饅頭・カステラを作っていました。将軍お手製のお菓子……気になりませんか?
14代将軍徳川家茂は徳川きっての甘党。文久3年(1863年)の上洛の道中も、全国から献上された和菓子を食べていました。彼の好物は柚子と餅米を練った柚子餅。淀川を行き来する舟が「くらわんか」と連呼して売り付ける、くらわんか餅もお気に入りだったそうな。
他にも氷砂糖・カステラ・最中・氷砂糖・金平糖・三色菓子を愛し、公務の傍ら常に摘まんでいた為、齢21にして重度の虫歯と脚気を患ってしまいます。お菓子の食べ過ぎが夭逝に繋がったというのは邪推でしょうか?
最後の将軍徳川慶喜がカステラを好んだ史実は有名。慶応3年(1867)には大阪城に英・仏・蘭・米の外交官を招き、晩餐会でデザートを振る舞っています。
気になる献立はカステラ・メレンゲ・ヌガー・オランジェット・蒸しケーキ。将軍様のご用命で馴染みのない洋菓子を再現することになった、お抱え職人の苦労が偲ばれますね。外交官たちの評判は上々で、皆口々に洋菓子の出来栄えを絶賛したそうです。
そんな慶喜と家茂が贔屓にしていたのが名店「とらや」の羊羹。「とらや」は御所と公家と幕府に和菓子を納品しており、5代将軍徳川綱吉や吉宗の心も射止めました。
おわりに
以上、江戸っ子と和菓子に纏わるコラムでした。江戸中期まで白砂糖がなかなか手に入らなかったと聞いて、現代に生まれたことを感謝しました。茶の湯と共に歩んできた歴史を知ると、雅な見た目にこだわり、四季折々の情感を取り入れた和菓子の味わいが一層奥深くなりますね。「とらや」の羊羹が将軍たちに愛されていたのは納得しかありません。【主な参考文献】
- 青木直己『図説 和菓子の歴史』(筑摩書房、2017年)
- 山本博文『江戸時代から続く 老舗の和菓子屋』(双葉社、2014年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。




コメント欄