脂を取るのか、血を取るか? ~纐纈(こうけつ)城の伝説
- 2025/07/17

「ここで人さらいに会うと、血を抜かれるんだって……」そんな、物騒な都市伝説を聞いたことはありませんか?もしくは学校の怪談や、昔話などでも。
想像しただけでゾッとしてしまう、「血抜き」もしくは「血取り」にまつわる言い伝え。それは、太らせた後に体の脂を絞りとられるという、「脂取り」の話として伝わっている場合もあるとか。
今回は、こうした「血取り」「脂取り」にまつわる伝説の歴史について調べてみました。
想像しただけでゾッとしてしまう、「血抜き」もしくは「血取り」にまつわる言い伝え。それは、太らせた後に体の脂を絞りとられるという、「脂取り」の話として伝わっている場合もあるとか。
今回は、こうした「血取り」「脂取り」にまつわる伝説の歴史について調べてみました。
纐纈(こうけつ)城伝説とは
「血取り」伝説は、古くは平安時代末期の成立とされる『今昔物語集』や、鎌倉時代前期の成立とされる『宇治拾遺物語』所収の「慈覚大師(じかくだいし)、纐纈(こうけつ)城へ入り行く事」というお話に登場します。慈覚大師とは第3代天台宗延暦寺座主である円仁(えんにん。794~864)の別名で、最後の遣唐使として唐に渡った僧でもありました。「纐纈城」の伝説はどんなお話なのか、簡単に見てみましょう。
昔、慈覚大師が仏法を学ぶために唐へ渡ったところ、唐の第18代皇帝・武宗(ぶそう)が廃仏令を出したために、捕まりそうになった。
それらの混乱から慈覚大師が逃げる途中、高い塀で囲まれた集落があり、中へ入ると人のうめく声が聞こえる一軒家があった。
家の中を見てみると、人が縛られて天井から吊り下げられ、血を流していて、下には血を受ける壺が並べられていた。
慈覚大師は驚いて、近くにいた人へ「これはどうしたことか」と聞くと、「ここは纐纈城です。ここへ来た人は、まず口がきけなくなる薬を飲まされ、太らされ、体の各所を刺されて血を抜かれます。その血で纐纈を染め、染まった布を売るのです」と知らされる。
その後、慈覚大師は仏法の導きによって無事に逃げだし、武宗が崩御したために仏法を学ぶことができ、日本へ帰国した。
「纐纈」という言葉は、手で書いても間違えてしまいそうな難しい漢字ですね。これはもともと布を染める染色に使う用語で、糸などで布を絞るという「絞り染め」をさします。
纐纈は日本の名字にも使われており、有名人の方もいらっしゃるようですね。纐纈という言葉には染色という意味しかありませんが、この伝説では「人の血で纐纈を染め、その布を売る」と記すことで、その残忍さを強調しているように思えます。
「血取り」「脂取り」伝説
さて、この纐纈城の伝説をもとに、後世ではさまざまなお話が生まれました。井原西鶴「人はしれぬ国の土仏」『本朝二十不孝』
江戸時代の作家・井原西鶴は、『本朝二十不孝(ほんちょうにじゅうふこう)』という浮世草子にて、親不孝を主題とした二十話を描いており、その中の「人はしれぬ国の土仏」という話に、「纐纈城」が登場します。主人公の藤助は親の言うことを聞かずに船旅へ出て、自らの欲に従った結果、唐の人々によって逆さまに吊り上げられ、脂を絞りとられるという責め苦に遭い、日本から来た僧へ「ここは纐纈城といって怖ろしいところだ」と知らせました。
僧は驚き、帰国した後に藤助の故郷へ立ち寄り、その話を伝えた、という内容になっています。
このお話では僧の名前が出てきませんが、先の「慈覚大師、纐纈城へ入り行く事」の話と同じく、「唐にある纐纈城」と、「吊られて体液を絞られる」、「日本からの渡僧」といったキーワードが出てきます。
昔話「脂取り」と子ぅ取り婆さん
日本では古くから「人を捕らえて太らせ、脂を絞りとる老婆」や「生き血を絞る染屋」に出会ったという昔話があり、北は青森県や岩手県、南は鹿児島県など、全国各地で語られています。これらの昔話はいずれも吊られて体液を絞られる場面があり、その結末は「絶体絶命のあと夢から覚める」という夢オチが多く、命からがら逃げだす、退治する、といったバリエーションもあります。
また、老婆が子どもをさらい、その血や脂を絞りとって南京皿(なんきんざら/中国で作られた色付きの磁器)の染付に使うなどといった噂もあり、「隠し婆」や「隠れ婆」などと呼ばれて恐れられていました。
明治4~6年(1871~1873)頃には、四国・中国地方の一部地域において、「子ぅ取り婆が子どもをさらって血や脂を取る」「異人が人体を焼いて膏(こう/あぶら)を取る」という噂が広まりました。
その後、噂は明治政府が血を絞りとるといった流言と合わさって、農民が暴徒化する事件が各地で起こり、「竹槍騒動」や「膏取り一揆」などと呼ばれました。
未完の伝奇小説『神州纐纈城(しんしゅうこうけつじょう)』
近代においては、明治20年(1887)に生まれ、怪奇・幻想小説ブームのさきがけと言われた伝奇作家の国枝史郎が、纐纈城の伝説をもとにして執筆した『神州纐纈城(しんしゅうこうけつじょう)』という長編伝奇小説があります。この小説の舞台は永禄元年(1558)、戦国時代の甲府。武田信玄の家臣、土屋昌恒(つちやまさつね)の甥である主人公・土屋庄三郎が、本栖湖の中にあるという纐纈城・水城(みずき)と自らの因縁を見いだし、その城に関わる人々の運命が描き出されるという物語で、未完に終わったものの、三島由紀夫にも高く評価されています。
中国にもあった「脂取り」の説話
一方、纐纈城の舞台とされる中国にも、「脂取り」の説話が伝えられていました。唐の時代に成立したとされる仏教説話集『冥報記(めいほうき/みょうぼうき)』では、ある金持ちの男が亡くなった際、殉死した従者が生き返り、あの世で主人が脂を取られていると語ります。
従者は、家の者がお経を唱えることで主人の脂が取られるのを妨害できると話し、家の者たちは主人の言いつけ通り仏像を作って法華経を唱えた、という終わりになっています。
血で布を染めることはできるのか?
ここで「血取り」の話に出てくる、人から絞りとった血で布を染めるという点に着目してみましょう。聞いただけで身の毛がよだちますが、本当にそのようなことは可能なのでしょうか。
古代に行われていた染色方法は、花びらや葉っぱなどを布へこすりつける「擦り込み」や、泥の中へ布を漬けこんで染めるといった「泥漬け」が主だったと考えられています。
その後、染色技術が発達する中で、染料に染まらない部分を作って染めあげることで模様をあらわす、「纈(けち)」という方法が確立します。
そこから、糸で絞って染める纐纈(こうけち)、蜜蝋で覆う臈纈(ろうけち)、板の間に布を挟んで締める夾纈(きょうけち)という、三纈(さんけち)の技法が生まれました。
こうした技法の元になった染色方法は、もともと弥生時代の3~4世紀頃に中国から伝わったと考えられ、奈良時代の美術工芸品を収蔵する正倉院(しょうそういん)にも、三纈で染められた布が多数保管されています。
※参考:正倉院HP「赤纐纈布(あかこうけちのぬの) 第52号(第73号櫃)」
また、植物を使って染色する際には、あらかじめ布を豆汁や牛乳などに浸してタンパク質を吸わせると色が染まりやすくなるという特徴があるものの、実際に動物の血などを使って染色するということは、現実的ではないようです。
なぜ纐纈(こうけつ)城伝説は広まったのか
先に引用した纐纈城の伝説は、慈覚大師が唐へ渡った時の出来事として語られています。しかし、慈覚大師が約10年にも及ぶ唐での生活などを記した旅行記『入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)』には、纐纈城についての記述はありません。
とはいえ、唐の第18代皇帝・武宗が道教に傾倒したことから仏教や外来宗教へ弾圧を行ったことは事実で、『入唐求法巡礼行記』によれば、慈覚大師もその影響を受けて、長安にて外出禁止の生活を送ることになりました。
その後、武宗の命により慈覚大師は還俗(げんぞく/出家した僧が再び俗世へ戻ること)をさせられるという災難に遭いましたが、俗人へ戻ったことにより長安での幽閉が解かれ、日本に帰国できたのでした。
遣唐使は渡航中の事故や病死なども多く、日本で慈覚大師の話を聞いた人々は、異国の地で弾圧を受けながらも帰還した慈覚大師が、どのように唐で過ごしていたのか、とても気になったことでしょう。
纐纈城の伝説は、そうした人々の興味や異国の地の説話などが合わさって生まれ、未知への恐れを抱く人々の心情から広まったのかもしれませんね。
おわりに
人の血や脂にまつわる伝説には、凄惨なイメージがつきまといます。「血取り」「脂取り」の話は、逆さに吊られた人間が体液を絞りとられる、という場面が特に強烈で、人々の記憶に残りやすく、炉端で語る昔話としても人気があるものだったのかもしれません。
人の血や脂を絞るなんて、実際には非効率と思えますが……。
なぜわざわざ人間を使うのかというところに、得体のしれない恐怖が見え隠れしている気がして、なんだか背筋が寒くなるのでした。
【参考文献】
- 小松和彦『神隠しと日本人』(KADOKAWA、2013年)
- 柳田国男『定本柳田国男集 第4巻』(筑摩書房、1963年)
- 『日本古典文学全集 : 現代語訳 第16巻』(河出書房、1955年)
- 柳田國男『遠野物語・山の人生』(岩波書店、1976年)
- 国枝史郎『神州纐纈城(Kindle版)』(青空文庫、2012年、底本の親本:1976年)
- 『日本国民文学全集 第12巻』(河出書房、1955年)
- 日本放送協会 編『日本昔話名彙 改版』(日本放送出版協会、1971年)
- 水木しげる『水木しげるの妖怪文庫 1』(河出書房新社、1984年)
- 東京大学出版会『講座日本歴史 7 (近代 1)』(東京大学出版会、1985年)
- 壬生台舜「叡山の新風 : 山家学生式<最澄>入唐求法巡礼行記<円仁>」『日本の仏教 ; 第3巻』(筑摩書房、1967年)
- 唐臨 撰, 内田道夫 編訳『校本冥報記』(志村良治、1955年)
- 木村光雄「染色の歴史と伝統技法」『繊維と工業 Vol.60』(繊維学会、2004年)
- 宮内庁HP:正倉院「正倉院宝物検索」(最終閲覧日:2024年10月17日)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
民俗学が好きなライターです。松尾芭蕉の俳句「よく見れば薺(なずな)花咲く垣根かな」から名前を取りました。民話や伝説、神話を特に好みます。先達の研究者の方々へ、心から敬意を表します。



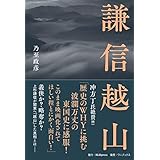




コメント欄