時代の流れとともにイメチェンする織田信長…残忍な悪役の評価から一転、勤皇家へ?
- 2025/07/03

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
そんな信長サマですが、ずっと一定の評価を得ていたのではなく、時代によって傲岸不遜・冷酷無比とされた時もあります。信長のイメージはどのように変わって来たのでしょうか?
信長のイメージって毀誉褒貶?勤皇の志し篤い?
信長が本能寺の炎に消えてから440年余り。豊臣秀吉から徳川家康へと天下の趨勢は移り、明治から大正・昭和・平成・令和、と時代が変わっても、常に信長という人物の事績は語られ続けます。しかしその評価は必ずしも一定ではなく、時代背景や時々の価値観の影響を受けて来ました。永禄11年(1568)、信長は室町将軍・足利義昭を奉じて上洛します。六角氏や三好氏が織田軍の京入りを阻もうと各所で抵抗しますが、いずれも織田軍に蹴散らされ、一行は9月26日に京都の東寺に入りました。
京都を制圧した織田軍の武力を背景に10月18日、義昭は征夷大将軍となります。これは日本史上において結構大きな出来事だったようで、戦前の歴史学者 W氏 は、室町と安土桃山時代の境をこの信長上洛に置いていますし、戦後のA氏も信長が天下布武を旗印に京都に入ったこの年を「日本の近世の幕開け」と位置付けています。
しかしそれまで地方の一有力大名に過ぎなかった信長の上洛は、当時の都人にとっては恐怖でしかありませんでした。100年前の応仁の乱と同じように、再び都が戦乱に巻き込まれるのではないか、とうろたえる者も多かったとか。
江戸時代では「不寛容で残忍な男」
時代は進み、江戸時代においては信長は不寛容で残忍な男とのイメージで語られます。これは信長の最期が、信頼していた家臣・明智光秀の裏切りによるものだった事が大きいのです。
当然両者の関係が問われ、伊勢長嶋一向一揆の鎮圧や比叡山焼き討ちに見られるような、敵対勢力に苛烈な態度で臨む信長の姿勢が強調されます。佐久間信盛や林秀貞など、長年信長に仕えた重臣でさえ不行跡を理由に突然追放されるなど、信長の不寛容な態度が光秀を謀反に走らせたとの解釈が強まりました。
江戸時代に奨励された朱子学が説く君臣の関係もこの説を補強します。朱子学者として有名な新井白石も自業自得として切って捨てます。
「天性残忍にして人を許すことが出来ない。その最後が良く無かったのも自分が招いたことで、不幸と言うには及ばない」
江戸時代に人気を集めた歌舞伎でも、信長の時代を取り上げた演目がいくつか作られました。その中でも信長は狭量で怒りっぽい性格の人間として描かれ、本能寺事件も彼の不徳の致すところとして片付けられます。
例えば『時今也桔梗旗揚(ときはいまききょうのはたあげ)』と言う芝居では、明智光秀は「武智光秀」として織田信長は「小田春永」として登場しますが、春永が光秀を陰湿に虐める場面が見所として登場します。特に二段目の「馬盥の場」では、光秀が春永からの愚弄を懸命に耐える場面が観客の心を打ち、春永は完全な敵役です。
豊臣秀吉の出世物語『絵本太閤記』でも同じく、小田春永が同じような役どころで登場し、光秀はすっかり悲劇の主人公となります。本能寺の真相も耐えに耐えた者がついに己を押さえかね、破滅への道を辿る日本人好みの物語となり、信長悪役のイメージが定着しました。
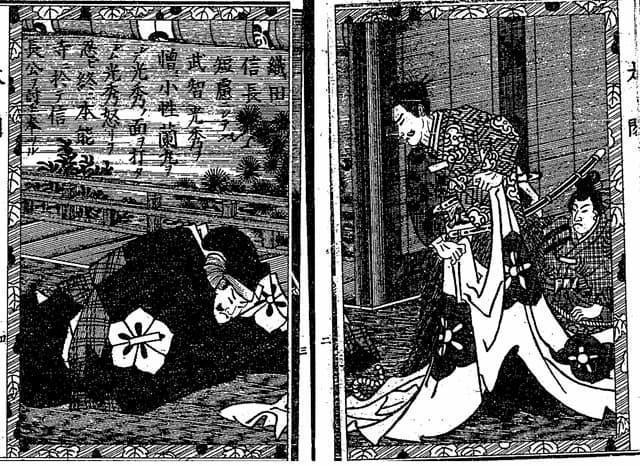
儒教道徳が尊ばれた江戸時代は、信長は不徳の君主として嫌われましたが、謀反を起こした光秀も不忠の臣です。「君君たらずとも臣臣たれ」ですから。江戸の儒学者湯浅常山は次のように光秀を切って捨てています。
「君臣共に悪逆の者ども、終わりを全うしなかったのも道理である」
しかし同時代の京都町奉行所与力が書いた『翁草』では「明智日向守の逆心は皆信長公の行いの故」と信長の方を責めており、これが民情に近いものでした。
幕末・明治に変化していく評価
さらに時代は進み、信長の評価は変化して行きます。頼山陽の『日本外史』では、「信長は礼節を欠く人物ではあるが、御所を修築したり禁裏御料を再興した行為は皇室を尊崇するものである」と高く評価しています。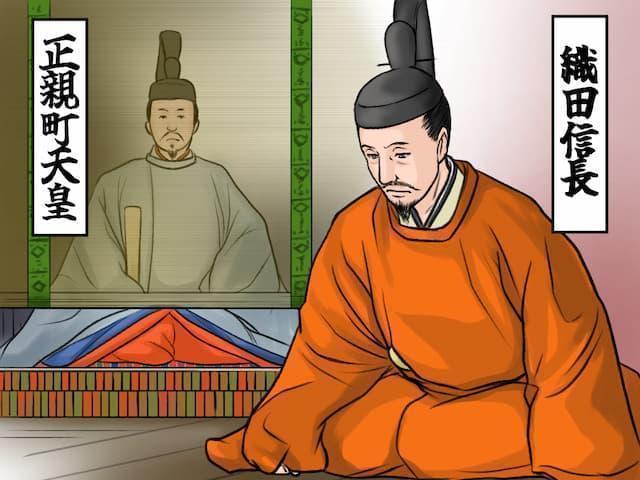
幕末に向かうにつれて、こうした傾向は強まり、尊王攘夷思想の基で “勤皇家信長” のイメージが定着して行きました。
幕末の館林藩士・岡谷繁実が著した『名将言行録』では、「信長上洛の本意は天皇を助けて天下を治めるためであった」旨が書かれています。おりからの勤皇思想の興隆が信長の行動に新しい解釈をもたらしました。
明治時代になると、明治天皇が朝廷を篤く遇した信長の功績を称え、神社を建てるよう命令され、朝廷より京都船岡山に別格官幣社に列せられた信長を祀る建勲神社(たけいさおじんじゃ)が建立されています。
また、「足利義昭が将軍職に就き、都の秩序が回復して行った背景には、信長の皇室尊崇の心が篤かったため」との解釈が通説になります。上洛後に信長が御所を修築したり禁裏御料の復興を行う等の行動も、信長の朝廷への忠節を表しているとされます。
このような意味付けは明治維新後にさらに顕著になっていったのです。
近世の信長像
近世以降の信長像は乱世の英雄であり、魅力に溢れた人物として定着し、清州城や桶狭間などは信長ゆかりの史跡として整備され、郷土の偉人として顕彰する動きが強まります。
映画では、昭和29年(1954)に片岡千恵蔵主演の日活映画『風雲児信長』が、5年後の昭和34年には大映から市川雷蔵の『若き日の信長』が、同じ年に東映でも中村錦之助主演で『風雲児信長』が公開されるなど、各社若手の看板俳優を起用しての作品が次々と発表されました。
小説においても、坂口安吾が昭和27年に夕刊紙新大坂連載の『信長』を、旧習を打破する近代的合理主義者として書き、昭和30年からは山岡荘八が信長の数々のエピソードを盛り込んだ『織田信長』を執筆します。この作品が世に与えた影響は大きく、その後の果敢な乱世の英雄としての信長像を定着させました。
おわりに
現在でもゲーム『信長の野望』をはじめ、コミック『新・信長公記』『信長のシェフ』『信長協奏曲』映画『本能寺ホテル』など、信長モノは大いに人気です。その中で信長は勇猛果敢・魅力的ではあるが、一癖も二癖もある人物として描かれています。NHK大河ドラマでも信長は度々取り上げられ、苛烈な性格・果敢な行動力・斬新な発想・精悍で胆力のある男とのイメージが定着しました。【主な参考文献】
- 呉座勇一『戦国武将、虚像と実像』(角川書店、2022年)
- 岡本良一/編『織田信長事典 コンパクト版』(KADOKAWA、2007年)
- 大石学/編『戦国時代劇メディアの見方・つくり方』(勉誠出版、2021年)





コメント欄