徳川家康の壮大な遺産の行方 ~息子たちに受け継がれた巨大コレクション
- 2025/04/30

天下人・徳川家康が亡くなって約400年の歳月が過ぎていますが、実は家康の遺産は大切に受け継がれて、現代に伝えられています。遺産は主に将軍家と御三家に譲られました。
天下人が集めた数々のコレクションとは一体どんなものなのか、とても気になりますよね。今回は、尾張徳川家に伝来した家康の遺産である「駿府御分物」(すんぷおわけもの)を紹介したいと思います。
天下人が集めた数々のコレクションとは一体どんなものなのか、とても気になりますよね。今回は、尾張徳川家に伝来した家康の遺産である「駿府御分物」(すんぷおわけもの)を紹介したいと思います。
天下人・家康の膨大な遺産と相続
徳川家康は元和2年(1616)4月17日、75歳にて駿府城で大往生を遂げ、長寿を全うしました。生前、家康は膨大な金銀財宝や道具類、貴重な書籍などを駿府城に保管していましたが、のちに遺産として主に徳川御三家に分け与えられました。徳川御三家とは、徳川家康が徳川の血筋を絶やさないようにするために、3人の息子たちを将軍家から独立させた大名家で、尾張徳川家・紀州徳川家・水戸徳川家の三家を指します。
- 九男 義直(よしなお):尾張徳川家の初代当主(1600~1650)、石高62万石
- 十男 頼宣(のりのぶ):紀州徳川家の初代当主(1602~1671)、石高56万石
- 十一男 頼房(よりふさ):水戸徳川家の初代当主(1603~1661)、石高35万石
御三家は親藩(しんぱん。徳川家一門の子孫で大名となったもの)の中においても最高位に位置付けられており、将軍家と同様に「徳川」の姓を名乗ること、「三つ葉葵」の家紋を使用することが許されました。
「駿府御分物」とは?
家康の遺産は、「駿府御分物」と呼ばれ、詳細は『駿府御分物御道具帳』という記録に残されています。この遺産には、以下のようなものが含まれていました。遺金:約200万両(現代の価値で約2000億円)
尾張家と紀州家に各40万両、水戸家に26万両分に分けられました。貴重な書物や古典籍
特に日本の旧記や貴重書は江戸城の紅葉山文庫(もみじやま)に保管され、それ以外は御三家に分与されました。『御書籍目録』によれば、尾張家に367部2825冊の書籍が譲られており、これらは「駿河御譲本」と呼ばれています。美術品・道具類
家康の財産には、天下人にふさわしい質の高い美術品や道具が含まれていました。残念ながら、多くの遺品はほとんどが使われて残っていません。尾張家本『駿府御分物御道具帳』が語る歴史
『駿府御分物御道具帳』は御三家それぞれに作成されたと考えられています。尾張徳川家においては、武具や刀剣、茶道具、衣類など幅広い種類の家康の膨大な遺産が、元和2年(1616)11月から約2年の間にわたり、8回に分けて分配されました。これらは古くから存在が知られている尾張家本『駿府御分物御道具帳』全11冊にて、詳細に記されています。尾張徳川家に伝わった約200件は現在、以下のように確認され、徳川美術館にて大切に保管されているのです。
- 刀剣:26件
- 茶道具:20件
- その他の遺品:137件

息子、そして子孫たちに受け継がれた漢籍コレクション
家康の古典籍収集と学問
徳川家康は学問を重視して、文治政策を進める中で多くの書籍を収集、その保存と活用に尽力。木活字印刷による伏見版書籍や銅活字印刷による駿河版書籍の刊行を命じ、日本における印刷文化の発展に大きく寄与しました。家康が収集した膨大な書籍は「駿河文庫」と呼ばれ、その蔵書数は約1万点にのぼったとされています。家康の没後、将軍家に引き継がれる一部の蔵書を除き、尾張、紀伊、水戸の御三家にて5:5:3の割合で分配されました。
尾張家に引き継がれた蔵書群は「駿河御譲本」と呼ばれ、儒教経典、歴史書、仏教書、諸氏百家(しょしひゃっか)の書、漢詩文集など多岐にわたる分野の書籍が含まれていました。
父から息子へ
尾張家初代当主の徳川義直も、父・家康の影響を受けて書物の重要性を認識し、大坂の陣以降に独自の書籍収集を始めます。その後、「駿河御譲本」によって蔵書がさらに充実し、「御文庫」の創設へとつながりました。また、義直は書籍の収集以外にも『類聚日本記』(るいじゅにほんぎ。引用:”『日本書紀』から『日本三代実録』までの六国史をそのまま年代順に一つにまとめたものである”)など、自ら主導で優秀な学者を招いて編纂事業にも力を注ぎました。
初期に収集された尾張家の書籍の約8割は、中国や朝鮮からもたらされた漢籍であり、その多くが朝鮮で印刷された中国の古典でした。当時、儒学が盛んだったことから、大名たちは中国の文化を教養として身に付けることを重視していました。
家康が収集した漢籍は朝鮮版が中心でしたが、義直やその子である徳川光友(みつとも/尾張家2代当主/家康の孫/1625~1700)が収集した書籍には、貿易を通じて日本にもたらされた明時代(1368~1644)の出版物が多く含まれています。これらの書籍は、文化的な価値が高いだけでなく、当時の東アジアにおける書物の流通状況を反映しており、中国・朝鮮との教養への影響の深さを示しています。
家康から始まった書籍の収集と保存は、優秀な学者を輩出させ、尾張藩の学術文化の担い手を教育することにつながりました。また、息子の義直の収集・編纂事業は、名古屋における学術文化発祥の原点とも言えるのです。
「駿河御譲本」に関して、紀伊家・水戸家についての実態を確認することが残念ながらできません。しかし、明治期に流出したものの、現在まで尾張家に受け継がれる259件1862冊は、原型をよく伝える存在として、とても貴重なコレクションとなります。
あとがき
天下人・徳川家康の膨大な数のコレクション。いかがでしたでしょうか?ちなみに私は戦国三英傑である織田信長や豊臣秀吉のコレクションも家康に負けないぐらい存在したと考えています。ただ、織田家は本能寺の変(1582)で衰退し、豊臣家は大坂の陣(1614〜15)で滅んだため、残念ながら両家に関する遺品等はわずかにしか残っていません。信長と秀吉それぞれの趣味趣向によるコレクションの特徴があったとは思いますが、とても気になりますね。
没後400年以上の時が過ぎた現在にも家康の遺産が伝えられてきたのは、ひとえに尾張家が書物の整理・管理を大切に行ってきた経緯があります。明治末期から昭和初期にかけて旧大名家の没落によって、道具の売り立てが相次ぎました。
こうした中、昭和6年(1931)に尾張徳川家19代当主・徳川義親氏(よしちか)が財団法人を設立、徳川美術館の創立によって、尾張家伝来の大名調度や蔵書を後世に伝え守ることができたのです。

義親氏の活躍なくして、現在に受け継がれてないと思います。先人たちが守ってきた文化財を大切にしていきたいですね。
【参考文献】
- 徳川美術館/編『開館80周年記念夏季特別 没後400年徳川家康~天下人の遺産』(徳川美術館 2015年)
- 名古屋市蓬左文庫/編『蓬左文庫 ~歴史と蔵書~』(名古屋市蓬左文庫 2015年)
- 『愛知県図書館デジタルアーカイブ』
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
生まれ育った「愛知県」の歴史を中心に発信する歴女ライターです。
★愛知学院大学文学部歴史学科卒業
★日本史専攻
★専門→尾張藩、源氏物語、刀剣、城、戦国武将、新選組、神社仏閣(元巫女)など
本業→大学図書館の現役司書(6年目)
資格→博物館学芸員、図書館司書、学校司書
☆図書館司書という ...





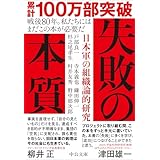


コメント欄