江戸時代の恋愛事情を覗き見!恋文はどんな風に書かれていた?
- 2025/09/05

想い人への気持ちをしたためて送る「恋文」。今で言うラブレターですね。メールやSNSが主流の現代では、手書きのラブレターは珍しくなってきました。古代の日本では和歌を送り合う習慣から恋文が発展しましたが、特に江戸時代では、文字の読み書きができる庶民が増えたことで多くの恋文が交わされていたようです。
江戸時代の識字率は6割を超えていたと言われます。彼らはどんな恋文を交わしていたのでしょうか?当時の恋愛事情と、流行していた恋文の指南書について見ていきましょう。
江戸時代の識字率は6割を超えていたと言われます。彼らはどんな恋文を交わしていたのでしょうか?当時の恋愛事情と、流行していた恋文の指南書について見ていきましょう。
恋文の意外な歴史
恋文の始まりは、古代日本で和歌を贈り合ったことだとされています。日本最古の和歌集『万葉集』には、男女の恋や親しい人との情をうたった「相聞歌(そうもんか)」が多く収録されています。
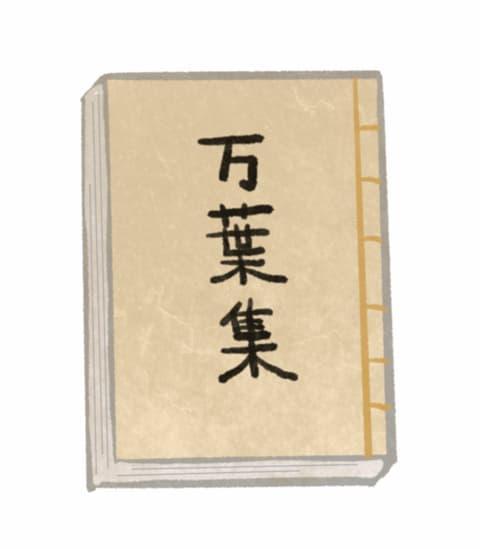
貴族のイメージがある恋の和歌ですが、『万葉集』には文字が書けない農民や庶民の歌も含まれていました。では、彼らはどうやって歌を作ったのでしょうか?実は「歌垣(うたがき)」と呼ばれる男女の出会いの場で、求婚の歌を互いに唱和し、合意を確認していました。そうした歌が口承で受け継がれ、『万葉集』に収められたと考えられています。
『万葉集』は、庶民の恋の歌がわかる貴重な資料なのです。
時代が下り、戦国時代には豊臣秀吉が妻や側室に頻繁に手紙を送っていたことも知られています。江戸時代になると、寺子屋や教科書が普及し、読み書きができる人が大幅に増えました。寺子屋で使われた教科書「往来物(おうらいもの)」は、元々手紙の文例集をまとめたものです。当時は、綺麗な字で読みやすく手紙を書くことが重要視されていたため、字を学べるうえに手紙も書ける実用的な往来物は重宝されました。
この往来物には、一般教養だけでなく、恋文の書き方を示した指南書もあったそうです。特に恋文は『源氏物語』などに出てくる和歌の教養も必要とされたことから、専門の指南書が多く作られたとされています。江戸時代の人々も、指南書を参考にしながら試行錯誤して恋文を書いていたのですね。
意外と不自由?江戸の恋愛事情
江戸時代の社会構造を見てみると、武家に生まれた女性は外出が制限され、教養を学び、身分の高い相手と結婚することが多かったようです。また、裕福な町家の娘も、身分の釣り合う相手と結婚するのが常識でした。儒教の教えが浸透していた当時、女性の地位は非常に低かったようです。「三従四徳(さんじゅうしとく)」という女性が守るべき教えの中には、「結婚前は父に、結婚後は夫に、夫の死後は子に従う」というものもありました。そんな時代、人々の恋愛はどのように描かれていたのでしょうか。
江戸時代前期に書かれた仮名草子『恨(うらみ)の介』は、高貴な女性に恋い焦がれる悲恋の物語です。これは、中世から続く御伽草子(おとぎぞうし)の流れを汲んだ作品とされます。
一方、井原西鶴が書いた『好色一代男』などの浮世草子では、一般庶民のドラマチックな恋が人気を博しました。同じく井原西鶴の『好色五人女』では、身分や社会のルールから外れた人々の悲劇的な結末が描かれています。
当時は、こうした男女の恋愛だけでなく、男色や遊女との恋など、さまざまな形の恋愛が物語として人々の興味を引いていたことがうかがえます。
これが江戸のラブレター!
江戸時代では、男性は漢字、女性はひらがなを多く使う傾向があり、初めての恋文は男性から送るのが多かったようです。恋文の指南書『詞花懸露集(しかけんろしゅう)』には、平安時代の歌合「堀河院艶書合(ほりかわいんえんじょあわせ)」が収められています。江戸の人々は、平安時代の和歌のやり取りを参考にしていたのですね。
指南書には、こんなアドバイス(現代語訳)が載っています。
恋文の書き方は通り一遍ではなく、心をこめて細やかに興味深く書き重ねるのがよろしい。歌でも一文字ちがうだけで別の意味になるが、文章も同様である。初めから終わりまで流れるように書かなければならない。
では、実際の文例(現代語訳)を見てみましょう。
男性から初めて女性へ送る手紙
風のたよりに私の想いをのせてほしいとは思っていても、つたなく思いますので、大変苦しい心の深さをご推量いただき、決して浅くない気持ちを知ってくださいませ。
住吉の浅香(あさか)の浦で漁るような甲斐のある今後をお知らせください。
「恋しい気持ちが風のたよりで届くようにと思ったけれど、それでは心もとないので手紙を書きました。どうか返事をください」という内容が、女性にも読みやすい仮名が多めの文章で丁寧に書かれています。
この文に対する女性の返答は以下の通りです。
女性からの返事
上の空のような風のたよりには期待できず、私があなたに思いを寄せても悔しいことになるのではないかと思います。
住吉の岸に寄せる白波のように、あなたに会う機会があればお会いしたいと思います。
面白いことに、当時は男性から恋文をもらった際、一度は断るそぶりを見せるのが良いとされていたようです。現代のやり取りとはかなり違う印象ですが、今も「手紙の書き方」の本が売られているように、お手本を参考にする文化は昔も今も変わらないのかもしれません。
遊女の切ない恋文
遊女とお客の関係は、お金を介した疑似的な恋愛です。多くの客を抱える遊女は、それだけたくさんの恋文をやり取りしていました。遊女が恋文を書いた後、紅をつけた唇で紙の端をくわえて色をつける習慣があったといいます。これは「天紅(てんべに)の文」と呼ばれ、歌舞伎でもこの手紙が読まれることがあります。
吉原の花魁が登場する以前、最高位にあった高尾太夫(たかおだゆう)が書いたとされる有名な恋文(現代語訳)を見てみましょう。

昨夜は船でのお帰り、ご無事でしたでしょうか。お宅でのおとりなしもうまく参りましたでしょうか。お目にかかったままで忘れていないからこそ、かえって思い出さないのです。
あなたは今、駒形あたりをお帰りの頃でしょうか。夜明けにほととぎすの声が聞こえます。
「いつでもあなたのことを考えているから、あえて思い出す必要がない」という粋な表現が素敵ですね。
また、遊女向けの恋文指南書『遊女案文(ゆうじょあんもん)』には、「初めて会った客」「常連の客」など、相手のタイプ別の文例が書かれています。
喜多川歌麿の絵には、文を書いている途中に物思いにふける遊女の姿が描かれています。手に持った文の端は紅に染まり、「御ゆかしさ 一筆とりむかい参らせ候」と書かれています。
意味は「あなたのことを恋しく思うので、筆をとりました」といったところでしょうか。恋しさのあまり、筆をとった後に何を書こうかと考える遊女の色香と教養がうかがえますね。遊女と客という関係の中でも、文を送り合うことで恋心が高まったり、時には冷めたりすることもあったのでしょう。
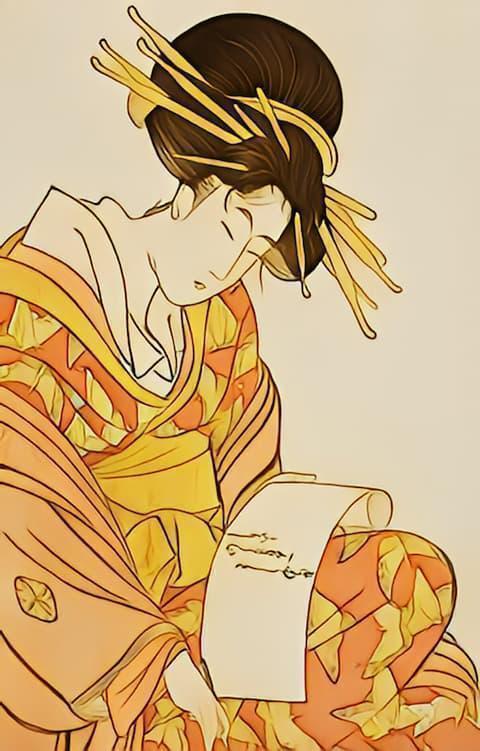
おわりに
墨をすり、筆をとって墨をつけ、紙へ書く。江戸時代に不可欠だったこの習慣は、現代においてスマホのメッセージへと変わりました。私たちが「さっき送ったLINE、誤字ってる…」と焦るように、江戸時代の人々も「書き方、間違えたかも!?」と不安に思っていたのかもしれない、と思うと、親近感が増しますね。どちらが良い悪いということではないのですが、心をこめて書かれた手書きのラブレターは、今も思いの丈を伝える術として効力があるものだと思います。
「年賀状じまい」が広まる昨今ですが、だからこそ、恋しい人へ改めて恋文を書いてみるのも素敵かもしれませんね。
【参考文献】
- 日本歴史編集委員会『恋する日本史』(吉川弘文館、2021年)
- 綿抜豊昭『江戸の恋文』(平凡社、2014年)
- 板坂則子『江戸時代 恋愛事情』(朝日新聞出版、2017年)
- 東京都藝術大学大学美術館『大吉原展 図録』(東京新聞、テレビ朝日、2024年)
- 石川謙『往来物について』(大東急記念文庫、1961年)
- 樋口清之『恋文から見た日本女性史』(講談社、1965年)
- 辻勝美「中世女流日記文学と手紙」『語文 92』(日本大学国文学会、1995年)
- 藤原公実, 周防内侍『堀河院艶書合』(奈良屋長兵衛、1698年)
- 喜熨斗古登子『吉原夜話 (青蛙選書)』(青蛙房、1964年)
- 三遊亭円生『円生古典落語 1』(集英社、1979年)
- 長松軒『遊女案文』(扇屋利助ほか1名、1796年)
- 国立国会図書館「本の万華鏡 第26回 恋の技法-恋文の世界-
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
民俗学が好きなライターです。松尾芭蕉の俳句「よく見れば薺(なずな)花咲く垣根かな」から名前を取りました。民話や伝説、神話を特に好みます。先達の研究者の方々へ、心から敬意を表します。



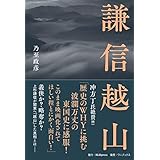

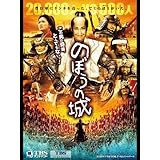
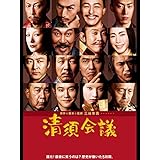

コメント欄