悪事をチクる?三尸の虫が天帝に報告…江戸を賑わせた「庚申講」の驚くべき実態
- 2025/10/27

起源は古代中国 道教由来の「庚申信仰」
庚申講、または庚申待(こうしんまち)とは、庚申(かのえさる)の夜に神仏を祀り、皆で料理を持ち寄り徹夜をする行事です。「宵庚申(よいごうしん)」、「おさる待ち」とも呼ばれ、古くから村単位で行われてきました。その起源は古代中国の民俗宗教・道教(どうきょう。儒教・仏教とともに、中国三大宗教のひとつ)の伝説に遡ります。人間の頭、腹、足には三尸の虫が棲んでいます。この三虫は、頭の「上尸(じょうし)」、腹の「中尸(ちゅうし)」、足の「下尸(げし)」に分かれ、常に人間の悪事を監視しています。そして、庚申の日には体内から抜け出て、宿主の行いを天帝(てんてい)に報告する役割を担っていました。道教の経典『太上三尸中経(たいじょうさんしちゅうきょう)』によると、大きさは2寸(約6センチ)ほどで、子供や馬に似た形をしていると記されています。
三尸の虫は、宿主が寝ている間に体内を抜け出し天に昇り、日頃の行いを天帝に告げ口します。天帝は、三尸の報告をもとに悪人の寿命を縮め、さらには地獄・餓鬼・畜生の三悪道のうち、死後に送り込む世界を決定したため、閻魔大王と同一視する説もあるほどです。
なぜ三尸は宿主の悪事を告げるのか。それは宿主が死ぬと自由になれるからだと言われています。4世紀に成立した葛洪『抱朴子』には、三尸の虫は実体を持たない鬼神の類であると記されていました。
同様の記述は『雲笈七籤』内『太上三尸中経』にも認められ、彼等が宿主の死を願うのはその肉体から解き放たれ、早く鬼神として祀られたいからだとか。宿主が死ぬとパワーアップできるなんて、なかなか面白い仕組みですね。そして、この三尸を避けるための呪文も存在し、『大清経(たいせいきょう)』に書かれたものが、後に『庚申縁起』を介して広く庶民に広まっていきました。
三尸はそれぞれ、頭に棲む上尸が「彭侯子(ほうこうし)」、腹に棲む中尸が「彭常子(ほうじょうし)」、足に棲む下尸が「命児子(めいじし)」と呼ばれています。
上尸は脳に巣食い、首から上の病気や暴食を引き起こし、中尸は内臓疾患や散財の原因に、下尸は腰から下の病気と色欲を司るとされました。『太上除三尸九虫保生経』では、上尸が道士、中尸が獣、下尸が牛頭(ごず)の怪人の姿で描かれています。
庚申講が日本に伝来したのは8世紀後半の奈良時代。当初は貴族の間でのみ行われ、庚申の夜は大勢で集まり、夜通し詩歌や和歌、歌舞音曲を楽しみ、碁や双六(すごろく)で遊んで過ごしました。「庚申の日は静かに夜明かしせよ」という道教の教えに反し、豪勢な宴が催されたことから、実質的には宴会の口実だった面も否めません。菅原道真や清少納言の『枕草子』にも庚申講の夜の様子が描かれています。
江戸時代初期に流行 青面金剛明王が「庚申さん」に抜擢
奈良時代に伝来した庚申講は、神仏習合を経て、江戸時代初期に最盛期を迎えます。この頃には地方の農村まで広がり、至る所に「庚申塔」が建てられました。庚申塔は、庚申講を3年で18回成就した記念碑であり、塚の上に石塔を置いた外見から「庚申塚」とも呼ばれます。そこには天帝や馬頭観音(ばとうかんのん)、仏教の本尊である「青面金剛」、神道の祀神・猿田彦などが彫られ、旅の道標としても道端に置かれました。干支の申(さる)にちなんで、「見ざる・言わざる・聞かざる」の三猿を彫ったものも数多く存在します。

珍しい例では、ぎょろ目を剥いた青面金剛が三猿を踏みつける庚申塔もあります。これは三猿を三尸に見立てて退治しているのでしょうか?青面金剛は病気から人々を守る明王様ですから、体に不調をもたらす三尸を撃退するには適任だったのでしょう。千葉県野田市には全853基の庚申塔が現存しており、他の地域では見られないユニークな意匠にお目にかかれますので、興味がある方はぜひ行ってみてください。都内で最も多いのは足立区で、合計168基が文化財に登録されています。
庚申(かのえさる)は、十干十二支(じっかんじゅうにし)の組み合わせにより、60日周期で巡ってくる日です。そのため、庚申講の日には村中の人々が一軒の宿に集まり、三尸が抜け出すのを防ぐため、途中で寝る人が出ないよう徹夜で酒盛りをしながらお互い見張り合いました。眠りさえしなければ三尸が抜け出すのは防げます。余談ながら庚と申はどちらも金の性質を帯びている為、庚申の年は人々がより残酷になり、政変が起こりやすいと危惧されていました。
庶民の間では「庚申待」の名称が最も一般的でした。江戸の町民たちも庚申講に参加し、近所の人々と飲み食いすることで地域社会の結束を強めました。
また、庚申講と関係が深い妖怪に「しょうけら」がいます。三尸を封じるまじない歌に「しし虫」「しゃうけら」といった語句が登場することから、三尸の虫がルーツなのは間違いありません。『庚申伝(こうしんでん)』にも以下のように明確に書かれています。
「ショウキラハ虫ノコト也 一説三尸ノコトト云」
江戸の町民たちは眠気覚ましに、呪文を唱えました。
これは、青面金剛を呼び出し三尸(=しょうけら)を封じ込める呪文とされ、地方の農村にも伝わっていったようです。
農家のお供え物はボタモチ 寝ずに夜を明かした人々
庚申講を重んじるのは農村の人々も同様で、江戸よりも人付き合いが密な分、一層力を入れていたと言えます。東京都狛江市では、庚申講の日に男たちの手打ち蕎麦とお神酒を庚申塔に供え、高張提灯を立てたそうです。他の村落では、猿田彦の掛軸の前で三社の祓(はらい)を唱えた後、皆が持ち寄った季節料理の重箱を開き、酒盛りに移行しました。精進料理やボタ餅、米の粉を練った庚申団子を供える村もありました。農民たちにとって庚申講は年6回だけの大事な日。平安時代とは違い、男女の交わりを禁じ、針仕事・藁仕事などを慎んで身を清めます。これは天帝への告げ口を警戒してのことでしょうか?
一方で、終始堅苦しい雰囲気でもなかったようで、会食後には農作物の作柄の世間話で盛り上がった記録も残っています。「ジッケッコウ」と呼ばれるくじ遊びも、庚申講の楽しみの一つでした。
おわりに
以上、庚申講の成り立ちと実態を解説しました。妖怪しょうけらのルーツが三尸の虫だったとは驚きですね。残念ながら現代ではすっかり廃れてしまいましたが、皆で集まって一晩中遊びに耽る情景を想像すると、非日常感が相俟ってワクワクしますね。【参考文献】
- 武藤祐嗣『庚申塔探訪記』(三省堂書店、2023年)
- 飯田道夫『庚申信仰: 庶民宗教の実像』(人文書院、1989年)
- 芦田正次郎『路傍の庚申塔: 生活のなかの信仰 (民衆宗教を探る)』(慶友社、2012年)
- 長沢利明『江戸東京の庶民信仰』(講談社、2019年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



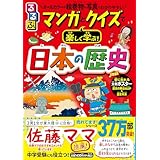
コメント欄