「直江兼続」文武に長け、主君景勝を支えて苦境を乗り越えた宰相
- 2019/09/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
上杉景勝の家老として名高い直江兼続(なおえ かねつぐ)。皆さんはその名を聞いてどのようなイメージを抱くでしょうか。恐らく、大河ドラマ『天地人』で描かれたような、義と愛に彩られた武人としての華々しい活躍が浮かぶかもしれません。
しかし、兼続の史実における動きをみていくと、我々が抱いている印象とは異なる姿を見せてくれるのも兼続という人物の特徴なのです。そこで本記事では彼の実像を読み解いていきたいと思います。
しかし、兼続の史実における動きをみていくと、我々が抱いている印象とは異なる姿を見せてくれるのも兼続という人物の特徴なのです。そこで本記事では彼の実像を読み解いていきたいと思います。
与六と喜平次
兼続は、永禄3(1560)年に樋口兼豊という人物の長男として誕生しました。幼名は与六と言いましたが、彼の出自はハッキリしない点が多いです。父の兼豊は上杉景勝の父である長尾政景に仕えていましたが、家臣としてどのような立場だったのかは諸説が存在しています。重臣として厚遇されていたというものから、城の薪を管理するという低い身分の人物であったというものまで様々です。
一方、兼続の母は信濃衆泉重蔵の娘という人物として伝わっていますが、直江景綱の妹という説もあります。

幼少の頃の兼続は、利発な少年であり、上杉景勝の母・仙桃院に才能を見込まれ、兼続より5歳年上の景勝(幼名は喜平次)の近習になったと伝わっています。
しかしながら、直江家が仕えていた長尾政景が酒に酔って溺死するという不可解な死を迎えると、兼続は上杉謙信の養子となった景勝に従い、彼らの本城である春日山城へと入っています。

直江家の家督を継承
兼続が成長して19歳となった天正6(1578)年には、謙信が急死してしまうという事件が発生します。彼は後継者を明言しなかったため、上杉家当主の座をめぐって景勝ともう一人の後継者候補・上杉景虎の間に家督争いが勃発してしまうのです。これを御館の乱といい、国内だけでなく周辺諸国を巻き込んだ大きな内乱へと発展していきました。
ここで兼続は景勝派に属し、彼に近侍して景勝方の勝利に貢献したと伝わっています。実際、御館の乱以降に兼続の名が頻繁に史料上で確認できるようになることから、彼にとって出世のキッカケとなったのはこの乱とみて間違いないでしょう。
乱の功績によって評価を高めた兼続でしたが、天正9(1581)年には戦後の恩賞をめぐるトラブルで直江家の当主・直江信綱が殺害されるという事件が発生します。
直江家に後継者がいなかったことから断絶の危機を迎えますが、これを惜しんだ景勝の命により、兼続が直江家の家督を継承することに…。ここに「直江兼続」が誕生するのです。
このとき未亡人となっていたお船の方に婿入りし、彼らが領有していた与板城の城主になっています。
もっとくわしく
名実ともに上杉家の有力な家臣となった兼続ですが、すぐに頭角をあらわして家中の政治のほとんどを取り仕切っていたと言われています。
実際、同年には戦後の恩賞がなかったことに不満を抱いた新発田重家が織田信長の勧誘で謀反を起こしていますが、越中国における織田軍の動向は逐一、兼続に報告がされていました。既にこの時点で景勝の家老として重要な役割を担っていたことがうかがえます。

豊臣政権と上杉家の架け橋を担う
天正10(1582)年には、本能寺の変で信長が横死したことが原因で、旧武田領をめぐる争い・天正壬午の乱が勃発すると、兼続がその仲裁役としての役割を羽柴秀吉に求められたようで、以後は豊臣政権と親密な関係を構築していきました。特に秀吉の側近として著名な石田三成との友情はこの頃から構築されはじめたとも考えられており、その関係性は関ケ原の戦いにまで続いたことは、上杉家が西軍に加担したことでも窺えるでしょう。
天正13(1585)年には、兼続の手引きもあって景勝が上洛して秀吉に従属したことで彼らの身分は保証され、やがて上杉家は最盛期を迎えることになっていきます。
まず、秀吉の名のもとに越後国内の平定を果たすと、その報告をするために再び上洛。その際には秀吉から山城守に叙任され、家臣の身としては異例の待遇を受けることになりました。
これは秀吉が兼続の技量に惚れこんでいたためとも、家臣を大きく出世させることで主君である景勝との関係を複雑なものにするためとも言われていますが、ともかく兼続の名は天下に轟くことになるのです。
その後、天正17(1589)年には佐渡を平定し、翌年には秀吉による小田原攻めに付き従いました。また、秀吉の命によって景勝と共に朝鮮の地を訪れており、同地では学問への造詣も深かった兼続が貴重な書籍などを日本に持ち帰ったとも伝わっています。
こうして豊臣の家臣でも屈指の地位を築いた上杉家は、慶長3(1598)年に会津120万石への国替えを命じられたのです。
この国替えは東国の統治を景勝に任せたいという秀吉の意図があったと思われますが、一方で新しい土地を統治するという難題を押し付けるねらいもあったことでしょう。
しかし、秀吉が同年中に亡くなると、生前は彼に付き従っていた徳川家康がにわかに政権奪取の動きを見せ始めます。大大名になっていた上杉家もまた、否応なくこの流れに巻き込まれていくことになるのです。
関ケ原で家康と敵対。領地は大幅減少へ
秀吉の死後、情勢としては「反豊臣家」を掲げる家康の勢力と、「新豊臣家」を掲げる石田三成の勢力に二分されていきました。景勝は当初都に残って豊臣政権の運営を補佐していたものの、新たな領地である会津の統治を優先させるべく帰国しています。その後は兼続が中心となって領国の国力増強に励んでいましたが、これを謀反の下準備と捉えた家康によって弁明のために上洛を求められました。
しかし、景勝がのらりくらりとこの要求をかわしているうちに、徳川勢はしびれを切らし始めました。そこで、慶長5(1600)年に家康の使いが会津に訪れ彼らに「最後通牒」を突きつけると、その返答として兼続は世に名高い「直江状」を叩きつけ、両者の戦は避けがたいものとなってしまいました。

一説では盟友である三成とのやり取りで「反家康の密約」をかわしていたとも伝わりますが、ここで家康は会津征伐軍を編成し、彼らの元へと進軍してきました。とはいえ、この進軍が三成方の蜂起を促すものであることはだれの目にも明らかで、予定通り彼らも兵を進ませ徳川方は反転して彼らを迎え撃ちました。
ここで退いていく徳川の勢力を前に兼続は追撃を進言したようですが、景勝はこれを受け入れなかったと言われています。この決断は景勝の「関ケ原は長引くため、まず家康に与する最上義光を討伐することが先決」という思いに起因するものとされていますが、この逸話が真実であるとすれば兼続の見立てが正しかったのでしょう。
とはいえ、主命を違えるつもりはなかった兼続は徳川追撃を諦め、最上領の侵攻を開始しました。彼らは大軍を率いて総攻撃をかけましたが、激しい抵抗に遭い戦局を決定づけることはできませんでした。

さらに、長引くことも予想された関ケ原の戦いがわずか一日で決着してしまい、上杉勢は一転して厳しい立場に置かれることになります。
ここで景勝は家康との和睦を決断し、兼続も徳川方ながら上杉に近しい立場にあった本多正信らに取次を求めるとともに、本庄繁長や前田慶次郎、結城秀康といった人物たちを通じて事前工作を惜しみませんでした。
その結果、なんとか家名の存続こそは許されたものの、これまでの領地から実に4分の1となる米沢30万石への大減封を命じられてしまいます。

当然ながら加増があると思っていたわけではないでしょうが、この苛烈な処置は上杉にとって衝撃的なものでした。ただでさえ領地が減少するうえに、彼らの貴重な財源であった佐渡金山をも失うという事実は、藩政開始以前から藩の将来を憂うに十分なものでした。
米沢の藩政で真価を発揮!
一気に領地を縮小された上杉家は、否応なく難しい藩運営を強いられました。しかし、ここで真価を発揮したのが直江兼続。これまでの彼は、「直江状」などで武士の気概を存分に見せつけていたものの、見方によっては「上杉家を衰退させた中心人物」とも考えられてしまうのです。そのため、個人的には「戦国武将」としての兼続を高く評価しているわけではないものの、「政治家」としての姿には一目置くところがあります。まず、兼続は家を去る者を拒みはしないものの、既存の家臣を「リストラ」することはありませんでした。当然ながら120万石の家にふさわしい人員を揃えていたわけで、それが4分の1になってしまっては明らかに人員過多であり、同時に藩政を苦しめるのは目に見えていましたが、それでもこの決断を曲げませんでした。
そこで、景勝や兼続は自身の直轄地を縮小し、家臣の家禄を三分の一に抑えることから着手しました。しかし、これだけでは当然ながら藩政を賄うには不十分です。さらに家臣が住む家にも困るという有様で、本城となる米沢城もボロボロの状態にありました。
兼続はこの難局に一つずつ対処していきます。
城下に住めない家臣らを荒れ地に住まわせ、彼らに土地を耕させると同時に、水害が酷かった米沢の治水事業に奔走しました。

さらに畑へ植える穀物としてごぼうやそばを奨励し、やせ地における農業を理論的に発展させていったのです。
その他にも、植林事業・商工業の振興・鉱山の採掘など、当時考えられる殖産興業の手段をことごとく実行に移していった兼続。彼の姿勢は後世でも高く評価され、後に藩政を立て直したことで名君と称される上杉鷹山も兼続の手法を参考にしたと伝わっています。
また、自身の趣味でもあった学問を藩政に取り入れていき、京都五山の僧を招いて米沢に禅林寺(現在の法泉寺)という寺社を建立。さらに禅林文庫と呼ばれる学問所を創設し、自身も中国の古典である『文選』という文書を出版する抗争を練るなど、文化面における功績は光るものがあります。

しかし、苦境に陥った米沢藩で活躍する傍ら、彼の後継者が現れないという問題を抱えていました。兼続とお船の間には一男二女がもうけられましたが、長男の直江景明は身体的に弱いところがあり、側室もいなかったため兼続は養子を迎える決断をします。
そこで目をつけたのは当時浪人の立場にあった本多正信の息子・本多政重であり、彼を娘と結婚させることで後継者に据えようと考えていました。しかし、肝心の娘が結婚直後に亡くなってしまい、さらに景明も結核と思われる症状で亡くなってしまいました。
ここでお家の断絶を決断した兼続は、大坂の陣で活躍した後、元和5(1619)年に60歳の生涯を終えました。
【参考文献】
- 『国史大辞典』
- 花ケ前盛明『直江兼続のすべて 新装版』新人物往来社、2008年。
- 鈴木由紀子『直江兼続とお船』幻冬舎、2009年。
- 歴史群像編集部『戦国時代人物事典』、学研パブリッシング、2009年。

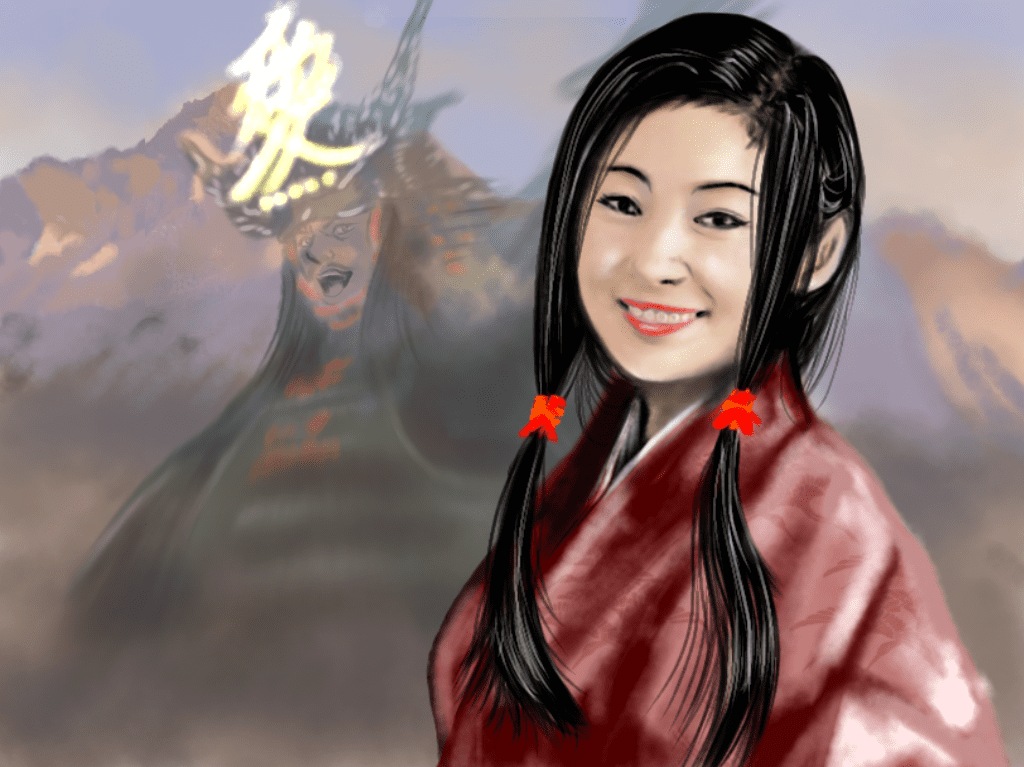



コメント欄