「四万十川(渡川)の戦い(1575年)」長宗我部の土佐統一戦
- 2020/09/16

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
土佐国の国衆の一角に過ぎなかった長宗我部氏が宿敵の本山氏を降し、さらに東の安芸氏を滅ぼした後、もはや対抗できる勢力は西の一条氏だけでした。今回はそんな一条氏を完全に土佐国から追い出すことに成功した「四万十川(渡川)の戦い」までの攻防についてお伝えしていきます。
長宗我部元親の全体像(生涯・主な合戦など)を知りたい方はこちらの「長宗我部元親の解説記事」をご覧ください。
一条氏との断交
一条氏と長宗我部氏の関係
長宗我部氏は当主が長宗我部兼序の代に本拠の岡豊城を追われています。本山氏ら他の国衆の恨みを買ったためです。兼序は敗死しましたが、嫡子の長宗我部国親は一条氏を頼って庇護を受け、のちに旧領を取り戻すことができました。つまり長宗我部氏は一条氏に多大な恩義があったわけです。
しかし国親は天文16年(1547)頃に一条氏の領土である大津城を攻めています。永禄7年(1564)になって、この恩を仇で返すような所業について、国親の跡を継いだ元親が謝罪しています。このとき弟の長宗我部弥九郎を人質として一条氏に送り届け、臣従を誓いました。この間を取り持ったのが一条兼定の重臣である土居宗珊でした。

こうして一条氏と長宗我部氏の関係は改善されたのですが、これは元親が一条氏と縁戚関係にある安芸氏を滅ぼすための時間稼ぎだったと考えられます。元親は本山氏を降すまでは安芸氏と和睦し、今度は安芸氏を滅ぼすまでは一条氏に臣従したということです。かなりしたたかな外交戦略です。
一条氏と大友氏の関係
一条氏としても眼前に伊予国黒瀬の西園寺氏という強敵の姿がありました。一条兼定は伊予国の押さえのために宇都宮氏の娘を正室に迎えていましたが、劣勢を覆すために離別し、豊後国の大友宗麟の娘を正室に迎えています。そして大友氏の援助を受けて一時は西園寺勢力の支城を落とすも、反撃を受けて敗北し、土佐国に逃げ戻りました。
永禄8年(1565)には長宗我部氏からも援軍を受けて、西園寺勢を撃退しています。このとき長宗我部勢200を率いて大活躍したのが江村備後守親家です。
兼定はこの活躍を喜び鎧と太刀を親家に与え、翌年には土居宗珊を答礼のための使者として岡豊城に送っています。この時点では両者の関係は良好でした。しかし長宗我部氏が安芸氏を倒す目処のついた永禄12年(1569)から一条氏と長宗我部氏の関係は急速に悪化していくのです。
蓮池城の攻略
『元親記』によると、一条氏攻めを提案したのは元親の弟で吉良氏の名跡を継いでいた吉良親貞です。土佐国統一のためには一条氏を倒す必要があります。そのため親貞は高岡郡蓮池城攻めを元親に提案したのです。以前に元親は本山勢を倒すため兼定と高岡郡には進出しないと約束していましたから、この提案を拒否したと記されています。しかしここまでの元親のやり方を見てみると、勢力が拡大した際には約定を破る気が最初からあったように思えます。
そもそも長宗我部氏が一条氏を攻める大義名分はありません。そこで親貞は蓮池城在番衆の平尾新十郎、土居治部、仲弥藤次らを調略し、謀反を起こさせます。そして永禄12年(1569)11月6日に蓮池城を乗っ取ってしまうのです。城兵は戸波城に逃げ込みましたが、親貞は勢いに乗ってこの戸波城も落としています。
もちろんこの裏切り行為に対し、兼定は怒り、元親に抗議しました。当然の反応でしょう。長宗我部氏は一条氏に臣従を誓っていたのです。元親はこの抗議に対し、これは弟の親貞がやったことであり親貞とは絶縁すると答えたと伝わっています。
この回答で兼定は怒りを収め、蓮池城が返されるのを待っていたのでしょうが、元親は親貞と縁を切るどころかさらに高岡郡へ進出していきます。
久礼城の佐竹信濃守はもともと親貞の誘いに乗って内応していたため、あっさりと城を明け渡しました。さらに仁井田五人衆も長宗我部氏に下り、長宗我部氏はあっという間に高岡郡を制圧するのです。
こうして元亀2年(1571)には、長宗我部氏の領土は一条氏の本拠である幡多郡に接するところまで拡大していました。
一条氏と長宗我部氏は完全に対立した形ですが、東の安芸氏はすでに滅んでおり、敵対勢力が少し残ってはいたものの元親は後背に脅威を感じず戦える状態です。これこそ元親が描いていたシナリオ通りの展開だったのではないでしょうか。
あわせて読みたい
一条兼定の評判と追放劇
下克上の戦国時代とはいえ、大恩のある一条氏を攻める大義名分は長宗我部氏にはありませんでした。兼定は長宗我部氏が本山氏と争った際には仲介役となって両者を和睦させたり、長宗我部氏と安芸氏との和睦にも一役買っているのです。土佐国を統一するためには一条氏を降す必要はありましたが、元親もこの後でどう対応していくべきか悩んでいたのではないでしょうか。そこで重要になってくるのが兼定の評判です。
『土佐物語』によると、
「生質軽薄にして常に放蕩を好み、人の嘲りを顧みず、日夜只酒宴遊興に耽り、男色女色し諂いをなし、叉は山河に漁猟を事とし、軽業力業異相を専ら」
と記されています。
『海南志』には、
「軍国の大事はすてて問はず」「将を御するの道は督責を加ふるに在りとて刑罰を苛酷にし」
と記されており、さらに『元親記』には、
「形義荒き人にて、家中の侍共、少しの科にも扶持を放し、腹をきらせなどせらる」
とあり、長宗我部氏に滅ぼされるのも当然という口調です。人心は兼定から離れており、実際に諫言していた重臣の土居宗珊は兼定に殺されました。
一条氏の家老は合議の末、当主の兼定を追放して、その子である一条内政を立てることに決め、元親に後見役を頼もうと江村備後守親家を通じて長宗我部氏に交渉をしました。元親にとっては幡多郡を手中に収める好機と受け取ったことでしょう。
天正2年(1574)2月、兼定は妻の実家となる豊後国の大友氏のもとに送られ、元服して家督を継いだ内政は、元親の娘を娶り、元親後見役新体制が開始されます。
しかし一条氏の家中ではこれに納得いかない勢力もあり、混乱が生じました。家老の安並因幡守や為松氏と、幡多郡の国衆らとの間で対立がおき、安並因幡守・為松氏らは戦死しています。
元親は内政をこのまま幡多郡中村城に置いておくのは危険だと判断し、内政を長岡郡大津城に移し、代わって弟の吉良親貞に中村城を任せました。
こうして長宗我部氏はあっという間に一条氏の拠点である中村城を制圧したのです。
兼定の逆襲
同年の秋には、土佐国東の安芸郡の羽根、吉良川、室津、崎浜、野根、甲浦といった城主らが協力して打倒長宗我部氏の兵を起こしており、羽根まで進軍して山中のゲリラ戦で長宗我部勢を苦しめました。しかし、ここは元親が自身で指揮を執って反撃し、敵を撃退して安芸郡東部の椎名まで降伏させています。次いで翌天正3年(1575)はさらに崎浜まで進出して制圧しましたが一度岡豊城に帰還しています。
一方、この時期に豊後国に追放されていた兼定は大友氏の助力もあり、九州から四国に渡り、一条氏当主復帰を目指して行動を開始しました。大友氏からの援軍の他、南伊予の法華津播磨守、御荘越前守らの援助も受け、宿毛に侵入します。
これに対し、幡多郡の旧臣のほとんどが兼定の挙兵に味方し、幡多郡で長宗我部の勢力は中村城と城下町ぐらいでした。一条氏の家臣の大半が兼定追放、長宗我部氏による支配に納得していなかったということを物語っています。
ちなみに兼定は豊後国に滞在した最中にキリスト教に入信しており、洗礼を受けて「ドン・パウロ」と名乗っています。ですので、キリシタンとなった兼定に反発する仏教徒は長宗我部氏に味方しています。
長宗我部氏は東西に敵を抱えていた状態でしたが、同年の7月には奈半利城主である桑名丹後守が調略によって敵対する野根城を攻略し、さらに甲浦に進軍して田浦城を攻略して、桑名丹後守の子である桑名将監を配して掌握。
ここで土佐国東は完全制圧となっており、後は兼定の勢力を滅ぼすだけとなっています。
最後の戦い「四万十川の戦い」
8月には中村城の周辺で、兼定の勢力と吉良親貞の軍勢が衝突しています。この段階ではまだ小競り合いといった感じです。9月中旬には兼定は四万十川(渡川)の西にある栗本に布陣し城を構え、中村城奪還を狙います。長宗我部勢は東に着陣しました。こうして土佐国を巡る最後の合戦「四万十川の戦い」が行われるのですが、長宗我部勢はわずか3日で栗本城を攻略しています。
この戦いの経緯については諸説あり、『元親記』によると、一条勢は川に杭を打って備えている間に吉良親貞が川上から渡河し、一条勢に奇襲をかけて打ち破ったと記されています。
『土佐物語』によると、長宗我部勢が川上に別働隊を派遣したところ、一条勢がこちらに気を取られており、その隙を突いて別働隊が川下から渡河して一条勢を挟撃して打ち破ったというものです。
その結果、西は伊予国境の宿毛から南の足摺岬まで幡多郡一円を平定しました。土佐国統一を果たした元親は岡豊城に帰還していくのです。
おわりに
なお、敗北した兼定は戦場からは落ち延びることができましたが、伊予国まで逃げ、その地で家臣の入江左近に追放され、天正13年(1585)に没したと伝わっています。元親の娘を娶った一条内政は「大津御所」と呼ばれて7年間ほど健在でしたが、謀反の罪で追放され一条氏は滅んでいます。調略を巧みに使いつつ、元親自身も大切な合戦にはしっかり参加して味方を勝利に導いているあたり、さすがは「土佐の出来人」と呼ばれた戦国大名です。だからこそ当主となってわずか15年で戦乱の土佐国を統一できたのです。
そして元親はこの手腕を用い、土佐国だけでなく四国統一に向けて動き出していきました。
長宗我部元親の全体像(生涯・主な合戦など)を知りたい方はこちらの「長宗我部元親の解説記事」をご覧ください。

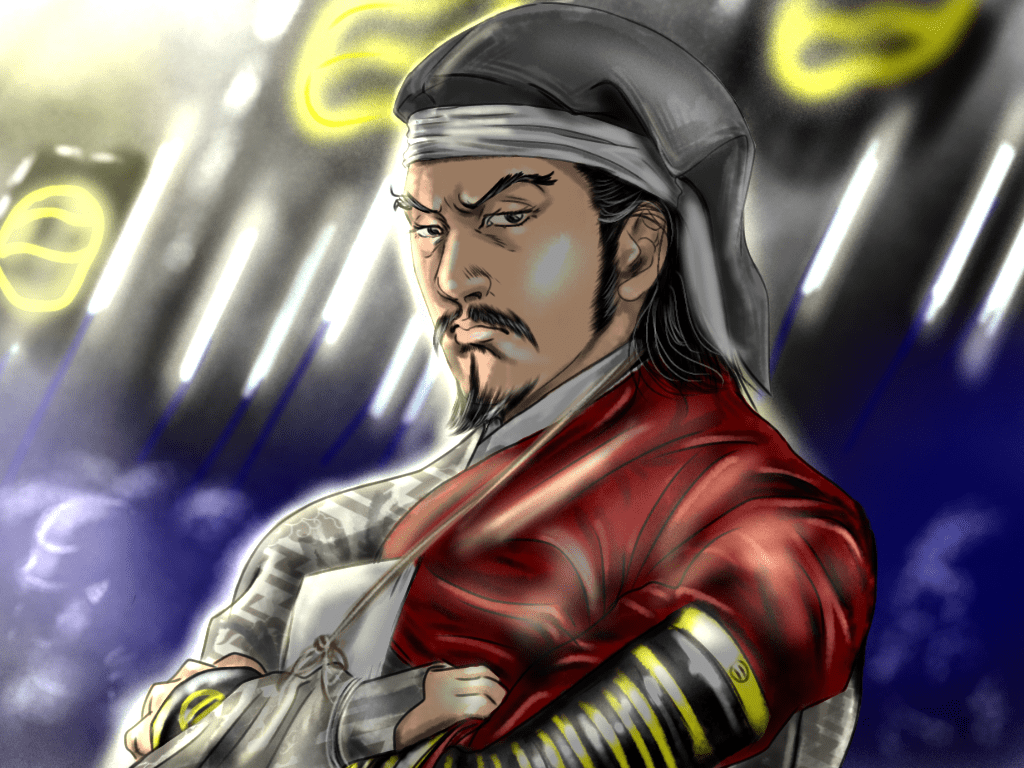



コメント欄