伊達政宗、まさかの「死装束姿」…黄金の十字架パフォーマンスで危機を乗り越えたことも!?
- 2025/07/27
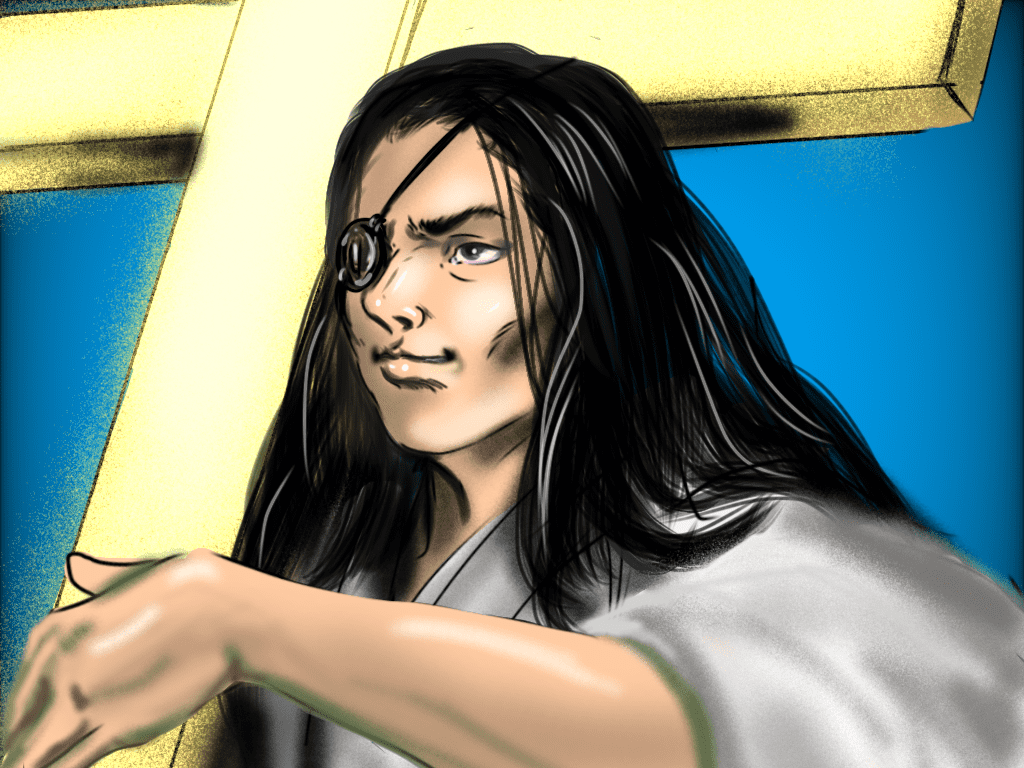
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
本稿では、まず世に名高い小田原攻めにおける死装束の真の効果を検証し、その後、政宗が同様の危機で披露した驚くべきパフォーマンスについてもご紹介します。
世に名高い「小田原の死装束」は秀吉の心を変えたのか?
さて、本論に入る前に、まずは「死装束」そのものについて解説していきましょう。「死装束」は世界中で見られる文化ですが、武士の世界では、切腹の際に着用する白い衣装を指すことが多く、それ以外の場面で身につけることは「切腹をも辞さない覚悟」を示す意味合いがありました。この死装束によるパフォーマンスを巧みに用いた代表的な武将が政宗です。
豊臣家への数々の「挑発行為」の末、時勢を鑑みて小田原攻めへの参戦を決めた政宗は、これまでの無礼を秀吉に許してもらう必要がありました。そこで死装束をまとい、覚悟を示したことで、秀吉はその意気に免じて政宗を許したというのが、小田原遅参における死装束パフォーマンスの通説でした。
しかし、現代の定説では、政宗の死装束は一種の儀礼的なパフォーマンスであり、小田原参戦前にはすでに政宗の処遇は決まっていたという見方が一般的です。
そもそも、豊臣家への「挑発行為」とされたのは、天下をほぼ手中に収めた秀吉が、大名の私戦を禁じる「惣無事令」を出した後も、政宗が湊合戦や磨上原合戦(1589)等を起こしたためでした。これは事実上、北条氏や伊達氏に向けて発せられた「惣無事令」を破ったとみなされ、豊臣政権への挑戦と解釈されたのです。
さらに、豊臣に下っていた蘆名(あしな)氏や佐竹氏を攻めたことも問題視され、『上杉家文書』によれば、会津を返上しない限り征伐も辞さないという意向が示されたほどでした。しかし、その後は浅野長吉や前田利家の取りなしによって、なんとか征伐を回避します。以降、政宗は秀吉の北条氏攻めによってさらなる好機を迎えることになります。
おそらく秀吉にとって、北条氏との戦を控える中で伊達家との敵対は望ましいものではなかったのでしょう。そのため、利家らからの書状には、「小田原に参戦して関係性を改善すべき」といった内容が記されていました。
この時、北条氏からも使者が来ていましたが、政宗は小田原への参戦を決断します。ところが、母・保春院(ほしゅんいん)の置毒事件によって参戦を延期した政宗は、その後も何度も出陣を装うなど、参戦に時間を要してしまいます。そうこうしているうちに、戦の形勢がほぼ確定したタイミングでの参戦、つまり遅参が決定的なものとなってしまいました。
もちろん、事前に態度は表明していましたが、まだ予断を許さない状況だったのは明らかです。そこで、政宗は「死装束」をまとうことで、秀吉本人や家臣たちに自身の覚悟を伝えるパフォーマンスに及んだのです。
結論から言えば、この死装束が秀吉の心を変えたわけではなさそうですが、無礼を詫びる効果は絶大で、特に秀吉の家臣たちには心情的に大きな影響があった可能性はあります。
政宗第二の危機!一揆扇動の疑惑に「黄金の十字架」で対抗
小田原への参戦で本領を安堵された政宗は、秀吉による奥州仕置に直面します。仕置に際しては、会津黒川城に蒲生氏郷(がもううじさと)が入城し、小田原に参戦しなかった大崎氏と葛西氏は所領を召し上げられ、木村氏が入封されていました。しかし、大崎・葛西の両氏から所領を引き継いだ木村氏は領内を統治できず、一揆衆が暴徒化。木村氏が領内を追い出されると反乱は奥州全体に拡散していきました。
ここで、氏郷と政宗の関係性が影響を与えます。彼らは言うまでもなく会津の覇権を争うライバルであり、氏郷はこの一揆の黒幕が政宗であるという「疑心」を抱くことになります。その情報源は伊達氏の家臣である須田伯耆(すだほうき)という人物で、一揆扇動の証拠となる密書を氏郷に届けました。その後、氏郷がこの疑いを秀吉に上申すると、両者に上洛の命令が下ります。
そこで政宗は再び死装束をまとい、さらに今回は黄金の磔柱(はりつけばしら)を先頭に上京するという「奇策」に打って出ます。その後の沙汰の詳細な内容は不明ですが、最終的には「白」と判断され、処罰どころか恩賞まで与えられたとされています。しかし、氏郷側も罰せられていないことから、政宗の行動を称えて「白」ということになった可能性も指摘されています。
近年の研究では、実際に政宗が一揆を扇動したかどうかは定かではないものの、一揆衆が葛西晴信の家臣であること、そして晴信と政宗が近しい関係にあったことは明らかです。そのため、一揆の扇動をしていたとしても不自然ではないとされています。
この記事では触れませんが、後には秀次事件への関与を疑われるという一幕もありました。そこでも政宗は、「家来とともに京で暴れまわる」という噂や、政宗や最上義光(もがみよしあき)の謀反をほのめかす立て札を立てられるなどの危機的状況に陥りますが、最終的には政宗赦免を知らせる『豊臣秀吉諚意覚書』によって危機を脱しています。
政宗は遅刻常習犯?近年発見された「大ピンチ」
ここまで、政宗の「豪気」なエピソードを紹介してきましたが、2015年には政宗に関する新たな書状が発見されています。これは、栃木県立博物館が発見した政宗が秀吉に宛てた書状で、時系列としては小田原参戦後、奥州仕置までの間に起こった「宇都宮仕置」の際のものと推定されています。この書状には、秀吉が宇都宮城に大名を集めた際、彼が東北に赴く際の先導役として指名されていたにも関わらず、どうにも集合日時に間に合いそうもない政宗が秀吉に宛てた「言い訳」が記されています。本来であれば先導役の遅参は許されるものではありませんが、最終的には秀吉から甲冑を賜るなど、むしろ上機嫌な対応を受けたことが記されています。
書状の中には、「荷物が到着しておらず、今夜出発し、あす午前10時には参上できる」という内容が含まれており、遅刻に焦る政宗が徹夜で宇都宮に急行している様子が浮き彫りになっています。しかし実際のところは、領内の反乱によって遅参したとされており、その遅参理由を明かせなかった政宗が「荷物が届いていない」という言い訳を使ったようです。ここには、宇都宮仕置をめぐる政宗の駆け引きが垣間見えます。
いずれにせよ、政宗が必死の言い訳をしているのは事実であり、やはり政宗といえども二度目の「大遅刻」には肝を冷やしたものと推測できます。これまでの「豪気」なエピソードとは少し異なり、やや格好が悪いようにも感じられますが、死後400年近くたっても「らしい」エピソードが発見されるあたりに、政宗が愛される理由が見て取れるようにも思えます。
おわりに
伊達政宗の数々の危機を乗り越える手腕、いかがでしたでしょうか?彼の型破りな行動は、現代の私たちにとっても非常に興味深いものがありますね。【主な参考文献】
- 小林清治『伊達政宗の研究』(吉川弘文館、2008年)
- 高橋富雄『陸奥伊達一族』(吉川弘文館、2018年)
- 中田正光『伊達政宗の戦闘部隊:戦う百姓たちの合戦史』(洋泉社、2013年)
- 産経ニュースHP 『「宇都宮仕置」駆け引き記載 県立博物館、政宗の書状16日から初公開』




コメント欄