「北条時行」いくども危機脱出 足利尊氏との死闘と北条復活の夢
- 2025/04/09
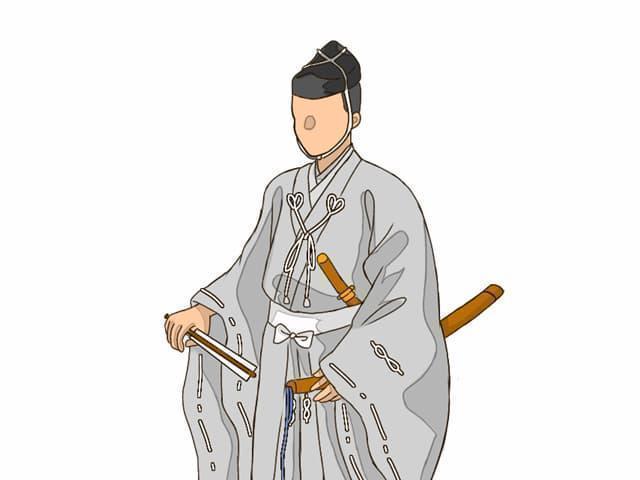
鎌倉幕府滅亡2年後の建武2年(1335)、北条氏残党が建武の新政に対する反乱を起こします。中先代の乱です。その中心は最後の得宗・北条高時の遺児・北条時行(ほうじょう・ときゆき、?~1353年)。
少年ながら北条氏残党を象徴する存在でした。それはなぜか。そして、その後の生涯は? 松井優征さんの人気漫画『逃げ上手の若君』で一気に知名度も上がった北条時行の実像に迫ります。
少年ながら北条氏残党を象徴する存在でした。それはなぜか。そして、その後の生涯は? 松井優征さんの人気漫画『逃げ上手の若君』で一気に知名度も上がった北条時行の実像に迫ります。
鎌倉炎上 劇的な脱出、兄は側近裏切りで落命
北条時行は正中2年(1325)~元徳元年(1329)ごろの生まれでしょうか。元徳元年に「高時に若御前(若君)誕生」とする史料があります。この若君は鶴岡八幡宮別当(長官)の門弟のもとに預けられるので出家予定だったようです。この若君とすると、中先代の乱の挙兵時7歳。幼すぎる気もします。一方、兄・北条邦時の異母兄弟なら同い年で正中2年生まれの可能性もあり、挙兵時11歳。いずれにしても少年ですが……。
実名・時行は「ときつら」と読む説もあります。通称は相模次郎。幼名は『太平記』では亀寿。勝長寿丸、勝寿丸とする史料もあります。
母は「新殿=五大院宗繁の妹=常葉前」?
母は『太平記』では新殿と呼ばれる女性で、御内人(北条氏直属の家臣)・五大院宗繁の妹。兄・北条邦時と同じです。史料からも邦時の母は五大院宗繁の妹と確認できます。高時の側室・常葉前です。一方、時行と邦時は異母兄弟であり、時行の母を北条高時の正室(安達時顕の娘)とする見方もあります。しかし、この女性に子がいたかどうかは分かりません。邦時の名は将軍・守邦親王の一字を受け、側室の子ながら嫡男と扱われているようなので、正室には男児がなかったと解釈するのが順当です。
北条貞時
┏━━┫ ┏━━━┓
泰家 高時 = 親殿 五大院宗繁
┏━━┫
時行 邦時
※参考:時行の略系図
御内人・諏訪氏に守られ信濃へ逃亡
元弘3年(1333)5月、鎌倉幕府は滅亡します。『太平記』によると、「もはやこれまで」と自害を勧める御内人・諏訪盛高に対し、北条泰家(高時の弟)は後日の北条氏再興を期して甥・北条時行を逃すよう指示。盛高は時行の母・新殿のもとへ向かいます。新殿:「万寿(北条邦時)は右衛門(新殿の兄・五大院宗繁)が連れていったので安心だが、この亀寿(時行)のことが案じられて死ねずにいるのです」
盛高:「大殿(北条高時)は若君(時行)とともに自害されるご覚悟。敵に見つかって家名を汚すのも残念です。大殿のお手にかけられて冥途にお供するのが親孝行です」
諏訪盛高は秘密漏洩を恐れ、あえて噓を言って母の手から奪うように時行を連れ去ります。乳母たちは大騒ぎして悲しみ、投身自殺する者まで出ますが、盛高は時行を連れ、地元・信濃に逃れました。
兄・邦時の悲劇 五大院宗繁まさかの裏切り
一方、北条邦時は五大院宗繁に守られて鎌倉近くに潜伏。北条高時は、側近であり、側室の兄でもある五大院宗繁を全面的に信頼し、嫡男・邦時を託しました。ところが、五大院宗繁は保身に走ります。北条邦時に伊豆への逃亡を勧める裏で新田義貞の家臣・船田義昌に密告し、「手柄を独り占めにされたら、わが所領安堵をご推挙ください」と取引。邦時はあえなく捕まって鎌倉で斬首されます。
しかし、新田義貞は五大院宗繁の功を認めず、卑怯者として処罰しようとします。五大院宗繁は逃げ隠れした挙げ句に飢え死に。『太平記』では笑い者になっています。
中先代の乱 鎌倉奪還も敗退後は自害を偽装?
それから2年後、建武2年(1335)7月に北条時行は信濃で挙兵。これが中先代の乱です。鎌倉幕府の支配者・北条氏を「先代」、室町幕府を開く足利氏を「当代」とし、その中間の時行を「中先代」と捉えた呼び方です。信濃で挙兵、一気に鎌倉占拠
北条時行は7~11歳の少年ですが、北条高時の遺児として、建武の新政への反逆のシンボルとなります。仕掛けたのは叔父・北条泰家。反後醍醐派の貴族・西園寺公宗のもとへ駆け込み、反乱を計画します。泰家が京の大将として京周辺の武士を、時行は関東の大将として甲斐、武蔵、相模、信濃の兵を従え、名越時兼(北条一族)は北国の大将として越中、能登、加賀の兵を集めるという構想です。連動して西園寺公宗が後醍醐天皇暗殺を企てますが、あっさり露顕して失敗。機会を逸した北条泰家は逃亡したまま歴史から姿を消します。
北条泰家の作戦は失敗しましたが、挙兵した時行は勢いが止まりません。(※中先代の乱の対立構図は以下)
◆ 旧鎌倉幕府方
- 北条時行
- 諏訪頼重
- 名越高邦
- 金刺頼秀
- 三浦時継
- 蘆名盛員
etc…
VS
◆ 足利方
- 足利尊氏
- 足利直義
- 渋川義季
- 岩松経家
- 今川範満
- 小山秀朝
etc…
時行の挙兵には、建武の新政で恩恵を受けなかった地方武士が大挙合流したのです。
尊氏出陣で形成逆転 諏訪頼重ら壮絶自害
建武2年(1335)8月、北条時行追討のため、足利尊氏が京を出発。『太平記』は京を500騎で発った尊氏に近江、美濃、尾張、三河、遠江の兵が合流し、駿河についたときは3万騎、足利直義と合流すると5万騎になったとしています。『太平記』の誇張としては穏やかな方で、いずれにせよ、足利勢はどんどん兵力を増して東進。対する時行は先制攻撃を決断します。時行:「源氏(足利勢)は非常に大勢なので迎え撃っても圧倒されてしまう。ここは先手を打つべきだ」
ところが、先発隊3万騎の出陣を天災が襲います。8月3日夜、猛烈な大風が来て、兵たちが避難した鎌倉大仏殿が倒壊し、500人が圧死。縁起の悪さを引きずったのか、8月8日朝、佐夜の中山(静岡県掛川市)での合戦では、高師泰や佐々木道誉ら足利勢に圧倒されて後退。2万騎のうち300騎余りしか残らない惨敗でした。この後も北条勢は劣勢を挽回できずに敗れました。
最終的に諏訪頼重ら主力武将43人が鎌倉・勝長寿院で自害します。しかも、顔の皮を削ぎ落とす壮絶な切腹です。『太平記』は「相模次郎時行もきっとこの中にいるのだ」と思わせぶりな書き方。北条高時の形見である太刀「鬼丸」も残されています。時行は自害したのでしょうか?
南朝への転身 吉野に使者、北条氏復活を諦めず
北条時行は死んでいませんでした。建武4年(1337)6月、吉野に使者を送り、南朝と和睦します。後醍醐天皇と南朝主将の新田義貞は鎌倉幕府を滅ぼした首謀者と張本人。時行にとって最も憎むべき相手のはずですが、そのすべてを忘れ、足利尊氏だけを敵とし、南朝に加わります。尊氏と戦うため、仇敵ともタッグ
使者:「亡き父・高時は臣下の道をわきまえず、帝(天皇)のお咎めを受けて滅びました。時行には君(後醍醐天皇)をお恨み申し上げる気持ちは塵ほどもありません。足利尊氏は朝敵となり、天下を奪おうとする心は明らかです。そもそも尊氏が今あるのは、わが北条家が大きな恩恵を与えてきたことによるものです。それなのに恩を受けて恩を忘れ、天にも背く悪逆非道の行いは人々が指摘するところです。故にわが一族はほかに敵を求めず、尊氏、直義への恨みを晴らしたいと思います」
使者に言わせた北条時行の口上です。時行はあえて父・北条高時の非を認め、南朝に参加。室町幕府での北条氏再興はありえず、尊氏との戦いを宿命と思い定めたのです。
再び鎌倉奪還 京方面へ転戦
建武4年(1337)8月、北畠顕家の軍勢が白河関を越え、奥州から南下。タイミングを合わせて北条時行5千騎が伊豆で、新田義興(義貞次男)2万騎が上野で挙兵しました。北畠顕家の奥州勢と下野・宇都宮氏の軍勢、時行の北条勢、新田義興の新田勢の南朝4軍が12月、鎌倉を攻めます。鎌倉を守っていたのは尊氏の嫡男・足利義詮。義詮は8歳、『太平記』で11歳とされた少年で、諸将を励まし、奮戦しますが、敗れて鎌倉から撤退します。時行にとっては中先代の乱に続く鎌倉奪還でした。
北畠顕家は暦応元年(1338)1月、鎌倉を出発し、猛スピードで西へ兵を進め、時行も同行します。しかし、連戦連勝で京近くまで攻め上った北畠顕家も最後は高師直ら足利勢精兵部隊に敗れ、5月に和泉・堺浦(大阪府堺市)で戦死しました。
時行がどこまで北畠顕家に同行していたかは分かりませんが、この後は東国へ戻ります。
2年後の暦応3年(1340)6月、諏訪頼継(諏訪頼重の孫)とともに信濃・大徳王寺城(長野県伊那市)で挙兵。信濃守護・小笠原貞宗と約4ヵ月戦いますが、敗れました。
武蔵野合戦 3度目の鎌倉奪還
文和元年(1352)閏2月、南朝が攻勢をかけます。室町幕府の内部抗争・観応の擾乱に乗じて京と東国で兵を動かします。京では、楠木正儀(楠木正成の遺児)らが一時、京を制圧。関東でも新田義興らが挙兵し、足利尊氏が駐留していた鎌倉を攻めます。尊氏と弟・足利直義が争った後遺症で、直義派残党が南朝に合流し、尊氏は鎌倉を撤退。時行は新田義興と合流し、3度目の鎌倉奪還を果たします。しかし、その後は尊氏が分散していた新田義興と弟・新田義宗を各個撃破し、劣勢を挽回。最終的には尊氏が勝利を収めます。
時行は足利勢に逮捕され、文和2年(1353)5月20日、鎌倉郊外の龍口(神奈川県藤沢市)で長崎駿河四郎、工藤二郎とともに処刑されました。御内人の長崎氏、工藤氏の一族の者のようです。諏訪氏を含めた御内人の多くは最後まで時行を支えていたのです。
おわりに
北条時行は鎌倉幕府滅亡時に炎上する鎌倉から脱出し、中先代の乱敗退時も自害したとみせて生き残り、生涯をかけて足利尊氏に挑み続けました。少年時の挙兵から3度、鎌倉を奪還。武蔵野合戦で敗れ、鎌倉で処刑されたとき、尊氏は京に戻る直前でした。20年近くにわたって戦い続けた尊氏との最後の対面はあったのでしょうか。時行は推定25~29歳。尊氏との戦いが全てだった生涯を閉じました。【主な参考文献】
- 兵藤裕己校注『太平記』(岩波書店、2014~2016年)
- 鈴木由美『中先代の乱 北条時行、鎌倉幕府再興の夢』(中央公論新社、2021年)
- 亀田俊和、生駒孝臣編『南北朝武将列伝 南朝編』(戎光祥出版、2021年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



コメント欄