「中先代の乱」少年大将・北条時行の一撃、建武の新政揺るがす
- 2025/04/08
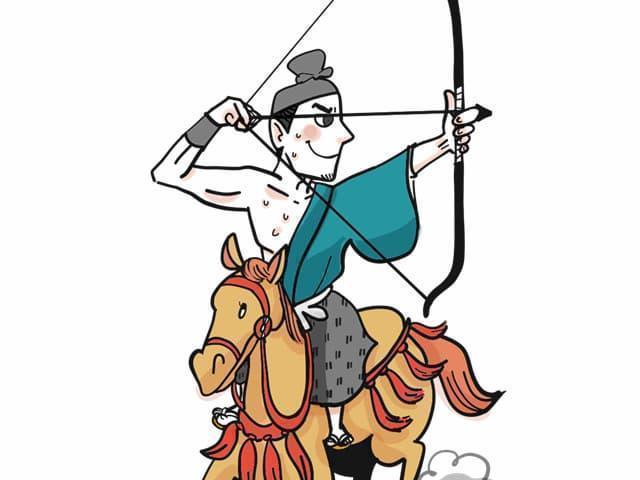
鎌倉幕府が滅亡した2年後の建武2年(1335)、鎌倉幕府14代執権・北条高時の遺児である時行(ときゆき)が挙兵しました。「中先代の乱」です。この時、北条時行は7~11歳の少年ですが、破竹の勢いで敵の有力武将を次々と撃破。あっという間に鎌倉を攻略します。
その後、足利尊氏が反撃に転じ、時行は1カ月もしないうち鎌倉から撤退、敗れ去りましたが、中先代の乱は建武の新政が崩壊するきっかけになり、南北朝時代の長い戦乱の幕開けとなったのです。
本記事では中先代の乱の経緯を追い、その意義を考えます。
その後、足利尊氏が反撃に転じ、時行は1カ月もしないうち鎌倉から撤退、敗れ去りましたが、中先代の乱は建武の新政が崩壊するきっかけになり、南北朝時代の長い戦乱の幕開けとなったのです。
本記事では中先代の乱の経緯を追い、その意義を考えます。
高時の弟・北条泰家と西園寺公宗の陰謀発覚
北条時行の挙兵は建武2年(1335)6月か7月。時行は鎌倉幕府滅亡後、信濃に逃れていましたが、鎌倉幕府再興を目指して兵を挙げます。少年大将・時行を支えたのは、諏訪頼重・時継父子や小県(ちいさがた)郡の滋野氏ら北条氏旧臣の信濃武士団です。そこに建武の新政に不満を持つ関東の武士が合流し、大軍となっていきます。先代・北条と当代・足利の間「中先代」
この戦乱は後世、「中先代の乱」とか「二十日先代の乱」と呼ばれました。「先代」は北条氏、「当代」は足利氏のことで、「中先代」はその中間として北条時行を指しています。「二十日先代」の異称も20日間ほど鎌倉を押さえたことに由来します。武士にとって、鎌倉は重要な都なのです。後醍醐天皇暗殺計画の失敗
北条時行挙兵前に京で大きな騒動がありました。時行の叔父・北条泰家(高時の弟)を匿っていた西園寺公宗による後醍醐天皇暗殺計画です。※北条泰家はこの時「時興」と改名していましたが、偽名のようなものだし、ややこしいので、そのまま「泰家」で進めます。
鎌倉幕府滅亡の時、後日の北条氏再興を期して時行の脱出を諏訪氏に指示し、自身も奥州に逃れた泰家はその後、京に出て、鎌倉幕府に近かった公家の西園寺公宗を頼りました。
北条貞時(9代執権)
┏━━┫
泰家 高時(14代執権)
┏━━┫
時行 邦時
※参考:北条時行の略系図
公宗は後醍醐天皇を自身の山荘に招いて暗殺しようと計画します。『太平記』には、湯殿(浴室)を急造し、中国・唐の玄宗皇帝と楊貴妃が遊んだ「華清宮」になぞらえ、後醍醐天皇を温泉の宴を勧め、その浴室の床が抜けて下に落ちるという手の込んだ仕掛けがあったといいます。この点はあまりにドラマっぽく、でっち上げかもしれません。未遂に終わった陰謀なので、いかようにも話が膨らませるといったところでしょうか。
北条泰家はこの陰謀に呼応して畿内で兵を挙げ、さらに東国で北条時行、北陸で一族の名越時兼が同時挙兵する手はずでしたが、建武2年(1335)6月、公宗の異母弟・西園寺公重の密告で全て露呈。逮捕された西園寺公宗は8月に処刑されます。『太平記』では、公宗の陰謀は北山の紅葉を口実に後醍醐天皇を誘い出す計画でしたが、実際は秋ではなかったのです。ちなみに、陰謀の舞台、公宗の山荘は没落した子孫の手を離れ、足利義満の別荘となり、その後、金閣寺(鹿苑寺)へと姿を変えます。
一方、北条泰家は逃亡したのか、その後の消息は不明。二度と登場することなく、歴史から姿を消しました。
信州で北条時行挙兵 足利勢撃破し、鎌倉奪還
北条泰家の計画は頓挫しましたが、北条時行は信濃で挙兵し、そのまま関東へ進撃します。建武の新政の恩恵を受けない武士による武装蜂起は北条氏残党を中心にたびたびあり、信濃でも建武2年(1335)の年頭から新守護・小笠原貞宗が反乱鎮圧に動いています。時行を擁立する諏訪頼重の子・時継は挙兵前の2月に諏訪神社の神官トップ・大祝(おおほうり)の地位を7歳の子息・頼継(頼重の孫)に譲っています。大祝は諏訪郡外に出てはならないとのしきたりがあり、頼重、時継父子はこの時点で挙兵を準備していたと考えられます。
時行、破竹の勢いで鎌倉侵攻
『太平記』によると、挙兵した北条時行の軍勢は総勢5万騎。信濃の諏訪頼重、時継父子や滋野氏を筆頭に、相模の三浦時継、三浦一族の蘆名盛員(あしな・もりかず)、上野の那和(なわ)政家、御内人の工藤氏らの兵が従ったといいます。さらに関東の諸将も参加し、進軍しながら兵力を増強していったようです。◆ 旧鎌倉幕府方
- 北条時行
- 諏訪頼重
- 諏訪時継
- 三浦時継
- 蘆名盛員
- 那和政家
etc…
VS
◆ 足利方
- 足利尊氏
- 足利直義
- 渋川義季
- 岩松経家
- 今川範満
- 小山秀朝
etc…
時行の軍勢は建武2年(1335)7月14、15日に信濃での合戦後、7月22日には女影原(おなかげはら、埼玉県日高市)で足利一族の岩松経家、渋川義季(足利直義の義弟)を討ち、自害させるなど破竹の勢いで足利勢の有力武将を撃破していきます。
小手指原(埼玉県所沢市)で今川範満を討ち、武蔵府中(東京都府中市)では下野守護・小山秀朝を一族300人の武将もろとも全滅させる圧勝劇で、鶴見(神奈川県横浜市)では佐竹貞義らを破るなど連戦連勝。武蔵・井出沢(東京都町田市)では鎌倉から出陣してきた足利直義を返り討ちにして敗走させます。そして、三方から攻め込んで7月25日に鎌倉を攻略、占拠しました。
どさくさ紛れに暗殺された護良親王
一方、北条勢に攻められて鎌倉を撤退することになった足利直義は建武2年(1335)7月23日夜、家臣・淵辺義博に命じて幽閉中の護良親王(もりよししんのう)を暗殺します。護良親王は鎌倉幕府倒幕の戦いの際に戦功を挙げ、建武の新政では征夷大将軍に任じられますが、足利尊氏を異常に警戒し、後醍醐天皇の寵妃・阿野廉子とも対立。ついには父・後醍醐天皇の信用を失って逮捕され、身柄を尊氏に引き渡されました。鎌倉に送られた護良親王は東光寺に幽閉されて足利直義の監視下に置かれていました。

足利直義は北条時行に護良親王を奪われ、反足利の旗頭に利用されることを恐れ、「敵に渡すよりは」と、かなり思い切った手段に出たのです。
『太平記』では、幽閉されていた土牢で淵辺義博に組み伏せられた護良親王は、義博の太刀の刃先をくわえ、嚙み折ったという凄まじさ。義博は脇差で親王の胸を刺し、首を落としますが、その首は嚙み折った刃先をくわえたまま鬼の形相だったと伝えられています。
勝長寿院の集団自害 時行逃亡…新たな戦いへ
関東での緊急事態に足利尊氏が京を出陣します。敗走した弟・足利直義と合流し、北条時行に反撃。鎌倉を奪還しますが、結局、尊氏は後醍醐天皇から離反。建武の新政は崩壊し、南北朝の動乱へとつながっていきます。そして後醍醐天皇を敵として挙兵した北条時行はその後、後醍醐天皇の南朝に加わるという分かりにくい経過をたどり、果てしない南北朝の戦乱が続いていきます。足利尊氏と後醍醐天皇の亀裂
足利尊氏と後醍醐天皇の決裂は尊氏の京出陣にその端緒があります。尊氏は出陣に際し、征夷大将軍と関東8カ国の管領として武士への恩賞決裁権を求めます。『太平記』によると、後醍醐天皇は関東管領の件を認め、征夷大将軍について関東平定後に検討するという返答だったといいます。曖昧な対応に、尊氏の武力を頼りにしつつ、その権限強化を警戒していた後醍醐天皇の苦悩が浮かび上がります。実際には尊氏の要求はいずれも認められていません。
征夷大将軍は武士を統率する官職であり、幕府を否定した後醍醐天皇としては、武士の統率を尊氏に一元化することは幕府復活の道を開くものであり、到底認められないという立場でした。
建武2年(1335)8月2日、尊氏は京を出発。北条時行追討に向けて東海道を東へ進みます。『太平記』は500騎程度で出発した尊氏の軍勢が近江、美濃、尾張、三河、遠江と進むにつれて続々と武士が加わり、駿河到着時は3万騎に膨れあがり、直義との合流で5万騎を超えたといいます。随分極端なようですが、『太平記』の数字の誇張としては割と穏やかな方です。北条時行の蜂起に加わった武士同様、尊氏の下に集結した者の中にも建武の新政に不満を持つ武士は多かったはずです。
北条の迎撃軍は台風で大損害
鎌倉を制圧した北条時行ですが、足利尊氏の軍勢が5万騎を超える状況は圧倒的に不利と自覚します。しかし、だからこそ積極的な迎撃策に出ました。時行:「源氏(足利勢)は非常に大勢で、迎え撃っても圧倒されてしまう。ここは先手を打つべきだ」
時行自身は鎌倉に残り、名越式部大夫(実名不明)の3万騎を差し向け、先制攻撃を仕掛けようとします。ところが、出陣前夜の8月3日夜、猛烈な風が吹いて兵たちは鎌倉大仏に逃げ込み、その大仏殿が崩れて約500人が圧死。とんでもない災難に見舞われます。季節柄、台風だったようですが、前途多難とはこのこと。鎌倉の人々はささやき合います。
人々:「戦場に向かう門出にこのような天災があっては、この戦はうまくいくまい」
不吉な門出の中、ともかくも名越軍は出陣し、8月8日早朝、佐夜(さよ)の中山(静岡県掛川市)で足利軍と激突したといいます。実際には、8月7日に矢作宿(愛知県岡崎市)で尊氏と直義が合流し、9日、遠江国橋本(静岡県湖西市)で激戦を展開。足利軍が連勝し、あっという間に鎌倉奪還の兵を進めました。
北条軍は壮絶な最期 時行は逃亡
最後は鎌倉・勝長寿院で諏訪頼重はじめ北条軍の主力武将43人が自害。しかも、顔の皮を削ぎ落とし、見分けがつかないようにした壮絶な方法で自害するのです。これは北条時行を逃がすためのトリック。少年の遺体もあり、これを時行に見せかける偽装として顔を分からなくしますが、この遺体だけ顔を削ぐと不自然で偽装にならないので、自害した全員の顔の顔を削ぎ落とすのです。それにしても壮絶というか、やり過ぎというか……。
諏訪頼重としては時行を何としても逃がし、再起を図らせたいという思いがあったのです。北条勢の中には三浦時継が船で鎌倉を脱出しています。時継は尾張に漂着後、捕らえられ、京で斬首されますが、時行も船で鎌倉を離れた可能性は大いにあります。
おわりに
北条時行の挙兵は連戦連勝の末、一時的に鎌倉を制圧しますが、最終的には挙兵した軍勢がほぼ全滅する悲劇的な結末を迎えました。この時、少年に過ぎない時行が反乱勢力のリーダーになり得るのかと不思議に感じられますが、この場合は北条高時の遺児であることを強調して同情を集めることができ、鎌倉幕府再興のシンボルとしても、建武の新政に不満を持ちながらもバラバラだった武士のシンボルとしても、反建武の新政派をまとめる看板としては大きな役割を果たします。この窮地を脱した時行は、室町幕府創設者・足利尊氏を敵と定め、尊氏と戦うために南朝に合流します。鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇に味方する時行の感情は何とも複雑で分かりにくいようにみえますが、敵の敵は味方というわけです。そして、後醍醐天皇よりも北条氏を裏切った尊氏への憎しみの方が大きかったと考えられます。
【主な参考文献】
- 兵藤裕己校注『太平記』(岩波書店、2014~2016年)
- 鈴木由美『中先代の乱 北条時行、鎌倉幕府再興の夢』(中央公論新社、2021年)
- 関幸彦『敗者たちの中世争乱』(吉川弘文館、2020年)
- 櫻井彦『南北朝内乱と東国(動乱の東国史4)』(吉川弘文館、2012年)
- 亀田俊和、生駒孝臣編『南北朝武将列伝 南朝編』(戎光祥出版、2021年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



コメント欄