自ら望んで神になった戦国三英傑
- 2025/04/21

死後に神格化され、神社に祀られて「神」となった人物は古来何人もいます。その多くは恨みを残して死んだ人間、非業の死を遂げた人間が悪霊と化してこの世に禍をもたらさぬよう、神として祀り上げて荒ぶる魂を鎮めるためでした。しかし、戦国の三英傑(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康)は生前より自ら神になる事を望んでいました。
生前から神になろうとした織田信長
織田信長は自らを「第六天魔王」と称したり、自身を神として崇めさせるために安土城に総見寺を建立したりしています。また、安土山に張り紙を張りだし、その中で「自分を礼拝する者は子孫と長寿に恵まれ、願いは成就し、健康と平安を得る」
と請け合っており、また、
「儂を信ぜぬ邪悪の徒は、現世においても来世においても滅亡するに至るであろう」
とも言っています。
これらの事はルイス・フロイスの『日本史』に書かれているのですが、信長は死後ではなく、自分が生きているうちから崇めよ、と言っていますね。そんな信長ですが天正10年(1582)6月2日、明智光秀の謀反に遭遇して本能寺の炎の中に消えました。
その後まもなく、山崎の弔い合戦で光秀を破った羽柴秀吉は、京都の名刹・大徳寺で信長を弔う7日間の大法要を執り行います。もちろん信長の後継者は自分だとのアピールの為ではありますが…。
さらに秀吉は信長の慰霊のため、京都市中にある小高い丘・船岡山に寺を建立し、信長の像を安置しようと計画、正親町天皇から天正寺の寺号も賜りました。結局、寺の竣工は途中で止まってしまいますが、その後の船岡山は信長の霊地として保護されます。
建勲神社建立
時は流れて明治2年(1869)、明治天皇は戦国乱世を治めて天下統一への道を開き、朝廷を篤く遇した信長の功績を称え、神社を建てるよう命令されます。翌明治3年、『建勲』の神号を賜って、信長の子孫で天童藩知事を務める織田信敏の東京の屋敷内と、織田家旧領地の山形県天童市に建勲社が建立されました。明治13年(1880)、建勲社は東京より秀吉が信長の廟所と定めた船岡山の中腹に遷座し、明治43年(1910)には現在地の山上に移されました。船岡山(京都府京都市北区紫野北舟岡町)は標高112mの小山で、東南側が建勲神社境内になっています。
“建勲神社”は、正式には “たけいさおじんじゃ” ですが、一般には “けんくんじんじゃ” として親しまれています。
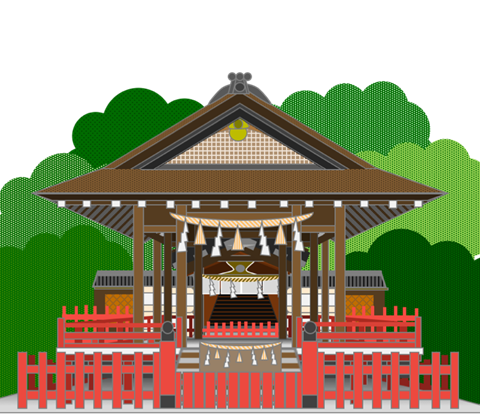
豊臣秀吉の遺体は荼毘に付されなかった?
「太閤様は自らの名を後世に伝えることを望み、遺体を焼却することなく入念にしつらえた棺に収め城内のしかるべき場所に安置するようにと命じられた。こうして太閤様は以後は神の列に列せられ、“シンハチマン”すなわち新しい八幡神と呼ばれることを望まれた」
宣教師フランシスコ・パシオの『太閤秀吉の臨終』に書かれていた文章です。
秀吉は慶長3年(1598)8月18日、伏見桃山城で亡くなります。第二次朝鮮出兵の最中でもあり、混乱を恐れてその死は伏せられ、遺骸はしばらく城中に留め置かれました。翌年、遺骸は東山三十六峰のひとつ・阿弥陀ヶ峰に葬られて麓に廟所が建てられ、これが豊国神社の始まりとなります。
豊国神社
秀吉の死の翌年の慶長4年4月16日、朝廷から豊国乃大明神(とよくにのだいみょうじん)の神号が与えられます。秀吉自身は “新八幡” として祀られるよう望みましたが、朝廷の意向とあればそちらが優先されます。4月18日に遷宮の儀があり、「兵威を異域に振るう武の神」として豊国大明神を祀る豊国神社が創建されました。4月19日には正一位の位が与えられます。
しかし時代は移ります。慶長20年(1615)、大坂夏の陣を経て豊臣家が滅びると、それまでは一応、豊国神社を敬う素振りを見せていた徳川家康が態度を一変させ、後水尾天皇に願い出て豊国大明神の神号は剥奪されてしまいます。
秀吉の正室・北政所が懸命に家康に願い出たことで社殿が壊されるのは免れましたが、その後は一切の修理・修築が禁じられ、荒れ果てるままに放って置かれました。御神体は心ある人が密かに自宅に隠し持って祀りましたが、江戸時代を通じて神社が顧みられることはありませんでした。
明治天皇の一声
慶応4年(1868)、明治天皇が大阪に行幸された時、所縁のある秀吉に言及されます。「(その業績は)皇威を海外に知らしめ、数百年たってもなお外敵の心胆を寒からしめる国家に大勲功ある今古に超越するものである」
こうして豊国神社の再興が布告されます。
明治6年(1873)には別格官幣社となり、明治13年(1880)に東山の現在地に社殿が建立されました。明治30年(1897)に阿弥陀ヶ峰山頂に石造りの五輪塔が建てられますが、その工事の最中に土の中から素焼きの壷に入った人間の骨が見つかります。これが記録に残る秀吉の遺骨らしいとされ、再度丁重に埋葬されました。

現在、豊国大明神を祀る神社は大坂の豊国神社をはじめ、秀吉ゆかりの全国各地に鎮座しています。
東照大権現となった徳川家康
家康も自分を神として祀り、徳川家の安泰を図ろうとしました。元和2年(1616)4月17日、家康は駿府城で75歳で亡くなります。家康:「儂の寿命もあと僅か…」
終わりが近い事を感じた家康は、自分の亡骸を駿府城に近い要害の地である久能城に葬る事と、日光に新しい神社を造る事を言い残します。
家康:「北天は宇宙の中心であり、不動の北極星の周りを星々が規則正しく運行する。これがこの世の規範である。日光は江戸のほぼ真北に位置し、その中心に自分が祀られることにより江戸幕府・徳川家ひいては日本の守り神となろう」
こう考えたのだそうです。
家康:「東国の諸大名の多くは徳川譜代の者たちであるからその心根は確かである。しかし西国にはいまだに豊臣に心を寄せる大名も多い。その者たちに睨みを利かすよう我が神像は西向きに安置せよ」
とも命じました。
遺命を守る秀忠と家光
家康:「儂の死後は駿河の久能山に葬り、一周忌を過ぎたら下野の日光山に小堂を建てて勧請せよ」
この遺命を守り、二代将軍秀忠は父親の死後ただちに久能山東照宮の造営を始めます。1年と7ヶ月の期間で建てられた久能山東照宮は、当時最高の匠たちが集められ、建築技術と装飾芸術の粋を尽くした“権現造”の様式で建立されます。これは日光東照宮をはじめ、全国で100社以上あると言われる東照宮建築のひな型となりました。
日光東照宮は元和3年(1617)に秀忠が創建しましたが、現存する建築物のほとんどは、三代将軍家光が寛永11年(1634)に行った“寛永の大造営”で建て替えたものです。とても“小堂”どころではない日本の社寺には珍しい極彩色の絢爛豪華な日光東照宮ですが、1年5ヶ月の改築期間中に延べ454万人もが携わったと言います。

狩野派の総帥・狩野探幽が装飾面を受け持ち、三神庫の『想像の象図』や拝殿天井画の『百頭の龍』は探幽の傑作です。
おわりに
元和3年(1617)、家康の遺骸は改葬のために駿府久能山から下野国日光山へ運ばれます。この“日光遷座”には名のある武将300余騎、雑兵1千人が従いました。同年4月には社殿が完成し、朝廷から「東に照る如来が現われた神」を意味する『東照大権現』の神号と正一位の位が追贈されました。
【主な参考文献】
- 河内将芳『所の変遷からみる 信長と京都』(淡交社、2018年)
- 柴裕之『図説 豊臣秀吉』(戎光祥出版、2020年)
- 小和田哲男『徳川家康』(静岡新聞社、2022年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。


コメント欄