※ この記事はユーザー投稿です
【やさしい歴史用語解説】「五大老」
- 2025/10/27

信長の後継者となって天下人へ昇りつめた豊臣秀吉ですが、そんな彼でも老いには勝てません。秀吉が最晩年に打ち出した「五大老と五奉行」の制は、幼い我が子・秀頼へスムーズに政権をバトンタッチさせる苦肉の策でした。
秀吉が関白になったことで武家貴族となった豊臣家ですが、徐々に政権基盤は脆弱になっていきました。なぜなら秀吉の近親者が次々に亡くなっていたからです。弟の秀長は嫡男がいて、姉の息子・秀勝や秀保らを養子として迎えますが、いずれも若くしてこの世を去っています。
また、秀吉も石松丸や鶴松という実子に恵まれますが、二人とも夭折していました。たしかに運がなかった面はありますが、秀吉の跡を継ぐべき候補は、もはや甥の秀次と小早川家に養子に入った秀秋しかいなかったのです。
そこで秀次に天下人を譲り渡すべく、秀吉は段取りを進めていたはずでした。しかし文禄2年(1593)になって実子の「お拾」が生まれてしまうのです。秀吉と秀次の間にできた些細な溝はだんだんと大きくなり、翌々年になると秀次の関白職剥奪から高野山への蟄居、そして切腹へと繋がっていきました。この秀次事件によってお拾の親族は秀秋しかいなくなります。しかし秀秋は小早川家へ入っていますから、後見役として適任ではありません。そこで「五大老と五奉行」の制を定めて、政権の安定を図ろうとしました。
五大老として選ばれたのは、徳川家康・前田利家・毛利輝元・宇喜多秀家・上杉景勝(小早川隆景が没して後から加わる)の5人です。いずれも大きな領地をもつ大大名ですから、この絶妙なパワーバランスで互いを牽制させようとしたのでしょう。
しかし当時から五大老と呼ばれていたわけではありません。寛永19年(1642)に林羅山が『豊臣秀吉譜』において「天下大老」と記載したのが初見ですし、寛政11年(1799)に編纂された『寛政重修諸家譜』の中で、ようやく前田利家のことを「五大老」と記載しています。
こうした点から決して明文化された制度ではなく、かなり曖昧な存在だったことが読み取れますね。
また、五大老の下に五奉行が付属しているという見解もありますが、実はそうではありません。大老はあくまで秀頼を支える立場であり、実質的な行政や裁判などは五奉行が権限を握っていました。つまり、五大老と五奉行は似て非なるもので、その職責はまったく異なっていたのです。
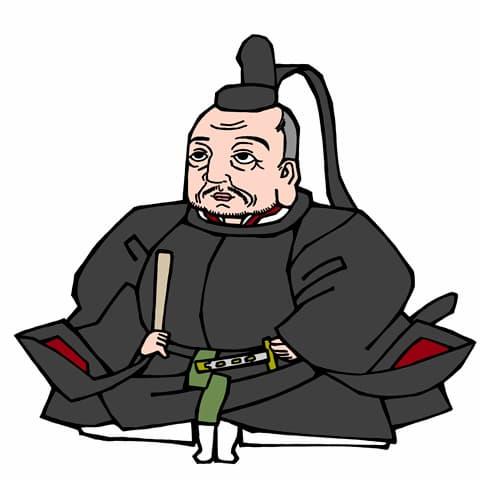
しかし、秀吉は徳川家康の実力を見誤っていたようです。秀吉の死後、家康は親徳川大名の結束を促し、さらに他の大老たちの力を削ぐ策略を講じます。前田家を屈服させ、次いで上杉家に照準を定めたところで、関ヶ原の戦い(1600)が起こりました。
家康にとって五大老の制が定まったからこそ動きやすくなった。そんな見方もできるでしょうか。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



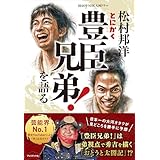
コメント欄