※ この記事はユーザー投稿です
【やさしい歴史用語解説】「五奉行」
- 2025/10/27

豊臣秀吉はその晩年に「五大老」と「五奉行」の制度を定めましたが、双方には大きな違いあります。
「五大老」は、まだ幼い豊臣秀頼を補佐する役割を与えられましたが、秀吉には裏の思惑がありました。彼らはいずれも数十万石の大領を持つ実力者ですから、互いに牽制させる狙いがあったようです。つまり、秀頼が成人するまで絶妙なパワーバランスで力の均衡を保とうとしたわけですね。
一方、「五奉行」は豊臣政権の行政を司った実務機関でした。そのメンバーは石田三成・前田玄以・浅野長政・増田長盛・長束正家の5人で構成されていたようです。とはいえ、五大老と同じく明文化された制度ではなく、かなり曖昧な存在だったことが読み取れるでしょうか。
また、通説では豊臣政権のリーダー格である五大老があり、その下に五奉行が付属しているという見解がありますが、決してそんなことはありません。そもそも任されている職責が違いますし、仕事の区分も異なっていました。
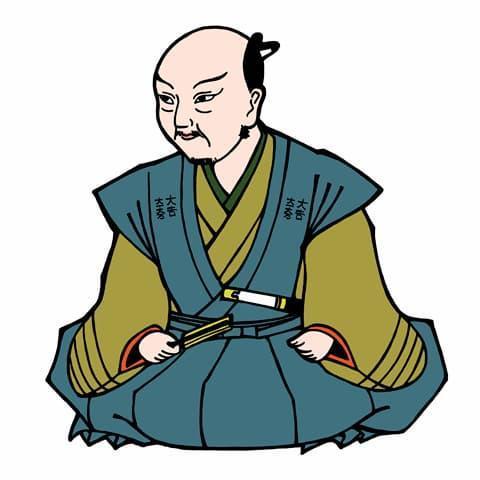
なお、石田三成をはじめ、五奉行の面々は、五大老のことを「奉行」と呼んでいて、自分たちのことを「年寄」と表現しています。これではどちらが格上なのかわかりませんよね?一方の五大老筆頭である徳川家康は、五奉行のことを「年寄」とは呼ばずに単に「奉行」と呼んでいるだけです。
なぜこれほど双方で捉え方が違うのでしょう?
おそらく三成には次のような認識があったのでしょう。
「年寄」とは政治に参与する武家を意味しますから、三成が自分たちをそう呼ぶのも間違いではありません。ましてや実質的に政権を運営しているのは五奉行です。「自分たちこそ国のトップだ」という自負やプライドを持っていたのも当然と言えば当然ですよね。
さて、慶長5年(1600)、徳川家康が軍勢を率いて会津討伐へ向かいます。そこで家康に突きつけた弾劾状が「内府ちかひの条々」でした。
五奉行のうち、三成は佐和山で謹慎中ですし、浅野長政は会津討伐軍に従軍しています。そんな最中、前田玄以・増田長盛・長束正家の三名が連名で出した、徳川家康に対する13ケ条の弾劾状(家康を糾弾したもの)です。
もちろん三成も陰ながら加わっていたはずですが、次々に秀吉の法度を破る家康に対し、具体例を列記しつつ、怒りを込めた空気が伝わってきます。
「誓紙に従わず、亡き太閤殿下の御遺命に背いては、何をもっての政なのか。この上は一人残らず決意の上、秀頼公ただお一人を主君と仰ぎ奉ること」
上記にあるように、政権の仕置をする者として家康の勝手は許さない。そんな奉行たちの心意気が伝わってくるようですね。しかし結果は関ヶ原合戦での敗戦に繋がり、五奉行の制度はたった2年で解体されてしまうのです。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。




コメント欄