※ この記事はユーザー投稿です
関ケ原の合戦の論功行賞で「東海道」を奪還した徳川家康
- 2025/01/27
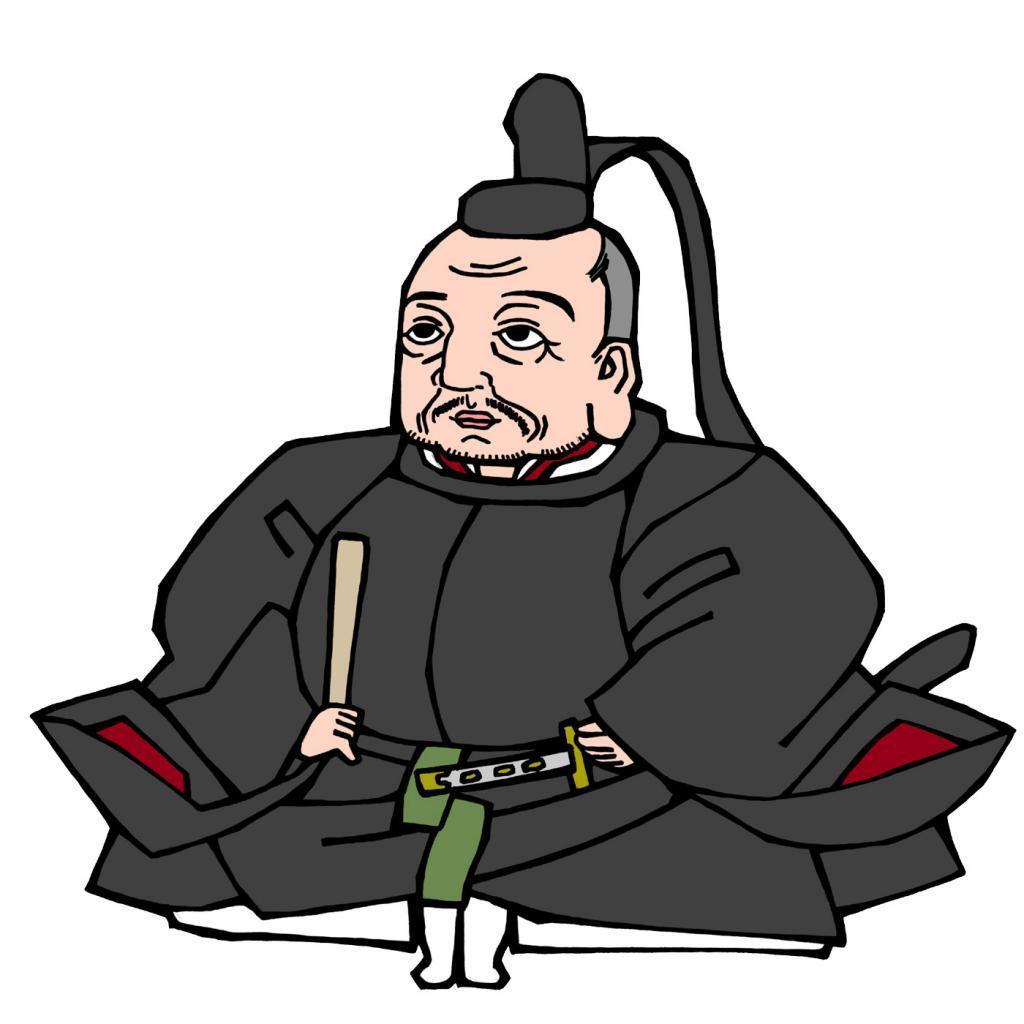
慶長5年(1600)の関ケ原の合戦に勝った徳川家康は、敵味方になった大名たちの論功行賞を断行しました。その大きな目的の一つに、父祖代々の領地だった「東海道の奪還」が潜んでいたのです。
東海道はもともと家康の領地だった
徳川家康は、永禄3年(1560)の桶狭間の戦い後に今川家からの独立を果たし、三河を統一してからは遠江、駿河へと領地を増やしていきました。ところが、豊臣秀吉が天下取りの仕上げとした北条氏討伐の後、家康に関東への移封を命じました。家康にとっては、これまで領有していた三河、遠江、駿河を明け渡さねばならなくなったのです。
秀吉は、旧家康領に子飼いの大名たちを配置させ、家康が容易に関東から東海道を上洛できないように「関門」を築いたのです。
小山評定での山内一豊の一言
慶長3年(1598)に秀吉が死去し、幼い秀頼が後継者になると、豊臣政権最大の実力者となっていた家康が、天下取りに向けて動き出します。慶長5年に家康は、上洛命令に従わない上杉景勝討伐のために東へと出陣しますが、家康を敵視する石田三成が毛利氏ら西国大名を束ねて決起したのです。家康は進軍を止め、小山(栃木県)で評定を開いて従軍する諸大名に引き返す意向を伝えました。
この時、遠江掛川城主だった山内一豊が「家康殿に城を明け渡します」と発言。これが引き金となって、東海道の諸大名が次々と同調し、家康は安心して西へと進軍することができたのです。
家康は「東海道奪還の布石が打てた」とほくそ笑んだことでしょう。
論功行賞で加増転封された豊臣系大名
関ケ原の合戦に勝利した家康は、主君・秀頼に代わって諸大名への論功行賞を行います。その手法は実に狡猾で、豊臣系大名(外様大名)に対しては領地を加増しながら、江戸から離れた土地への移封を行ったのです。東海道の諸大名はどうなったのでしょうか?
戦いで中心的な活躍をした福島正則は尾張清洲24万石から安芸広島50万石という倍増となり、発言の口火を切った山内一豊も掛川5万石から土佐24万石へと大出世を果たします。
駿府府中14万石の中村一氏は伯耆米子17万5千石に、遠江浜松12万石の堀尾吉晴は出雲富田24万石に、三河岡崎10万石の田中吉政は筑後柳川32万石にと、それぞれ加増されたわけですが、東海道からは切り離されたのです。
論功行賞の結果、東海道はどうなった?
家康にとって、三河岡崎は出身地ですし、駿府府中は人質として過ごした地、遠江浜松はかつての本拠地というゆかりの深い領地。関ケ原の勝利によって、10年ぶりに奪還することができたのです。岡崎には三河譜代として家康の信頼が厚かった本多康重を、浜松には一族でもある松平忠頼を配し、掛川には異父弟の松平定勝が入りました。
東海道の重要な拠点である尾張清洲は、四男である松平忠吉に与え、忠吉の死去後には九男の義直が継いで、御三家の尾張徳川家となりました。
駿府には譜代大名の内藤信成が配されましたが、家康が将軍職を秀忠に譲って大御所となってからは、家康自ら駿府城に入り、幕政を取り仕切ることになります。
東海道は幕府直轄地もしくは譜代大名の領地として固められたのです。
おわりに
徳川家康が奪還した東海道の諸藩のうち、岡崎藩と浜松藩は何度か藩主の入れ替わりがあったものの、江戸時代を通じて常に譜代大名が配置されています。江戸と京都を結ぶ大動脈・東海道は、徳川将軍家の支配下に置かれ続けていたのです。 この記事を書いた人
フリーランスでライターをやっています。歴女ではなく、レキダン(歴男)オヤジです!
戦国と幕末・維新が好きですが、古代、源平、南北朝、江戸、近代と、どの時代でも興味津々。
愛好者目線で、時には大胆な思い入れも交えながら、歴史コラムを書いていきたいと思います。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



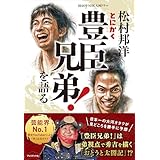
コメント欄