太閤・豊臣秀吉の死因は、あの意外な病だった!?
- 2023/09/11

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
豊臣秀吉が体調を崩し、病床に伏せるようになったのは、慶長3(1598)年5月のことであったという。先立つこと2ヶ月前、京において醍醐の花見を催したばかりであった。
既に体調不良を感じていた秀吉は有馬の湯に湯治に出かけたものの、側近の金森長近の記した『 自語録』 によると、自力で浴室まで歩くことができない状態だったらしい。医師の見立てでは「脈に異常がある」とのこと。しかしこの後に食欲は衰え、そのために筋肉量も落ちてみるみる衰弱していったと伝わる。下痢や腹痛、そして手足の痛みもあり、その後錯乱状態になったとか、失禁したとかいう記述まであるという。
かなり症状が幅広いため、複数の死因が推定されていて未だ確定していない。今回は、史料の記述と現代医学の知識を組み合わせて、秀吉の死の真相に迫ってみたい。
既に体調不良を感じていた秀吉は有馬の湯に湯治に出かけたものの、側近の金森長近の記した『 自語録』 によると、自力で浴室まで歩くことができない状態だったらしい。医師の見立てでは「脈に異常がある」とのこと。しかしこの後に食欲は衰え、そのために筋肉量も落ちてみるみる衰弱していったと伝わる。下痢や腹痛、そして手足の痛みもあり、その後錯乱状態になったとか、失禁したとかいう記述まであるという。
かなり症状が幅広いため、複数の死因が推定されていて未だ確定していない。今回は、史料の記述と現代医学の知識を組み合わせて、秀吉の死の真相に迫ってみたい。
胃癌もしくは大腸癌説
秀吉の死因において、大腸がん説が唱えられたのは、症状として下痢や腹痛が含まれているためであるが、代表的な症状とされる「血便」や「下血」について記述が史料にないようだ。さらには癌が進行した際に起こることが多いとされる腸閉塞からくる「嘔吐」などの症状も確認できなかった。もっとも、末期大腸癌だからといって、必ずしも血便や腸閉塞が見られる訳ではないし、S状結腸がんであれば血便といっても黒っぽいタール状の便が見られることがある。
当時はタール状の便が血便と認識されない可能性もあったと思われるので、完全に否定できないように思う。
これは胃癌に関しても同様である。篠田達明氏の『戦国武将のカルテ』では、胃癌や大腸癌等の消化器癌説を取っている。
癌末期に起こる「 がんカヘキシー( 悪液質) 症候群」により癌が分泌する汚濁した体液が身体を巡ることでむくみや気だるさ等の症状が現れ、脳に障害が生ずることすらあるという。
がんカヘキシー症候群は多様な症状を示すので、秀吉の病状をほぼカバーしているように思える。しかし、秀吉の半昏睡状態は一過性のものであったと言われているので、この辺はどうなのだろうかという疑問は残る。
赤痢説
赤痢は下痢、腹痛、血便等の症状を呈する感染症である。便にしばしば血液が混じることが ”赤痢” という名の由来だそうだから、この症状がなかった可能性が高い以上、赤痢が死因という線は薄いのかもしれない。
尿毒症説
尿毒症は、通常末期腎不全にともなって見られる症状であるが、秀吉の場合は結核性萎縮腎による尿毒症が疑われている。また、前立腺肥大症が進行して排尿が困難となり、腎不全を併発したことによる尿毒症発症という見立ても存在する。
尿毒症は様々な症状を呈するが、中でも、「脈の乱れ」、「食欲低下」、「下痢」等は秀吉の病状と一致しており、ある程度の信憑性はありそうだ。
ところが、尿毒症で見られる「意識障害」とは一時的なものではなく、幻覚等を見る状況を経て、昏睡状態に至る症状であるから話はそう単純ではない。
確かに秀吉は一時錯乱状態になっているものの、その後一時回復して秀頼の行く末のことを案じているのだ。
これを考えると、どうやら尿毒症である可能性は低いようだ。
神経梅毒説
神経梅毒説は昔から根強く支持されてきた説の1つであるという。これは、やはり秀吉が大の女好きであったということと大いに関係があるだろう。神経梅毒は、腹部の痛み、認知症、抑うつ、誇大妄想などの症状が見られ、これらは秀吉の病状ともほぼ矛盾がない。
また、発症までに10年~25年もの期間を要することが多いため、30代に感染し晩年期になって初めて発症する可能性は大いにあり得る。
しかしながら、神経梅毒説には大きな問題点があるのだという。若林利光氏の『戦国武将の病が歴史を動かした』によると、神経梅毒の精神症状は通常、無気力・無欲状態が前面に出ると言われているそうだ。
この状態で、秀頼の行く末を案ずることが果たしてできたのか、という点を若林氏は疑問視しているようなのだ。
もう一点、正室のおねや側室の淀殿に感染の兆候が現れていない点も神経梅毒説に疑義を唱える理由となっているようだ。
私もこの見立てに大いに賛同している。
脚気説
そもそも、脚気説を唱えたのは前出の『戦国武将の病が歴史を動かした』の著者で医師の若林利光氏である。脚気とは、ビタミンB1の欠乏によって起こる病だ。初期の症状は全身の倦怠感、動悸、食欲不振等であるが、末梢神経障害を引き起こすと手足のしびれや痛みを訴えるようになるという。
これは秀吉の病状と酷似している。そして、重症化すると心臓や脳にまで障害が出るというから恐ろしい。脳への障害はウェルニッケ脳症と言われるもので、錯乱状態等を経て昏睡状態に近い症状を示すことがあるそうだ。
ただ、尿毒症等の昏睡状態とは異なるのは、症状が一過性であるという点である。これも秀吉の病状と一致している。
私が脚気説を知ったのは10年ほど前であるが、脚気説ならば秀吉の病状をすっきり説明できることに驚いた記憶がある。
秀吉はおそらく、公家と同様に白米や贅沢な食材を日常的に食していたに違いないと思い込んでいた私には、彼が脚気に罹っても不思議はないと思っていた。
これ以降、戦国武将の死因に興味を持った私は、これに関する情報をしらみつぶしに探し回るようになったのであるが、ひょんなことから意外な事実を知ることとなる。
なんと秀吉は天下を統一した後も、貧しい頃食べていた田舎料理が好物だったというのだ。
主食は豆味噌のおにぎりもしくは麦飯であったというし、里芋や大根、そしてごぼうなど、ビタミンB1が豊富に含まれている食材を好んだらしい。
このことから、少なくとも秀吉が食生活によって脚気に罹った可能性は低くなった。
もしかすると、脚気が死因ではないのだろうかという考えが脳裏をかすめていたとき、たまたま手にした本が若林利光氏の著書『戦国武将の病が歴史を動かした』だったのである。
若林氏は、当時来日していた宣教師パシオの手紙に注目している。それによると、秀吉の初期の症状は下痢と胃痛であるという。
下痢は脚気の症状の1つであるが、逆に何らかの要因による激しい下痢によってビタミンB1が失われて脚気を発症することがあるらしい。
この場合、胃痛は脚気によって心臓に障害が出たことによる心窩部痛(みぞおちの痛み)で説明できるそうだ。
下痢が原因で脚気を発症したとするならば、やはり脚気説が有力ではないかと私は睨んでいる。
感冒説
感冒説は、桔梗湯が処方されたことから提唱された説であるという。感冒が死因であるとすると肺炎や脳症を併発したことによる死が考えられる。ちなみに乳幼児以外で脳症を併発するケースは少ないらしいが、成人の発症例も稀ながら存在するので、高齢であった秀吉が発症する可能性は0ではない。
症状も、嘔吐・痙攣・錯乱、さらには昏睡に至るというから、秀吉の症状と結構被っている。肺炎も高齢者で発症すると、食欲不振・失禁・錯乱等の症状を示すようだ。
症状的にはあり得る話であるが、秀吉が発病してから亡くなるまで3ヶ月ほどの期間があったことを考えると、脳症や肺炎にしては期間が長すぎるように思える。
毒殺説
18世紀の朝鮮の古文書である『燃藜室記述』には、「秀吉は沈惟敬によって毒殺された」という記述があるという。沈惟敬は朝鮮出兵(文禄の役)の和議交渉の際に明側の使節として交渉にあたった人物である。しかし、沈惟敬が来日したのは慶長元(1596)年であり、秀吉の死はその2年後のことであるから、いかに遅効性の毒を用いようとも毒殺は無理だろう。
ただ、他の人物が毒殺を画策し、後に朝鮮側に「沈惟敬が秀吉を暗殺した」という噂を流したとすれば話は別である。
ここでは、沈惟敬と和議交渉にあたった小西行長と宗義智に目を向けてみよう。
文禄の役の戦況は、日本軍が朝鮮軍を次々と破り、援軍要請を受けた明が軍を派遣するが、これをも退けたという状況であった。
明軍は戦意喪失していたし、日本軍は戦況的には有利であったが、兵糧不足が足かせとなり積極的に兵を進められない状況に陥っていたのである。
そのため、講和交渉が開始されたのであるが、小西行長は沈惟敬と謀って、秀吉には明が降伏し、明には秀吉が降伏したということにして講和を結ぼうとしたようだ。
これは、秀吉が明の降伏以外の条件での講和を頑なに拒むことが予想され、その場合、再出兵を余儀なくされる可能性が高いと踏んだからであろう。もはや、豊臣政権の最大のネックは、その長たる秀吉の暴走になり始めていたようだ。
結局、小西行長と沈惟敬の謀は失敗に終わり、秀吉は案の定、再出兵を命じた。いわゆる慶長の役である。
衰えてきたとはいえ、明は大国である。この時期の明の人口は8000万人から1億人と推定されている。一方、同時期の日本の人口は1200万人程度であったというから、短期的には勝利を収めても長期戦となれば、不利となることは明らかだったろう。
ここまで来ると、無謀な出兵を止めるには太閤殿下に死んで頂くしかあるまいと考える人物が出てきても不思議はないのではないか。
私は以前、豊臣秀頼の記事で、秀吉が暗殺されたとすれば、対馬領主であった宗義智が徳川家康に相談して図られたのではないかと書いた。
あわせて読みたい
対馬は平野が少なく農業に適さない地であり、朝鮮との交易で生計を立てるしか道のない国であるから、出兵が長引けば国内が疲弊することは明らかだったのである。
暗殺説を取るならば、水銀やヒ素を用いた可能性が高いだろう。水銀中毒は腹痛、下痢、頭痛、悪寒、しびれ、めまい等を経て精神錯乱に至ることがあるという。ヒ素中毒は腹痛、嘔吐、発熱、下痢、そして精神錯乱等を示すことがあるとされている。
確かに、秀吉の病状に似ているようだ。
あとがき
秀吉の死因は戦国史の中でも、大きな謎とされていることは有名である。特に、最初はそれほど重症とも思われなかったにも関わらず、発病してから短期間で死に至ったという点が謎を深めている要因ではないかと思われる。実は、あまり知られていないが秀吉は天下人となった辺りから、「番医制」という制度を整えた。番医とは医師団のことであるから、秀吉は当時のスーパードクターたちに自らを診察してもらっていたということになる。
名医に囲まれながら、なぜ秀吉はあっさり亡くなってしまったのか。これには裏話がある。秀吉が発病したとき、番医のメンバーの中でも抜きんでた腕を持つ医師が何故か秀吉の側にいなかったというのだ。
その医師の名は曲直瀬玄朔。
玄朔は脚気の治療経験も豊富であったという。豊臣秀次の主治医でもあった玄朔は、次第に秀次の相談役となっていった。その矢先の文禄4(1595)年、秀次事件が起こり、相談役だったということで玄朔までもが常陸に流罪となってしまったのだ。
そんなわけで、秀吉が発病したとき玄朔は側について治療ができなかったのである。秀吉の病が脚気であったとしたら、これは致命的であろう。『曲直瀬某氏所蔵文書』によると、秀吉の最期の治療に携わっていることが確認できるが、時すでに遅しだったのではないか。
ここまできて、なんだか秀次の呪いが秀吉に死をもたらしたような気がして背筋が寒くなってきた次第である。
【主な参考文献】
- 若林利光氏『戦国武将の病が歴史を動かした』(PHP研究所、2017年)
- 篠田達明氏『戦国武将のカルテ』(KADOKAWA、2017年)
- 松田毅一・川崎桃太 翻訳『完訳フロイス日本史』(中央公論新社、2000年)
- 宮本義己『戦国武将の養生法』(KADOKAWA、2014年)

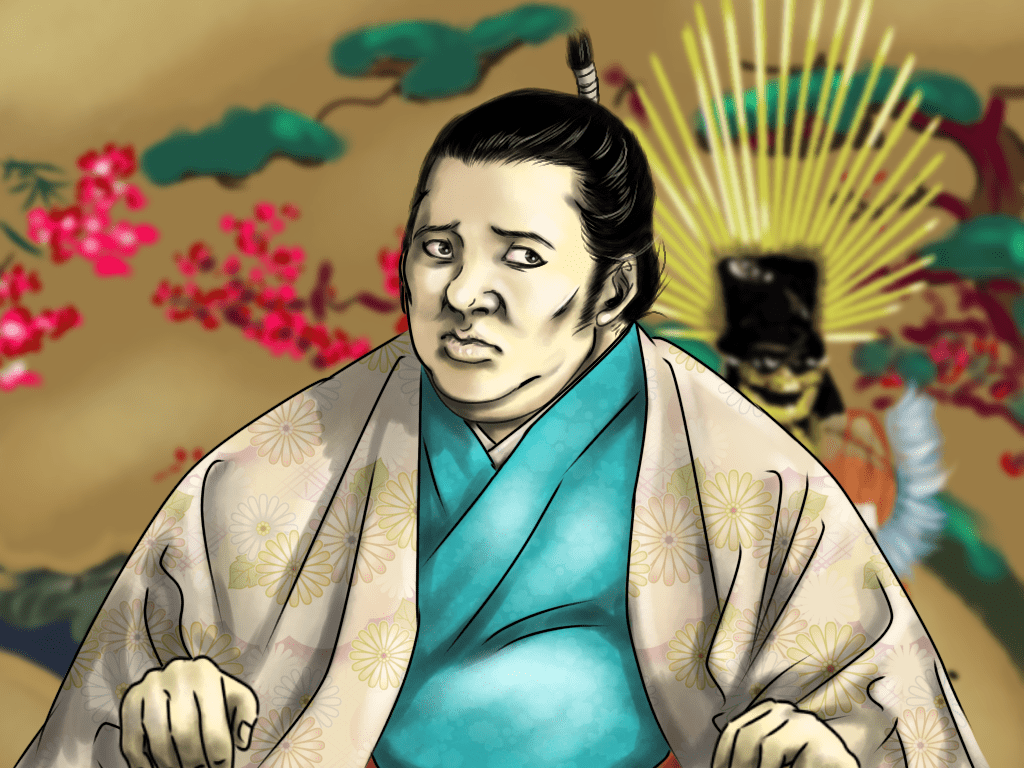



コメント欄