英雄たちのお手植え伝説 ~偉人とともに語りつがれる樹木伝説
- 2025/02/21

「お手植え伝説」というものをご存じでしょうか?その土地に生えている大木や神木といった、高い樹齢をもつ木の由来として語られる伝説のことです。たとえば、「何百年も昔、ここに英雄が訪れ、この木を植えたのだ」……といったように。
伝説の内容は、木を寄進するといったメジャーなものから、地面へ杖や箸を挿したという奇跡まで、実にさまざま。木を植える伝説の英雄は、その地域で名の知られた武将や僧などが多いようですね。
今回は、お手植え伝説に出てくる樹木はどんなものなのか、どんな英雄が登場するのか、ということにスポットを当てていきます。
伝説の内容は、木を寄進するといったメジャーなものから、地面へ杖や箸を挿したという奇跡まで、実にさまざま。木を植える伝説の英雄は、その地域で名の知られた武将や僧などが多いようですね。
今回は、お手植え伝説に出てくる樹木はどんなものなのか、どんな英雄が登場するのか、ということにスポットを当てていきます。
樹木がもつ長寿の力
日本で一番樹齢が高い木として有名なのは、屋久島の縄文杉。その高さは25mを超え、2500年以上生きているとされています。また、杉ほど背の高い木ではないですが、松の木は環境によっては500~1000年ほど生きると考えられています。
「日本一の松」として知られる善峯寺(京都府京都市)にある「遊龍(ゆうりゅう)の松」は、樹齢600年以上の五葉松であり、国の天然記念物に指定されています。

大きな木で、幹がたくましく、がっしりとしていて、青々と茂った葉が風に揺れている様子などを見ていると、なんだか涙が出てきて拝みたくなってしまうような、不思議な気持ちになりますね。
奈良時代に編纂された日本最古の和歌集『万葉集』では、「木の枝を飾りとして髪に挿すのは千年の長寿を祝うためだ」という内容の和歌があります。
あしひきの 山の木末(こぬれ)の 寄生(ほよ)取りて 挿頭(かざ)しつらくは 千年寿(ほ)くとぞ
現代語訳:山の木の枝先にある寄生木(ヤドリギ)を取って頭に飾ったのは、千年の長寿を祝ってのことである。
二月十九日、左大臣橘家の宴に、攀(よ)ぢ折れる柳条(やなぎのえだ)を見る歌一首
青柳(やぎ)の 上つ枝(ほつえ)よぢ執り かづらくは 君が屋戸(やど)にし 千年寿くとぞ
現代語訳:青柳の枝先を引き寄せて折り取り、鬘(かづら/頭の飾り)にして自分たちが遊ぶのは、君の御屋敷で、千年をお栄えになるようお祝い申上げるという気持なのであります。
ヤドリギは樹齢の高い木ではありませんが、他の木に寄生して成長することから、強い生命力の象徴としてとらえられていたのかもしれません。
また、現代で柳というと幽霊のイメージがありますが、柳は風雪に強い木であるため、こちらも古代ではたくましい生命力を持つと考えられていたようです。

古代より人は、植物の持つ生命力を不思議な力ととらえて、長寿などの恩恵を受けたいと考えていたことが分かりますね。
お手植え伝説のあらすじ
お手植え伝説は日本各地で語られており、樹木伝説とも呼ばれます。そのあらすじは、大まかに分けると以下のようなものがあります。- ある人物が、訪れた地や関わりの深い地へ木を寄進する
- ある人物が地面へ箸(または杖、楊枝)を挿すと樹木となった、などの奇跡を起こす
- ある人物が戦で負けて逃げる際、逃走の手助けをした村にて、敗走の無念と村への感謝とともに箸を挿すか樹木を植える
次からは、どんな人々が樹木を植えたのかを見てみましょう。
武田信玄のお手植え伝説
甲斐国(山梨県)の有名な戦国大名といえば、武田信玄。武田信玄にまつわるお手植え伝説には、以下のようなものがあります。武田信玄のお手植え伝説
信玄に関する伝説では、「武田信玄が木を植えた」という内容で、松や桜、梅など、比較的樹齢の高い植物が挙げられています。特に、富士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市元城町)のしだれ桜は信玄が植えたとされている中でも有名で、「信玄桜」と呼ばれ、2代目となる現在でも人々に親しまれています。

八房梅(やつぶさうめ)の伝説
川中島の戦いの際、信玄が喉の渇きを訴えて水を求めたところ、従者は水の代わりに梅を差し出しました。信玄がその梅を噛むと実が8個に割れ、そこへ捨てられた梅の実はやがて芽を出して成長し、1つの花に8個の実を結んだため、「八房梅」と呼ばれました。
梅の花が1つの花に8個も実を結ぶことは珍しいとされています。
楊枝梅/楊枝杏の伝説
信玄が楊枝をさしたままの梅(または杏)を残して行ったところ、そこから芽が出て成長し、穴の開いた実が成るようになったという伝説があります。徳川家康のお手植え伝説
続いて、江戸幕府を開いた戦国大名として名高い徳川家康のお手植え伝説についても見ていきましょう。徳川家康の敗走
家康が信玄と戦って負けた際、とある村に逃げ込み、農家の者へ頼んで隠してもらったことで、敵の追手をかわすことができました。後日、家康はその農家へお礼として土地を与え、その家は大富豪として栄えたといい、庭には家康が植えたとされる黒松などがあったそうです。三度栗(再栗)
家康が敗走した時に、とある老婆の家にて栗のご飯を食べ、そのお礼にと栗の木へ念じたところ、一年に複数回実を結ぶ栗となったそうです。また、同じ系統の伝説としては、家康が武田信玄と戦っている最中に弁当を食べようとしたところ箸がなく、近くにあった栗の木の枝を箸の代わりとして、「天下統一を遂げることができたら三度実を結べ」と念じ、その結果、家康が念じた栗の木は三度実を結ぶようになったといいます。
その他のお手植え伝説
武将にまつわるお手植え伝説を紹介してきましたが、不思議なことに、これらと似ているものの、別の人物が奇跡をおこす伝説も存在しています。それは、弘法大師や親鸞聖人といった、高名な僧による伝説です。
弘法大師空海
平安時代初期を生きた真言宗の開祖、弘法大師空海が杉の箸を地面に挿したところ、成長して大木となった、という伝説は、長野県や奈良県などにも伝えられています。箸の種類は柳であったり、杉や銀杏などの杖を挿したという伝説もあります。
親鸞聖人
鎌倉時代において、浄土真宗の宗祖とされる親鸞聖人が、お寺にて食事の際に使った杉(もしくは松やザクロ)の箸を地面に挿したところ、根が生えて大木となったという言い伝えがあります。また、前項にて紹介した家康の三度栗の伝説も、地方によっては、弘法大師または親鸞聖人によるものだった、という言い伝えが残っています。
その他にも、神話に登場する英雄・日本武尊(やまとたける)、第15代応神(おうじん)天皇の母である神功皇后(じんぐうこうごう)、鎌倉幕府初代征夷大将軍の源頼朝、鎌倉時代の僧であり日蓮宗の開祖・日蓮上人など、歴史上の偉人とされる人々にも、これらと同様の伝説があります。
名の知られた高僧が奇跡を起こす伝説は、当時の仏教への信仰、仏法の不思議な力を期待する民衆の影響があったのかもしれません。
ただ、武将による奇跡については、なぜ武将が木を植えることと結びついたのか、ちょっと疑問に感じるところですね。
語りつがれるお手植え伝説
各地で語りつがれるお手植え伝説には、以下のような共通点があります。- 松、杉、桜、梅など、比較的長寿の木が多い(柳などの場合もある)
- 僧や武将など、歴史的に有名な人物が植えたものとされる
- 箸や杖などを地面に挿すと、根が出て育ったという奇跡を起こす話がある
- その地域や寺などで大切にされている大木、もしくは神木の由来として語られることが多い
お手植え伝説に長寿の木が多く登場するということは、その伝説は何代も続けて人の心に残っているということ。逆に、伝説があっても枯れてしまった木に対しては、それ以降言い伝えられることなく、人々に忘れられてしまうといった側面もあるのかもしれません。
この土地には偉大な人が植えた木がある、という伝説は、その土地が重要な場所であることを示すものですし、周辺の地域に暮らす人々の結束を強めるという効果もあったことでしょう。
お手植え伝説が広く長く言い伝えられることで、大自然の不可思議な力に対する畏敬の念が生まれ、さらに過去の偉人という権威の象徴とともに語ることで、大木の価値を高めていったのではないかと考えられますね。
おわりに
古くから人々は、地域の言い伝えにある大木や神木を敬い、信仰してきました。森林資源が豊富な日本には、お手植え伝説の他にも、樹木に関する伝説や逸話が数多く残っています。かつての日本、とある村で「この大きな木はね、昔むかし、ここを訪れた偉い人が、杖を挿したものなんだよ」と、父母や祖父母、大人たちが、そうやって子どもに語る時。
驚きとともに子どもが見上げる大きな木は、地面にどっしりと根を下ろしてそびえ立ち、自分たちを守ってくれているように感じられたことでしょう。
皆さんも、旅行で訪れた寺社や地元などで、古い大きな木を見つけたら、その由来を調べてみると面白いかもしれませんよ。
【主な参考文献】
- 西村真次『万葉集伝説歌謡の研究』(第一書房、1843年)
- 高木敏雄『日本伝説集』(郷土研究社、1913年)
- 水垣久 編『万葉集(現代語訳付)』(やまとうたeブックス、2018年)※本文中の引用はこれに拠る。
- 柳田國男 監修『日本伝説名彙 改版』(日本放送出版協会、1971年)
- 及川祥平『偉人崇拝の民俗学』(勉誠出版、2017年)
- 善峯寺HP「諸堂案内(全体MAP)」(最終閲覧日:2024年8月20日)
- 富士山本宮浅間大社HP「御由緒」(最終閲覧日:2024年8月20日)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
民俗学が好きなライターです。松尾芭蕉の俳句「よく見れば薺(なずな)花咲く垣根かな」から名前を取りました。民話や伝説、神話を特に好みます。先達の研究者の方々へ、心から敬意を表します。




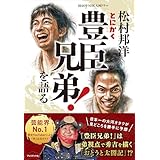
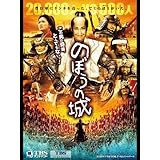
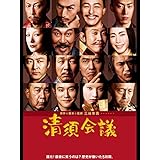

コメント欄