「米余り」に翻弄された農家たち…戦後日本の食糧難を救った“モデル農村”の知られざる物語
- 2025/09/03

八郎潟が干拓され、日本の農業のモデル地域としてできた大潟村。干拓に至った背景とその後、社会の変化に翻弄された干拓地について探ってみます。
八郎潟干拓地誕生までの道のり
秋田県の男鹿半島の近くにある八郎潟干拓地は、秋田市から北に約20キロメートル離れた場所に位置します。日本地図をよく見ると、男鹿半島の近くに楕円形にくり抜かれたような土地が見えるでしょう。八郎潟は干拓される前、東西12キロ、南北27キロ、周囲82キロ、総面積22.173平方キロメートルという広大な湖でした。その面積は琵琶湖に次ぐ日本第二の大きさを誇っていました。

国による開拓案が立てられたのは昭和16年(1941)、いわゆる戦時下でした。昭和13年(1938)の国家総動員法の一環として、政府は食糧自給強化を全国に実施し、農地開発営団が設立され、開発施行予定地に八郎潟が適地とされたのです。しかし、戦況が悪化したことで結局この案は実現しませんでした。
昭和20年(1945)の敗戦後、大混乱に陥った日本は早急に食糧自給対策を講じる必要に迫られました。政府は全国で干拓国営事業を発足させ、千葉の印旛沼、九州の有明海、岡山の児島湾など、全国6ヵ所に国営干拓事務所を設置して対策を急ぎました。中でも最も規模が大きかったのが八郎潟です。もちろん、地元の漁師や住民からの反対が多かったのは言うまででもありません。
昭和26年(1951)に対日講和条約が結ばれ、国は輸入食料を減らすために食料増産5ヵ年計画を策定しました。農林省は八郎潟干拓調査事務所を設置し、オランダから技術者を招きました。干拓専門家・ヤンセン教授が来日し、八郎潟が干拓の最適地であるとする案を提出。海抜の浅さが最大の条件でした。漁業者との補償問題の話し合いを経て、昭和32年(1957)に八郎潟干拓事業が着工されました。
干拓された土地は約157平方キロメートルにも及びます。これは、東京都の山手線内側の面積(約63平方キロメートル)をはるかに上回る広さです。干拓地内にまっすぐに伸びる長い道路は、北海道のような牧歌的な景色を連想させます。
着工から7年後の昭和39年(1964)10月1日、「大潟村」という名称で、いよいよモデル農村が発足しました。
「モデル農村」大潟村の挑戦と苦難
大潟村の農家には、入植時に1世帯あたり15ヘクタールの農地が配分されることが決まりました。これは当時の全国平均の約10倍にあたります。大規模農地を活用し、近代的な稲作地帯を目指したのです。これだけ壮大なプロジェクトですから、全国の農家からの関心は非常に高く、広大な農地を使い、大型機械による近代的な農業モデルの一員になりたいという希望は多かったようです。大潟村への入植にあたって選定が実施され、5回の入植試験の平均倍率は4.2倍だったそうです。
選定は書類審査、筆記試験、面接試験を通じて慎重に行われました。人生を一転する決意があるかどうかも、確かめられたのかもしれませんね。合格基準は以下の通りです。
- 八郎潟中央干拓地に新しい農村を建設する意義を十分に理解している人。
- 八郎潟新農村建設事業団の計画に沿って、自立経営および生産性と所得水準の高い協業経営を行う意欲がある人。
- 入植に先だって行われる1年間の訓練により、新しい農業経営に必要な知識と技術を身につけることができる人。
- 入植する時の年齢が20歳以上40歳未満であること。(ただし、体が丈夫で営農経験が十分にある人は45歳未満でもよい)
- 営農をする十分な体力があること。
- 入植するときに、営農する労働力として1.8人以上を有していること。
- 入植後に営農を行うにあたり、水の利用や作付け協定、農業機械の共同使用などにおいて協調できること。
- 資金として、1年間の入植訓練期間の生活及び入植初年目の秋までの営農と生活に必要な分を用意できること。
これらの細かな条件からも、米作りへの大きな夢を持った人々が選ばれたことがわかります。第一次入植者56人が耕作を始めたのは昭和43年(1968)のことでした。
しかし、日本の戦後復興は加速し、食糧難の時代は終わりを告げ、逆に米が余る「米余り」という事態に一転してしまいます。これを受け、国の政策は米の生産調整へと転換されました。いわゆる「減反政策」が昭和45年(1970)に導入され、米農家は苦境に立たされることになったのです。
村の発足からわずか6年後のことです。大潟村の生産者たちも国の政策転換への対応を余儀なくされました。いい米をたくさん作って日本を豊かにしようという希望を抱いて入植した人々は、どれほどの理不尽さを感じたことでしょう。
変化の時代を生きる大潟村
干拓から68年が経った2025年現在、大潟村は外国米の輸入増加、後継者問題、気候変動など、かつてのモデル農村が直面する多くの課題を抱えています。それでも、大潟村の生産者の意識の高さは変わっていません。高品質な米の生産はもちろん、メロンやカボチャ、豆類など、多岐にわたる作物が栽培され、全国から注文が寄せられているようです。
戦後の食糧難を克服するために開発された八郎潟干拓地(大潟村)は、村が軌道に乗り始めた頃に国の減反政策という窮地に立たされました。しかし、新しい農業を目指してきた人々は、大潟村ならではの独自の米作りや管理、物流を検討しながら今もおいしい米を作り続けています。
農業という産業が、社会の変化に強く影響される一つの例として、八郎潟干拓地の歴史は多くのことを教えてくれます。
【参考文献】
- 大潟村干拓博物館 公式HP
- 小林智仁・ 藤田龍之・ 知野泰明『土木史研究 第20号八郎潟干拓事業の成立過程の変遷について』(土木学会、2000年)
- 宮田正馗『ゼロから自治体を創ったらどうなるか?元村長宮田正馗が語る大潟村のあゆみ』(公職研、2023年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。




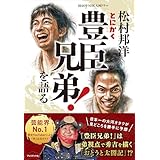
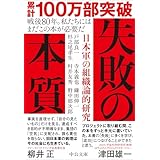


コメント欄