なぜ武装化?武士を凌駕した「僧兵」の隆盛と滅亡の歴史
- 2025/10/24
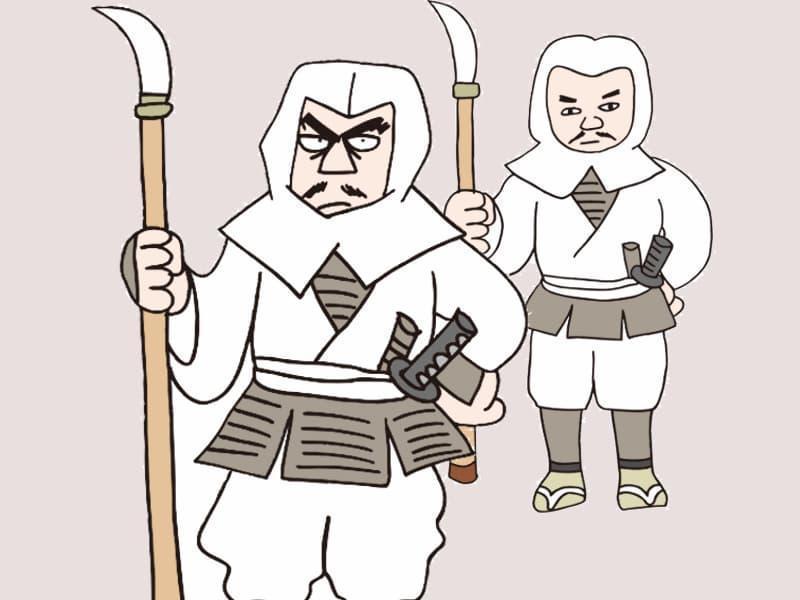
「僧兵」、それは文字通り武装した僧侶を指す言葉です。初めてその存在を知った時、「殺生を禁じるはずの僧侶が武器を取る?」と驚いた方もいるのではないでしょうか。
仏教の教えに反して武器を持ち、戦いの場に身を投じた彼ら。日々修行に励む彼らが、なぜ武装し、何を守ろうとしたのか。本稿では、武士にも引けを取らない強さを誇った「僧兵」たちの実像に迫ります。
仏教の教えに反して武器を持ち、戦いの場に身を投じた彼ら。日々修行に励む彼らが、なぜ武装し、何を守ろうとしたのか。本稿では、武士にも引けを取らない強さを誇った「僧兵」たちの実像に迫ります。
僧兵の装束とは?
「僧兵」の一般的な姿を見ていきましょう。彼らの多くは、頭に裹頭(かとう:頭を包む布)を被り、僧衣の下に腹巻(はらまき)といった軽装の鎧を着用していたとされています。足には高下駄を履き、武士と同様に薙刀や刀などの武器を携行。戦国時代には、一部の寺院では鉄砲を駆使する僧兵も現れています。ちなみに「僧兵」という呼称は江戸時代頃から定着したもので、それ以前は、寺院によって異なるものの、主に「衆徒(しゅと)」、「悪僧(あくそう:「悪」は「強い意)」、「行人(ぎょうにん)」、「山法師(やまほうし)」、「寺法師(てらほうし)」、「奈良法師(ならほうし)」などと呼ばれていました。
また、神社にも寺院の僧兵と同様、武装して奉仕する人々がおり、彼らは「神人(じにん)」と呼ばれています。
自衛の必要性から誕生した「僧兵」
そもそも、なぜ「僧兵」という存在が生まれたのでしょうか。その要因をいくつか探ります。寺院の財宝の防衛と警備
8世紀頃、国家の後ろ盾を得て仏教が発展するにつれ、寺院の勢力は拡大しました。それに伴い、寺院は仏像や経典、高価な品々などの仏具や財宝を多く所有するようになります。例えば、奈良の東大寺正倉院には、国内外の宝物が数多く保管されていました。まさに「宝の山」である正倉院ですが、現代のような高度な警備技術がない時代、常に盗難の危険と隣り合わせでした。 そこで必要とされたのが、寺宝を守り警備する人々。これこそが「僧兵」のルーツの一つだと考えられています。
寺院が所有する土地(荘園)の維持・拡大
平安時代から鎌倉時代にかけて、各地で荘園が開墾され、中には寺院に寄進されるものも多くありました。その規模は時とともに拡大し、記録によれば奈良の興福寺は2万石以上、比叡山の延暦寺は5万石以上の石高を領有していた時期もあったとされます。これは封建領主に匹敵するほどの大地主でした。広大な領地を狙う者は絶えず、朝廷から派遣された国司による年貢横領や、他勢力との土地の奪い合いなどが頻発します。これらの防衛や時には武力による弾圧のため、僧や地元の農民たちを武装させていたのです。
他宗派の排斥と武力衝突
宗派が違えば、意見や思想の違いから対立が生じるのは、日本に限らず世界的な現象です。特に鎌倉時代は、浄土宗・浄土真宗、法華宗、曹洞宗、臨済宗など、新仏教が次々と台頭した時代であり、旧仏教勢力との間で激しい対立が頻繁に起きました。例として戦国時代には、延暦寺が近江の大名・六角氏を誘い、日蓮宗との大規模な武力衝突を引き起こしています。これは天文法華の乱(てんぶんほっけのらん)と呼ばれ、京にあった日蓮宗の寺院21箇所を焼き討ちし、壊滅させました。寺院同士の争いが、こうした大規模な“宗教戦争”ともいえるような事態に発展することもあったのです。
寺院内部の揉め事の解決
古代から中世にかけて、寺社勢力の拡大は目覚ましく、それに伴い寺院に従事する人数も増加しました。その結果、寺院内部での内紛も多く発生し、話し合いだけでは解決しない問題も生じます。それらの紛争を収めるため、やむを得ず武力行使を行うこともありました。以上、こうした要因から、自衛や他組織への対抗手段として、寺院にとって武装することは必要不可欠となっていったのです。
権力者への強硬手段「強訴」
僧兵たちは、自らの要求を通すため、朝廷など時の権力者に対し「強訴(ごうそ)」という手段を用いました。この強訴とは具体的にどのようなものだったのでしょうか。強訴とは、簡単に言えば、朝廷や幕府などの権力者へ武装して直訴することです。 その際、朝廷や幕府の兵と武力衝突が起きることもあり、僧兵はそれに対抗しうる武力を身につけていったといいます。
要求の内容は、横領を働いた国司の解任や流罪、寺院トップの人事への介入停止など多岐にわたります。 そして、僧兵の強訴で最も特徴的なのが、武装するだけでなく、神輿や寺社の御神木を掲げて臨んだことです。特に信仰心の厚い朝廷は、神輿や御神木を前にすると、要求を無碍にすることもできず、聞き入れざるを得なかったケースもあったと言われています。
また、神輿を担いでの強訴は京都近辺に限りません。伯耆国(現在の鳥取県)にある大山寺からも神輿を担ぎ、遠路京の都に押し寄せたという記録も残っています。
権力者を震撼させた!?最強僧兵集団3選
白河法皇が、自身の思い通りにならないものとして挙げた三つが「賀茂川の水」、「双六の賽」、そして「山法師(僧兵)」です。院政を行い、権勢をほしいままにした法皇でさえ、僧兵という集団には手を焼いていたのです。ここでは、時の権力者たちをも悩ませた僧兵集団を3つ紹介します。
【興福寺】
藤原氏の氏寺として、奈良で強大な勢力を誇った寺院です。ここの僧兵は「奈良法師」と呼ばれ、その力は大和国一国を支配下に置くほどでした。戦国時代には織田信長と同盟を結び、乱世の中で勢力を維持したとされます。また、槍術の流派「宝蔵院流槍術」は、興福寺の僧侶・胤栄(いんえい)が開祖となって生まれた流派です。
【延暦寺】
比叡山を本拠地とし、興福寺と並ぶ勢力を誇った寺院です。ここの僧兵は「山法師」と呼ばれ、数千人規模の僧兵団を擁していました。そう、白河法皇が手に負えないと嘆いた「山法師」こそ、この延暦寺の僧兵のことでした。 平安時代から隆盛を極めた延暦寺ですが、戦国時代に織田信長による比叡山焼き討ちに遭い、以降、軍事力は衰退してしまいます。
【根来寺】
真言宗から独立した宗派「新義真言宗」の寺院です。ここの僧兵は「根来衆」と呼ばれ、その数は約1万人に上り、紀州屈指の大勢力であったと言われます。 根来衆の驚異は数だけでなく、当時最先端の武器であった鉄砲を巧みに扱い、強大な鉄砲隊を組織していた点にあります。しかし、戦国時代に豊臣秀吉の紀州征伐を受け、その強大な軍事力を失うこととなりました。
おわりに
僧兵たちは、動乱の時代を生き抜き、寺院の権益を守るため、武力を持って戦いました。朝廷や幕府に対し強訴という手段で要求を押し通し、その強大な武力は武士さえも畏怖するほどでした。しかし、戦国時代には天下を狙う戦国大名たちの攻撃に遭い、その勢力は衰退の一途をたどります。それでも、武士にも引けを取らない彼らの強さは、後世まで語り継がれていくこととなったのです。【参考文献】
- 衣川仁『僧兵=祈りと暴力の力』(講談社、2010年)
- 渡辺守順『僧兵盛衰記』(吉川弘文館、2017年)
- 成瀬龍夫『比叡山の僧兵たち』(サンライズ出版 、2018年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
大学で日本中世史を専攻。
現在本業のかたわら、日本史メインでWeb記事やYouTubeシナリオを執筆中。
得意分野は古代~近世の日本文化史・美術史。
古文書解読検定準2級取得。








コメント欄