大河ドラマ「べらぼう」 俳優の城桧吏さんが演じる11代将軍・徳川家斉は暗君だったのか?
- 2025/09/01

大河ドラマ「べらぼう」第33回は「打壊演太女功徳」。「べらぼう」において11代将軍・徳川家斉(1773〜1841)を演じるのは俳優の城桧吏さんです。
『続徳川実紀』には家斉が誕生した時に瑞兆(めでたい前兆)があったと記されています。ちなみに同書は家斉を「英主」(優れた君主)と記しているのですが、それではどのような瑞兆があったのでしょうか。
家斉の父親は一橋治済であります。一橋邸で家斉は誕生するのですが、誕生の直前まで、産屋は屏風などを巡らせていたこともあり、少し暗かったとのこと。ところが誕生の段になると突然、辺りを「火光」が照らしたと言います。当然ながら人々は大いに驚きました。それだけではなく、その時には屋上に鶴が舞い、庭に降り立ったのでした。鶴が庭に降り立つということはこれまでなかったと言います。
また同書には家斉の少年時代の逸話も記述されています。家斉がまだ12・3歳の時のこと。邸の庭に鳥がやって来て、飼っていた鳩を追い回します。近習の者らはその鳥を捕え打ち殺そうとしました。家斉はそれを見て次のように言ったとされます。
「飼鳥を捉えようとした事は憎むべきことではある。しかしそれは子を養おうとしてのことであろう。子を思う想いは皆同じであろう」
と。家斉はこう言って近習が鳥を打ち殺そうとしたのを制したのでした。まだ15歳にもなっていない年齢であるにもかかわらず「仁心」(深い愛情をもって思いやる気持)が鳥獣にまで及んでいることは有り難いことであると同書は記載しています。

また家斉は、風俗が奢侈になり人々の家計が窮迫し、武備も疎かになることを憂え倹約を命じたとあります。衣食・冠婚の式、調度類などを簡素にし、下々の手本になるようにと命じたのでした。
- 「(家斉は)かならずしも凡庸な君主ではなかったが、幕政の退廃に有効に対処できず、大御所政治の象徴として大奥に爛熟の生活を送った」
- 「将軍職は象徴化し、側近政治の中で政治に無頓着になり、生活は華奢に走っていた」
と評される家斉ですが『続徳川実紀』にはそれとは逆の家斉の姿も描かれているのです。
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



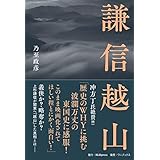




コメント欄