戦国大名も神頼み?…出陣日、先鋒、戦術まで「くじ引き」で決めていた大名たち
- 2025/10/21

人生は決断の連続と言われています。直感で決めてしまう人もいれば、なかなか決められず迷ってしまう人もいるでしょう。どうしても決められない時は、いっそ神様に決めてもらおう……ということで、昔からくじ引きが用いられてきました。
今回は戦国時代、くじ引きで様々なことを決めていた武将たちのエピソードを紹介してまいります。
今回は戦国時代、くじ引きで様々なことを決めていた武将たちのエピソードを紹介してまいります。
出陣の日取りをくじ引きで決めていた大友家
豊後国(大分県)の大友義鎮(宗麟)に仕えていた立花道雪(鑑連)は、大友家の重臣たちに訓戒状を送りました。その中には、出陣の日取りをくじ引きで決めていたという事例が記されています。時は天正7年(1579)9月、重臣の田原親貫(たばる ちかつら)が謀叛を起こしました。これは親貫と同族の田原親賢(ちかかた。紹忍)が主君と共謀し、親貫の家督を乗っ取ろうとしていたことが動機とされています。
早急に鎮圧すべきですが、親貫の勢力は強大であり、軽々に攻め込めば痛手を負いかねません。かと言って手をこまねいている訳にも行かず、家中で議論は紛糾。攻める時機を計りかねていました。
いよいよ議論も煮詰まって来たため、もはや神慮にすがるよりないと筥崎宮(はこざきぐう。福岡県福岡市)にゆかりの深い易者を招きます。そしてくじ引きの結果は「すぐに攻めるのが吉事である」という結果が出ました。神のお告げであれば疑いなしとさっそく攻め込み、大勝を得られたということです。
立花道雪はこの故事にならい、今度もくじ引きによる神慮を仰いで勝機を逃さぬように、と訓戒したのでした。
出陣の日取りをくじ引きで決めたとのことですが、詳細な方法については記録されていません。恐らく神慮に関することだから非公開だったのでしょうが、くじに何が書かれていたのかが気になります。
1、具体的な日付が現実的な範囲(例:3月1日~3月5日)で書いてあった?
2、すぐ攻めろ、向こうの出方を見ろ、守りを固めろ、など抽象的だった?
3、あらかじめ決めていた日だけを入れ、神慮という箔をつける儀式となっていた?
さまざまなケースが考えられるでしょうから、今後の究明がまたれます。
先鋒や殿軍をくじ引きで決めた例
いざ出陣!した後も、くじ引きで神慮をうかがう例がありました。合戦に臨んで手柄を立てる機会が多い先鋒を決めたり、退却する際に敵の追撃を防いで仲間を逃がす殿軍(しんがり)を決めたりする時にも、くじ引きが活用されたのです。例えば天正5年(1577)の暮れ、羽柴秀吉が播磨国の上月城(こうづき。兵庫県佐用町)を攻めた際、先鋒を決めるためにくじ引きを行いました。この時は特段神仏に祈念していた訳ではなく、秀吉がくじを作らせ、それを先鋒を希望する武将たちに引かせたようです。
くじに書かれた内容はシンプルなもので、印の入ったくじを引いた者が先鋒を務める、程度のものでした。神仏に祈念していなくても、先鋒くじを誰が引き当てるかは神仏の計らいがあったはずですから、これもまた神慮の一つと言えるでしょう。

他方の大友家では先鋒を決めるくじ引きを行う際は、大友家の氏神である柞原八幡宮(ゆすはらはちまんぐう)を陣中に勧請(かんじょう。神様をお招きすること)して、その神前でくじを引くという崇敬ぶりでした。
これは先鋒を決める時のくじ引きですが、大慌てで退却する際に殿軍をくじ引きで決める余裕はあったのでしょうか。恐らくは陣払い(講和や計画的撤退などで陣地を引き払う、比較的ゆとりのある退却)の時などで、誰が最後の後始末をしていくかをくじ引きで取り決めたものと考えられます。
戦術や進軍ルートをくじ引きで決めた例
御当家(ごとうけ)御弓箭(おんゆみや)は、御籤(おみくじ)肝要候間(かんようにそうろうかん)、霧島(きりしま)へ御籤可然(しかるべく)ニ相定候(あいさだめそうろう)
【意訳】島津家における軍事行動は、くじ引きで神慮を仰ぐことが重んじられたため、霧島神宮(鹿児島県霧島市)のくじ引きを用意するように定められた。
上述のように、薩摩国(鹿児島県西部)の島津氏では、戦術や進軍ルートなど、何かにつけてくじ引きで決定されていたようです。もちろん例外はあり、くじ引きを行うまでもなく早急に出陣したり、出陣中で判断に迷ったためにくじ引きを行ったりした例もありました。
時は天正11年(1583)10月、島津勢は肥後国へ進攻し、ある城を攻めあぐねた折にくじ引きを行っています。この時は三枚のくじが用意され、一枚目には「一」二枚目には「ニ」そして三枚目は白紙でした。それぞれの意味は記録されていませんが、恐らくは包囲継続・力攻め・撤退などの意味が持たされていたのでしょう。
また天正14年(1586)9月には同じ三枚のくじが用いられ、「一」は予定通り出陣で「二」は出陣取りやめ、そして白紙は進軍ルートの再考という意味が持たされていたと言います。
島津と言えば、泣く子も黙る「鬼島津」「薩摩隼人」のイメージ。神慮をうかがうどころか、神も仏もなぎ倒して進みそうな印象でしたが、意外ですね。関ヶ原における島津の退き口(1600)など、絶体絶命の苦境にあっても挫けることなく斬り抜ける強さの根底は、神仏に対する篤い信仰心が支えていたのでしょう。

不本意な結果で引き直しはアリ?ナシ?
くじ引きは神慮をうかがうものですから、当然ながら人間の意にそう結果が出るとは限りません。そんな時、くじ引きの引き直しはアリだったのでしょうか?基本的にくじ引きは対象者の決定に神慮というお墨付きを得るための手段でした。そのため、あまりに権威を損ねるような結果となった場合、引き直しや小細工も行われたようです。
島津家では、秀吉による九州征伐を控えた天正14年(1586)、どう立ち向かうかで家中の議論が紛糾しました。一族や重臣たちの利害や思惑が交錯し、ただ「徹底抗戦すべし」「すみやかに和睦すべし」だけでは済まなかったのでしょう。
くじ引きも行われたものの、あっちを立てればこっちが立たずで引き直しを余儀なくされ、これでは神慮もへったくれもありません。こうしたことから、次第にくじ引きに対する態度が冷淡になっていったということです。
秀吉の襲来という驚愕の事態に際して、伝統的な神慮が軽んじられてしまう様子は残念でなりませんね。こればかりは仕方がないとは言え、数百年の歳月を越えて胸が痛くなってしまいます。
終わりに
今回は戦国時代の武将たちが、ここ一番の決断にくじ引きを用いていたエピソードを紹介してきました。現代人の感覚からすると、合戦という人の生死が関わってくることをくじ引きで決めてしまうのは、少し無責任に感じられるかも知れません。しかし「人事尽くして天命を待つ」とも言うように、初めからくじ引き(丸投げ)ありきではなく、人事を尽くした上で最後に天意を問うていたのでしょう。
これからも、戦国時代の興味深い人物やエピソードについて、紹介してまいります。
【参考文献】
- 川口素生『戦国時代なるほど事典 合戦・武具・城の真実から将軍・庶民の生活事情まで』(PHP研究所、2001年)
- 盛本昌広『増補新版 戦国合戦の舞台裏 兵士たちの出陣から退陣まで』(洋泉社、2016年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
鎌倉の最果てに棲む、歴史好きのフリーライター。時代の片隅に息づく人々の営みに強く興味があります。
得意ジャンル:日本史・不動産・民俗学・自動車など。
執筆依頼はお気軽にどうぞ!






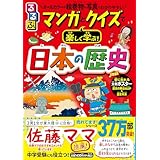

コメント欄