豊臣と徳川の狭間で苦悩した「片桐且元」 方広寺鐘銘問題とその後の去就の真相とは?
- 2023/11/22

関ヶ原合戦(1600)の後、豊臣秀頼の家老として豊臣氏と徳川氏の間を取り持ち、大坂の陣(1614~15)では家康方に付いた片桐且元(かたぎり かつもと)。「方広寺鐘銘問題」で家康に翻弄された人物としてのイメージが強い且元ですが、賤ヶ岳合戦(1583)では「賤ヶ岳の七本槍」の1人に数えられる活躍をするなど、彼は若い頃から秀吉に仕え、秀吉の合戦に数多く参戦しました。
秀吉古来の家臣であった彼がなぜ、戦国最後の合戦・大坂の陣では徳川方に味方したのか?今回はその真相に迫りたいと思います。
秀吉古来の家臣であった彼がなぜ、戦国最後の合戦・大坂の陣では徳川方に味方したのか?今回はその真相に迫りたいと思います。
なお、近年は研究の進展によって「豊臣氏」を「羽柴氏」とする研究があります。これは秀吉が豊臣姓となった後も、名字は羽柴であったことによるものですが、本記事では乱雑を避けるため「豊臣氏」と表記します。
且元の生い立ち
片桐且元は弘治2年(1556)に生まれました。片桐氏は元々は浅井長政(淀殿の父)の家臣であり、且元の父・直貞は天正元年(1573)の浅井氏滅亡まで長政に仕えました。のちに豊臣秀頼の母となる淀殿とは、幼少期より面識があったものとみられています。当時の史料の残存状況の兼ね合いから、淀殿と且元との関係は関ヶ原合戦後から大坂の陣に至るまでの期間に注目されがちです。しかし実際には、両者の関係はもっと早い段階から構築されていたのでしょう。
浅井氏滅亡後、その旧領は織田信長の家臣であった秀吉が領するようになります。この頃から且元は秀吉に仕えるようになったと考えられていますが、確実な史料から且元が秀吉の家臣として確認できるのは、天正10年(1582)本能寺の変後のことになります。
当時の且元は秀吉の近習衆・馬廻衆として仕えていたようで、前述のとおり、天正11年(1583)には、賤ヶ岳合戦で活躍し、「賤ヶ岳の七本槍」の1人に数えられています。ちなみに「賤ヶ岳の七本槍」とは、このときの合戦で特に活躍した7人の若き武将、福島正則・加藤清正・片桐且元・脇坂安治・加藤嘉明・平野長泰・糟屋武則を指します。
豊臣政権下での役割
その後、秀吉の九州征伐(1586~87)では物資の供給にあたり、小田原征伐(1590)にも出陣しました。また、丹波国・紀伊国高野山領・出羽国などの検地を担当していることがわかっています。文禄元年(1592)からの朝鮮出兵では、渡海して日本軍の補給路の確保にあたりました。慶長3年(1598)8月には秀吉が伏見城で亡くなり、翌年正月に秀頼が正式に豊臣家の家督を継承し、大坂城を居城とします。その際に大坂城の勤番体制が定められましたが、秀頼に直接言上できるものの中には、且元も含まれていました。
その他の面々としては、豊臣五大老・五奉行の10人に加え、徳川秀忠(家康の嫡男)、前田利長(利家の嫡男)、石川光吉(大谷吉継の妹婿)、石田正澄(三成の兄)、石川一宗(三成とは相婿)など、錚々たるメンバーだったようです。
豊臣五大老・五奉行とその後継者(秀忠・利長)とは別に、片桐且元をはじめ、石川光吉・石田正澄・石川一宗らが秀頼付の重臣として存在していました。ここから、且元は秀吉没後の豊臣政権において、秀頼の側近として重要な位置にいたことがうかがえます。
且元は秀吉からの信頼を厚く得ていただけでなく、秀頼の生母である淀殿との近江浅井氏以来の関係も考慮されたものと思われます。
秀吉死後の且元の地位
慶長5年(1600)、関ヶ原合戦の結果によって、五大老の家康が豊臣政権の運営を掌握する政治体制となりました。諸大名の統制・朝廷との関係・外国との交渉などは家康が中心となって進められるようになり、家康や秀忠が征夷大将軍に就任することによって、やがて全国政権の主宰者(天下人)の地位は豊臣氏から徳川氏(江戸幕府)に徐々に移行していきます。豊臣氏は主に摂津・河内・和泉3ヶ国内を中心に65万石の大名に転落したとされていますが、家康が将軍になったのと同時期、秀頼が関白に任官する噂が流れており、豊臣氏が天下人の地位を失ったわけではないと捉えていた者も存在していたようです。
確かに秀頼は幼少であったため、徳川氏が代行して天下人の務めを果たしていたと考える人がいてもおかしくはないでしょう。また、家康は秀吉の遺言に従って孫娘の千姫(秀忠の娘)を秀頼に嫁がせました。家康が将軍に就任した時点では、豊臣氏に対して家康の一定の配慮があったように思えます。
そうした政治情勢の中、且元はどのような立場にいたのでしょうか? 当時の豊臣氏は、幼少の秀頼に代わって母親である淀殿が家長を代行していました。その中でも家臣筆頭の地位にいたのが且元であったといわれます。
関ヶ原合戦後の11月、領地を没収された西軍の立花宗茂は、以下のように述べたことがわかっています。
「豊臣氏から家康に申し入れできるのが、小出秀政・寺沢正成(のち広高)・且元の3人であった」
小出秀政は秀吉の母方の親戚とされています。すでに60歳を超え、当時としては高齢でした。そのため、関ヶ原合戦の4年後に亡くなっています。寺沢正成は秀吉の奉行衆の1人として活動していました。しかし、関ヶ原合戦の翌年、家康から肥前国天草12万石を与えられ、領地に赴くことになり、秀頼付の家臣からは離脱しました。
関ヶ原合戦によって「五大老・五奉行」体制は崩壊、さらに小出秀政が亡くなり、寺沢正成も豊臣氏から離れたことで、且元の地位は自動的に引き上げられました。このときの且元は、豊臣家家臣の筆頭として、徳川氏と交渉ができる数少ない重臣であったと考えられています。
また、且元は家老として豊臣家の蔵米や金銀などを管理する権限を有しており、豊臣氏の家政を取り仕切る立場にあったとみられています。つまりは外交・財政の両面において、豊臣氏を取り仕切る程の立場にあったのです。
さらに且元は家康から摂津・河内・和泉3ヶ国の「国奉行」も任されています。国奉行とは、江戸時代初期に畿内を中心に11ヶ国置かれたとされ、その国全体の農政を管轄しました。その管轄範囲は徳川氏直轄領と大名領の区別なく、その国全体に及んでいました。摂津・河内・和泉は、主に豊臣氏の領地でしたが、一部徳川氏の直轄領や給人領も混在していました。
且元は豊臣だけでなく、徳川からも信頼されていたことがわかります。
方広寺鐘銘問題と且元の大坂退去
慶長年間、豊臣氏は京都や畿内を中心に寺社の復興を積極的に実施していました。且元も家老として豊臣氏の寺社復興事業に大きく関わっていたとみられます。これらは家康のすすめ、承認を得て実施されていました。余談ですが、豊臣氏の寺社復興事業に関するものとして、豊臣氏に金銀を大量に消費させ、豊臣氏の財政を圧迫させようとした家康の策略があった、とする見解が以前にありました。しかし同時期に徳川氏も寺社の復興事業を実施していることから、現在では家康の策略は無かったものと考えられています。
さて、豊臣氏の寺社復興事業の中には、京都方広寺大仏の再建がありましたが、この大仏再建をきっかけに起きたのが「方広寺鐘銘問題」です。 豊臣家による方広寺大仏の再建に際し、鋳造した鐘の銘文の中にある「国家安康」と「君臣豊楽」の文字について、家康は問題視したのです。
- 「国家安康」→ 徳川家康の名前が分割されていて、家康の身首両断を意図している
- 「君臣豊楽」→ 豊臣家の繁栄を祈願している


慶長19年(1614)、この問題の弁明のため駿府に遣わされたのが且元と大蔵卿局(淀殿の乳母・大野治長の母)でした。そこで家康から提示された要求が次の3点になります。
- 1、秀頼は駿府と江戸に参勤すること
- 2、淀殿を江戸住まいとすること(事実上の人質)
- 3、秀頼が大坂城を退去して他国に移ること
従来の説では家康の謀略として、大蔵卿局は家康と面会しますが、且元は家康とは面会ができずに、本多正純(家康側近)から上記の3つの条件を提示されたことになっていました。しかし、近年の研究によると、大蔵卿局と且元は共に3つの条件を提示されたと考えられています。
9月18日、大坂城に戻った且元は家康からの3つの条件を秀頼・淀殿に伝達しました。これに対して秀頼・淀殿は不快感を示したとされています。且元としては豊臣氏が生き残るには、正式に徳川氏の臣下になるしかないと考えていたようですが、その姿勢に秀頼・淀殿は反対でした。
その後、織田有楽の嫡男である織田頼長や大野治長といった秀頼の重臣たちが且元の殺害を企て、軍勢を集める事態となります。当時、織田有楽・大野治長は且元に続く秀頼の重臣として存在していました。
この事態を知った且元は、出仕を取りやめて自身の屋敷に引きこもり、備えとして軍勢を集めました。このような一触即発の事態のなか、淀殿は且元に隠遁するよう命令を出します。
且元の隠遁に際して、淀殿は最初穏便に済ませようとしましたが、結果として大野治長を支持する姿勢を取りました。ただし、命まで取らなかったところに、且元への配慮がみられます。
おわりに
隠遁命令が決定打となり、且元は大坂を退去する決意を固めました。10月1日に大坂を退去しましたが、且元はその直前まで豊臣家の収支決算を行なっていたことがわかっています。後任の者が困らないようする配慮とみられ、ぎりぎりまで豊臣氏に忠義したのでしょう。ここに且元の性格がよく出ていると思います。
しかし、且元にも家族がおり、また1大名である彼に従う家臣団もいました。且元は片桐家の当主として、家族や家臣を守る責務がありました。且元は事の顛末を駿府の家康に伝えます。家康は且元の無事を喜び、徳川氏に仕えることを認めています。
その直後の大坂の陣(1614~15)において、且元は徳川方として参陣しました。大坂の陣後、片桐氏は大名として存続しましたが、且元は豊臣氏滅亡からわずか20日後に病死しました。
【主な参考文献】
- 黒田基樹『羽柴家崩壊 茶々と片桐且元の懊悩』(平凡社、2017年)
- 片山正彦「京都所司代と国奉行」(渡邊大門編『江戸幕府の誕生 関ケ原合戦後の国家戦略』文学通信、2022年)
- 小川雄「大坂の陣への道程」(黒田基樹編『戦国大名の新研究3 徳川家康とその時代』(戎光祥出版、2023年)
この記事を書いた人
大学・大学院で日本史を専攻。専門は日本中世史。主に政治史・公武関係について研究。現在は本業の傍らで歴史ライターとして活動中。
※旧ペンネームは yujirekishima
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。



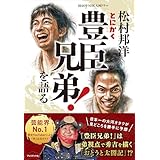
コメント欄