【解説:信長の戦い】越前一向一揆(1575、福井県越前市ほか) 一揆衆に支配された越前 信長による衝撃の殲滅劇とは?
- 2023/08/31

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
織田信長と一向一揆との戦いといえば、門徒を2万人も虐殺したことで有名な長島一向一揆が有名です。この戦いは信長の残虐さを印象付けていますが、その翌年にも同様に一向一揆を殲滅する戦いがありました。それが越前一向一揆です。
朝倉氏が滅亡した後の越前は
越前といえば、もとは朝倉氏が支配する地域でした。しかし天正元年(1573)8月に当主の朝倉義景が信長によって滅ぼされると、越前は信長が治める土地になりました。戦いのきっかけは旧朝倉家
発端は、信長が桂田長俊(前波吉継)を越前国守護代に任命したことにありました。旧朝倉氏家臣の中で重臣であったわけでもない長俊がなぜ……。他の旧朝倉氏家臣らはこれを不満に思ったのです。そもそも、信長の支配下に入ったのであれば織田家譜代の家臣を守護代に据えれば旧朝倉氏家臣らも従ったでしょうが、なぜ信長は長俊を据えたのか。ひとつは、越前は蓮如が訪れて以来隣国加賀と並ぶ浄土真宗の国であり、一向一揆との付き合い方は朝倉氏のほうがよく知っていることが挙げられるでしょう。よく知りもしない織田家臣が治めるよりも、うまくいくかもしれないと考えたのかもしれません。
もうひとつは、長俊が早い時期に信長に降っていたことが挙げられます。ほかに信長に降った旧朝倉氏家臣には、朝倉景鏡(かげあきら)・朝倉景健(かげたけ)・朝倉景盛・朝倉景泰・溝江長逸(ながゆき)・魚住景固(かげかた)らがいます。
中でも景鏡は朝倉一門で、義景家臣の筆頭でした。しかし景鏡はギリギリのところで主君・義景を裏切り自害させた人物で、義景の首級やその母・妻子らを信長に差し出した張本人でもあります。それを考えると信長としては、守護代を任せるに足る人物である、といえるほど信用できないと判断したのではないでしょうか。
その判断により、特に不満を持っていた国人の富田長繁は天正2年(1574)1月、一揆を味方につけて長俊を殺してしまったのです。では次は長繁が一揆を率いたまま支配したかというとそういうわけでもなく、長繁自身は孤立していきました。
長繁によって立ち上がった一揆は長俊を殺した勢いのまま、信長が北庄に置いていた奉行三人衆(木下祐久・明智光秀・津田元嘉)を追放してしまいます。
あわせて読みたい
本願寺門徒「国中一揆」の蜂起
こうしてわずか半年で信長による越前支配は終わってしまいました。遠く大坂の本願寺顕如は、この越前の混乱を見て、越前を加賀と同じように一揆持ちの国にしようと考えます。顕如は加賀から七里頼周(しちりらいしゅう)を越前に派遣します。すると一揆勢は長繁から離れて頼周のもとに集い、長繁を破って討死させました。朝倉景鏡もまた平泉寺を味方につけて一揆勢と戦いましたが、同様に敗れて討死しています。
『越州軍記』によれば、本願寺は下間頼照(しもつまらいしょう)を越後国守護に、杉浦玄任(法橋)を大野郡司に、下間和泉守を足羽の郡司に任命し、頼周には上郡・府中辺を支配させたようです。こうして越前は一揆が支配する国になったのです。
信長は共通の敵をもつ味方を集める
一方、そのころの信長はというと、越前の動きは当然注視していたものと思われますが、動くに動けない事情がありました。実際に信長が越前に向けて動いたのは、武田勝頼との長篠の戦いや、長島一向一揆など、各地の戦いで勝利した後のことでした。しかし、その間もただじっと手をこまねいていたわけではありません。天正2年(1574)の間に、本願寺派と敵対する派閥に声をかけ、味方を集めていたのです。
親鸞の高弟・真仏を開祖とする真宗高田派は、蓮如の布教が始まるまでは真宗内でも勢いのある教団でした。ところが本願寺派の蓮如が現れると、流れはそちらに移っていきました。また、加賀国守護の富樫氏の家督争いが起こったとき、高田派は富樫幸千代に味方しましたが、本願寺派が味方した富樫政親が勝利したため高田派は徐々に勢いを失っていきました。つまり、高田派にとって本願寺は因縁の相手だったのです。
敵の敵は味方。信長は「所領は望みどおりに」とか「新たな知行を与える」とかいう約束を取り付け、同様に反本願寺の立場にある勢力を味方につけていきました。
たとえば高田派の流れを汲む三門徒と呼ばれる一派。信長はその鯖江誠照寺・横越証誠寺・中野専照寺に、地位を安堵するという朱印状を送っています。
実は越前が一揆持ちの国になってから、また新たな対立が生まれていました。もともと越前にいた坊主衆と、この度の件で顕如に派遣されてやってきた者たちの対立、そして坊主衆と農民の門徒との対立です。
越前を一揆のものにするに至った戦いで主たる戦力として戦ったのは、農民の門徒らです。しかし今や国の支配権は顕如がよこした下間頼照らが握っている。門徒の不満は膨らみ、内部で争いが始まります。
長篠の戦いや長島一向一揆で勝利し、越前に向き合う余裕が生まれた信長は、この一揆内部の争いを攻め入る好機ととらえたのです。
織田軍による総攻撃
信長は8月12日に越前に向けて出陣しました。翌13日には羽柴秀吉が守る小谷城に泊まると、そこで軍の兵糧を得て14日には敦賀の武藤舜秀(きよひで)の城に陣を構えました。『越州軍記』によると織田軍は総勢15万5千騎という大軍ですが、これは誇張のようです。『信長公記』には3万騎ほどとあります。
織田軍は越前の牢人衆を先陣に、織田の部将は以下のとおりです。
佐久間信盛・柴田勝家・滝川一益・羽柴秀吉・明智光秀・丹羽長秀・簗田広正・細川藤孝・塙直政・蜂屋頼隆・荒木村重・稲葉良通・稲葉貞通・氏家直通・安藤守就・磯野員昌(かずまさ)・阿閉(あつじ)貞征・阿閉貞大(さだひろ)・不和光治・不和直光・武藤舜秀・織田信孝・織田信澄・織田信包・織田信雄(伊勢衆含む)。
そして別動隊の金森長近と原長頼。
さらに海上から攻める軍勢に、粟屋勝久・逸見(へみ)昌経・粟屋弥四郎・内藤重政・熊谷直之・山県盛信・白井光胤・松宮玄蕃允・寺井源左衛門・香川・畑田加賀守。一色義道・矢野・大島・桜井が丹後から船を出して参陣しました。
対する一揆勢の戦力がどの程度だったのかはわかっていませんが、複数に分かれて立て籠もっていたようです。
- 虎杖(いたどり)城……下間頼俊を大将に、加賀・越前の一揆勢が集結。
- 木芽(きのめ)峠……石田の西光寺が一揆勢を指揮。
- 鉢伏(はちぶせ)城……専修寺・阿波賀三郎兄弟・越前衆が守備。
- 今城・火燧(ひうち)城……下間頼照を大将として守備。
- 大良(だいら)越え・杉津(すいつ)城……大塩の円強寺(えんこうじ)と加賀衆が守備。
- 海岸の新城……若林長門・甚七郎父子を大将に、越前衆が集結。
- 府中の竜門寺……三宅権丞。
8月15日、強い風雨にさらされながら、織田の全軍が総攻撃をかけました。陸では杉津砦・河野丸砦を攻撃し、続いて大良城・河野城へ。海上から上陸した軍は方々に火を放ちました。
一揆勢は応戦しますが、円強寺と若林長門父子らは秀吉・光秀の部隊に200~300人ほどが討ち取られています。彼らの城はその日のうちに焼き払われ、討ち取った首も同様にその日のうちに敦賀の信長の元へ送られて首実検が行われました。
同日の夜には、府中の竜門寺に攻め込み、立て籠もる三宅権丞を討ち取って城や周辺に火をかけました。木芽峠・鉢伏城・今城・火燧城の一揆勢は府中に向かって退却しますが、待ち構えていた秀吉・光秀の部隊によって2000人あまりが切り捨てられたといいます。鉢伏城の阿波賀三郎兄弟は信長に許しを請うたものの、信長は許さず。塙直政に命じて斬首させました。
翌16日には、信長自身が馬廻衆ほか1万あまりを率いて木芽峠を越え、竜門寺の砦に布陣し、後方との連絡のため、福田三河守を今城に置きました。
このようにして越前は織田軍によって制圧されたわけですが、ここからさらに残党狩りが繰り広げられていくのです。
残党狩りでことごとく斬首
下間頼照・下間頼俊・専修寺の面々は山林に隠れていたところを朝倉景健に捕らえられて斬首。その景健はその首をもって信長に許しを請いましたが、許されずに斬首されています。頼照は浮浪者のような姿で加賀方面へ逃れようとしたようですが、脱出はなりませんでした。18日には、柴田勝家・丹羽長秀・織田信澄が鳥羽城を攻撃し、500~600人を討ち取るなど、その後も越前の一揆勢はあちこちで織田軍の攻撃にあい、一揆は混乱して山中へ逃れました。

信長は男女の区別なく切り捨てるよう命じており、『信長公記』によれば、15日から19日までの間に生け捕りにした敵の数だけでも、1万2250人あまりであったということです。この捕虜はことごとく斬首されました。最終的に生け捕りになった者と殺された者らをあわせると、3~4万にものぼるとか…。中には、一揆とは関係のない人々も含まれていたでしょう。
信長は村井貞勝に対して告げたことによると、「府中の町は、死骸ばかりにて一円あき所なく候。見せたく候」(『泉文書』)とあり、鼠一匹逃さないほど徹底して虐殺が行われていたことがうかがえます。
23日、信長は一乗谷に陣を移すと、稲葉父子・明智光秀・羽柴秀吉・細川藤孝・簗田広正を加賀へやり、進撃させました。加賀でも一向一揆の勢力が弱い能美・江沼の二郡を平定し、引き上げています。信長自身はその後も越前に留まり、戦後処理を行いました。
織田軍による殲滅は残虐か
越前一向一揆を見ると、長島一向一揆と同様に「そこまでするのか」と思うほどの一揆狩りが行われていたことがわかります。この様子は、越前に荘園をもつ興福寺大乗院の門跡・尋憲が見ていました。尋憲の旅日記『越前国相越記』には、残党狩りを行う織田軍が一揆衆を切り捨て、鼻を削いだことが記されています。
戦で敵の死体の鼻を削ぐというと、秀吉の朝鮮出兵の際に耳や鼻を削いだ例を思い浮かべますね。これはあまりに残虐で常軌を逸した行為だという見方をされがちですが、中世の戦では、首を切るのと違いはない行為だったようです。
秀吉の朝鮮出兵時も、首では大きくて重く持ち帰るのに不便だから耳や鼻で代用したのであって、相手が同じ国の人間ではないから死体から体の一部をそぎ落として弄んだ、というようなことではありません。越前一向一揆の場合も、討ち取った敵があまりに多いので鼻で代用したのでしょう。
他にも同様の例はあり、夏の熱さで死体が腐敗しやすいから耳や鼻で代用して首実検を行う場合もあったようです。ただ、鼻では手柄欲しさに関係のない人(たとえば女性)の鼻を削ぐ可能性も考えられ、唇まで一緒に削ぎ取って髭が見えるようにしたり、死体が持っていた道具をセットにしたり、工夫がなされたようです。
というわけで、「鼻を削いだ」ことをもって、他の戦と比べて特別残虐な行為だということはできないでしょう。
北陸支配は柴田勝家を中心に
越前は再び信長の支配下に置かれました。信長は越前8郡を柴田勝家に、2郡は佐々成政・前田利家・不和光治に、大野郡の3分の2は金森長近に、大野郡3分の1は原政成に、敦賀郡は武藤舜秀に与えました。越前は北ノ庄城の柴田勝家を中心に統治されることになりました。その与力「府中三人衆」と呼ばれるのが、佐々成政・前田利家・不和光治の3人です。
信長は越前国掟を作ってその後を勝家に任せ、9月26日にようやく岐阜へ帰城しました。
【主な参考文献】
- 『国史大辞典』(吉川弘文館)
- 『世界大百科事典』(平凡社)
- 『日本人名大辞典』(講談社)
- 神田千里『信長と石山合戦 中世の信仰と一揆』(吉川弘文館、2008年)
- 谷口克広『尾張・織田一族』(新人物往来社、2008年)
- 小和田哲男監修『週刊 ビジュアル日本の合戦 顕如と石山合戦』(講談社、2005年)
- 谷口克広『織田信長全戦全録 桶狭間から本能寺まで』(中央公論新社、2002年)
- 奥野高広・岩沢愿彦 校注『信長公記』(角川ソフィア文庫、1969年)

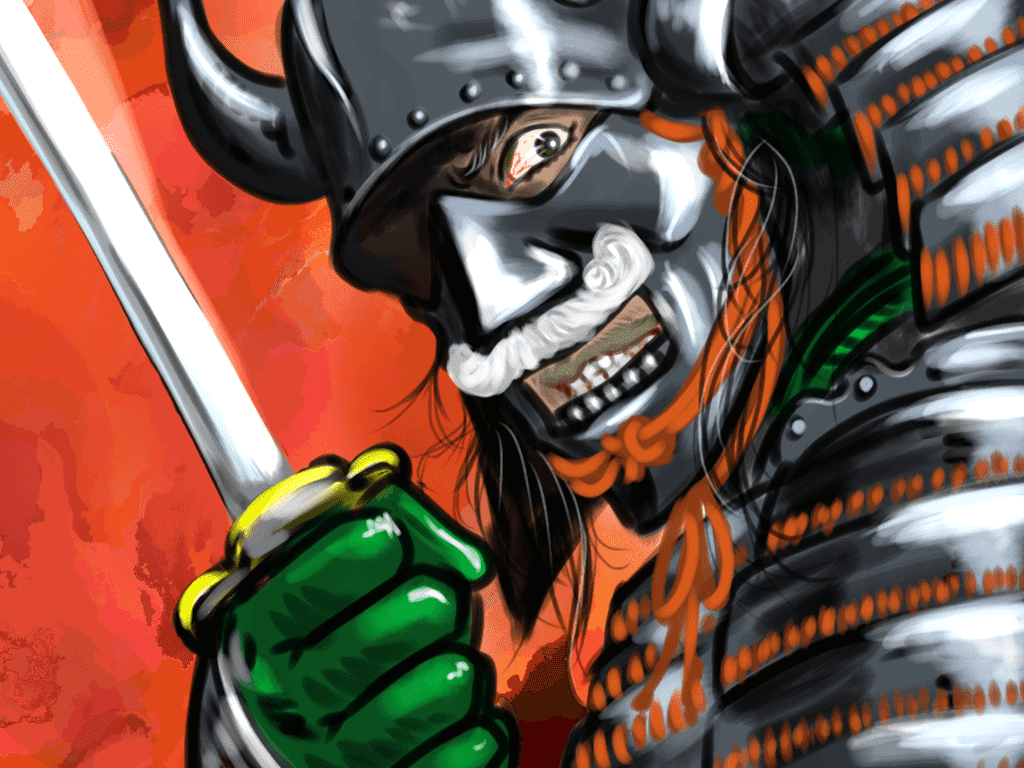



コメント欄