生き延びていた?石田三成の懐刀「島左近」の生き様と最期
- 2025/08/26
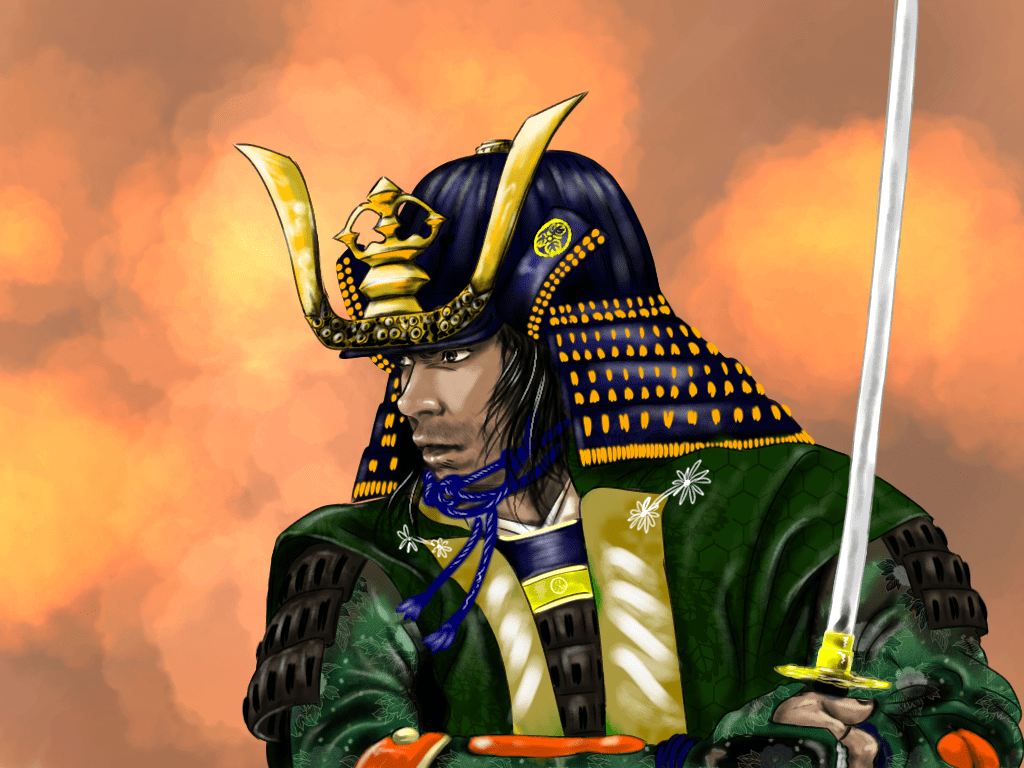
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
しかし、その華々しい活躍とは裏腹に、彼の出自や最期については多くの謎が残されています。そのため、現代でも左近の生涯には不確かな点が多く、未だに解明されていない部分も少なくありません。
なお、彼は生前「清興」と名乗っていたとされますが、本記事では最も知られている「左近」の名で統一します。それでは左近の知られざる実像を紐解いていきましょう。
不確かな出自
左近の出自については、確かなことがほとんど分かっていません。生年すら不明ですが、一説には天文9年(1540)生まれとされており、もしこれが真実であれば、主君である三成よりも年上の家臣だったことになります。また、出身地についても諸説あり、有力なのは「大和説」と「対馬説」です。
現在のところ、有力視されているのは大和説で、彼は大和国(現在の奈良県)の在地領主である島家に生まれたと考えられています。一方、信憑性は低いものの、史料に「左近は対馬の人」という記載があったり、対馬に彼の墓が現存していたりすることから、対馬説も興味深い説です。

ただ、本記事では信頼度の高い大和説を中心に記述を進めていきます。
大和国の国人として生まれた左近は、まず隣国である河内国の守護大名、畠山氏に仕えたといわれています。永禄5年(1562)の教興寺の戦いに参加したという説もありますが、この戦で畠山氏は大敗を喫しています。しかしこの際に左近は筒井氏の指揮下で行動したため、畠山氏の没落後は筒井氏に仕えるようになったと考えられています。
ただし、そもそも畠山氏に仕えていたかも定かではありません。島家が興福寺の僧侶を輩出していた縁で、興福寺の衆徒であった筒井順紹に仕えたという説も存在します。筒井氏に仕えるまでの経緯としては、こちらの説の方が自然かもしれません。
筒井家臣として名を上げる
筒井氏に仕え始めた時期は不明ですが、左近は順紹の跡を継いだ筒井順慶の時代に侍大将へ抜擢されたと伝えられています。しかし、当時の日記類に彼の名前は確認できず、あくまで言い伝えの域を出ません。経緯こそ不確かではあるものの、左近が筒井氏の配下として働いていたことは間違いないようです。具体的な戦果や内政での功績は不明ですが、後に筒井家を去った際に多くの仕官の誘いがあったことから、彼の優れた才能は当時から高く評価されていたと考えるほうが自然です。
筒井氏は、松永久秀らとの抗争を乗り越えて成長し、織田信長、そして豊臣秀吉に服従することで大和一国を安堵されます。しかし、その2年後に順慶が亡くなり、養子の筒井定次が家督を継ぐと、左近はこの新君主と合わなかったようで、天正16年(1588)に筒井家を去ります。出奔の理由は諸説あり、筒井家の将来性に見切りをつけたとも、領内の農民と対立したためともいわれますが、確かなことは分かっていません。
その後、左近は浪人として各地を放浪したとされ、法隆寺や興福寺に身を寄せたともいわれています。この時期にも仕官の誘いから、蒲生氏郷や豊臣秀長に仕えていたという説もあり、彼の能力が依然として高く評価されていたことがうかがえます。
破格の待遇で三成に招かれる
豊臣政権で確固たる地位を築いていた石田三成は、放浪中の左近に目をつけました。なんとしてでも彼を家臣に迎えたかった三成は、自身の石高が4万石に満たなかったにもかかわらず、1万5千石という破格の条件でスカウトしたという伝説が残されています。この逸話の真偽は不明ですが、左近が三成の家臣となったのは事実です。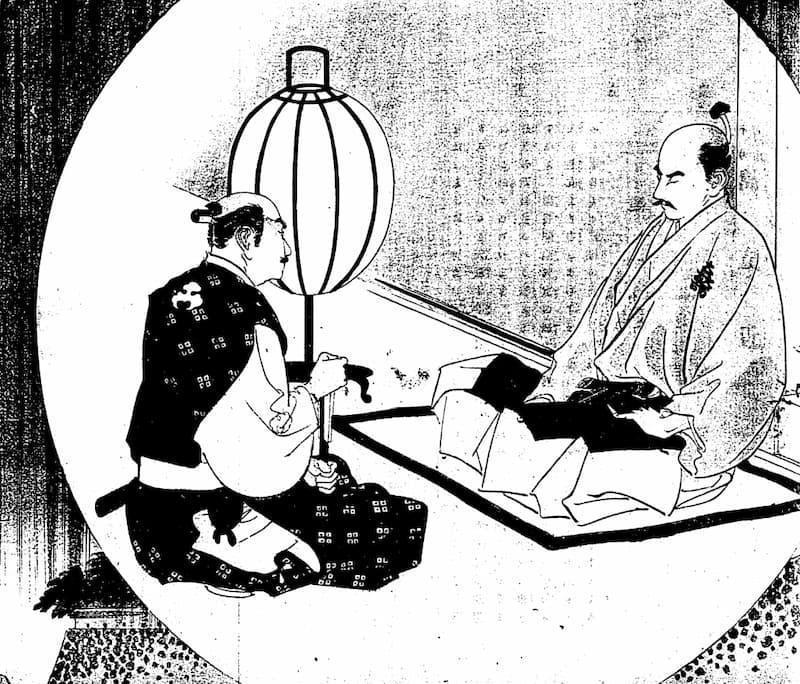
三成に仕えてからの左近の活動についても、確かな記録は多くありません。しかし、近年発見された書状から、三成と親交のあった佐竹氏との外交交渉で重要な役割を担っていたと考えられます。また、三成が関わった文禄の役(1592~93)にも従軍したと推測されますが、その動向を裏付ける明確な記録はなく、新史料の発見を待つしかありません。
朝鮮出兵は慶長3年(1598)の秀吉の死をもって終結しますが、その後は三成と家康の対立が激化し、天下は一触即発の事態へと向かいます。左近は戦前の調略にも貢献したとされ、一説には三成と共に家康の暗殺を計画したものの、露見して失敗に終わったといわれています。
関ヶ原で敵を震撼させる
慶長5年(1600)、家康が会津征伐へ向かった隙をつき、三成が挙兵します。これを知った家康が引き返し、両軍は関ヶ原で激突することとなります。決戦の前日、左近は西軍の士気を鼓舞するため、わずか五百ほどの兵を率いて東軍の陣に奇襲をかけ、混乱に陥れます。この関ヶ原の前哨戦の一つとされる「杭瀬川の戦い」は、西軍の勝利に終わりました。
そして迎えた関ヶ原本戦。左近は黒田長政や加藤嘉明らの軍勢と対峙します。その奮戦ぶりは後世まで語り継がれており、徳川方からは「身の毛がよだち冷汗が出た」と記録されています。黒田隊の将兵は、左近の姿を思い出そうとしても叶わず、「誰一人姿を思い出せないほど恐怖を味わった」という逸話も残されています。

しかし、鬼神のごとき奮戦も虚しく、左近はついに負傷。これは黒田隊の鉄砲によるものと言われています。「関ヶ原合戦図屏風」には、負傷して脇を抱えられた左近の様子が描かれています。その後、左近は討ち死にしたと考えられています。
死因は鉄砲傷や、加藤隊の戸川達安に討ち取られたなど諸説ありますが、その最期については詳細不明です。彼の首や遺体も発見されておらず、このことが後述する「生存説」につながっていきます。
実は生きていた?数々の生存説
関ヶ原で敗れ、遺体が見つかっていないことから、左近には数多くの生存説が語り継がれています。その一つは、三成の本拠地である近江国(滋賀県)へ逃げ込み、奥川並という山の奥深くにあった集落に隠れ住んだという伝説です。彼が住んでいたとされる洞窟が現存しており、地名にも左近に由来するものがあります。しかし、その後この地が井伊氏の領地になったため、身の危険を感じて現在の静岡県浜松市あたりに移って、ひっそりと余生を送ったとされています。
そしてもう一つは京都の銀閣寺周辺に隠れ住み、やがて立本寺(京都府上京区)の僧侶になったという説です。左近が寺社に縁があったことを考えると、この説は違和感がありません。関ヶ原から約30年後の寛永9年(1632)に亡くなったとされ、現在も同寺に左近の墓が残っています。注目すべきは、他の遺体がすべて火葬されているのに対し、左近だけが土葬で葬られている点です。これは、彼が特別な人物として扱われていた証拠かもしれません。
彼の生涯は謎に包まれていますが、その武勇と主君への忠誠心は、今なお多くの人々を魅了し続けています。
【主な参考文献】
- 『国史大辞典』(吉川弘文館)
- 花ケ前盛明編『島左近のすべて』(新人物往来社、2001年)
- 楠戸義昭『戦国武将「お墓」でわかる意外な真実』(PHP研究所、2017年)




コメント欄