光秀の家臣団の結束力と軍事力 ~光秀への忠誠心はどれほどあった?
- 2020/04/17
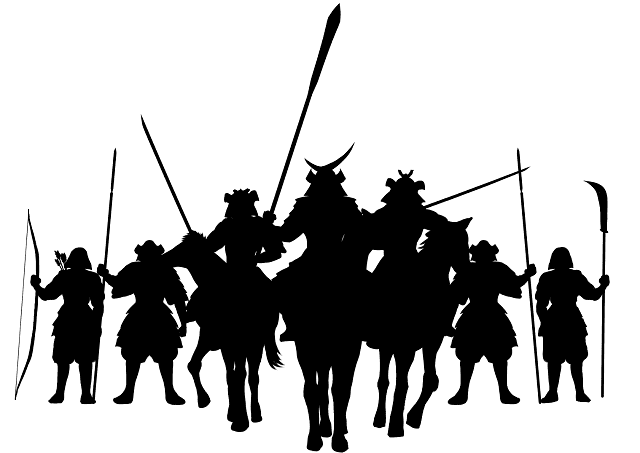
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
光秀を語る上で、また本能寺の変から山崎の戦いまでの情勢を追う上でも、光秀ただひとりに目を向けていても何もわかりません。戦ったのは光秀ひとりではなく、家老はじめ多くの家臣です。
光秀の若いころはたったひとりの召使いしかいなかったといいますが、最盛期には二万もの軍勢を率いるようになります。その過程をたどりながら、家臣団の結束力や軍事力についてまとめてみました。
光秀の若いころはたったひとりの召使いしかいなかったといいますが、最盛期には二万もの軍勢を率いるようになります。その過程をたどりながら、家臣団の結束力や軍事力についてまとめてみました。
【目次】
五人の家老
光秀は本能寺の変の前日の6月1日、五人の家老を集め、謀反の決意を打ち明けたといいます。その五人が、明智秀満、明智光忠(次右衛門)、藤田伝五、斎藤利三、溝尾庄兵衛(三沢秀次)。彼らがそれを聞いてどのように感じたかはわかりませんが、誰も異を唱えることなく、離反することもなく光秀に追従しました。
この重臣らの光秀に対する忠誠心の強さは、そのまま光秀の人望を表わしているとも言えますが、メンバーを見ると従うのも当然のように思えます。
秀満と光忠は明智一門。藤田伝五は詳細がよくわからないものの、光秀の父の代から明智に仕えていたといいます。
斎藤利三は光秀に仕え始めるのは遅いものの、光秀の甥ともされており、また利三の妹は土佐長宗我部元親の正室。信長は四国攻めを命じており、長宗我部とのつながりを守りたい利三にとっては利害も一致していたものと思われます。
溝尾庄兵衛は光秀が信長に仕官する以前からの家臣であったとされています。
あわせて読みたい
あわせて読みたい
家臣団の構成
光秀家臣団の構成について、『明智光秀 野望!本能寺の変』(新人物文庫)の中で横山住雄氏が天正9年当時を一覧にまとめているので、そちらを引用してみましょう。天正9(1581)年時の光秀家臣団
明智一族衆
明智秀満、明智光忠、明智半左衛門、明智孫十郎、妻木氏ら旗本
溝尾庄兵衛、斎藤利三、藤田伝五、藤木権兵衛、四王天政孝、藤田藤八、御牧勘兵衛、加治石見守、阿閉貞征、松田左衛門、柴田源左衛門、並河掃部、伊勢貞興(与三郎)、諏訪飛騨守組下大名(与力)
- 【丹後衆】細川忠興、一色義有、矢部藤一郎
- 【大和衆】筒井順慶、島左近
- 【摂津衆】池田恒興、中川清秀、高山重友、塩川勘十郎
- 【和泉衆】寺田又右衛門尉、松浦安太夫
- 【河内衆】池田丹後守、三好康長
家臣団構成の過程は?
家臣団構成の過程においては、上記一覧に含まれない人物も登場します。その過程をざっとまとめてみましょう。1、朝倉義景家臣時代
朝倉義景から拝領した知行は五百貫で、家臣団と呼べるほどの家臣がいたかどうか微妙なところですが、このころは明智一門に正妻・煕子の実家である妻木氏らが家臣であったとされています。また『細川家記』(『綿考輯録』)によれば、溝尾庄兵衛、三宅藤兵衛らが家臣であったようです。
2、幕臣時代
義昭の奉公人時代、光秀は山城に知行を与えられており、このとき北山城衆が与力として付属していました。山本対馬守、渡辺昌、佐竹宗実、また近江山中の磯谷久次がいました。3、比叡山焼き討ち後
元亀2(1571)年比叡山焼き討ち後、光秀は信長から近江国志賀郡を与えられます。そのとき従属させたのが、志賀郡の堅田衆であった猪飼野昇貞、馬場孫二郎、居初又次郎、また元浅井氏に属していた林員清らです。義昭との対立後
幕臣でもあった光秀が義昭と決別したころ、『兼見卿記』によれば、幕臣時代の与力であった北山城衆の山本、渡辺、磯谷が光秀に背いて義昭についています。与力として光秀の組下に入ったといっても、実際は主君・義昭に与えらえた部下です。彼らは幕臣としての立場を重視したのでしょう。
義昭追放後
義昭が京を追放されたのち、旧幕臣で信長に降った者の多くは光秀の与力となりました。伊勢貞興、諏訪飛騨守、津田重久です。このうち伊勢貞興はもともと幕府の政所執事の家柄でしたが、祖父・父の代に衰退しています。同じころ、細川藤孝も信長の家臣となり、光秀の与力となっています。幕府では光秀よりも上にいた者たちが、こうして今度は部下となったわけです。
丹波攻めに際して
信長の丹波攻めに際し、信長に味方した東丹波の川勝継氏、小畠左馬助、片岡藤五郎らは光秀の与力となりました。大坂本願寺攻め後
このとき、信長は塙直政のもとにいた、南山城衆、大和衆、さらに摂津衆、和泉衆、河内衆を光秀の与力としています。南山城は井戸良弘、御牧景重・景則、狛綱吉。大和衆からは筒井順慶。摂津の高山重友、池田恒興、中川清秀、和泉の寺田又右衛門尉、河内の池田丹後守、三好康長です。丹波一国を拝領後
丹波平定後、光秀は信長からこの一国を拝領しています。丹波の国人が家臣団に組み込まれ、並河掃部、荒木氏綱、松田左衛門、四王天政孝、荻野彦兵衛、中沢豊後守、波々伯部権頭、尾石与三、酒井孫衛門、加治石見守らです。この時点で光秀家臣団は最大規模になり、およそ二万の軍勢になっていたとされています。
光秀はこうして畿内の多くを掌握していたわけですが、軍の統制は光秀が制定した軍規定書によって行動していたようです。しっかり軍を教育し、合理的に指揮していたことがわかります。
また、光秀が丹波一国を拝領したのは天正8年のこと。本能寺の変までわずか2年たらずですが、光秀は重税を課すことなく、善政をしいていたとか。丹波の領民たちは福知山に御霊神社をつくり、光秀を「御霊さま」と慕い祀っています。
丹波衆はほかの家臣らに比べると光秀家臣団に加わったのは遅かったものの、善政をしいた光秀に対する忠誠心はあったのではないでしょうか。
あわせて読みたい
本能寺の変以後光秀に従ったのは
その後、本能寺の変から山崎の戦いへと動いていくわけですが、家臣団のうち光秀に従った者はどれほどいたのか。最初に挙げた五人の家老が従ったことはもちろんですが、山崎の戦いにおいて、家臣になって日の浅い丹波衆も明智軍として戦っています。近江衆や、旧幕臣の三名も明智軍として戦いました。
ここで特筆すべきは、古くからの友人であった細川藤孝とその息子・忠興、また筒井順慶が光秀に味方しなかったことでしょう(筒井順慶は一応協力はした)。
光秀は忠興に対し、自らは畿内をまとめたら隠居して嫡子の光慶と忠興に天下を譲るから、とまで条件を提示したにも関わらず、忠興は頑として動かず、妻・玉(ガラシャ)を幽閉しています。
父の藤孝も同様に協力要請を拒否し、親子ともども剃髪して信長への弔意を表したとか。藤孝は忠興に家督を譲り、幽斎と号しました。
光秀はここまでして、まさか断られるとは思っていなかったのではないでしょうか。古くから付き合いがあり、趣味も同じくした無二の親友でもあったのです。
しかしそれでも与力であった彼らが断ったのは、与力は信長の家臣であり、光秀の組下に編成されていただけということ、さらに与力である彼らは家を守る立場にあったことが大きいでしょう。
光秀は丹波拝領時点で二万の軍勢を抱えていたとはいえ、その実態は一門や譜代を除き、ちょっとしたことで崩壊してしまう脆いものだったのかもしれません。
あわせて読みたい
【参考文献】
- 歴史読本編集部『ここまでわかった! 明智光秀の謎』新人物文庫、2014年。
- 明智憲三郎『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫、2013年。
- 新人物往来社『明智光秀 野望!本能寺の変』新人物文庫、2009年。
- 谷口克広『検証 本能寺の変』文芸社文庫、2007年。
- 二木謙一編『明智光秀のすべて』新人物往来社、1994年。
- 高柳光寿『人物叢書 明智光秀』吉川弘文館、1986年。

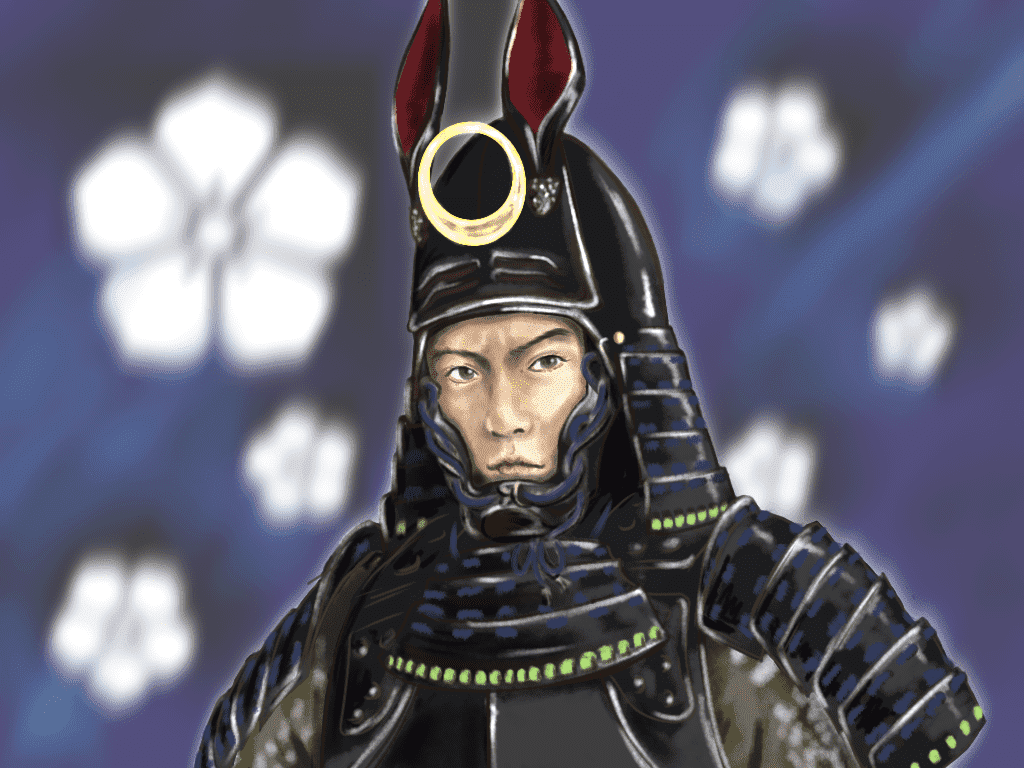

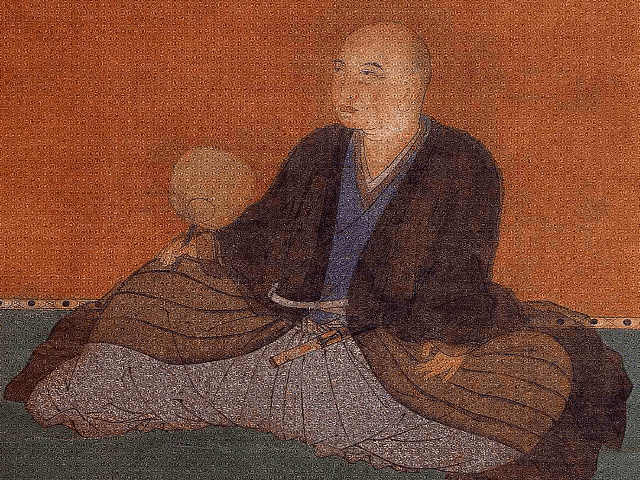

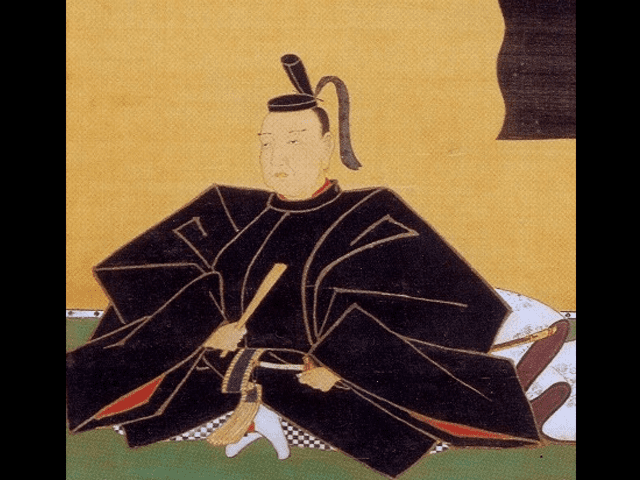

コメント欄