【麒麟がくる】第44回「本能寺の変」レビューと解説
- 2021/02/09
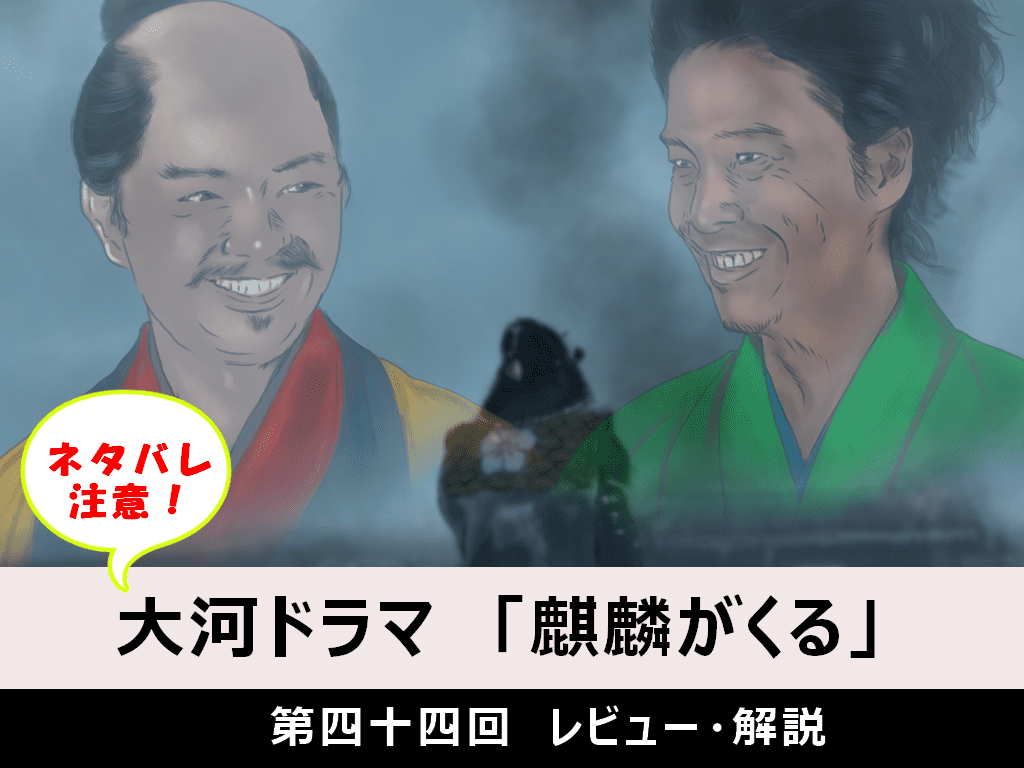
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
なぜ光秀は信長を討ったのか、光秀の謀反を知った信長はどう受け止めたのか。「麒麟がくる」というタイトルの意味とは何か。全44回、もっとここを描いてほしかったという思いはありますが、最後まで観て納得できるエンディングだったように思います。
動機全部入り!
家康の饗応役を解かれた光秀の前に、機嫌のよさそうな信長が現れます。宴の場での行動は家康を脅すパフォーマンスだったなどと言われてもドン引きですよね。でも、それでも光秀ならついてきてくれるという思いがあったのでしょう。信長はこの場でさらに次々と爆弾を落としていきました。光秀が窓口となってつないできた身内同然の長宗我部を討つ、将軍・足利義昭を討て、帝をも超える権威を持つ。
どれかひとつだけでも十分謀反の動機になり得るのに、饗応の場での面目失墜からこうも矢継ぎ早に燃料を注がれて……。また本能寺の変は黒幕説もあります。朝廷、義昭、秀吉、家康などなど。
これも、秀吉以外の全員が「信長死んでほしい」と光秀に言っているようなもので、まるで『オリエント急行の殺人』。全員が信長を殺したといってもいいのではないかと思います。
全部投入しても破綻のない展開だというのがすごいところですよね。
たまと忠興
最終回でいろいろ見せなければならない場面が多い中、残されるたまに焦点が当てられたのが印象的でした。たまと忠興の夫婦。すでに嫉妬深いらしい忠興の性格の片鱗が見えておもしろいですね。「思ひ出すとは忘るるか 思ひ出さずや忘れねば」
「戦に出ている間、自分のことなど忘れているのだろう」と言う忠興にたまが「いいえ、いつも思い出していますよ」と言うと、忠興がわざと歌うのだという歌。これは室町時代後期の歌謡集『閑吟集』に収録された歌です。
『閑吟集』は庶民的な恋をテーマにした歌が多く、今回の歌を見ても普遍的で、現代にも通じる感情です。「思い出すのは忘れていた証拠。忘れていなければ思い出すとは言わないものだ」。
のちのこの夫婦のことを思うとゾッとするのですが、「面白い旦那様だな」で片づけてしまう光秀、知らぬが仏です。
あわせて読みたい
光秀決起
饗応役からおろされた光秀は安土から京の邸へ戻り、戦支度へ。「丹波勢を中心に4000の兵を用意」してあるという台詞がありました。これは、本能寺の変の動機のひとつとされる「丹波を召し上げられて自分で山陰を取ってこいと言われた」という説を否定するものですね。5月末、丹波に入った光秀はひとり愛宕山に籠り、決意を固めます。そして亀山城にて、藤田伝五、明智秀満(左馬助)、斎藤利三の三人にその決意を打ち明けます。実際は本能寺の変の前日に家老5人に伝えたとされます。
第42回でもそうでしたが、この場面でもホトトギスの鳴き声が効果的に使われていたように思います。亀山城での場面のはじめからホトトギスが鳴いていて、「我が敵は本能寺にある。その名は織田信長と申す」の直前で鳴き止んでいます。光秀ならどんなホトトギスの句になったでしょうね。
あわせて読みたい
秀吉の中国大返し
驚くのは、あれほど派手にやった信長自身はまったく無警戒なのに、その周りでは「信長と光秀の間にすきま風」「光秀が信長を討つらしい」といううわさが広まってしまっていることです。おかげで藤孝は光秀に会う前から警戒してしまっています。「声をそろえて申し上げる覚悟があると言ったが、今もあるか」と問われ、これは謀反を仄めかすような言葉ではありますが、決定的なものではありませんでした。しかしどうも怪しい、用心せねば、と秀吉に文を送るに至ったのは、やっぱりうわさが大きかったこともあるのでしょう。
そのおかげで、備中にいた秀吉はさっさと戦を切り上げて京に戻ることができたという展開でした。よく、信長の死を知って嘆き悲しむ秀吉に、官兵衛が「今がチャンス」と中国大返しを成功させた、と言われていますが、今回はそうではありませんでした。
「やればよいのじゃ。明智様が上様をやれば面白い」
ものすごく黒い秀吉。いつも飄々として本心の見えない人物ですが、官兵衛の前では真っ黒い腹の内を見せていたのがあの短いシーンでもわかります。これだけ悪い秀吉だと、謀反のうわさを流したのもこの人なのではと勘繰ってしまうほど。
「是非に及ばず」
本能寺の変で注目されるひとつがこの信長が言ったという言葉です。「是非に及ばず」は解釈が分かれるところで、一般的には「仕方がない」「やむを得ない」と解釈されますが、「是非を論ずる余裕もない(時間もない)」「意味がわからない」という解釈もあります。「仕方がない」ひとつとっても、そのまま諦めかもしれないし、「仕方がない、じゃあ応戦しよう」となるかもしれない。
「麒麟がくる」の信長はどうだったか。本能寺を囲んでいるのが明智の軍だと知ると、「そうか、十兵衛か」とひとしきり泣き笑いし、「であれば是非もなし」と笑いました。「十兵衛であれば仕方がない」と。
饗応後のあの回想シーンで、信長は「子供の頃のようにながく眠りたい」「(すべてが終わったら)一緒に茶でも飲もう」と言っていました。基本狂っている信長ですが、そのどこかに自分を俯瞰してみる「普通の人間」な自分もいるのでしょう。ずっと突き進んできたのは、早く穏やかな世にして解放されたいという思いもあったから。光秀も疲弊していますが、それは信長も同じなのです。
そんな自分を討ちに来たのが光秀だった。それを知った時の感情は喜び、悲しみ、安堵、いろいろでしょうが、一番は自分を終わらせるのが光秀であることの喜びなのではないでしょうか。ある意味、長く(永く)眠りたい信長の願望を叶えにきてくれたわけでもありますし。
また、信長を討つという光秀の選択は、「将軍」か「信長」かの選択を迫られ、信長を選んだということ。ずっと武家の棟梁として支えていきたいと思っていた将軍の命か、一緒に歩んできた信長を始末することか。光秀は将軍の命を守ることを選んだというより、自分がここまで育ててきた信長を始末せねばならないという責任を選んだのだと思います。将軍よりも、信長に注いできた感情の方が大きかったということ。
愛情コンプレックスで「自分を見てほしい」信長にとって、光秀が殺すことを選ぶほどの感情を自分に向けていると知った喜びは大きかったでしょう。
描かれなかった定番
「麒麟がくる」は尺も短い中で、何を描いて何を描かないか、その取捨選択にも随分こだわったと思います。描かれなかったものに注目すると、本能寺の変では定番中の定番である信長の「敦盛」と、光秀の「愛宕百韻」が挙げられます。まず、「愛宕百韻」の「ときは今あめが下しる(なる)五月かな」について。これは光秀の「天下をとる野望」を示すとされますから、野望があったわけではない「麒麟がくる」では必要のないものでした。
続いて幸若舞の「敦盛」について。燃え盛る本能寺で敦盛を舞い、自害するというのがお決まりの描写ですよね。しかし桶狭間の戦い前に舞ったという記述は『信長公記』にありますが、本能寺で舞ったという記述はありません。だからなければならないということもないでしょう。
また、光秀と信長の感情に焦点を当てて描いたこの作品で、最後に「人間の人生って儚いものだね」というのは蛇足でしょう。
そして、山崎の戦い。これは尺が短かったことも関係しているのかもしれませんが、詳しく描かれることはありませんでした。でも、自分の半身であった信長を殺した光秀はその時点で死んだともいえるわけで、それ以後を詳細に描かないことできれいに終わったようにも思います。
あわせて読みたい
「麒麟がくる」
最後に、タイトルについて少し。本能寺の変から数年後、駒と会った義昭は、小早川隆景を「まるで志がない男」と評し(登場してすらいないのにかわいそう)、「世を正しく変えようと思うのは志じゃ」「信長にはそれがあり、十兵衛にははっきりそれがあった」と言います。「世を平らかにする」「大きな国をつくる」これが「麒麟をつれてくる」ことに集約されているのですが、この光秀と信長の夢が、義昭の言う「志」なのだとすると、確かに隆景にはないかもしれませんね。隆景は毛利家を存続させること第一でしたし。
すぐさま秀吉についた隆景は、中国大返しをする秀吉を追撃しようとする毛利の家臣一同を止め、秀吉に恩を売ったと言われます。ここから見えてくるのは、状況に応じた適切な行動ができること。その場に合った動きをするところは秀吉に通じるかもしれません。とすると秀吉にも志はない。しかし秀吉は天下を取りました。
ここで思い出したのが、映画『パラサイト』の主人公の父の台詞です。「計画は立てるから失敗する。計画しなければ失敗することはない。絶対失敗しない計画は無計画だ」という。この後、「金持ちになって父を救い出す」という無謀な計画を立てる主人公、父の論理からすると当然失敗するだろうというオチです。
信長も光秀も、まっすぐすぎて、ゆるぎない大きな「志」を持ったから失敗したのかもしれません。そしてそれがない秀吉は成功するのです。
さて、麒麟は来たのか。本能寺の変の後、光秀が敗れて秀吉が関白になりました。しかし帝は「世が平らかになるのはいつのことであろう」と言っていて、まだ麒麟は来ていないことがわかります。それでも、ラストのまちを歩く駒の背景の人々は、第1回に西へ向かう光秀が見た人々よりは明るく楽しそう。少しずつ近づいてきているのかもしれません。
「麒麟がくる」というタイトルについて、義昭の言葉を借りるなら、「志を持って麒麟の到来を待った人々」が込められているのではないかと思います。「麒麟がくる」とは「まだ来ていない状態」「待っている状態」を表しています。誰も来るとは言ってない。来るかもしれないし来ないかもしれない。
サミュエル・ベケットの戯曲に『ゴドーを待ちながら』という作品があります。第一幕・二幕通じて浮浪者ふたりが「ゴドー」という人物をただ待ちながら喋るというのが繰り返される不条理演劇の代表作。「ゴドー」とは何か。解釈がいろいろあり、「神(ゴッド)」であるという説もあります。神不在の舞台で「何も起こらない」ことが繰り返されるのは絶望的ではありますが、神を待っている間は希望があります。
「麒麟がくる」も、麒麟という平和をもたらす「神」不在の世の中でもがき苦しみながらも、麒麟の到来を待つ、麒麟を連れてくるという志を持っていて、麒麟を待ちながら平和が訪れると信じた、希望を持ち続けた人たちの話だったのではないでしょうか。義昭の言葉はタイトル回収とはいかないまでも、説明にはなっていたと思います。
光秀が生き残ったのかどうかはどちらでもいいのですが、光秀の志は家康に引き継がれたと思うので、希望は確かに続いているでしょう。「鳴くまで待とう」じゃないですが、麒麟を待って待って待って、最後に手にするのは家康です。
【主な参考文献】
- 奥野高広・岩沢愿彦・校注『信長公記』(角川書店、1969年)



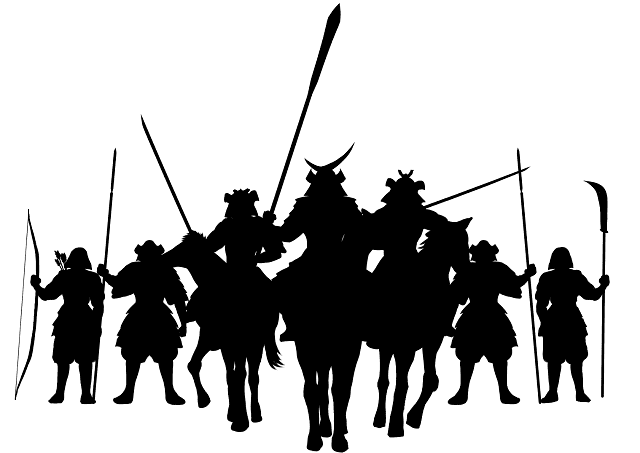
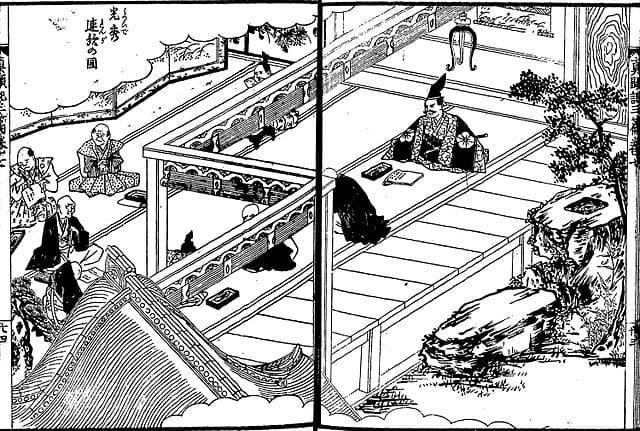

コメント欄