信長を討つ”刃”から”盾”に…信長の兄・織田信広、大罪を許されて得た信頼と忠誠
- 2025/10/03
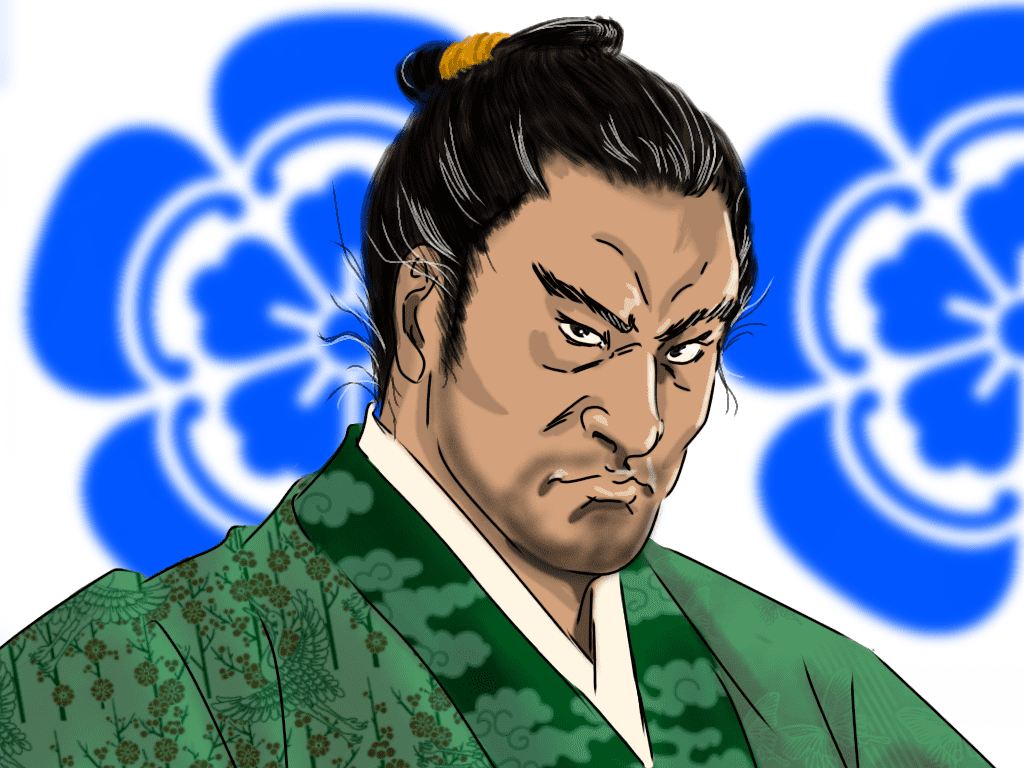
天下統一を志した織田信長には、その偉業の影で苦悩し、やがて忠誠を捧げた異母兄がいました。名を織田信広(おだのぶひろ)。彼は母の身分の低さゆえに家督相続の権利を失い、弟・信長に道を譲らざるを得ませんでした。
長子でありながら日陰の身に置かれた信広は、深い屈辱と野心に苛まれ、一時は弟・信長への謀反を企てます。しかし、謀反失敗後に信長から寛大に許されると、その才能を武力ではない外交手腕として開花させ、織田家の中枢を担う重臣へと変貌を遂げました。
この記事では、家督を追われた男が、いかにして弟の「天下布武」を支え、波乱の人生の終着点を見つけたのか。その知られざる生涯をみていきましょう。
長子でありながら日陰の身に置かれた信広は、深い屈辱と野心に苛まれ、一時は弟・信長への謀反を企てます。しかし、謀反失敗後に信長から寛大に許されると、その才能を武力ではない外交手腕として開花させ、織田家の中枢を担う重臣へと変貌を遂げました。
この記事では、家督を追われた男が、いかにして弟の「天下布武」を支え、波乱の人生の終着点を見つけたのか。その知られざる生涯をみていきましょう。
庶兄の宿命、嫡男の座を逃した長子
信長の唯一の兄として知られる信広は、父・織田信秀と側室との間に誕生しました。織田家にとっては最初の男子であり、当主の座に最も近い存在であったはずです。しかし、信長の母が信秀の正室である土田御前であったのに対し、信広の母は家柄の低い側室でした。当時の戦国武家の慣習では、家督は正室が生んだ子、すなわち嫡男が優先的に継ぐのが常でした。信長は長子ではありませんでしたが、正室腹の最初の男子であったため、家督は信長に継承されることが既定路線となります。信広は長子でありながら家督相続権のない「庶兄」という、複雑な立場を強いられました。この生い立ちの差は、彼の後の人生における鬱屈と野心の根源となります。
家督は継げなくとも、信広は父・信秀の存命中は一定の期待をかけられていました。天文17年(1548)8月には、信秀が攻略した安祥城の守備を任せられます。安祥城は、織田家が三河国(現在の愛知県東部)へ進出するための拠点で、対今川氏の最前線となる極めて重要な要衝でした。信広は若くして今川氏に「にらみ」をきかせる重責を担いますが、ここで武将としての最大の挫折を味わうことになります。

生け捕られ、屈辱の人質交換
信広の武将としての評価を大きく下げたのは、人質交換の「駒」とされた出来事です。当時、織田家は松平竹千代(のちの家康)を人質としていました。竹千代は、松平家家臣団が当主として仰ぐべき人物であり、また今川義元にとっても松平勢力を支配下に置くための重要な存在でした。
竹千代奪還を図った義元は、軍師・太原雪斎に命じ、信広の居城・安祥城を攻略させます。雪斎の作戦の巧妙さは、信広を討ち取ることではなく、あくまで「生け捕り」にすることにありました。狙いは、生け捕った信広を竹千代との人質交換に利用することでした。
天文18年(1549)、義元の狙い通り信広は生け捕りにされ、松平竹千代との人質交換によって、辛くも織田家へ戻ります。戦国時代において、城を攻略された城主は、その責任と名誉をかけて切腹するのがあたりまえでした。しかし信広は、弟や家臣が命を懸けて奪還するのではなく、「人質交換の道具」として生きて帰ってきたのです。

家督相続権がない上に、武功よりも屈辱的な生還という汚点を背負ったことは、信広の自尊心に深い傷を残し、その後の信長への反発心を決定づけたことは想像に難くありません。
鬱屈の果てに企てた謀反
父・信秀の死後、家督を継いだ信長は、奇行から「大うつけ」と呼ばれ、家中の不満分子の格好の標的となっていました。信広の鬱屈は、弟への反発と「自分が正当な当主であるべきだ」という野心へと変化していきます。信長の弟・織田信行(信勝)が柴田勝家と組み、弘治2年(1556)に謀反を起こしたことに触発された信広は、今度は自らが当主の座を狙う行動に出ます。
信広は、信長と敵対していた美濃の戦国大名・斎藤義龍と極秘裏に連携し、信長を討つための具体的な策謀を練ります。その計画は、美濃勢が信長を清須城からおびき出した隙に、信広が兵を連れて清須城下に入り、城の留守を守る佐脇藤右衛門を騙して討ち取り、城を乗っ取った後に信長を挟み撃ちにする、という周到なものでした。
信広の思惑通り、美濃勢の出兵に反応した信長は急ぎ清須城から出陣します。しかし、信広の策謀は、信長の卓越した情報収集力と危機察知能力によって未然に防がれます。
信長は、放っていた諜者から「これから戦だというのに、美濃勢が妙に浮かれている」という不自然な報告を受けます。敵の緊張感のなさに、近辺での裏切り、すなわち信広の策謀を瞬時に悟った信長は、すぐさま清須城に指示を飛ばしました。
「佐脇は一切外に出さぬこと。町人も惣構えの城戸を閉めて、信長が帰陣するまで人を入れてはならぬ」
清須城下に到着した信広は、門を閉ざされて惣構えの中に入ることすらできず、謀反が露見したことを悟って撤退するしかありませんでした。武将としての屈辱の記憶を持つ信広は、一族の血筋を持つ者として、戦う前に弟の謀略に敗れたのです。
謀反は未遂に終わったとはいえ、信広は弟に刃を向けようとした大罪人です。通常であれば即刻死罪は免れません。しかし、信長の判断は、家中の誰もが予想し得ないものでした。信長は、この一件を不問に付し、信広を許したのです。
この寛大な処置こそが、信広の生涯を決定づけ、後の忠誠を生む土壌となりました。
外交官「津田信広」の誕生と功績
忠実に信長に仕える道を選んだ信広は、本家の織田姓ではなく、織田の分家筋が名乗る津田姓を名乗るようになります。これは、弟・信長への遠慮と、自らの立場を「織田家の分家、すなわち家臣」として明確にする忠誠の証でした。信広の能力を見抜いた信長は、彼を外交の舞台で重用し始めます。
永禄11年(1568)、信長が上洛を果たすと、信広は京に駐在し、室町幕府の将軍・足利義昭との連絡・交渉役という、極めて繊細で重要な役目を任されます。不安定な足利幕府と信長の関係を維持することは、信長の天下布武を正統化する上で不可欠であり、信広は織田家における外交の責任者として極めて高い地位に就きました。
元亀元年(1570)頃には、京の治安維持を担う将軍山城(北白川城)の城主を務め、後の重臣・明智光秀と並んで京の北東の守りを固めるなど、軍事と政治の両面で信長の信頼を得ていました。天正元年(1573)には、信長と義昭との間で緊張が高まる中、義昭に接して和睦を実現させるなど、織田家の中枢で類まれな外交手腕を発揮し、人望も集めたのです。
伊勢長島で散った忠誠の最期
天正2年(1574)、信広は信長が総力を挙げて臨んだ伊勢長島一向一揆攻めに、中核部隊の一員として参戦します。長島は、沼沢地に囲まれた天然の要害の地であり、一揆衆が強固な宗教的結束力をもって独立国の様相を呈していました。信長は8万の大軍で長島を包囲し、兵糧攻めで一揆勢を降伏に追い込みます。しかし、信長はここで、「命は助ける」という約束を反故にし、退却しようとした一揆衆を徹底的に殲滅するという苛烈極まりない手段を選びます。
これに逆上した一揆勢の一部は、刀一本で織田軍へ決死の突撃を敢行しました。この激しい乱戦の最中、信広は最前線で一歩も引かずに果敢に戦い続け、そこで命を落としてしまうのです。
若き日に人質交換という屈辱を味わい、武将としての名誉を失った信広でしたが、最期は忠誠を誓った弟のために、その身を賭して戦場に散るという武士としての本懐を遂げました。彼の死は、信長が外交面で最も頼りにした有能な人材の喪失であり、その忠誠心は、信長の政治的度量と「適材適所」の成功を象徴する出来事であったと言えるでしょう。
【参考文献】
- 西ヶ谷恭弘『考証 織田信長事典』(東京堂出版、2000年)
- 太田牛一著、中川太古訳『現代語訳 信長公記 上<新訂版>』(新人物文庫、2006年)
- 谷口克広『信長と消えた家臣たち -失脚・粛清・謀反』(中公新書、2007年)
- 井沢元彦『英傑の日本史 激闘織田軍団編』(角川学芸出版、2009年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。


コメント欄