「大政奉還(1867年)」武家政権500年余りの終焉!最後の将軍・徳川慶喜の決断
- 2023/07/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
鎌倉幕府開闢以来、日本史上では朝廷と幕府という二つの政府が併存する時代が続いたと例えることができます。現実には武家政権下では幕府が実務上の統治を担っていましたが、将軍とは征夷大将軍のことであり、朝廷=天皇という最高権威から任命されて職務を行うという体裁は変わっていません。
幕末期には相対的な幕府の求心力低下と朝廷権威の復興が進み、政治的権限を朝廷から幕府が委任されているのだという大政委任論での文脈が多く登場します。これは同時に反徳川幕府や尊王攘夷の立場をとる勢力にとっての拠り所ともなっていきますが、やがて幕府は弱体化し、最後の将軍である徳川慶喜は、政権を朝廷に返上するという道を選びます。
これが世にいう慶応3年(1867)の大政奉還(たいせいほうかん)です。これは通算で500年以上続いた武家による政権の終焉を意味し、日本が新政府のもと近世から近代へと移行する画期となった出来事でした。そんな大政奉還について、その背景や経緯を概観してみることにしましょう。
幕末期には相対的な幕府の求心力低下と朝廷権威の復興が進み、政治的権限を朝廷から幕府が委任されているのだという大政委任論での文脈が多く登場します。これは同時に反徳川幕府や尊王攘夷の立場をとる勢力にとっての拠り所ともなっていきますが、やがて幕府は弱体化し、最後の将軍である徳川慶喜は、政権を朝廷に返上するという道を選びます。
これが世にいう慶応3年(1867)の大政奉還(たいせいほうかん)です。これは通算で500年以上続いた武家による政権の終焉を意味し、日本が新政府のもと近世から近代へと移行する画期となった出来事でした。そんな大政奉還について、その背景や経緯を概観してみることにしましょう。
大政奉還の背景
江戸時代最末期において幕府の求心力が失墜していたことは先に述べた通りですが、それは海外勢力との交渉を巡ってのことだけではありませんでした。いくつか例を挙げてみましょう。ひとつには朝廷内の諮問機関・参与(預)会議の解散があります。
文久3年(1863)末から翌年3月まで設けられた機関でしたが、一橋慶喜らと後に四賢侯と称される藩主群の一角を担う福井の松平春嶽・薩摩の島津久光・伊予の伊達宗城らとの対立があり、空中分解してしまいます。慶喜は会津・桑名と連携しつつ朝廷内での勢力を確立しますが、上記雄藩との溝は人心の乖離を招く一因となりました。
また、元治元年(1864)の禁門の変、それに次ぐ第一次長州征討でも幕府に貢献した雄藩・薩摩藩が、意見の相違から幕府に反発するという事態を招きます。これは土佐藩などの仲介で薩摩と長州が水面下で攻守連合を形成する、慶応2年(1866)の薩長同盟として結実します。
この効果によって最新の洋式兵器を導入した長州藩は、第二次長州征討では幕府側諸隊を圧倒。パワーバランスは大きな転換点を迎えることになりました。
薩長同盟に含まれる盟約の内容には対幕府への武力行使を辞さない旨が記されていましたが、当初は必ずしも武力倒幕を主眼としたものではなかったとも考えられています。
一方で薩長両藩を仲介した土佐藩は、倒幕ではなく将軍が自主的に政権を朝廷に返上し、公議政体体制への移行によってゆるやかに幕府の一元統治を脱する策を講じます。これがいわゆる大政奉還策であり、この理論を推進したのが土佐参政・後藤象二郎でした。
一般にこの草案は坂本龍馬が船中において考案したものといわれることがありますが、史実である可能性は低いと考えられています。
しかしこれに先立って土佐は慶応3年(1867)5月21日、薩摩との同盟である「薩土密約」を締結しており、倒幕と平和的政権移行の狭間で苦慮した形跡をうかがえます。
薩土密約において交わされた条文の概要は以下の通りです。
- 1.日本を国際社会で通用する国家にすること
- 2.王政復古を推進すること
- 3.天皇・将軍という二重権力を排し、一括統治体制とすること
- 4.将軍の地位を諸大名と同列にすること
以上が挙げられ、幕府の打倒というよりは廃止を前提とした統一見解を確認しました。しかし長州をはじめとして武力倒幕の可能性を念頭に置く勢力も多数あり、必ずしも平和裡の幕府廃止のみが企図されたわけではありませんでした。
大政奉還の経緯
政局的に苦しい状況はありましたが、四賢侯の一角・土佐の山内容堂は基本的には一貫して将軍と幕府に忠節を尽くす立場でした。しかし後藤象二郎・福岡藤次らの働きかけにより、容堂は大政奉還の建白を決意。同年10月3日、老中・板倉勝静を窓口として大政奉還建白書と、建白に関する趣旨を詳述した八か条の改革意見書を将軍・慶喜へと提出しました。
事実上の武家政権解体を意味することながら、そこには倒幕を企図する勢力との大規模内戦を回避し、国内政情の安定を優先する意思が働いていたとも考えられるでしょう。
また同10月6日にも広島藩主・浅野長訓も同様に大政奉還を勧告し、これらを受けて幕府は10月13日に在京都の10万石以上の藩の重臣を二条城に召集しました。御三家の尾張・紀伊をはじめ、彦根など40藩におよぶ重臣ら50名余りが参集し、老中・板倉勝静が大政奉還案を示してその可否を問いました。
多くの藩がその場での即答を避けて退出しましたが、その後薩摩の小松帯刀、広島の辻将曹、土佐の後藤象二郎と福岡藤次、岡山の牧野権六郎、宇和島の都筑荘蔵らが相次いで慶喜に大政奉還の決断を促しました。
これを受けて慶喜はついに大政奉還を決意。翌10月14日に高家右京大夫大沢基寿に参内を命じ、奉還のための上奏文を作成させました。
少し長いですが、以下『国史大辞典』より転載します。
「臣慶喜謹テ皇国時運之沿革ヲ考候ニ、昔王綱紐ヲ解テ相家権ヲ執リ、保平之乱政権武門ニ移テヨリ、祖宗ニ至リ更ニ寵眷ヲ蒙リ、二百余年子孫相受、臣其職奉スト雖モ、政刑当ヲ失フコト不少、今日之形勢ニ至候モ、畢竟薄徳之所致、不堪慙懼候、況ヤ当今外国之交際日ニ盛ナルニヨリ、愈朝権一途ニ出不申候而者、綱紀難立候間、従来之旧習ヲ改メ、政権ヲ朝廷ニ奉帰、広ク天下之公議ヲ尽シ、聖断ヲ仰キ、同心協力、共ニ皇国ヲ保護仕候得ハ、必ス海外万国ト可並立候、臣慶喜国家ニ所尽、是ニ不過ト奉存候、乍去猶見込之儀も有之候得者可申聞旨、諸侯江相達置候、依之此段謹テ奏聞仕候、以上 詢 十月十四日 慶喜」
これの意味するところを要約すると以下の通りです。
「臣下である私、慶喜は今般の時局を鑑み、鎌倉幕府開設以来武家がお任せ頂いていた政権を朝廷にお返しいたします。外国との関係も盛んになる情勢ながら自身の力不足を痛感し、天皇を中心とした政権のもと日本を国際社会に並ぶ国家とするよう、力を尽くす所存でございます」
これを受けた朝廷では10月15日、摂政・二条斉敬、左大臣・近衛忠房、右大臣・一条実良、また議奏や武家伝奏らが小御所において会議を行い、この申し出を受ける決定を下しました。
同日夜に参内を命じられた慶喜は大政奉還了承の意、そして暫時は徳川支配地や市中の取締りを従来通り行い、追っての通知を待つようにとの御沙汰書を授けられました。
このようにして、形式上は大政奉還が滞りなく行われたことになります。
大政奉還後
形式上、と述べた通りに朝廷へと政権が返上されても即座にそれを運営する機構も能力も当時の朝廷には備わっていませんでした。したがって依然として徳川幕府が政治実務を担当する構図は変わらず、慶喜もこれを承知のうえでの行動だったと考えられています。実は大政奉還の上奏文を提出した10月13日同日、薩長両藩に朝廷より討幕の密勅が授けられていました。僅差でその動きを先制する形での大政奉還実行だったため、10月21日には当面の倒幕行動中止を通達する御沙汰書が両藩に出されています。しかしこのことによって政局はさらに混乱、最終的には戊辰戦争という内乱へと至り近世が幕を閉じるのは周知の通りです。
おわりに
大政奉還というあまりにも大胆な施策を振り返ると、そこには徹底して内乱を回避しようと智謀をめぐらせた痕跡が浮かび上がるかのようです。結果として戦は起きましたが、内戦によって海外勢力が干渉してくる懸念についていずれの陣営もよく理解していたのではないでしょうか。慶喜をはじめとした旧幕府勢は、この後も難しい局面にさらされていくこととなります。
【主な参考文献】
- 『世界大百科事典』(ジャパンナレッジ版) 平凡社
- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館


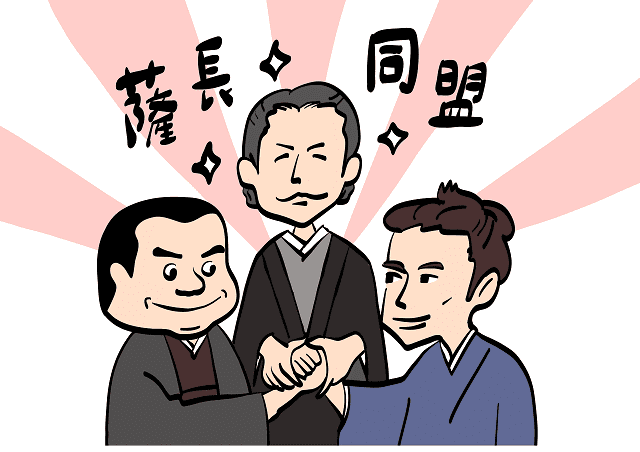



コメント欄