【やさしい歴史用語解説】「租庸調」
- 2025/03/26

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
- ※本記事はユーザー投稿です
日本の歴史上、税の取り立て方や名称は時代によって異なります。
例えば鎌倉・室町期の中世の場合、年貢や公事(手工業製品や採取物)、あるいは夫役(労働で納める税)などが課せられたましたし、江戸時代には年貢として米が納められました。また、商工業者に対しては運上金・冥加金を税として徴収しています。
ところで今回解説する「租庸調」ですが、これは飛鳥・奈良時代に導入された税制でした。当時の日本は中国大陸(唐)の制度や文化を積極的に導入していた時期で、「律令制度」と呼ばれる国家体制がスタートしています。
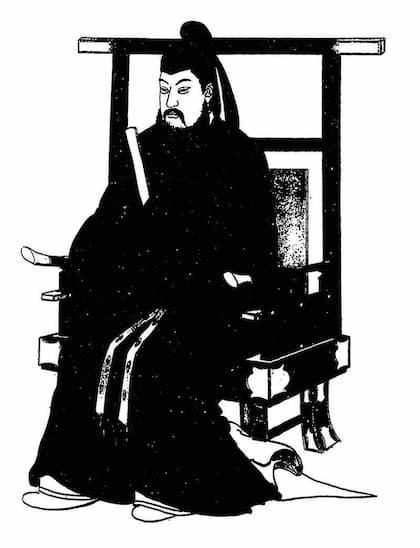
税制上、この制度の画期的だった点は、まず「班田収授法」にありました。人民の私有地化を禁じ、全ての土地は国有であることを明らかにします。次いで国有地から農民へ口分田と呼ばれる土地を支給し、それに応じた税を納めさせました。これがいわゆる「租」です。それでは「租庸調」について、それぞれ見ていきましょう。
中には翌年に植え付けるための種籾すら残らない農民もいたといいます。とはいえ耕作できなければ「租」は徴収できませんから、その場合は「出挙(すいこ)」が広く行われました。「出挙」とは籾を貸し付ける制度ですが、利息とともに返還しなければなりません。その率はなんと50%もあったとか。むしろこちらの方が効率よく取り立てできるため、いっそう搾取が進むことになりました。
もちろん調絹の方が高級ですから量が少なくて済みますが、貨幣流通が発展してきた畿内では、現金で納める者も多かったようです。

ちなみに平城京にはおよそ10万の人々が暮らしたとされていますが、そのほとんどが庶民でした。皇族や八位以上の役人は無税となりますが、庶民も「租庸調」のうち「庸」と「調」は免除されていたようです。都の建設工事や寺院の建設などが続いており、その雇役として働いていたからですね。

とはいえ「租庸調」の税制は、庶民に多大な負担を与えたことは間違いないでしょう。耐え切れなくなった農民たちの逃亡が相次ぐようになり、「班田収授法」の原則は破れられ、やがて律令制度の崩壊へと繋がっていくのです。




コメント欄