「蜻蛉切」天下三名槍のひとつ、本多忠勝愛用の名槍を徹底解説!
- 2021/11/30
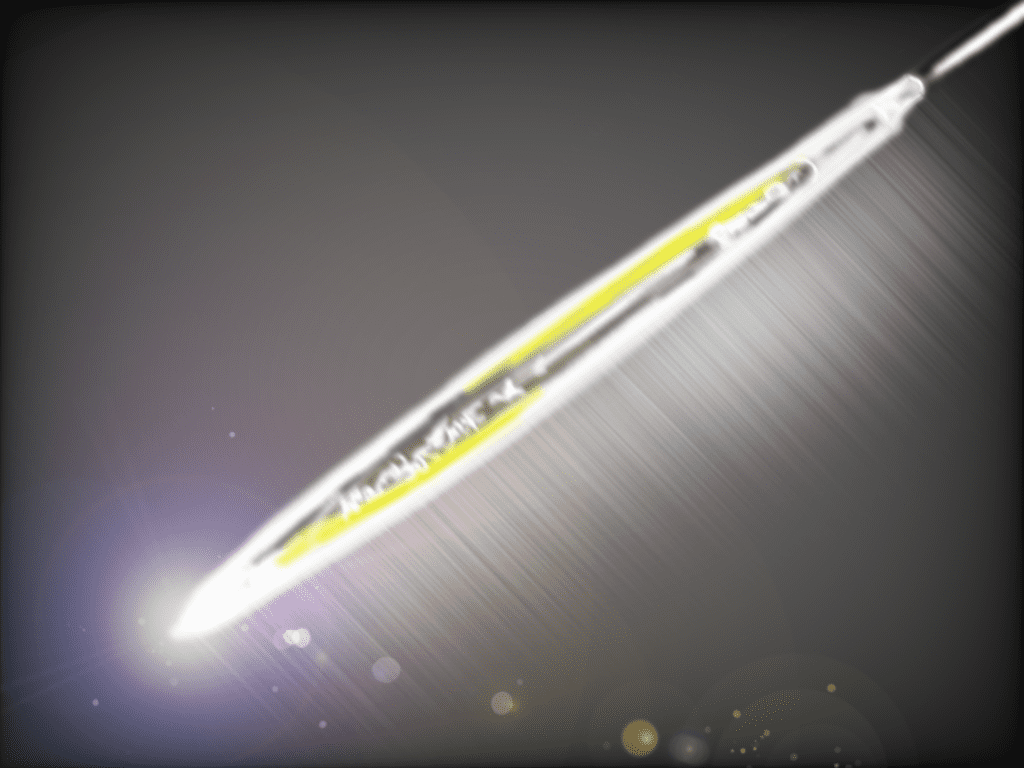
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
古来、優れた武器は多くの逸話を残し、ある種の伝説となって語り継がれてきました。日本の戦国時代においてもそれは同じで、戦場を主とともに駆け抜けたあまたの名器についてのエピソードが知られています。
そんな中でも、戦国時代の主兵装の一つだったのが「槍」。足軽から上級武士に至るまで広く使われ、なおかつ武者働きの象徴とされた武器です。特にその名が轟いた三筋を「天下三名槍」といい、本コラムではその内の一角で猛将・本多忠勝の愛槍、「蜻蛉切」にフォーカスしてみましょう。
そんな中でも、戦国時代の主兵装の一つだったのが「槍」。足軽から上級武士に至るまで広く使われ、なおかつ武者働きの象徴とされた武器です。特にその名が轟いた三筋を「天下三名槍」といい、本コラムではその内の一角で猛将・本多忠勝の愛槍、「蜻蛉切」にフォーカスしてみましょう。
蜻蛉切の基本スペックについて
蜻蛉切は槍ではありますが、よくイメージされる刺突専用の武器に留まりません。穂先(刃部)の長さは43.7cm、最大幅は3cm、厚さは1cmでまるで剣のような姿をしています。このように、突き刺すだけではなく斬撃用にも使える長大な刃をもった槍を「大身槍」といい、蜻蛉切は笹の葉のような形の穂先から「大笹穂槍」と呼ばれています。
柄に埋め込むようにして装着される茎(なかご)の部分も55.6cmと穂先よりも長いですが、通常の槍も相当深く柄に入るよう、長い茎が設けられています。槍術の流派によっては「槍は斬るもの」と伝えられているように、この蜻蛉切を振るって獅子奮迅の戦働きをした本多忠勝の姿が想像されます。

蜻蛉切の作者は「村正」って本当?
名槍と讃えられる蜻蛉切は、どのような名工によって生み出されたのでしょうか。近年のメディア作品などでも蜻蛉切は大人気ですが、刀工は「村正」とされていることがあるようです。村正といえば徳川家康が幾度も同銘の刀槍で傷を負ったことから、徳川家に祟る「妖刀」のイメージで有名かと思います。はたして家康の側近中の側近として名高い忠勝の武器として、本当に村正作のものが使われたのでしょうか。そこで蜻蛉切の茎に切られた「銘」を確認してみましょう。
銘とは製作者の名前のことで、いわゆるブランドにあたるものです。刀や槍などは「〇〇作のもの」という意味から銘で呼ばれることが多く、「蜻蛉切」などの個別に与えられた名前は「号」といいます。
お話を戻すと、蜻蛉切には「藤原正真」の銘が切られていることが確認できます。ところが、この藤原正真なる刀工は極めて謎の多い人物であり、正確なプロフィールが分かりにくいのが実情です。
「正真」の銘をもつ刀工は『古今鍛冶備考』の記載によると8名存在しており、うち「三河文殊正真」が蜻蛉切の作者として有力視されています。ただし、村正を開祖とする門派の「伊勢千子正真」、槍の製作で有名な「大和金房正真」という同じ正真が実は同一人物なのではないかという説も古くからあったようです。
もとは奈良の住人だったと伝わる三河文殊正真とは、三河に移住してきた大和金房正真その人であり、作品の特徴や年代などから伊勢千子派との関連性が指摘されてきたのです。仮に上記の三人が同一人物だとすると、千子派の影響により村正との関連も出てきますが、千子正真の作風はあまり村正とは似ていないとも言われています。
したがって、蜻蛉切の作者を「村正」と言い切ってしまうのにはどうやら無理があるようです。
蜻蛉切の「柄」はどんなものだった?
蜻蛉切を名槍たらしめているのは、造りの見事さだけではありません。あまりの鋭さゆえ穂先に止まった蜻蛉がそのまま両断されたという、号の由来となった伝説や、戦国最強ともいわれる本多忠勝が愛用したこと等々のエピソードに彩られていることも大きいでしょう。なかでも、最大で二丈(約6m)にも及ぶ長大な柄を有していたといわれていることがよく知られています。いまでは穂先のみが残っている蜻蛉切ですが、往年の柄はどのようなものだったのでしょうか。いくつかの文献で寸法は異なるものの、その様子を伝える記述をみてみましょう。
まず、18世紀初めの新井白石著、『藩翰譜』では「青貝をすつたり」という記述があり、南方産のヤコウガイを用いた螺鈿が施されていたことが伝わります。また、『岡崎市史(第貳巻)』では黒漆塗であり、「シホゼノ打柄」だったとやや詳しく記されています。螺鈿は漆に埋め込むようにして磨き出すことが多く、また槍柄の表面仕上げとしても黒漆はよく使われたといいます。
一方で「シホゼノ打柄」がどのようなものであったか、考察を試みたいと思います。
よくできた槍の柄は単純な一本の棒ではなく、芯となる木材の周囲を細かい割り竹で覆い、麻布などを巻きしめて漆で塗り固めるという手法が用いられました。つまり、簡単に折れないように靭性を高める加工が施されていたのです。
「シホゼ」を辞書で引くと「塩瀬(厚地の羽二重織)」、つまりシルクの布を表す単語に行き当たりました。このことから、シホゼノ打柄とは強度を高めるためにシルクを用いた槍柄を示すとは考えられないでしょうか。蜻蛉切の柄は現存しないため確認の方法はありませんが、そうだとすると本多忠勝クラスの武将の武器としても、相応しい造り込みのように思えます。
蜻蛉切に刻まれた、三つの「梵字」の謎
最後に、蜻蛉切に施された美しい彫金の謎について触れ、まとめとしたいと思います。穂先の裏側には梵字を中心とした刀剣類に典型的な彫り物があります。梵字(ぼんじ)とはサンスクリット語の文字のことで、一字である種の仏尊を表します。
蜻蛉切には下から不動明王の「カンマーン(梵字)」、破邪の剣「三鈷剣(線刻)」、聖観音菩薩の「サ(梵字)」、阿弥陀如来の「キリーク(梵字)」、地蔵菩薩の「カ(梵字)」がそれぞれ刻まれています。
不動明王の梵字や三鈷剣は、武人を守護する象徴として刀剣類にもよく使われる意匠ですが、問題は「聖観音・阿弥陀・地蔵」の三つの梵字です。これらは衆生を救い、魂を極楽へと導く仏であり、戦国武将の武器には一見似つかわしくないようにも思われます。
ここで思い出されるのが、忠勝の「改宗」に関する問題です。元来、一向宗徒であった本多一族ですが、忠勝は永禄6年(1563)の「三河一向一揆」に際し、浄土宗へと改宗することで徳川家康の軍に残り、武功をあげます。
浄土宗といえば「阿弥陀三尊」と呼ばれるように、阿弥陀如来を中心として両脇に二尊の仏を配する本尊形式で知られており、現在一般的な脇侍仏は「聖観音」と「勢至菩薩」です。ところが、これに「龍樹菩薩」と「地蔵菩薩」を加えた五尊とする説、あるいは上記の三尊に地蔵を加えた掛軸などが存在しています。
また、愛知県指定文化財には阿弥陀如来に「十一面観音」と「地蔵」を加えた、南北朝~室町初期のものと思われる特殊な阿弥陀三尊の掛軸が存在しています。
十一面と聖との違いはありますが、「阿弥陀・観音・地蔵」の組み合わせは蜻蛉切に刻まれた梵字と合致しています。つまり、蜻蛉切は三河地方に見られる「阿弥陀三尊」をその身に宿す、「鎮魂の槍」とも考えられるのではないでしょうか。
忠勝は敵・味方の供養のため、甲冑に巨大な数珠をかけていました。蜻蛉切にも、いわばやむなく手にかけた命への哀悼の念が込められていたとするならば、実に忠勝らしいと言えるでしょう。




コメント欄