信長と茶の湯 「世人がありがたがるものは活用せねばな」
- 2025/09/02
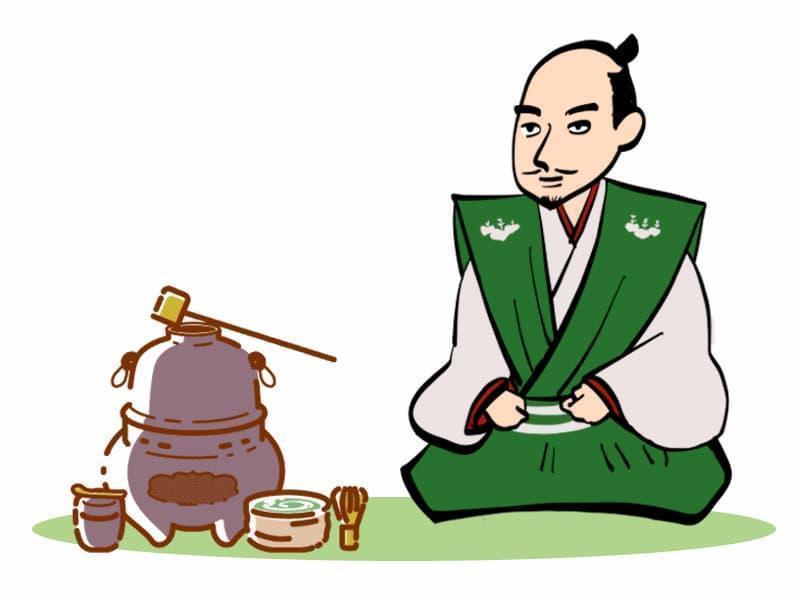
茶の湯の心とは、本来は簡素な趣や落ち着いた風情を尊ぶものです。しかしそこに俗世の権威を持ち込み、茶器に妙な付随価値を付けてしまった男がいます。戦国乱世の覇者・織田信長です。
信長の父も守役も茶人だった
武田信玄はライバルの”人となり”を知ろうとしたのでしょうか? 館を訪れた天台宗の僧侶天沢に命じます。
信玄:「信長の日常の様子をありのままに語り聞かせよ」
天沢:「毎朝馬に乗り鉄砲や弓の稽古に励み、絶えず兵法を学び鷹狩をしげしげと行われます」
そう答えた天沢に対し、さらに尋ねる信玄。
信玄:「その他に数寄は何がある?」
天沢:「幸若舞の敦盛を何度も舞われます」
幸若舞の敦盛というのは、信長が今川義元を討ち取る直前に舞ったと言う例の「人間五十年、下天のうちをくらぶれば」ですね。この時は信長の数寄に茶の湯は挙げられていませんが、彼の周りに茶人が居なかったわけではありません。
天文2年(1533)、信長が誕生する1年前ですが、公家の山科言継が信長の父・織田信秀の勝幡城を訪れます。城内の新館に入った言継はその造作のあまりの見事さに目を見張りますが、中でも数寄を凝らした茶室に感嘆したとか。信秀は篠耳の香炉や有名画家の掛け軸など、茶道具を集めており、信長の守役であった家老の平手政秀でさえ見事な茶室を持ち、古瀬戸の茶入れや合子の水翻(みずこぼし)を大事にしていました。
このように環境は整っていましたが、信長が茶の湯に注目しだしたのは永禄11年(1568)、35歳で上洛を果たしたころのようです。
名物狩り
信長の茶の湯と言えば「名物狩り」と「茶会の許し」です。信長といえども相次ぐ合戦や油断のならぬ敵との駆け引きに、一服の茶に疲れた心の癒しを求めたのかもしれません。しかし高名な茶人が世間に持て囃され、人々が争って名物茶器を求めるのを見れば「これは使える」と考えるのも信長。献上されたり買い集めた茶器を秘蔵してしまわず、実益に役立てようとします。戦功があったり日常職務精励の武将や、信長に従って役に立つ町衆にこれ見よがしに名物茶器を与えます。「御茶湯御政道(おんちゃのゆごせいどう)」です。この言葉は羽柴秀吉の書状に見られ、どうやら秀吉の命名のようです。
永禄11年(1568)9月、室町将軍・足利義昭を奉じて上洛した信長は、翌永禄12年(1569)正月に三好一族を打ち払い、天下は信長の意思で動くようになります。強力な武将や有力町人が嗜んだ茶の湯の世界も同じで、信長の意志と行動が基準になって行きます。
同年10月、陣中に在った信長は大和多聞山城主の松永久秀から九十九茄子の茶入れを、堺和泉の有力町衆・今井宗久から松島の葉茶壺と紹鷗茄子の茶入れを献上されます。宗久は信長が堺と対立した時に裏で信長と誼を通じており、その手柄もあって信長の御用商人となり、堺の代官的地位を得ていました。

同じ頃、信長は松井友閑と丹羽長秀に命じ、大っぴらに“名物狩り”を始めます。
信長:「もはや金銀や米銭に不足は無い。この上は唐物天下の名物を集めよ」
その結果、京都では大文字屋栄甫の初花肩衝の茶入れ・祐乗坊の富士茄子の茶入れ・法性寺の竹の茶杓・池上如慶の蕪無の花入れ・佐野氏の平沙落雁の絵・江村氏の桃底の花入れなど、多くの名物が信長の元に集まります。信長は代価として莫大な金銀や米を与えており、決して無理に取り上げたのではありませんが、天下の権力者に「くれ」と言われては断ることも出来ませんでした。
茶会は派閥確認の場
天正元年(1573)11月23日、信長は京都妙覚寺に津田宗及・塩屋宗悦・松江隆仙ら、宗及を筆頭とする堺町衆の天王寺屋グループを招いて茶会を開きます。天王寺屋グループとは、信長が堺に軍使金として銭二万貫を要求した時に、三好一族や大坂石山本願寺との関係も絶たず、信長も拒絶せずに堺の独立を守ろうとしたグループです。茶頭は京都茶の湯を開いた珠光の流れを汲む不住庵梅雪が務めます。信長は天王寺屋グループをしっかり自陣に取り込もうと、自ら酒肴を勧めるなどもてなしに努め、その日の夜には茶会の礼に参上した宗及に馬・雁・鱈を引き出物として与えました。
翌24日には今度は同じ妙覚寺に今井宗久・松井友閑・山上宗二を招いて茶会を開きます。このグループは信長が堺に迫った時に最初に信長と誼を通じたグループです。信長は手に入れた蕪無の花入れに白梅をたくさん生け、利休の点前で濃茶を服し、宗久の点前で薄茶を味わい、いたってご機嫌だったそうです。
天正4年(1576)には宗及主催の天王寺での茶会に招かれますが、振舞いは五ノ膳にまで及び、菓子の類が11種類も出たそうです。信長はフロイスの言う通り、甘党だったのかもしれません。
信長流茶器の活用法
信長は掻き集めた茶器を後生大事にしまいこんだりせず、しっかり活用します。中でも秀吉は与えられた品に見合った働きをします。天正9年(1581)中国・山陰の攻略が一段落がつき、12月に安土城へ参上した秀吉を、信長は自ら茶を点ててねぎらいます。さらに竹林の雀の絵・砧の花入れ・朝倉氏が持っていた肩衝の茶入・大覚寺天目茶碗・朱徳作の竹の茶杓・鉄の火箸・高麗茶碗を与えるなど、大盤振る舞いです。秀吉もこの安土名物の拝領物に大いに感激しています。本能寺の変(1582)で信長が横死した後、自害した織田信孝(信長三男)の家老に送った書状から伺えます。
「御茶湯道具まで取り揃え下しおかれ、我らは免しおかれ茶湯を仕るべしと仰せ出され候事、今生後世忘れ難く候」
茶器を拝領しただけでなく、茶会を開くのを許されたと感謝しています。さらに次のようにまで書いています。
「夜昼涙を浮かべ御一類の御事まであだにも存ぜず候」
信長の家臣たちは主君の許しを得て初めて茶会を開けました。まさに御茶湯御政道で、茶会の開催にまで妙な有難味を持たせます。
初花肩衝茶入れこそ後継者の証
信長長男の信忠は、天正3年(1575)に信長から家督相続の地位を約束、尾張・美濃両国の支配権を与えられて三国の重宝なども譲られますが、茶道具は貰えませんでした。しかし2年後の天正5年(1577)12月、岐阜城主であった信忠を安土城に招き、初花肩衝茶入れ・松花の葉茶壺・平沙落雁の絵・竹子の花入れ・藤波平窯・道三茶碗・内赤盆・珠徳作竹の茶杓などを与えています。安土城で年越しした信忠は翌天正6年(1578)正月4日に安土城内の万見仙千代邸で茶会を開き、信長から譲られた初花肩衝茶入れを始め、数々の名物茶器を披露します。招かれたのは滝川一益に丹羽長秀・羽柴秀吉ら9名の織田家を支える武将たちでした。天下の名物初花肩衝茶入れを所持する者こそ信長の後継者である事を知らしめる茶会でした。
おわりに
天正10年(1582)6月1日、信長は本能寺で茶会を開きます。この会のために安土城から多くの名物茶器を運び込ませました。翌2日未明、炎上する寺と共に多くの茶器が灰燼に帰しました。
フロイスが信長の死をイエズス会会長に知らせた報告書で書き送ったそうです。
「当都において日本の富は無くなった」と。
【主な参考文献】
- 江口浩三『茶人織田信長』(PHP研究所、2010年)
- 井上辰雄『茶道をめぐる歴史散歩』(万来舎、2009年)
- 岡本良一/編『織田信長事典 コンパクト版』(KADOKAWA、2007年)
- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。
- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。
この記事を書いた人
Webライターの端っこに連なる者です。最初に興味を持ったのは書く事で、その対象が歴史でした。自然現象や動植物にも心惹かれますが、何と言っても人間の営みが一番興味深く思われます。






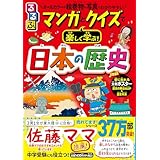

コメント欄