活動弁士、日本の演芸史を華やかに彩ったその活躍
- 2023/01/16
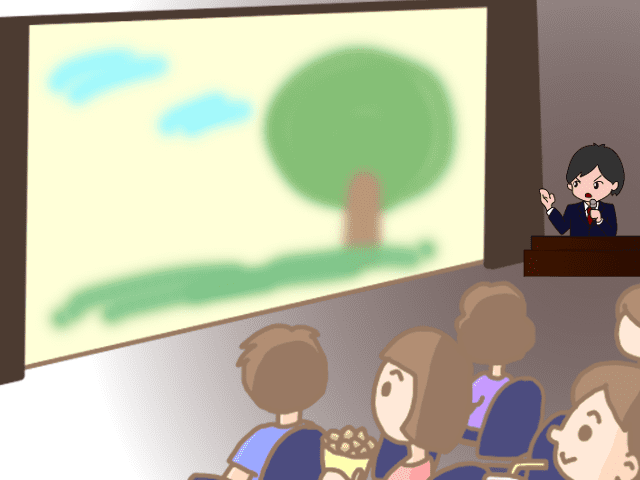
- ※本記事は一部にプロモーションを含みます
映画の第一歩は、1893年、かのアメリカの発明王トーマス・エジソンが、キネトスコープ(自動映像販売機)を一般公開したあたりでしょうか。フランスのリュミエール兄弟が、こちらに向かって来る蒸気機関車の映像で観客を驚かせたのも同じころです。
では、映画はいつごろ我が国にやって来たのでしょうか…。
では、映画はいつごろ我が国にやって来たのでしょうか…。
映画の最初は覗き箱
キネトスコープとは木箱に内蔵された装置にフィルムを装着して蓄電池モーターで動かし、連続した映像として客に見せるものです。上部の覗き穴から1人ずつ覗いて楽しみました。このキネトスコープが日本で初めて公開されたのは明治29年(1896)神戸でのことです。急速に発達した映画技術は1900年代に入ると、娯楽として立派に人々の鑑賞に耐えるものを造り始めます。しかしこの頃は当然「無声映画」でした。映像と音声が同時に楽しめるトーキー「発声映画」が一般的になったのは1930年代になってからです。つまり、それまでは活動弁士が活躍した時代でした。

弁士が活躍したのは日本だけ?
無声映画の上演時にはオーケストラやバンドでの音楽伴奏が付くのが普通でした。これはスクリーンの傍に楽団が入っての生演奏ですから、今から考えれば贅沢な話です。そしてバンドと共に弁士と呼ばれる人間が映画の筋を説明しました。諸外国でも初期には弁士が付いたようですが、無声映画の全期間を通して存続し、それがひとつの話芸にまで発展したのは日本と韓国とタイだったと言われます。当時の韓国は日本の統治下にありましたし、タイで最初の映画興行を行ったのは日本の興行者たちでしたので、いずれも日本の影響と考えられます。
なぜ日本でのみ彼らは活躍でき、独特の話芸にまで高められたのでしょうか? 日本には落語や浪曲・現在の講談の元となった辻講釈など、1人語りの話芸が広く人々に親しまれる演芸として確立していました。それぞれに名人・上手と言われる演者を排出するなど、独立した立派な芸として認められていたのです。また人形浄瑠璃では演じるのは人形、物語りを語るのは人間の浄瑠璃語りと役割分担が普通の事で、映画における俳優と弁士それぞれの役割を楽しむ下地が出来ていました。
初期には1本の映画に5、6人もいた弁士
実は初期には弁士も複数人居て、それぞれが1人、および2、3人程度の俳優の声を受け持っていました。その後、弁士の人数は整理されて行きましたが、映画が長編になると1人で全編語るのは肉体的にも難しく、ここぞというクライマックスの部分を主任弁士が語り、その他の部分は他の弁士が語る役割分担が行われます。そのころの映画は映像としての俳優の魅力と、語り芸としての弁士の魅力の両方を売り物にしており、有力映画館は競って優れた弁士を抱えました。映画スター以上の人気を誇った弁士も現れ、美辞麗句を散りばめた流れるような話しぶりや、大袈裟な絶叫調を売り物にする弁士、また静かで知的な説明を得意とする者、落語家のようなおどけた口ぶりの者まで様々なタイプの弁士が人気を競いました。
有名弁士たち
徳川夢声
有名な弁士としてまず名前が挙がるのは、東京赤坂葵館で主任弁士を張った徳川夢声(とくがわ むせい)です。
ドイツの恐怖映画「カリガリ博士」での知的で冷静な語り口は、同時代の全ての芸人の中でも第一級の芸術であるとまで評価されています。「山の手派」の代表弁士と言われますが、「山の手派」とは新宿武蔵野館などに代表される山手地区で活躍していた弁士のスタイルで、感情を抑えた淡々としたインテリ好みの語り口が特徴です。このように弁士の語り口が分類されるまでになっていたのですね。
松田春翠
徳川夢声の向こうを張ったのが松田春翠(まつだ しゅんすい)です。この方は二代目で若い頃から少年弁士として活躍し、流れるような華麗な語り振りが人気でした。また各地に散逸してしまった無声映画のフィルム収集に当たり、その保存に力を尽くされます。集めるばかりではなく、7000巻に上るフィルムを活用しようと、昭和34年(1959)に「無声映画鑑賞会」を立ち上げ、弁士付きで月1回の上映を始めます。昭和23年(1948)年には全国映画説明者競演会で優勝しますが、弁士全盛時にはこんなコンクールも開かれていました。
大辻司郎
大辻司郎(おおつじ しろう)はトレードマークのおかっぱ頭で「勝手知ったる他人の家」や「胸に一物、手に荷物」など現在にまで残る名ゼリフを残しました。当時の映画館ではよく停電が起こり、そんな時彼はお喋りだけで観客を飽きさせませんでした。徳川夢声・古川緑波らと共に弁士のかくし芸大会「ナヤマシ会」なる物を結成し、そこでも活躍しました。
数々の名調子
「春や春、春南方のローマンス」無声映画の名ゼリフと言えばこれです。このセリフを吐いたのは生駒雷遊(らいゆう)。大正中期ブルーバード映画の弁士を務め、人気絶頂となります。ブルーバード映画とは、アメリカのブルーバード映画社で作成された映画の事で、50分ほどの明朗な青春映画が主流、日本の若い映画ファンに人気を博しました。雷遊は下町派の弁士で、下町派とは浅草や神田など東京下町の映画館で活躍した弁士の語り口です。華やかなセリフを感情を込めて滔々と謳い上げます。
他にも弁士たちの名調子が残っています。
「秋の夜風の冷え深く、沁みる心の露時雨、袖を濡らして忠治はどこへ、国定忠治はどこへ行く」
「暮れるに早い早春の、闇に飛び散る十手の声。御用提灯よそにして、惚れた男の心を抱いて、水に流れる女の意気地」
「愛の証(あかし)のシャープペンシル、波間に恋(ラブ)と書いては消える。消えて儚い青春の、夢が流れる潮風に、落ちる涙のひとしづく」
さすがに七五調・五七調が身に染みついている日本人ですね、いくらでも出て来ます。
おわりに
隆盛を誇った活動弁士たちですが、トーキー映画が主流になるにつれ、その活動の場は失われて行きます。優れた話術を生かして多くの者が漫談師や司会者・朗読者などに転身しましたが、時流に乗れず自ら命を絶ったものもいます。現在でも無声映画を上映する映画館は存在し、弁士の活動場所となっていますが、弁士一本での暮らしは難しく、ほとんどの方が声優やラジオパーソナリティとの兼業です。
40年に満たない期間でしたが、彼らの華やかな活躍は日本演芸史に特筆されるべきものです。
【主な参考文献】
- 岩本憲児『日本映画の誕生』森話社/2011年
- 木村茂光ほか『モノのはじまりを知る事典』吉川弘文館/2019年




コメント欄